『構造としての語り』に示されている「私の子ども」の母親が先生の奥さんであるという小森陽一の説を,僕と同様に懐疑的に評価しているのが水川隆夫で,それは『夏目漱石「こゝろ」を読み直す』という著作の中で主張されています。確かに懐疑的であるという点で僕と水川は一致しますが,僕は水川がそこで展開している主張はいっかな受け入れられず,それなら小森説の方がまだ正しいくらいに考えているのですが,その点については後に書くことにして,先に書評を掲載します。
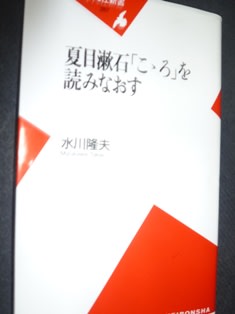
基本的にこの本は,『こころ』のテクストを丹念に追うことによって,どう読解すべきかを示すことを目指しています。水川は正しい読解というのがあると考えているように窺えるふしがあり,僕はその見解には疑問を有しますが,作家論と作品論という僕の区分けでいえば,方法としては作品論であり,僕の好みの文芸評論に該当します。
ただし,この区分は便宜的なものです。宮井一郎の『漱石の世界』は作家論の典型ですが,作品論として読める部分も含まれています。蓮実重彦の『夏目漱石論』は作品論に極度に偏っていますが,多くの作品が縦横無尽に語られるという点で,作家論的要素をみることが不可能であるとはいえません。大抵の文芸評論は,両者が混在しているのであり,どちらを重視するのかということが区分けの規準になります。水川のこの著作にも作家論的要素が含まれます。
含まれること自体は何ら否定的要素になりませんが,僕には,この本は作家論的要素が最悪に近い形で入り込んでいると感じられました。というのも,テクストの読解が困難になった時点で,それを解決するために,作者である夏目漱石の思想的観点に論拠を置こうとするからです。それが水川の考える正しい小説の読み方なのだと思うのですが,僕はあるテクストの読解は,同一作品の別のテクストに依拠するべきであり,だから文学作品に正しい理解などというものは存在しなくて構わないと考えているので,水川のこの手法には不満の方が大きかったです。
僕の個人的感想とは別に,『こころ』の文芸評論としては,読む価値が高いものだと思います。
人間が現実的に存在する場合には,本性の変化と完全性の移行を同一視してよいことはこれでいいでしょう。あとはライプニッツがスピノザを訪問するという運動をするときに,ライプニッツの身体に,完全性の移行が生じるかどうかです。生じるということであれば,少なくともこの運動に対して,ライプニッツの身体が,十全な原因の一部としての,意味ある部分的原因を構成することになります。
現実的に存在するライプニッツに関しての言及ですから,本当ならライプニッツ以外に確実なことはいえないと考えるべきかもしれません。しかし僕は,この運動をなすライプニッツに,完全性の移行が生じないと主張することには無理があると思います。
一般に人間の精神の現実的本性がそうであるように,ライプニッツの精神も,共通概念notiones communesを代表するようないくつかの十全な観念と,表象像に代表されるようないくつかの混乱した観念によって組織されています。そしてライプニッツの身体が何らかの運動をなすならば,必然的にライプニッツは何事かを表象します。これを否定しようとするならば,第二部定理一七により,ライプニッツは運動をしても外部の物体によって刺激されることは一切ないといわなければなりませんが,これはそれ自体で不条理であるといえるでしょう。あるいは論理的に考えても,岩波文庫版117ページの,第二部自然学②要請三から,この主張を否定することが可能です。
もちろん,単に事物を表象するだけで,完全性の移行が生じるとは限りません。いい換えれば,喜びも悲しみも感じないような表象が存在します。しかし,ライプニッツがスピノザを訪問するという運動をなすなら,ライプニッツは確実にスピノザのことを表象するでしょう。そしてその表象像から他の表象像へ,第二部定理一八に応じて移行していく筈です。それがライプニッツの喜びであるか悲しみであるかは分かりません。他面からいえば,第三部諸感情の定義六と第三部諸感情の定義七にあるように,ライプニッツのスピノザへの感情が,愛であるか憎しみであるかは分かりません。しかしどちらでもないということはあり得ないでしょう。
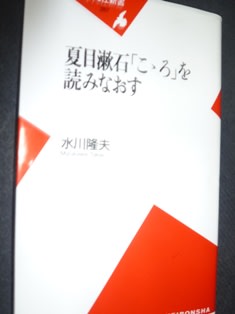
基本的にこの本は,『こころ』のテクストを丹念に追うことによって,どう読解すべきかを示すことを目指しています。水川は正しい読解というのがあると考えているように窺えるふしがあり,僕はその見解には疑問を有しますが,作家論と作品論という僕の区分けでいえば,方法としては作品論であり,僕の好みの文芸評論に該当します。
ただし,この区分は便宜的なものです。宮井一郎の『漱石の世界』は作家論の典型ですが,作品論として読める部分も含まれています。蓮実重彦の『夏目漱石論』は作品論に極度に偏っていますが,多くの作品が縦横無尽に語られるという点で,作家論的要素をみることが不可能であるとはいえません。大抵の文芸評論は,両者が混在しているのであり,どちらを重視するのかということが区分けの規準になります。水川のこの著作にも作家論的要素が含まれます。
含まれること自体は何ら否定的要素になりませんが,僕には,この本は作家論的要素が最悪に近い形で入り込んでいると感じられました。というのも,テクストの読解が困難になった時点で,それを解決するために,作者である夏目漱石の思想的観点に論拠を置こうとするからです。それが水川の考える正しい小説の読み方なのだと思うのですが,僕はあるテクストの読解は,同一作品の別のテクストに依拠するべきであり,だから文学作品に正しい理解などというものは存在しなくて構わないと考えているので,水川のこの手法には不満の方が大きかったです。
僕の個人的感想とは別に,『こころ』の文芸評論としては,読む価値が高いものだと思います。
人間が現実的に存在する場合には,本性の変化と完全性の移行を同一視してよいことはこれでいいでしょう。あとはライプニッツがスピノザを訪問するという運動をするときに,ライプニッツの身体に,完全性の移行が生じるかどうかです。生じるということであれば,少なくともこの運動に対して,ライプニッツの身体が,十全な原因の一部としての,意味ある部分的原因を構成することになります。
現実的に存在するライプニッツに関しての言及ですから,本当ならライプニッツ以外に確実なことはいえないと考えるべきかもしれません。しかし僕は,この運動をなすライプニッツに,完全性の移行が生じないと主張することには無理があると思います。
一般に人間の精神の現実的本性がそうであるように,ライプニッツの精神も,共通概念notiones communesを代表するようないくつかの十全な観念と,表象像に代表されるようないくつかの混乱した観念によって組織されています。そしてライプニッツの身体が何らかの運動をなすならば,必然的にライプニッツは何事かを表象します。これを否定しようとするならば,第二部定理一七により,ライプニッツは運動をしても外部の物体によって刺激されることは一切ないといわなければなりませんが,これはそれ自体で不条理であるといえるでしょう。あるいは論理的に考えても,岩波文庫版117ページの,第二部自然学②要請三から,この主張を否定することが可能です。
もちろん,単に事物を表象するだけで,完全性の移行が生じるとは限りません。いい換えれば,喜びも悲しみも感じないような表象が存在します。しかし,ライプニッツがスピノザを訪問するという運動をなすなら,ライプニッツは確実にスピノザのことを表象するでしょう。そしてその表象像から他の表象像へ,第二部定理一八に応じて移行していく筈です。それがライプニッツの喜びであるか悲しみであるかは分かりません。他面からいえば,第三部諸感情の定義六と第三部諸感情の定義七にあるように,ライプニッツのスピノザへの感情が,愛であるか憎しみであるかは分かりません。しかしどちらでもないということはあり得ないでしょう。













