『夏目漱石「こゝろ」を読み直す』で水川隆夫が『構造としての語り』で示される「私の子ども」に関する小森陽一の読解が論拠に乏しいというとき,僕はそれを肯定します。しかしそれに続けて水川が,執筆時点での私に子どもがいると解釈する必要がないというとき,僕は否定します。僕にいわせればこの部分の水川の論述は,出せない結論を出そうとしているため,支離滅裂です。
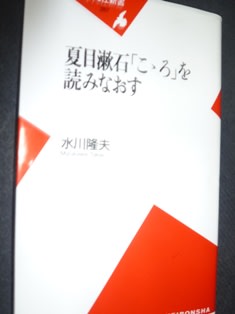
当該のテクストは,執筆時の私が,奥さんをあしらった過去の私の弁護士になる目的だけで書かれています。物語全体とは無関係ということからこれは明らかです。これだけであれば,その時点では子どもをうるさいだけと思っていた私が,そうは思わなくなっただけだという,水川の見解も成立します。というか,時系列を無視すれば,テクストはそう読む方が自然です。その時点での私は,子どもをうるさいものと思っていることには自覚的であり得ますが,自分に子どもがないということは意識できる筈がありません。それは子どもを持って初めて自覚できる筈だからです。
要するに,テクストの中には虚偽があるのです。奥さんに素気ない態度を示したのが,子どもをうるさいものと感じていたからだったのは事実だったとしても,子どもをうるさいものと感じていた原因が,そのときの私には子どもがいなかったからだというのは,執筆時点での私が,過去の自分の思いの原因を後になって考察した上で書かれているのであり,当時の私にとっての事実ではないからです。そしてこのような回顧の仕方が可能になっているのは,執筆時点では私に子どもがあるからに違いありません。過去にも執筆時点でも子どもがないなら,この説明は執筆時点の私にも妥当してしまいますが,執筆時点で子どもに対する思いに変化があるということは,水川も認めているように疑い得ないからです。
なおかつ,テクストの目的は自己弁護なのです。もし執筆時の私に子どもがなかったら,このテクストがそうなり得ないことも明白でしょう。
なので僕は,水川のように解釈するなら,小森の解釈の方がましだと思えるのです。小森は執筆時の私に子どもがいるということは認めているからです。
人間の身体と自転車との一体化は,人間の精神の方と関連させると分かりやすいと思いますが,各人において一様の様相を示すわけではありません。多くの人にとっては,一体化できるか否か,つまり自転車に乗れるか乗れないかの差異が最も顕著に表象される筈ですが,それが万人に通用されるというわけではありません。同じような一体化の中にも,好ましくない一体化とよりよき一体化というのはあるのであって,ある種の人にとっては,そちらの差異の方が大きいと表象され得るのです。意味がよく分からないかもしれませんが,たとえば自転車の競技者は,よりよき一体化を追求するような存在であると理解してください。ここで一体化というような説明をしたのは,この例の場合に,単に人間の身体の場合だけではなくて,自転車の方にも焦点を当てるためです。
僕はそうした競技者ではありませんから,どういう一体化がよき一体化であり,どういう一体化はそうではないのかということはよく分かりません。他面からいえばそうした認識は僕の精神のうちには生じません。しかし競技者にとってはそうでなく,一体化できるかどうかよりも,よき一体化を組織できるかどうかが重要であるということは分かります。これは僕だけでなく,競技者ならもちろん,そうでないすべての方にもお分かり頂けるでしょう。
こうした認識の差異が発生するのは,第三部定理五一にあるように,異なった人間が同一の対象から異なった刺激を受け得るからです。いい換えれば競技者の現実的本性とそうでない人間の現実的本性が異なるからです。したがって競技者は,そうでない人間が感じることがないような表象により,そうでない人間なら感じることがないような喜びや悲しみに刺激され得ることになります。というか実際にそうした喜びや悲しみが競技者にはあるといってよいでしょう。
このことが,「人が変わる」という慣用表現が程度問題でしかないのと同じような意味で,程度問題なのです。つまり,自転車に乗れない人間が乗れるようになるのは,だれでも顕著に表象できます。しかし競技者がうまく乗れるようになったかどうかはそういうわけにはいかないのです。
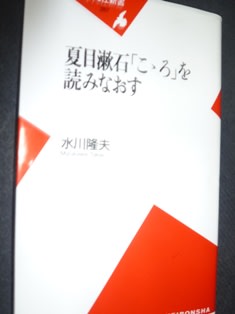
当該のテクストは,執筆時の私が,奥さんをあしらった過去の私の弁護士になる目的だけで書かれています。物語全体とは無関係ということからこれは明らかです。これだけであれば,その時点では子どもをうるさいだけと思っていた私が,そうは思わなくなっただけだという,水川の見解も成立します。というか,時系列を無視すれば,テクストはそう読む方が自然です。その時点での私は,子どもをうるさいものと思っていることには自覚的であり得ますが,自分に子どもがないということは意識できる筈がありません。それは子どもを持って初めて自覚できる筈だからです。
要するに,テクストの中には虚偽があるのです。奥さんに素気ない態度を示したのが,子どもをうるさいものと感じていたからだったのは事実だったとしても,子どもをうるさいものと感じていた原因が,そのときの私には子どもがいなかったからだというのは,執筆時点での私が,過去の自分の思いの原因を後になって考察した上で書かれているのであり,当時の私にとっての事実ではないからです。そしてこのような回顧の仕方が可能になっているのは,執筆時点では私に子どもがあるからに違いありません。過去にも執筆時点でも子どもがないなら,この説明は執筆時点の私にも妥当してしまいますが,執筆時点で子どもに対する思いに変化があるということは,水川も認めているように疑い得ないからです。
なおかつ,テクストの目的は自己弁護なのです。もし執筆時の私に子どもがなかったら,このテクストがそうなり得ないことも明白でしょう。
なので僕は,水川のように解釈するなら,小森の解釈の方がましだと思えるのです。小森は執筆時の私に子どもがいるということは認めているからです。
人間の身体と自転車との一体化は,人間の精神の方と関連させると分かりやすいと思いますが,各人において一様の様相を示すわけではありません。多くの人にとっては,一体化できるか否か,つまり自転車に乗れるか乗れないかの差異が最も顕著に表象される筈ですが,それが万人に通用されるというわけではありません。同じような一体化の中にも,好ましくない一体化とよりよき一体化というのはあるのであって,ある種の人にとっては,そちらの差異の方が大きいと表象され得るのです。意味がよく分からないかもしれませんが,たとえば自転車の競技者は,よりよき一体化を追求するような存在であると理解してください。ここで一体化というような説明をしたのは,この例の場合に,単に人間の身体の場合だけではなくて,自転車の方にも焦点を当てるためです。
僕はそうした競技者ではありませんから,どういう一体化がよき一体化であり,どういう一体化はそうではないのかということはよく分かりません。他面からいえばそうした認識は僕の精神のうちには生じません。しかし競技者にとってはそうでなく,一体化できるかどうかよりも,よき一体化を組織できるかどうかが重要であるということは分かります。これは僕だけでなく,競技者ならもちろん,そうでないすべての方にもお分かり頂けるでしょう。
こうした認識の差異が発生するのは,第三部定理五一にあるように,異なった人間が同一の対象から異なった刺激を受け得るからです。いい換えれば競技者の現実的本性とそうでない人間の現実的本性が異なるからです。したがって競技者は,そうでない人間が感じることがないような表象により,そうでない人間なら感じることがないような喜びや悲しみに刺激され得ることになります。というか実際にそうした喜びや悲しみが競技者にはあるといってよいでしょう。
このことが,「人が変わる」という慣用表現が程度問題でしかないのと同じような意味で,程度問題なのです。つまり,自転車に乗れない人間が乗れるようになるのは,だれでも顕著に表象できます。しかし競技者がうまく乗れるようになったかどうかはそういうわけにはいかないのです。













