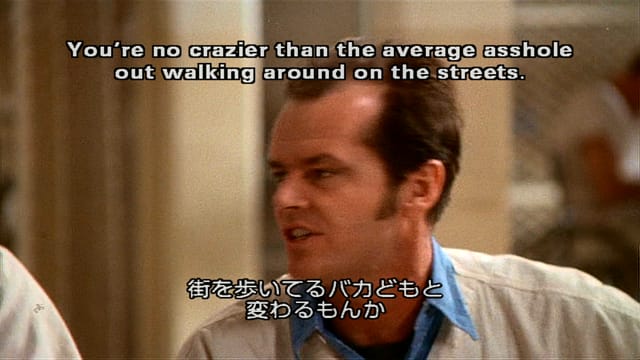先日、上司の替え玉で労働局に研修を受けに行ってきました。もっとも非正規社員に毛が生えた程度でなんの権限もない私ですから、雇用側の管理者向け研修を受けたところで、それを何かに使う機会が訪れるとは思えません。まぁ会社的には労働局主催の研修に参加した実績が出来たわけですから、これでいいのでしょう。
基本的には雇用者向けの、労働法の話もあれば、その抜け穴を暗に示唆するような話もありました。会社側の言い訳がどのように作られているか、何処までなら労働局が目をつぶるか、察することができないでもなかったですね。一方で労働時間の考え方については例外的に、会社側の一般的な見解と労働局のそれとで、相違を見せる部分もあったのが幾分か驚きでした。
労働局の講師が例に挙げたのが「懇親会」の扱いで、会社が業務として出席を命じたのであれば、それは会社の士気命令下にあるのだから労働時間に該当する、というものでした。しかし私は会社の上司だけではなく、労働組合の分会長からも、懇親会は上長から出席を命じられた場合でも勤務時間には当たらない、と説明を受けています。
自分でも頷けるのは労働局の方で、上司及び組合の考え方は間違っていると確信しています。とはいえ労働局の見解の如何によらず、労働時間を管理し、そこに給与を払うべきかどうかを決定するのは――労働時間を短くカウントしようとしている会社の管理職や組合の方だったりするので、懇親会出席はいつだってサビ残です。
まぁ一般論として出張にかかる移動時間なんかも労働時間にカウントされませんけれど、日の出前に家を出て、日付が変わった後に家に帰ってくる、そんな日程にもかかわらず労働時間にカウントされるのは8時間で残業は0の扱いだったりすると、徒労感は尽きませんね。これも実質的にはサビ残の内に入りそうなものです。
ちなみにサービス残業以外にも「アピール残業」略して「アピ残」とか、ラマダンならぬ「ラマ残」とでも呼ぶべきものが、日本中の職場で存在するのではないかな、とも思っています。つまりは「頑張っています」「たくさん仕事をしています」とアピールするための残業等々。
私の職場でも、毎日チャイムが鳴ると同時に駆け込んでくる人がいます。始業ではなく、終業のチャイムが鳴ると、ですね。時間外にもかかわらず仕事に忙殺されている自分をアピールすべく、終業時間となるや俄に走り出し、周りを巻き込んであれやこれやと打ち合わせのセッティングなどを始めるわけです。彼は努力の甲斐あって、課長に昇進しました。
営業社員のように明確な数値が結果として出てくるのならいざ知らず、非営業社員ともなりますと評価の対象は専ら「心意気」となりがちですので、そうした普通の職場では残業してやる気をアピールするのが出世への最短コースです。仕事は終業のチャイムが鳴ってから、そんな日夜アピ残に励む人々が、管理職として大活躍しています。
一方では日中の飲食を絶つことで苦しみを共にし連帯感を高める、そんな習俗のある宗教もあるわけです。では日本の会社ではと振り返ってみれば、会社に己の時間を捧げるという苦しみを共にすることで連帯感を高める、そんな文化があります。言うなればラマダンならぬ、ラマ残ですね。
なおムスリムのラマダンは特定期間に限られますが、日本の会社のラマ残は――当面のところは終わる様子が見えません。もちろんラマダンがそうであるようにラマ残もまた強制ではないのですが、ラマ残に参加しなければ、異教徒として扱われます。苦しみを共にしてこそ仲間、それが今も昔も変わらぬ家庭的な日本企業の文化ですから。