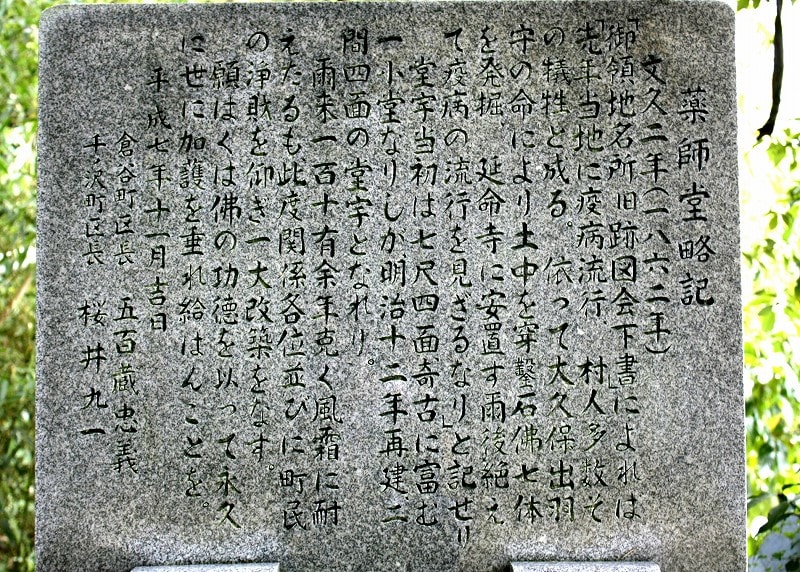哀しい悲話を今に伝える石棺仏です。
やっぱり此処も加古川北岸域、前回紹介の報恩寺から車で約10分足らず、ほんの3km程・・・・。
田園地帯の真ん中に有る見土呂集落の北奥のほう、公民館脇に石仏への小さな案内板が建っている。
車を邪魔にならないように脇に寄せ案内どおり細い通りを少し登ると木立に囲まれた小さなお堂が見える。

お堂の脇の狭い境内にこの石仏を目にして思わず感歎の声を挙げた。
少し前のめりに立つ大きな割りと薄い石棺部材に幽玄とも言おうか、細身で美形の阿弥陀三尊立像が刻まれている。

このように細身で簡略化した像にも係わらず写実的な印象の残る石仏も稀である、そもそも石棺仏で阿弥陀三尊立像と言うのも珍しい。
どこか寂しげに見える顔立ちは、哀しい物語の表示板を読んだせいなのかも??
中央に二重光背を背にして立つ結構厚肉彫りの阿弥陀如来立像、右脇には勢至、左脇には観音と両脇侍を従えている。

<裏に廻るとやっぱり石棺そのものの姿>
石棺は高さ 175Cm 幅 125Cm 厚さ 25Cm も有ってどちらかと言うと正方形に近くかなり大きな印象を持った。
哀しい話は事実なのか?はたまたこの哀しげな石仏に合わせたつくり話なのか??、そんなことは知る由も無いがこの石仏に良く合う話だと・・・。

石仏に手向けられる花は今でも枯れることは無いと言う。
撮影2007.9.13