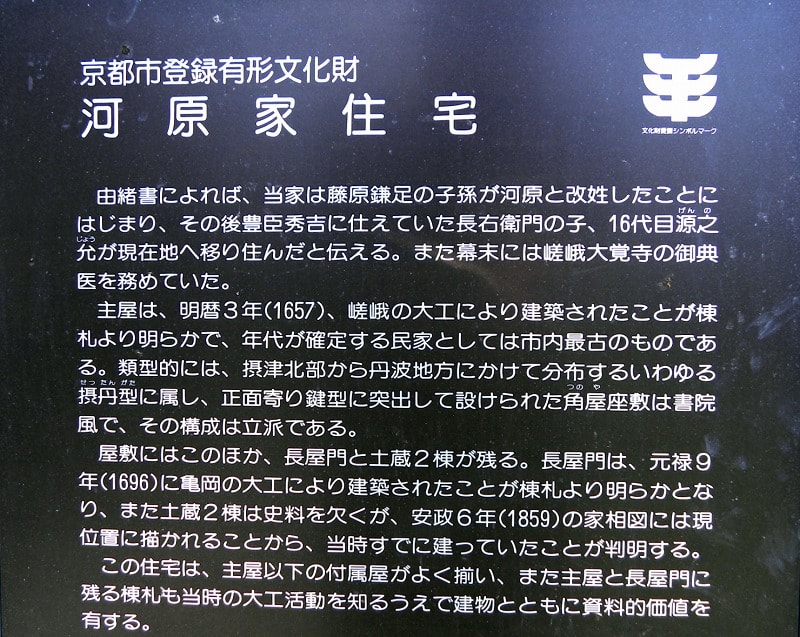我が京都山城には滅多に雪の積もる事など無いのだが・・・今年は年明け早々の元日、夕方近くから激しい雪になり瞬く間に周りを見慣れぬ白い景色に変えてしまった。

気になって表に飛び出すとこの通り・・・思ってもない様な横殴りの雪で景色もぼんやり・・・・・

お向かいさんの茅葺き屋根はどんな塩梅かと・・・・今降り出したばかりなのに、もう少し白く成りだしていた。
夜、9時頃には恐らく聞き始めの大雪警報まで発令され、何事かと少々戸惑う。

しかし夜が明けてみると何てことは無く積雪10cm弱、道路には黒い轍の痕が残り、茅葺き屋根もなんとか白く見える程度。

裏に廻って見てもこんな程度で綿帽子を被ったようにモッコリした雪景の茅葺き屋根には程遠い景観。

山城ではこうして雪をかぶることなど滅多にないから、これほどの雪景でも、やっぱりもの珍しい。
午後1時頃に表に出ると、すっかり雪は溶け、茅葺き屋根は見慣れた元の姿に戻って居た。
撮影2015.1.1~1.2