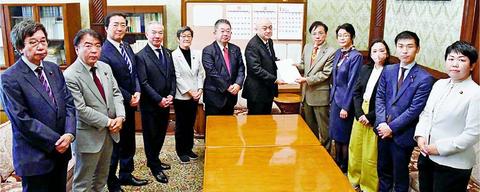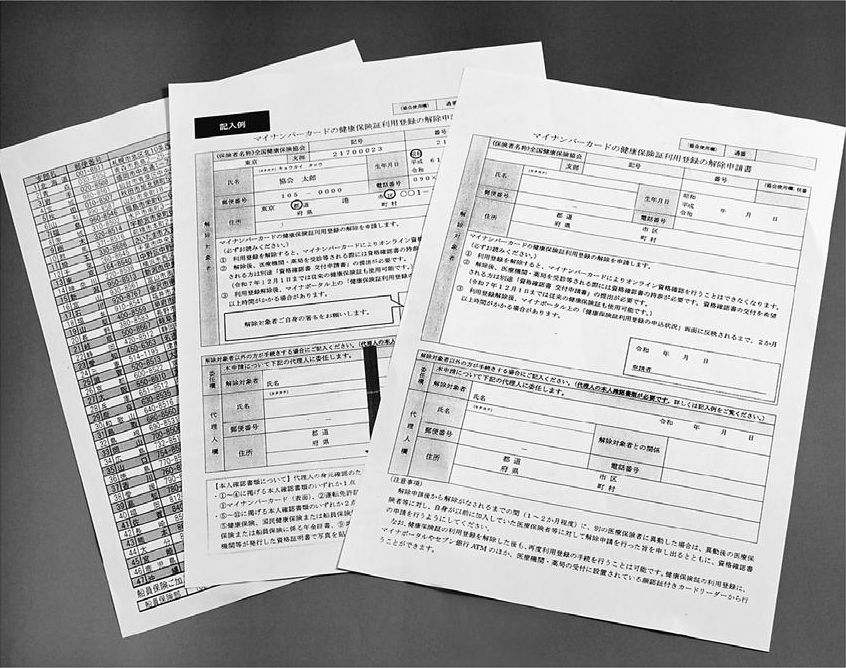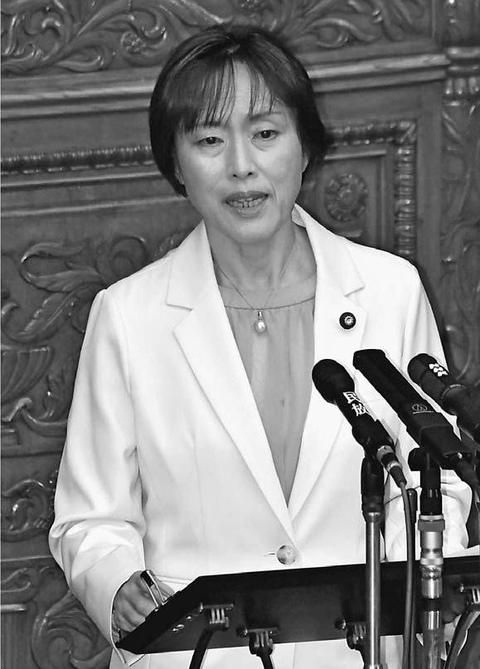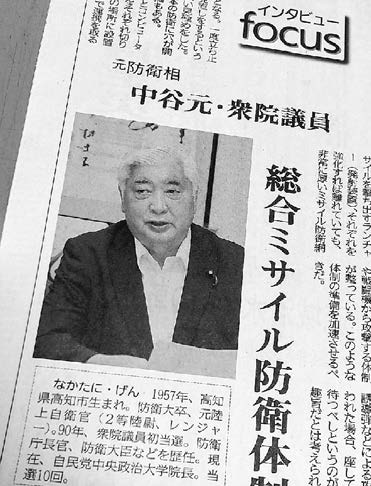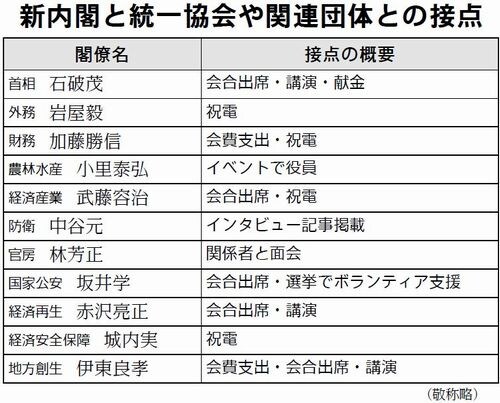2024年12月4日(水)
田村委員長の代表質問 衆院本会議
日本共産党の田村智子委員長が3日の衆院本会議で行った石破茂首相に対する代表質問は次のとおりです。
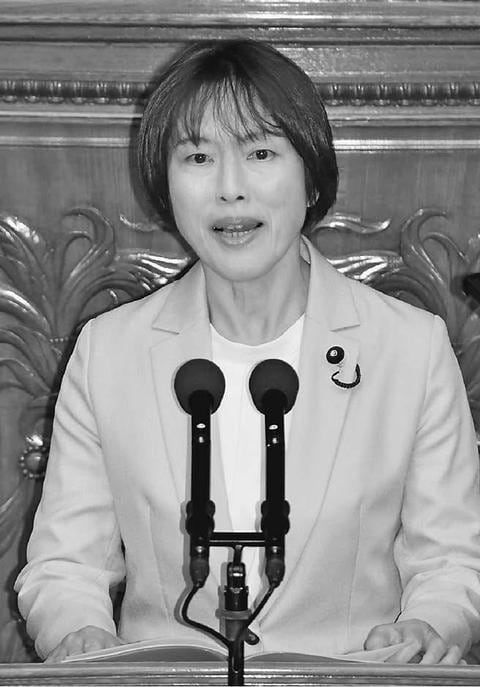 (写真)質問する田村智子委員長=3日、衆院本会議 |
私は日本共産党を代表し、石破総理に質問いたします。
冒頭、能登地域の復旧・復興についてお聞きします。
総理、所信表明演説には、被災者の生活と被災地域の再建への支援策が一言もありませんでした。能登のみなさんは、地震と豪雨により大切なものを失った悲しみ、支援がゆきとどかないことへの怒り、それでも能登に住み続けたいという切実な願いを持ち、先の見えない生活をなんとか打開しようと苦しんでいます。避難生活の改善、医療費など被災者の負担軽減、地震と豪雨という二重の被害の実態に見合った支援の拡充、積雪時の安全と生活の確保など、いま求められている支援を、政府の責任で届けきる、そのために、具体的にどうするのか。お答えください。
裏金真相解明と企業・団体献金の禁止を
総選挙によって、与党が少数の国会となりました。この臨時国会では、選挙で示された民意にどう応えるかが、鋭く問われます。
何よりも、自民党の裏金事件に対する国民の厳しい審判に、総理がどう向き合うのか、その政治姿勢が問われています。
まずお聞きしたいのは、非公認候補者の支部に、自民党本部が振り込んだ2000万円の問題です。これを暴いた「しんぶん赤旗」の報道に、総理は「政党支部に支給したのであり、非公認の候補者に出しているのではない」と説明された。しかし「赤旗」のさらなる調査で、自民党が小選挙区候補を立てていない支部には、支給されていないことがわかりました。総理、これをどう説明しますか。非公認候補への選挙資金としか言いようがないではありませんか。
裏金問題の真相にフタをして「政治改革」を語る資格はありません。総選挙での審判に誠実に向き合い、裏金がいつから、誰の指示で始まったのか、何に使われたのか、総理の責任で真相を明らかにし、国民に説明すべきではありませんか。答弁を求めます。
裏金は、政治資金パーティーで企業から巨額のカネを集めてつくられました。抜本的な再発防止策は、政治資金パーティーを抜け道とした企業・団体献金も、政党・政党支部への企業・団体献金もキッパリと禁止することです。
ところが、総理は所信表明で、このことに一言も触れず、自民党の渡海(紀三朗)政治改革本部長は、「自民党は企業献金が悪で、個人献金が善という立場には立っていない。党内の議論でも企業・団体献金をやめろという人は一人もいない」と述べました。驚くべき無反省ぶりです。総理、そもそも30年前、政治家個人への企業・団体献金は禁止したが、政党支部とパーティー券は温存する抜け道がつくられた。これが利権・腐敗政治を生んできた。それでも企業献金をまだ放置するのですか。
企業は利益を求めるのが当然であり、企業献金は本質的にわいろ性をもちます。主権者である国民が支持する政党に寄付をする、これは、政治に参加する権利そのものです。選挙権をもたない企業が、多額の献金で政治に関与する、これは、国民の政治参加の権利や選挙権を侵害するものではありませんか。
国民一人ひとりに依拠して政治資金をつくってこそ、国民の立場で政治を行う確かな土台となると考えますが、総理の認識をお示しください。
日本共産党は、企業・団体献金、政党助成金をいっさい受け取らず、党員、国民からの個人献金、新聞発行などの事業収入で党運営を貫いています。この活動によって、物価高騰での暮らしの大変さ、中小企業の苦難も、わがこととしてつかむことができると確信するものです。
経済政策の緊急かつ抜本的な改革を
次に経済政策です。
総理は所信表明演説で、30年前との比較で日本経済の落ち込みに言及し、「配当は増え、海外投資も増えた一方で、国内投資と賃金は伸び悩んできた」と述べました。しかし、30年間のほとんどは自民党が経済政策を担い、うち12年はアベノミクス以降です。問われているのは、歴代自民党政権の経済政策そのものです。総理は「大株主への配当は増えたが、賃金が伸び悩んできた」原因と責任がどこにあると考えているのですか。
暮らしと経済を立て直すには、大企業と大株主の利益を最優先する経済政策のゆがみをただす、緊急かつ抜本的な改革こそ必要です。
一つは、大企業の利益が賃金に回らずに、配当、役員報酬、そして巨額の内部留保へと流れてしまう、このゆがみをただすことです。
上場企業1071社の3月決算では、純利益が昨年より20%も増え、大企業は3年連続の史上最高益です。しかし、その利益にふさわしく賃上げが進んだとはとても言えず、その一方で内部留保は、昨年1年間で28兆円増え、539兆円にも膨張しました。内部留保は株主の利益を増やすためには使われ、自社株買いが16兆円に及びます。
大企業は空前の利益、しかし賃上げにも取引企業の単価引き上げにも回らず、巨額の内部留保が毎年積み上がる、多くの労働者は物価上昇に賃上げが追い付かず、暮らしが追い詰められていく――総理、この現状をどう思われますか。
わが党は、大企業の利益が、ただただため込まれるゆがみをただして、労働者の賃金に還流させる政策を提案してきました。内部留保のうちアベノミクス以降の積み増し分に課税し、これを財源として、中小企業の賃上げを大胆に直接支援する、大企業が賃上げに活用する分を控除することで、大企業での賃上げも進めるという政策です。
総理は、政治の責任で内部留保を賃金へと還流させることが必要だと考えますか。そうであるなら、わが党の提案以外に、何か具体的な方策を検討しているのでしょうか。答弁を求めます。
次に税制のゆがみの改革です。税のあり方として、生計費非課税、応能負担という二つの原則が重要だと考えますが、いかがですか。
消費税は、日々の生活、食事の回数を減らすような生活であっても、容赦なく課税する最悪の生計費課税です。生計費非課税の原則にたち、消費税廃止を目指すべきです。せめて、物価高騰が消費税負担を増やしているのですから、緊急の減税を行うことは当然ではありませんか。税制の民主的原則に照らして答弁を求めます。
応能負担原則も、大きくゆがめられています。大企業の税負担割合が中小企業よりも軽い、「所得1億円の壁」をもたらす証券優遇税制、所得税・住民税の最高税率が95年当時から10%下げられたまま――これらを応能負担原則からみて、どう評価しますか。抜本的な見直しが必要ではありませんか。
「103万円の壁」の問題は、こうしたゆがみの一部分であり、生計費非課税の原則に立って、物価高騰・賃上げを超える水準への引き上げが必要と考えますがいかがですか。答弁を求めます。
学生のアルバイト収入が103万円を超えると、保護者の扶養控除がなくなり世帯の収入が減ってしまうという「103万円の壁」。そもそも、学生がアルバイトに追われる生活をせざるをえないことが問題ではありませんか。根本的な解決は、アルバイトをもっと増やせる環境整備ではなく、高すぎる学費を下げ、無償化へと向かい、アルバイトをしなくても安心して学べる環境をつくることではないでしょうか。
ところが、国立も私立も大学授業料値上げが相次いでいます。わが党は、学費値上げを止めるために、大学への緊急助成を政府に要請しました。石破総理も、自民党総裁選で「国立大学授業料を無料に」と掲げました。まず政治の責任で、これ以上の値上げを止めることは当然と考えますがいかがですか。答弁を求めます。
沖縄の民意にこたえ、辺野古新基地は断念を
いま、日米同盟という4文字で思考停止となる政治で良いのかが問われています。端的に2点お聞きします。
一つは、沖縄への姿勢です。
沖縄県民は、名護市辺野古への米軍新基地建設に反対の意思を示しつづけてきました。米兵による少女への性的暴行事件を隠蔽(いんぺい)した政府への怒りも渦巻いています。第2次安倍政権のもとで、自民党幹事長だった石破総理は、沖縄県選出の党所属国会議員を辺野古容認へと態度を変えさせ、「平成の琉球処分」とまで評されました。こうした沖縄に象徴される強権政治に「ノー」の審判を突きつけたのが、総選挙の結果だったのではありませんか。
沖縄県民が自ら米軍基地を受け入れることはあり得ない、軟弱地盤に巨大基地建設は不可能、一体、辺野古新基地はいつ完成するというのでしょうか。辺野古新基地建設を中止し、普天間基地の無条件撤去をアメリカに求める、これこそ、沖縄の基地負担軽減として、直ちに政府がやるべきことではありませんか。
核兵器禁止条約に参加せよ
いま一つは、核兵器問題への姿勢です。
今月10日、日本被団協のノーベル平和賞授賞式が行われます。核兵器の非人道性と、核兵器は二度と使われてはならないことを世界に訴え、約80年にわたり戦争での核兵器使用を許してこなかった、これが授賞理由です。
石破総理は、「核兵器の非人道性を世界に知らせる」と言いながら、一方で「アメリカの核抑止の強化」を主張しています。核抑止とは、いざとなれば核兵器を使用するぞと恐怖を与えることで、相手の攻撃を思いとどまらせるというものです。ましてアメリカは核兵器先制使用の方針を掲げています。「核兵器の非人道性」を批判することと、「アメリカの核抑止の強化」を主張することは、根本的に矛盾するのではありませんか。
被爆者の皆さんの命懸けの訴えによって誕生したのが、核兵器禁止条約です。唯一の戦争被爆国の政府として、被爆者とともに歩む責務があります。核兵器禁止条約への参加を決断すべきです。少なくとも、3月の締約国会議にオブザーバー参加することは表明いただきたい。答弁を求めます。
選択的夫婦別姓の導入について国会での審議を
最後に、ジェンダー平等についてお聞きします。
10月、女性差別撤廃条約にもとづく日本政府のとりくみについて、国連・女性差別撤廃委員会による審査が8年ぶりに行われ、選択的夫婦別姓の導入を求める4度目の勧告が出されました。
総選挙での候補者アンケートによれば、選択的夫婦別姓に圧倒的多数が賛意を示して議員となった、これまでと同じ棚上げは許されません。総理は、参議院での私の質問に「さまざまな意見がある」と答弁された。ならば、そのさまざまな意見を、法案審議の場で国民の前で議論しようではありませんか。
女性差別撤廃条約の批准国の多くが、条約の実効性を強めるため、個人通報制度と調査制度を定めた選択議定書を批准していますが、日本政府は「検討中」のまま四半世紀がたっています。一体いつまで検討するのか、この姿勢が日本をジェンダー平等後進国にしているのではありませんか。答弁を求め、私の質問を終わります。