昨日TCUでキリスト教と福祉研究会がありました。
発題は、岩上敬人先生。
「新約学から見た教会、宣教、福祉のつながり 」
がテーマでした。
イエスさまは、絶えず
- 貧しい人
- 捕らわれ人
- 目の見えない人
- 虐げられている人
- 社会的弱者
に目を向け、
関心を持ち、
彼らの霊的、実際的必要に応え、
愛を実践して来られた。
そしてペテロやパウロにも
それが引き継がれている。
ルカ文書ではそれが顕著。
そしてそれは今日の教会にも
引き継がれているということ。
1974年ローザンヌ誓約以降、
教会の社会的責任ということが叫ばれ、
福音的な教会でももう一度、
そのことに目が向けられることになりました。
ところが現実は…。
教会が社会的な活動をすることに対するアレルギーが、
未だに存続していて、
なかなか乗り出せない、
積極的に社会的な活動をしている教会を裁く、
といった現状があるようです。
残念なことです。
また逆に、
地域社会にコミットし、
社会的なステータスも得、
社会的なステータスも得、
公の援助を受ける中で、
教会としてアイデンティティと、
宣教スピリット、機会を
失ってしまう…、
あるいは自ら放棄するような
現象が起きてしまうのも残念。
今振り返ってみると、
台湾の教会は自然に、
社会とのネットワークの中で、
社会的な責任を果たしていたなと。
貧困家庭をサポートし、
子どもや母子家庭、高齢者に関心を持ち、
学校や社会福祉機構、
キリスト教系の機構、基金を上手に利用し、
彼らを援助していました。
その地域に教会があるというのは、
そういうことだから。
でも、日本の教会だって、
心の病をもった人が教会を訪れ、
話しを聞いてほしいと言えば話しを聞くし、
話しを聞いてほしいと言えば話しを聞くし、
必要なサポートもする。
教会に貧困家庭の子どもが来ていれば、
ご飯を食べさせたり、
できるサポートをしているんじゃないのかな。
ある意味、それが教会本来の自然な姿だから。
そして、その中でも、
時に社会的な活動に重荷を持ち、
賜物と使命感を持った牧師がいれば、
自然とそのような活動に力を入れ、
組織化し、地域との連携の中で、
組織化し、地域との連携の中で、
社会のリソースを活用しつつ、
その活動を広げていくのではないかなと。
構えず、
そのような教会を批判せず、
牧師に水を差すようなことを言わず、
温かく見守ってほしい。
むしろ応援し、サポートしてほしい。
そんなことを思わされた今回の学びでした。
感謝主!
















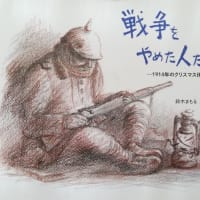
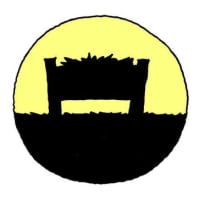








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます