陰謀と幻想の大アジア・海野弘・平凡社
このブログに興味がある方は、ここをクリックして、小生のホームページもご覧ください。
本の大筋は、戦前戦中の日本がユダヤやイスラム、モンゴル、ウラル・アルタイと言った、アジアのみならず中東、中欧の諸民族との提携の模索や研究が深く行われていて、現在の日本の状況は、それらに遥に劣る、という壮大なものである。ウラル・アルタイ=ツラン民族圏と日本の関係や満洲にユダヤ国家を建てる構想など興味深いテーマが並ぶ。しかし所詮、筆者は東京裁判史観や親ソ親中思想に深く毒されていて矛盾が露呈して本論が矮小化されているように思われる。それがなければもっと深い洞察が出来て面白いものになるはずである。
例えば内モンゴルのオロン・スムでスエーデンの探検隊が発掘した遺跡からの出土品が、戦後中国に返還された(P225)と書くが、たとえ内モンゴルは現在中共の領土であるにしても返されるべき相手はモンゴルのはずである。スターリンは強力にモンゴルをバックアップした(P210)といいながら、蒙古連合自治政府というのは、日本の傀儡政権だ(P204)と平然とダブルスタンダードを犯す。ソ連が傀儡政権を作ればバックアップなどというのだ。中共や北朝鮮、東欧のソ連の衛星国などは全て傀儡政権から出発している。
また平然と、日本軍はハルハ河付近で軍事行動を起こした(P209)、とノモンハン事件を起こしたのが日本であると断定しているが、支那事変を戦っていた当時の日本はソ連と紛争を起こす理由はない。そればかりか、もし日本がノモンハン事件で勝っていたら、真珠湾攻撃による対米戦争はあったろうか、とし、ノモンハン事件は日本の南進政策への転機となっている(P210)という馬鹿げたことを言う。要するに戦争の原因は全て日本の都合による、というもので、世界の流れにおける日本の位置というものは考えもしない。まさに東京裁判とGHQがたくらんだ、日本罪悪史観に見事に洗脳されている。この本のテーマが、せっかく日本と多くの異文化の接触の体験という壮大なものであるのに、実にちぐはぐである。
大東亜戦争がアジア諸国の解放をもたらしたという点は否定できない、と言いながら、もし勝っていたらアジアの解放はなかったかもしれない、と書くのは(P258)余計である。日本に勝機があるとしたら、インド独立などのアジア解放が必要だからである。筆者はGHQに洗脳された人間の特色として、西欧に対しては国家エゴは必要で当然であるとしながら、日本の対外行動に対しては完全無欠な自己犠牲の行動でなければ正当化できないと考えるのである。
意外なのは、「以上の例でもわかるように、大東亜戦争における南方謀略工作は単なる日本の謀略、戦略だけではなく、東南アジア諸民族の独立のための地下運動との関係で読み直すべきではないだろうか。」と書いている事だ。当然ではないか。日本が東南アジア解放を目指したのは、日本のためだったのは当然ではあるが、それが独立運動と連携することなしに成功するはずがないし、成功したのである。たとえ国家エゴを内包していたとしても日本はアジア解放という歴史的できごとを為したのである。日本では産業革命を讃えるが、それは西洋人が純粋に金儲けをしたいと言う動機と知的好奇心が一致したものである。産業革命と呼ばれるようになったのは結果であって目的ではない。しかし一方で、生産物を輸出し原材料を奪うためにアジア・アフリカ地域を植民地化し、その混乱は特にアフリカでは収まっていないと言う甚大な悪を為したことも忘れてはならない。日本人は産業革命の陰の部分に無邪気過ぎる。
また、ジョイス・C・レブラの「チャンドラ・ボースと日本」の序で「日本の歴史家たちは、東南アジアにおいて日本が大東亜共栄圏に托した理念、実現の方法などを吟味することに今まで消極的であった」と書いている事を紹介している。この文言を著者は、モンゴル研究や満洲イスラエル構想など、日本が過去に広くアジアで行った事績を忘れ去った、という平板な意味で捉えようとしている節があるのだが、もっと素直に読むべきであろうと思う。いずれにしても、著者の戦前に対する捉え方の振れが大き過ぎてせっかくの着想が「日本帝国主義」という悪罵で矮小化しているように見えるのは残念である。
モンゴルに作られた西北研究所について、かの梅棹忠夫が著書で、敗戦直前にモンゴルで純粋でアカデミックなのんびりした研究ができたことを懐かしく回想している事に対して、日本がモンゴルに「純粋にアカデミックな研究所」を作ったと梅棹は本気で信じていたのか(P200)と批判している。さらに1981年にかの地を再訪した梅棹が、なつかしさをのどかに記しているのに対して、この感傷旅行には、戦争はまったく影を落としていない(P204)とも書く。梅棹は戦争責任について反省すべきだと言うのだ。同じ時期に同じ研究所で働いた磯野氏の妻が戦後の感想で「西北研究所の楽しき日々は、日本帝国主義に守られていたものであった」という主旨のことを想い、夫はそれに強い痛みを感じていた(P205)のに梅棹にはなぜかみられないという。筆者は戦前と戦後の梅棹の姿勢が一貫している事をタフだと批判するのだが、私には世間の風潮に迎合しない一貫した梅棹の姿勢が素晴らしく思われる。
この研究所が日本帝国主義の先鋒であったなどという者に限って、日本が勝っていれば平然と別な事を言うのだ。磯野氏は現実にモンゴルで研究をしていた当時その痛みを感じていたのかどうか疑問に思う。戦後世間が変わったから痛みを感じているのではないか。現に筆者は、戦前転向し、戦後再度転向した人物を、何の説明もなく転向し、しかも世間もそれを黙って受け入れたと批判しているではないか。要するに世間は迎合するものは批判しないのである。家永三郎は戦後のある時期まで典型的な「皇国史観」の論者であった。ところが何の説明もなく転向し皇国史観批判を行ったのに、多くのマスコミは絶賛する。何と典型的な転向者の家永を一貫した信念の持ち主と持ち上げるマスコミすらあるのだ。
最後に興味深い記述をひとつ。日露戦争で日本が勝利するとソ連からイスラム系トルコ人が日本に亡命し、「かれらは主としてイディル・ウラル・トルコ人に属し、タタルと俗称されてゐるものである」「いわゆる白系露人といわれたのは大部分、この〈タタール人〉であったらしい」(P178)という。満洲にも白系露人が亡命して住んでいた話があるが、タタール系と言われる人たちなら納得できる。



















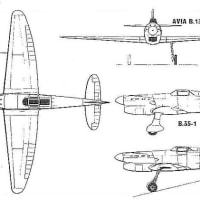
私は中国語が話せませんが、戦前の方が大陸浪人みたいな中国やアジアでもいつでも生きて行ける日本人が沢山いて視点がアジアに向いていたように感じています。
戦前の日本人の語学力は、現地人と間違えられるほどの人が大勢いたそうですから。我々は狭い史観に囚われているのですね。