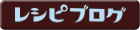久しぶりに、大学時代の同級生と週末に会ってきました。
年に数回会っているのですが、私以外は皆さん子持ち。
よって、事前に日にちを調整して集まるだけでも大変なのですが、まだ全員就学前児童さまなので外でランチというわけにも行かず、持ち回り的に各自宅でポットラックをしています。
よって、いつもどおり持参品の製作です。
前回はバックリブを焼き、その前はチーズケーキとかぼちゃグラタンでした。
今回は、スタッフド・ポークロインとクラブ・キッシュを持参することに。
どちらも御用達書のレシピを参考にしました。









まず、スタッフド・ポークロインの製作過程から。
最初にフィリングから作り始めます。
鍋にレーズン、ドライアップル、三温糖、玉ねぎのみじん切り、しょうが、マスタードシード、オールスパイス、カイエンヌペッパー、アップルサイダー、リンゴ酢、を加えて煮立たせます。
生のリンゴではなく、ドライフルーツを使うと煮込んでも形が崩れにくく、食感が失われないので、詰め物としてのボリュームを保つことができます。
味の面でも、ドライフルーツの方が甘みも酸味を強く出るためお勧めです。


煮立ったら蓋をして弱火でドライ・アップルが柔らかくなるまで20分程度煮込みます。

今回はかなりレシピに忠実に材料を準備。サイダーやドライリンゴなど、普段なら代用品で適当に賄うところですが、今回は輸入食品店で見つけ出して、珍しくほぼレシピどおりの製作過程を踏みました。代用したのは、クランベリーぐらいでレーズンで代用しました。砂糖はドライリンゴに砂糖がまぶしてあったので量を減らしましたが。。。。
さすがにスケールはパーティ用に作ったとは言え、1/2としました。


リンゴが柔らかくなったらザルで固形物と煮汁を分けます。できるだけ水分を搾り出すために、固形物をスプーンの背でザルに押し付けて水気をきります。






固形物の方はフードプロセッサーに入れて荒みじん切りにします。
小器に移し、冷蔵庫に入れて肉に詰め込むまで冷ましておきます。


煮汁の方は鍋に戻して、中火でとろみとツヤが出るまで煮詰めて取り出しておきます。これは最後に肉表面に塗って、カラメル化させるグレーズ用。
フィリングができたら豚肉の準備。
今回は豚ロース肉の塊を使いました。
御用達書によれば、詰め物をする塊肉は同じロース肉でもカットの違いで"向き・不向き"があるため、購入する際には注意するようにとのこと。
つまり、フィリングをする場合は肉の幅が必要で、ヒレ肉のように細長いものよりも大判型の肉が開いた際に詰め物をする表面積が増えるため適しているようです。

よってヒレ肉の方がローストしても柔らかく、仕上がりが良いのですが、フィリングの面から考えて今回は断面の大きいロース肉を使うことに。





ロース肉の側面から包丁を入れて、かつらむきの要領で1.2cm厚で切り開いていきます。


開いた肉に塩を振り、冷やしておいたフィリングを散らしてのせます。
巻き終わり部分になる端は2cmほどフィリングを乗せないようにします。



包丁で切り終わりになった端側からしっかりと肉を巻き込んでいきます。




まきおわったら脂身部分を上にして2.5cm間隔でタコ糸で結わえて成形します。
肉の外側全体に塩をまぶしてから、脂身側を上にして170度のオーブンで1時間焼きます。
焼いている途中で表面が焦げそうになったらアルミホイルをかぶせて焼き色は調整します。
焼き上がりの目安は内部温度。

中心部分に温度計を差し込んで60度程度になっていたらO.k.。予熱と最後の仕上げ焼きで火がふんわりと通ります。

一度オーブンから肉を取り出して、煮詰めた煮汁を肉の表面に塗りつけて、再度オーブンに入れてカラメルが肉に照りとツヤを与えるまで5分間焼きました。

肉を取り出して、アルミホイルにふんわりと包んでこのまま1時間程度休ませて完成。
ちょうど休ませ時間の間に、友人宅へ移動しました。


フィリングを巻き込んだときは肉の断面積が大きすぎないかと心配しましたが、焼くとかなり縮むので出来上がりはちょうどいい感じ。
フィリングは表面積が大きかったせいもあるのか、やや少なかった感が。
以前に作ったスタッフドポークロインはロースト用のレシピで作ったため、肉を事前に塩水につけておきましたが、今回はなにも下準備せずにグリルするレシピを試してみました。
塩水につけた方が多少柔らかく焼きあがったように思いますが、今回のポークロインでも固さはあまり気にならなかったです。今回の方が薄く切り開くので肉の厚みをしては薄くなるからかもしれませんね。パサツキもあまりなく、甘いフィリングよくあっておいしかったです。
前回よりも断面が大きいので薄めにきっても十分ボリュームもあり、こちらの方が見栄えはしておもてなしには良かったです。
もう一品は"クラブ・キッシュ"。
もちろんキッシュ生地から作ってみました。この製作模様は次回に。
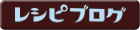
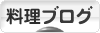
 にほんブログ村
にほんブログ村
年に数回会っているのですが、私以外は皆さん子持ち。
よって、事前に日にちを調整して集まるだけでも大変なのですが、まだ全員就学前児童さまなので外でランチというわけにも行かず、持ち回り的に各自宅でポットラックをしています。
よって、いつもどおり持参品の製作です。
前回はバックリブを焼き、その前はチーズケーキとかぼちゃグラタンでした。
今回は、スタッフド・ポークロインとクラブ・キッシュを持参することに。
どちらも御用達書のレシピを参考にしました。









まず、スタッフド・ポークロインの製作過程から。
最初にフィリングから作り始めます。
鍋にレーズン、ドライアップル、三温糖、玉ねぎのみじん切り、しょうが、マスタードシード、オールスパイス、カイエンヌペッパー、アップルサイダー、リンゴ酢、を加えて煮立たせます。
生のリンゴではなく、ドライフルーツを使うと煮込んでも形が崩れにくく、食感が失われないので、詰め物としてのボリュームを保つことができます。
味の面でも、ドライフルーツの方が甘みも酸味を強く出るためお勧めです。


煮立ったら蓋をして弱火でドライ・アップルが柔らかくなるまで20分程度煮込みます。

今回はかなりレシピに忠実に材料を準備。サイダーやドライリンゴなど、普段なら代用品で適当に賄うところですが、今回は輸入食品店で見つけ出して、珍しくほぼレシピどおりの製作過程を踏みました。代用したのは、クランベリーぐらいでレーズンで代用しました。砂糖はドライリンゴに砂糖がまぶしてあったので量を減らしましたが。。。。
さすがにスケールはパーティ用に作ったとは言え、1/2としました。


リンゴが柔らかくなったらザルで固形物と煮汁を分けます。できるだけ水分を搾り出すために、固形物をスプーンの背でザルに押し付けて水気をきります。






固形物の方はフードプロセッサーに入れて荒みじん切りにします。
小器に移し、冷蔵庫に入れて肉に詰め込むまで冷ましておきます。


煮汁の方は鍋に戻して、中火でとろみとツヤが出るまで煮詰めて取り出しておきます。これは最後に肉表面に塗って、カラメル化させるグレーズ用。
フィリングができたら豚肉の準備。
今回は豚ロース肉の塊を使いました。
御用達書によれば、詰め物をする塊肉は同じロース肉でもカットの違いで"向き・不向き"があるため、購入する際には注意するようにとのこと。
つまり、フィリングをする場合は肉の幅が必要で、ヒレ肉のように細長いものよりも大判型の肉が開いた際に詰め物をする表面積が増えるため適しているようです。

よってヒレ肉の方がローストしても柔らかく、仕上がりが良いのですが、フィリングの面から考えて今回は断面の大きいロース肉を使うことに。





ロース肉の側面から包丁を入れて、かつらむきの要領で1.2cm厚で切り開いていきます。


開いた肉に塩を振り、冷やしておいたフィリングを散らしてのせます。
巻き終わり部分になる端は2cmほどフィリングを乗せないようにします。



包丁で切り終わりになった端側からしっかりと肉を巻き込んでいきます。




まきおわったら脂身部分を上にして2.5cm間隔でタコ糸で結わえて成形します。
肉の外側全体に塩をまぶしてから、脂身側を上にして170度のオーブンで1時間焼きます。
焼いている途中で表面が焦げそうになったらアルミホイルをかぶせて焼き色は調整します。
焼き上がりの目安は内部温度。

中心部分に温度計を差し込んで60度程度になっていたらO.k.。予熱と最後の仕上げ焼きで火がふんわりと通ります。

一度オーブンから肉を取り出して、煮詰めた煮汁を肉の表面に塗りつけて、再度オーブンに入れてカラメルが肉に照りとツヤを与えるまで5分間焼きました。

肉を取り出して、アルミホイルにふんわりと包んでこのまま1時間程度休ませて完成。
ちょうど休ませ時間の間に、友人宅へ移動しました。


フィリングを巻き込んだときは肉の断面積が大きすぎないかと心配しましたが、焼くとかなり縮むので出来上がりはちょうどいい感じ。
フィリングは表面積が大きかったせいもあるのか、やや少なかった感が。
以前に作ったスタッフドポークロインはロースト用のレシピで作ったため、肉を事前に塩水につけておきましたが、今回はなにも下準備せずにグリルするレシピを試してみました。
塩水につけた方が多少柔らかく焼きあがったように思いますが、今回のポークロインでも固さはあまり気にならなかったです。今回の方が薄く切り開くので肉の厚みをしては薄くなるからかもしれませんね。パサツキもあまりなく、甘いフィリングよくあっておいしかったです。
前回よりも断面が大きいので薄めにきっても十分ボリュームもあり、こちらの方が見栄えはしておもてなしには良かったです。
もう一品は"クラブ・キッシュ"。
もちろんキッシュ生地から作ってみました。この製作模様は次回に。