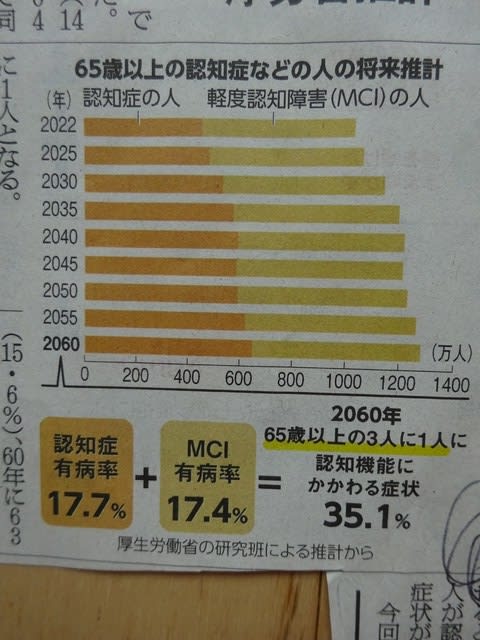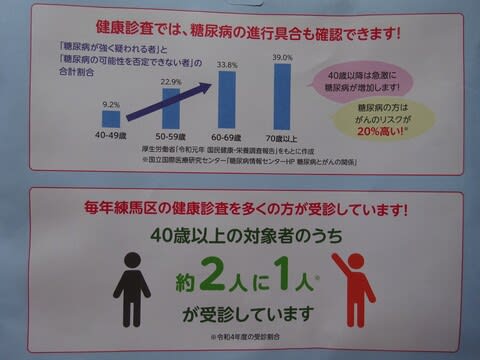(冒頭写真は、原左都子23歳頃に医学関連企業にて 鏡検(顕微鏡を覗く)作業を頑張っていた時代に同輩が撮影してくれた写真。)
本日のエッセイは、2024.06.10付朝日新聞夕刊記事 「ぶらっとラボ・2種類の照明でみる顕微鏡」より引用する。
早速、当該記事の本文を以下に要約引用しよう。

(阪大などの研究チームが開発した、細胞の内部まで観察できる顕微鏡の写真。 いつものことながら、どういう訳か写真が縦にならないことをお詫びしておきます。)
大阪大学吹田キャンパス・工学部ナノフォトニクス研究室に、新たなタイプの顕微鏡ばあると聞いて尋ねた。 なんでも、複雑な細胞の内部まで見られると言う。
以前から光学顕微鏡を使えば、細胞を生きたまま観察することが出来た。 しま状の光を当てる「構造化証明顕微鏡で、細胞内の構造や動きまで見られるようになっている。
それでも、厚みのある資材の場合、不要な光が混じることで、ぼやけてしまい、内部の細かな観察をすることは難しかった。
そこで辿りついた解決策の一つが、シート状の照明の活用だ。 さらに、発行状態を切り替えられる「傾向たんぱく質」を使う手法を開発した。
L字型の片方の装置ではシート状の照明を、もう片方からは構造化照明を当てるしくみで、これまでに研究室が培ってきたノウハウを詰め込んだ。(中略)
球状になった細胞のかたまり「スフェロイド」の内部まで細かく観察できた。 臓器に似せた組織「オルガノイド」の観察などへの活用も期待される。
現在の装置は操作が複雑で、扱える人が限られるのが弱点だ。 研究者は、「よくある顕微鏡のように、誰でも観察できるタイプも開発中です」と意気込む。
(以上、朝日新聞記事「ぷらっとラボ」より一部を引用たもの。
一旦原左都子の感想と見解だが。
冒頭写真で私が顕微鏡を通して観察している対象も、「細胞」だ。
もう少し詳しく述べるならば、「ヒトの免疫細胞(T細胞、B細胞及びそのサブクラス」の分類・観察によるヒト血液中のそれらのパーセンテージの定量測定をこのラボ(実験研究室)で私は日々担当していた。
免疫細胞は、その種類によりそれぞれ特徴がある。
例えば、T細胞は“何故か”羊の赤血球”とくっついたり(ロゼット形成との表現をしていたが)。 あるいは T細胞の種類の一つであるサプレッサーT細胞は、羊の赤血球に加えてニワトリの赤血球もくっつける、なる特質が既に研究されていた。
B細胞に関して我が記憶に頼って表現すると。 こちらは細胞表面に免疫抗体の受容体があり、それが免疫グロブリンに対する抗体を引き寄せる現象を蛍光顕微鏡を使用してそれらのパーセンテージを求めれば、T細胞同様にある程度のヒトの体内のB細胞数を定量できたものだ。
それらの特徴を活かして、それらのサブポピュレーションの定量試験をおこなったものだ。
この鏡検(顕微鏡を覗く)作業の経験がおありの方はご存じだろうが。
特に、私が過去に扱っていた生の細胞等の画面上で動く対象物を鏡検するのは、並大抵のことではなかった。
慣れないうちは、まるで「車酔い」のような症状が誰しも出たものだ。
この私もその一人だったが、とにかくほとんどの研究者がこの作業には難義させられたものだ。
ところが経験を積むほどにその作業に慣れるもので、この私など気が付けばずっと1.5を誇っていた我が効き目である右目の視力が0.7まで下がった… その後も執拗に当該業務を続行していると、不思議と車酔いの症状が無くなるのだ… それが無くなった後も数年この業務を続行したと記憶している。
(参考だが 今尚我が右目視力は0,7なのだが、これが不思議! このお陰で我が右目の老眼化が阻止されていて。?!?! 有難い事に、私は高齢域に達した今も「老眼鏡知らず」の身だ!!)😁 😶 😷
最後は、話題が大いにズレたが。
冒頭の話題に戻すと。
大阪大学の研究者たちによる「構造化照明顕微鏡」の開発研究は、今後更なる素晴らしく目覚ましい医学や理学方面の発展をもたらすことであろう。
今度機会があれば、その顕微鏡を一度覗かせていただきたい気もするなあ。