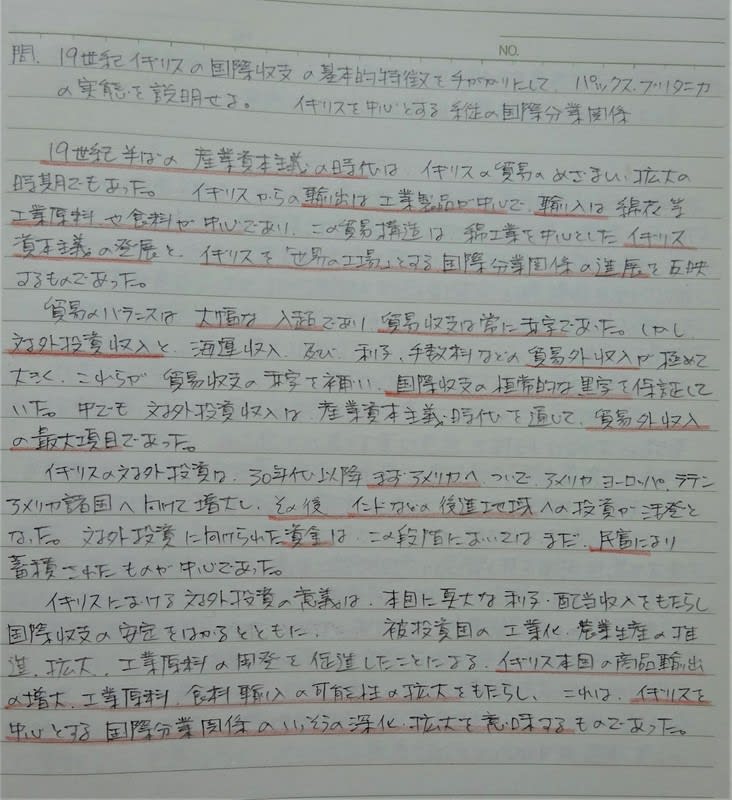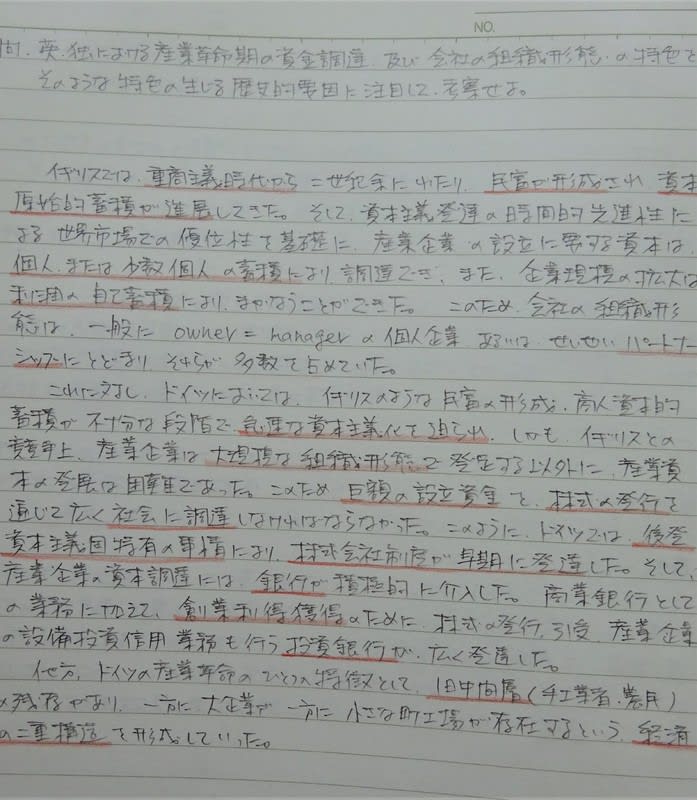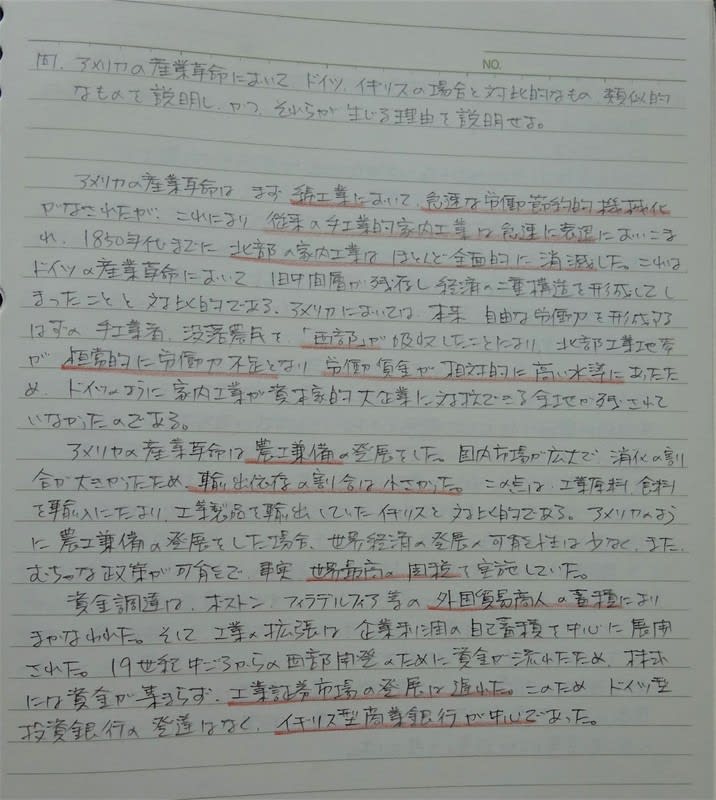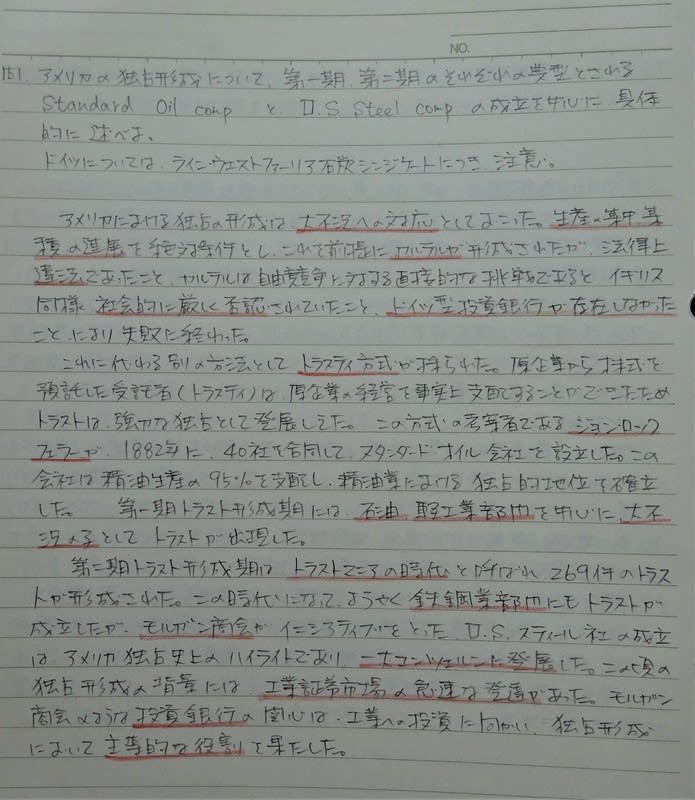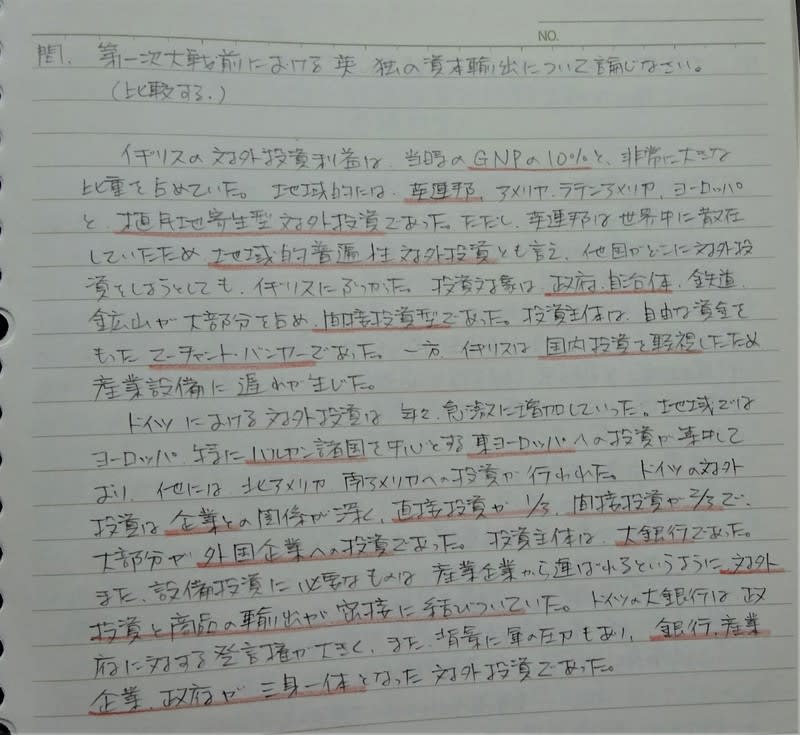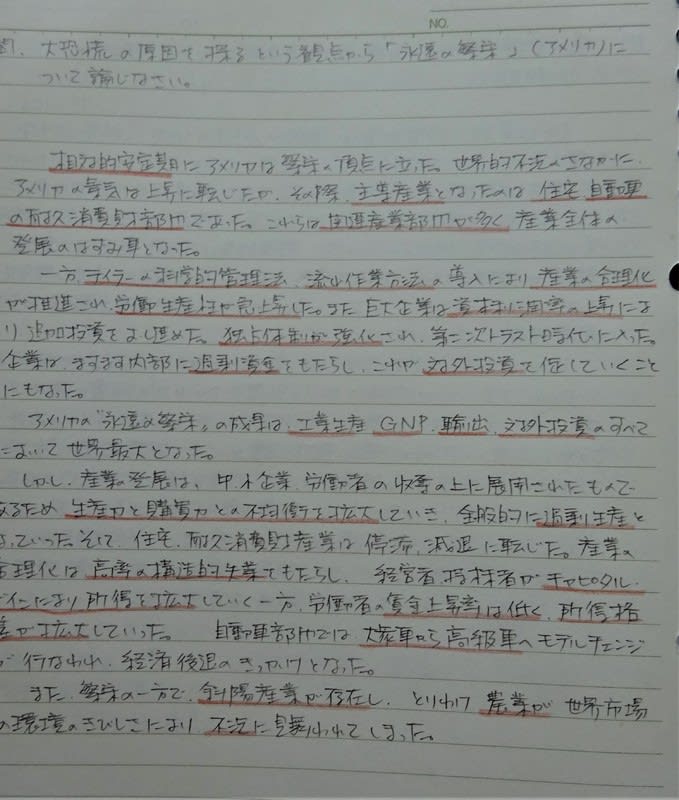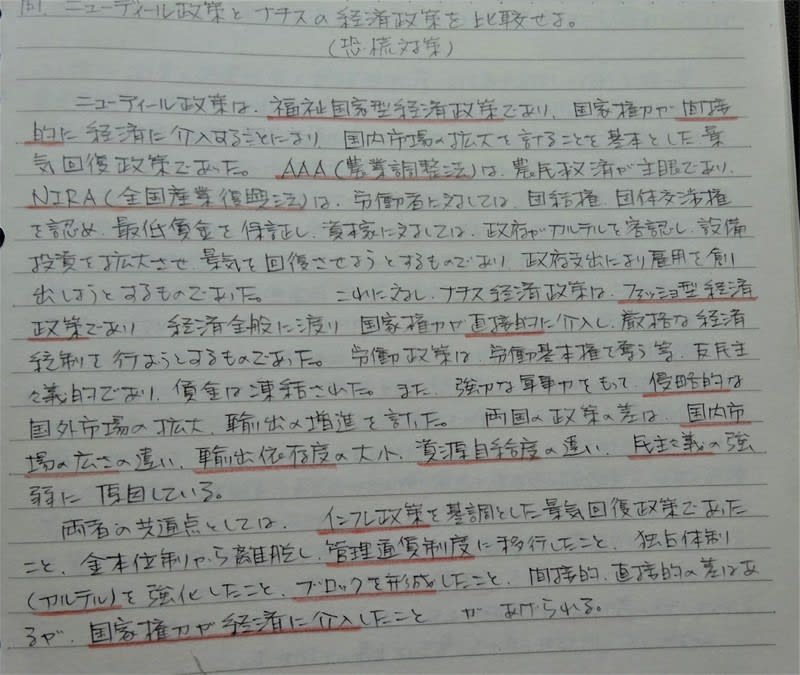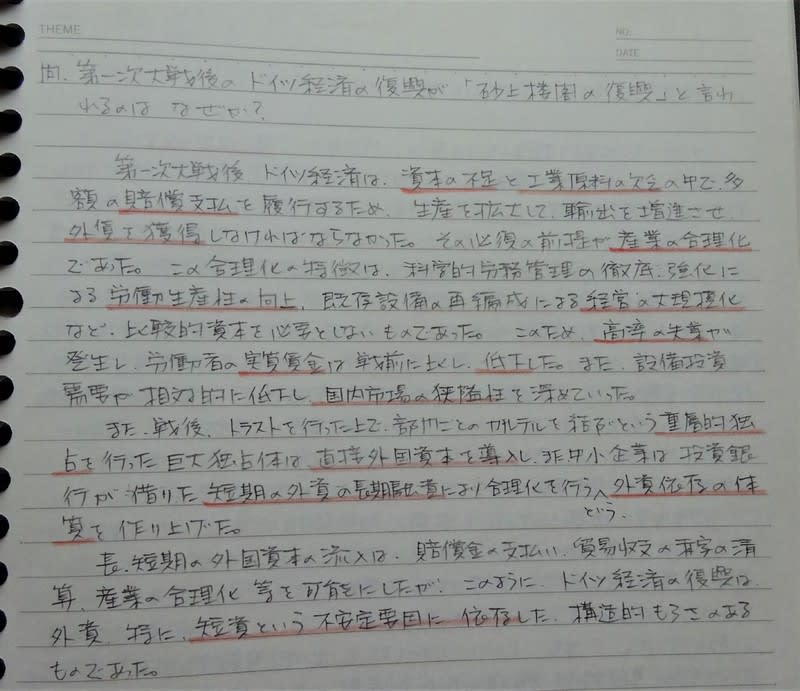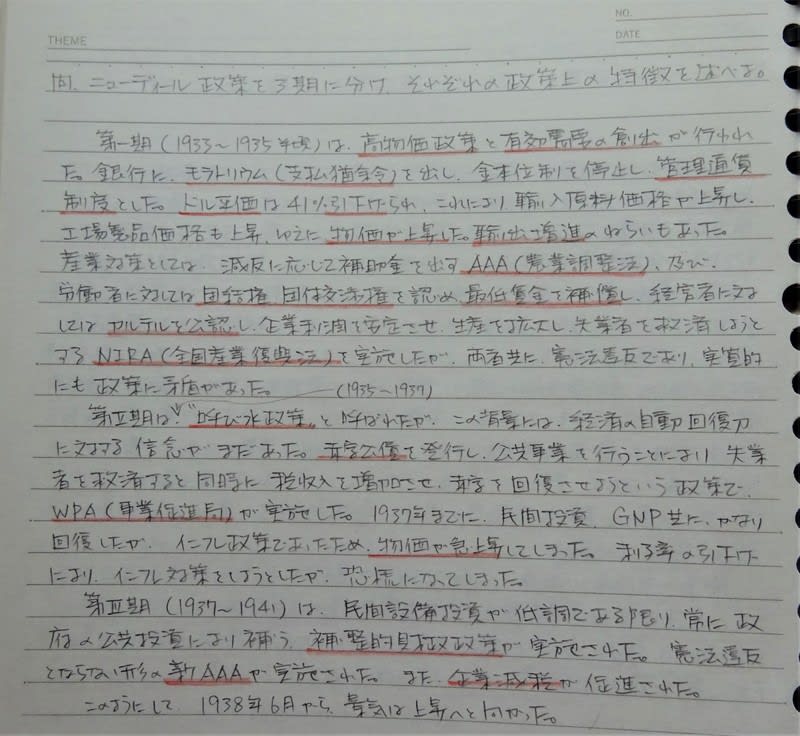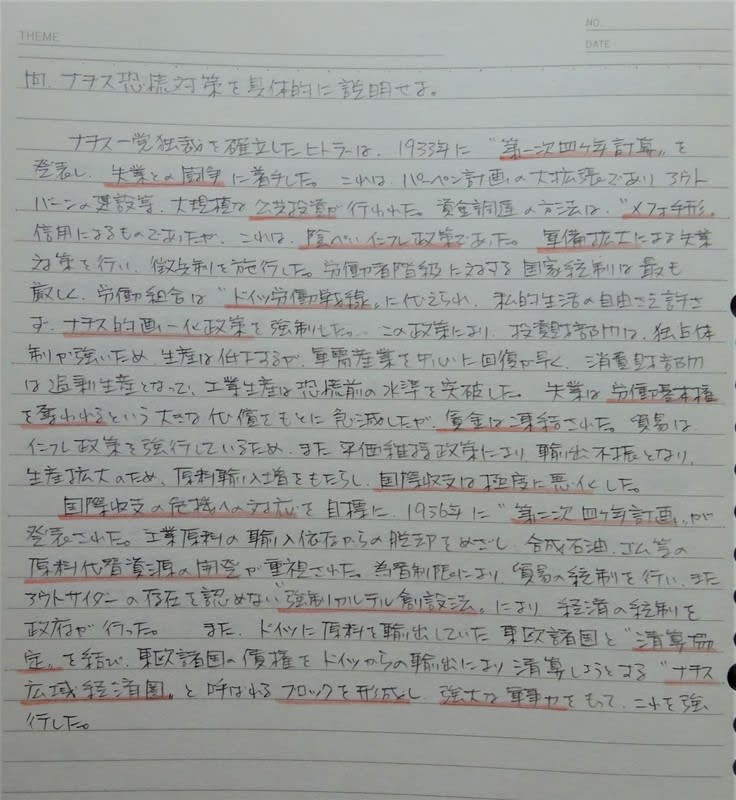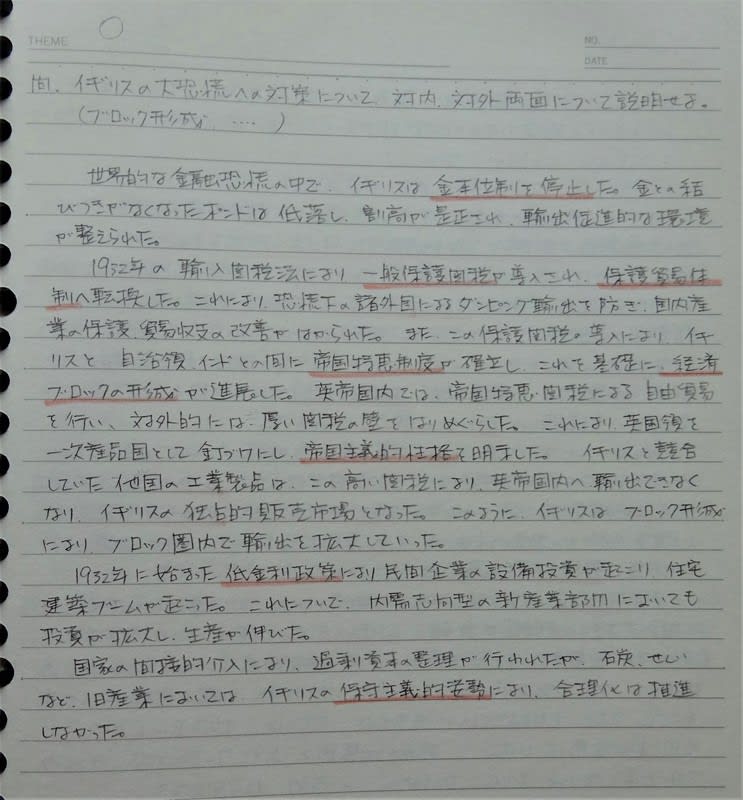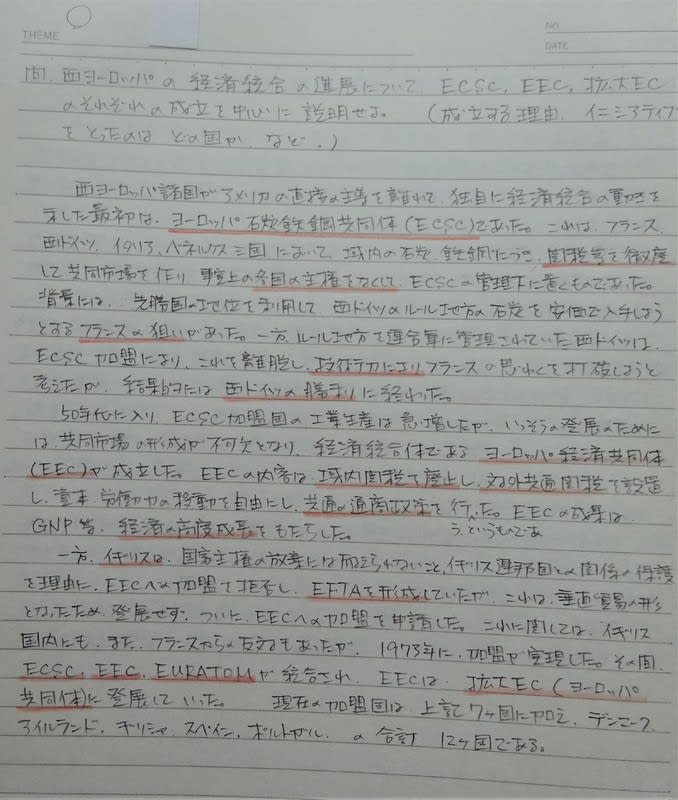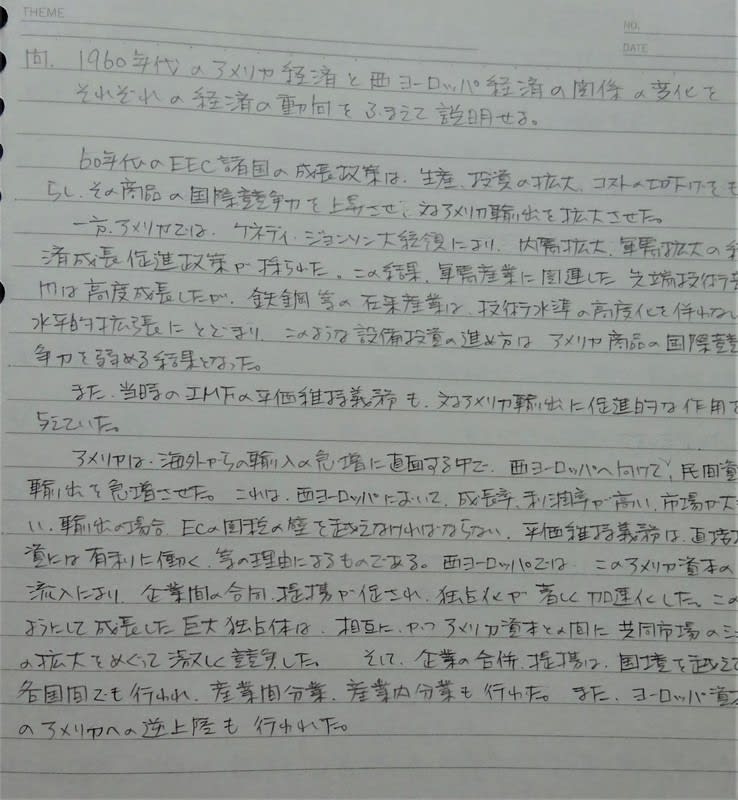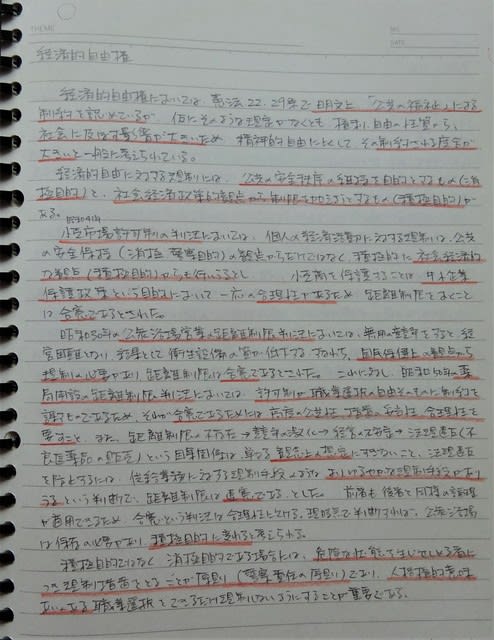(冒頭写真は、我が2度目の大学の講義ノート「法学概論」より転載したもの。)
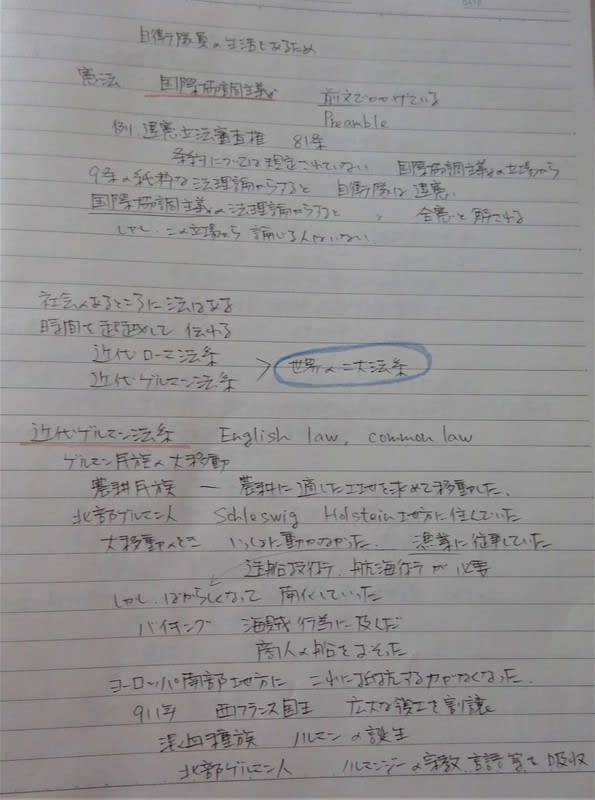

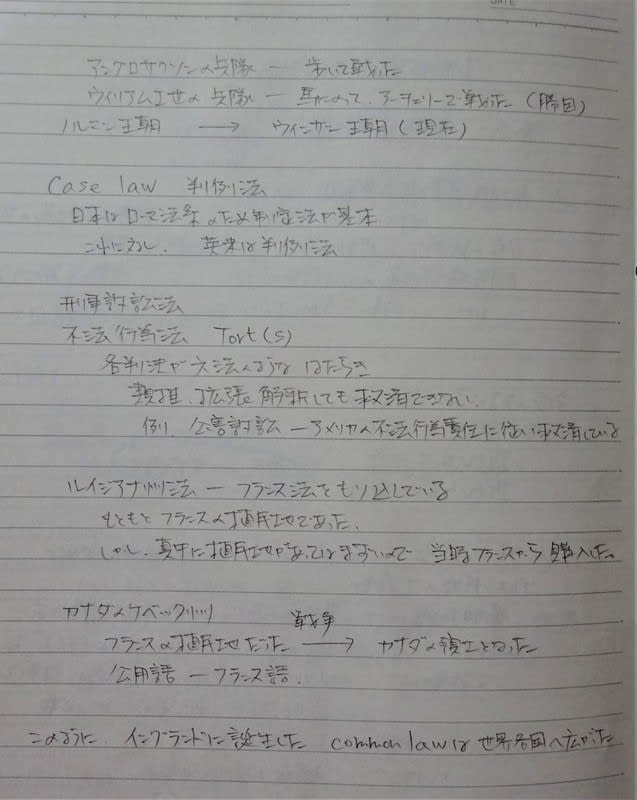
冒頭写真ページの講義テーマは「権利とは何か?」である。
我が「左都子の市民講座」カテゴリー内にも、同名のテーマエッセイが存在する。
それを以下に引用させていただこう。
今回の「左都子の市民講座」では、“権利”について考えてみましょう。
○権利と利益との違い
権利とは、人が単に自分の利益を主張することであろうか?
例えば、誘拐犯が人質と引き換えにお金を要求することが権利であろうか?
そんな訳はない。
↓
相手方がその要求の“社会的妥当性”を承認し、その要求に応じる義務を
認めた場合に初めてその利益は権利となる。
要するに、権利とは
“私的利益”や“生活要求”を基礎とするが、それにとどまらず
“社会的正義”としての“公的性質”をおびたものとして
“普遍的”に承認された利益内容のことをいう。
○権利成立の条件
権利が成立するための基礎的条件、前提は何か?
①平等性
個人対個人の関係が平等な社会であること
例:戦前の日本は身分制社会であったため権利が成立する
社会的基盤は存在しなかった。
↓
戦後、日本国憲法が“法の下の平等”をうたい身分制社会は
解体された。
↓
しかし、例えば、男女差別、外国人差別等深刻な差別問題は
社会の中に根強く残っている。
↓
真の権利社会を成立させるためには、まず差別をなくし、
平等についての基礎観念を確立する必要がある。
②対立性
権利は、個人対個人、あるいは個人対国家の関係が対立関係に
あることを前提とする。
法的な対立関係がない場合、もともと権利を問題にする必要がない
例 : 夫婦間で財産の所有権の帰属が問題となるのは
離婚など、夫婦に利害の対立が生じた場合である。
③社会的正当性についての合意
当事者の一方の利益の正当性が相手方によって承認され
両者の間に合意が成立することが前提となる。
↓
権利を主張する人は、その正当性を相手にわかってもらうように
説得する必要がある。
↓
その結果、対立している両者の“平和的共存”のルールとしての
権利が確立する。
例 : 嫌煙権問題
喫煙者には煙草を吸う権利がある。
しかし、他人に害を与えることは許されない。
↓
他人に害を与えないように喫煙者を義務付けること
により、嫌煙権は成立する。
(ただこの問題は、実際上解決策が困難な問題である。)
④利益の範囲の確定
誰が誰に対し、どのような利益を、なぜ、どの範囲まで主張する
ことが正当であるのかが、論理的に確定されることが前提となる。
日本の社会はもともと義理人情の世界だった。
↓
近年、急激に日本の社会は移り変わり、
人と人とのかかわりが希薄化していく中・・・
↓
日本経済や政治をめぐる資本と権力との癒着、汚職は
相変わらずはびこり…
残念ではあるが、日本の社会はいまだ“権利社会”と言えるには程遠い…
○権利と利益との違い
権利とは、人が単に自分の利益を主張することであろうか?
例えば、誘拐犯が人質と引き換えにお金を要求することが権利であろうか?
そんな訳はない。
↓
相手方がその要求の“社会的妥当性”を承認し、その要求に応じる義務を
認めた場合に初めてその利益は権利となる。
要するに、権利とは
“私的利益”や“生活要求”を基礎とするが、それにとどまらず
“社会的正義”としての“公的性質”をおびたものとして
“普遍的”に承認された利益内容のことをいう。
○権利成立の条件
権利が成立するための基礎的条件、前提は何か?
①平等性
個人対個人の関係が平等な社会であること
例:戦前の日本は身分制社会であったため権利が成立する
社会的基盤は存在しなかった。
↓
戦後、日本国憲法が“法の下の平等”をうたい身分制社会は
解体された。
↓
しかし、例えば、男女差別、外国人差別等深刻な差別問題は
社会の中に根強く残っている。
↓
真の権利社会を成立させるためには、まず差別をなくし、
平等についての基礎観念を確立する必要がある。
②対立性
権利は、個人対個人、あるいは個人対国家の関係が対立関係に
あることを前提とする。
法的な対立関係がない場合、もともと権利を問題にする必要がない
例 : 夫婦間で財産の所有権の帰属が問題となるのは
離婚など、夫婦に利害の対立が生じた場合である。
③社会的正当性についての合意
当事者の一方の利益の正当性が相手方によって承認され
両者の間に合意が成立することが前提となる。
↓
権利を主張する人は、その正当性を相手にわかってもらうように
説得する必要がある。
↓
その結果、対立している両者の“平和的共存”のルールとしての
権利が確立する。
例 : 嫌煙権問題
喫煙者には煙草を吸う権利がある。
しかし、他人に害を与えることは許されない。
↓
他人に害を与えないように喫煙者を義務付けること
により、嫌煙権は成立する。
(ただこの問題は、実際上解決策が困難な問題である。)
④利益の範囲の確定
誰が誰に対し、どのような利益を、なぜ、どの範囲まで主張する
ことが正当であるのかが、論理的に確定されることが前提となる。
日本の社会はもともと義理人情の世界だった。
↓
近年、急激に日本の社会は移り変わり、
人と人とのかかわりが希薄化していく中・・・
↓
日本経済や政治をめぐる資本と権力との癒着、汚職は
相変わらずはびこり…
残念ではあるが、日本の社会はいまだ“権利社会”と言えるには程遠い…
(以上、「原左都子エッセイ集」より2007.12.05公開エッセイを引用したもの。)
どうやら、我が恩師である「法学概論」指導教授(S先生とする)の「権利とは何か?」の講義とは内容が異なるようだ。 (我が講座は、一体何処から引用したのだろう?? てっきりS先生講義より引用したものと思い込んでいたのだが、原左都子の完全自作だったかもしれない。)
それでは、S先生講義よりの「権利とは何か?」の講義内容の一部を以下に掲載させていただこう。
権利の定義に関する主張
1.法益説
特定の人が一定の利益を供授するために、法が貸してくれる力。(法的保護利益)
貸してくれる力の違いにより権利を分類することが出来る。
〇 人格権 (個人の尊厳)
〇 肖像権、 氏名権、 名誉権、 貞操権
〇 親族権 (親族法、相続法 昔は身分法であり、地位の承継の意味合いがあった。 今は、限定相続、相続の放棄 の権利もある。
〇 社員権 (社員ー 民法上の社団法人を人と同じ扱いとする。→法人
民法34,35条
(以下略)
最後に余談だが、上記写真で紹介しているS先生の講義内に興味深い記述がある。
Bioethics 生命倫理学
日本の大学医学部では、この講義がおかれているところはない。
確かに、我が20代に通った大学医学部では、「生命倫理学」の講義はなかった。
ただ、30代に通った大学の医学部には「生命倫理学」(講義名が多少異なるかもしれないが)の授業があった。
学部を越境してこの私がその授業を受講したため、間違いない。😶