『ドストエフスキイその生涯と作品』の中で埴谷雄高が『悪霊』について論じるとき,この作品の主人公であるスタヴローギンと同時に,キリーロフについて多くを語るのは,当然ながら埴谷が『悪霊』においてキリーロフが重要な登場人物であると考えているからです。多くの登場人物がいる『悪霊』の中で,なぜキリーロフが重要なのかということについては,埴谷はふたつの観点から説明しています。
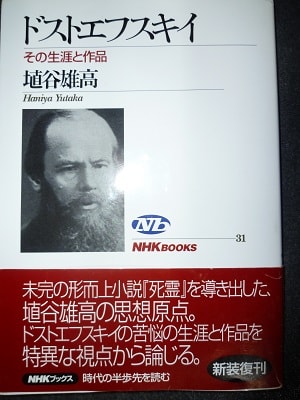
ドストエフスキーの小説の中には,癲癇の発作を起こす人物が少なからず存在します。『悪霊』の中でその役目を与えられているのがキリーロフです。埴谷がキリーロフに注目する理由のひとつがこのことです。
ドストエフスキー自身が癲癇の発作を起こすことがありました。ですから小説の中にもそういう人物が存在するといえるわけですが,このことだけでも発作を起こす人物が小説の中で特別の役割が与えられているといえるでしょう。さらに,これは自身の経験も影響しているのでしょうが,ドストエフスキーが神の似姿として呈示する人物は,癲癇の発作を起こすということがひとつの特徴になっています。ですから癲癇を起こすキリーロフに対して埴谷が注目するのは,当然といえば当然といえます。
さらに埴谷は,キリーロフの癲癇の描写には,たとえば『白痴』のムイシュキンの描写とは異なった面があると指摘しています。ムイシュキンの癲癇の記述が文学的な表現であるのに対して,キリーロフの癲癇の描写は形而上的な把握がなされているというのがその指摘です。僕はこの指摘の是非については追及しませんが,同じように癲癇の発作を起こすのであっても,ムイシュキンの場合とキリーロフの場合とでは,その意味合いには相違があるということは確かだと思います。ムイシュキンの発作は神の似姿ではあり得ても,キリーロフの発作が神の似姿であるとは思えないからです。
まとめると,スペイン語とポルトガル語,ヘブライ語とラテン語そしてオランダ語に関しては,時期は特定できない面はあるものの,それでコミュニケーションをとったり読み書きしたりすることはスピノザにはできたと考えてよさそうです。
一方でスピノザにはそうしたことが不可能だった言語としてはっきりしているのは英語です。ロバート・ボイルRobert Boyleとスピノザの間で直接的に書簡のやり取りが行われず,すべてがオルデンブルクHeinrich Ordenburgを介しているのは,スピノザは英語が,ボイルはラテン語が不得手であったたため,オルデンブルクが通訳する必要があったからだと思われます。また,オルデンブルクに宛てた書簡二十六の中に,もしスピノザが英語に堪能であったら,ボイルが出版した英語の本をホイヘンスChristiaan Huygensはスピノザに貸してくれただろうという主旨のことが書かれていますから,少なくともスピノザは英語が分からなかったということは確定的にいっていいでしょう。
『ポール・ロワイヤル論理学Logique de Port-Royal』はフランス語で書かれたものです。ですから,スピノザがフランス語が理解できたのかは重要です。普通に考えれば蔵書として残っている以上,それを読むことができたからスピノザは所有したのだということになるのですが,蔵書の中に,たとえば贈られたもののように,必ずしも自身で所望して所有するに至ったのではない本があったとしてもおかしくはないからです。
上野と近藤は,スピノザはそれを読むことができたのだといっています。少なくともラテン語ができる人間は,辞書を引きながらであればフランス語は読めるというのが上野の主張です。そしてフランス語の辞書もスピノザの蔵書の中にはありました。なので,程度についてはどうあれ,それをスピノザが読んでまた理解し得る環境にあったということは確かです。そしてここでは『ポール・ロワイヤル論理学』をスピノザが読むことができたかということだけが問題なのですから,たとえばスピノザがフランス語でコミュニケーションをとれたのかといったようなことまでは詮索する必要はありません。
上野はラテン語とフランス語との間には一定の類似があるという主旨のことをいっています。
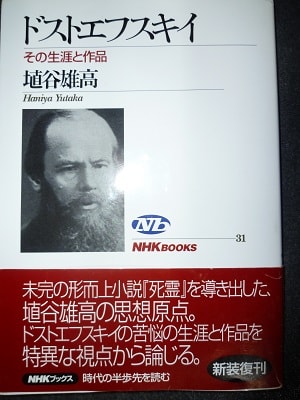
ドストエフスキーの小説の中には,癲癇の発作を起こす人物が少なからず存在します。『悪霊』の中でその役目を与えられているのがキリーロフです。埴谷がキリーロフに注目する理由のひとつがこのことです。
ドストエフスキー自身が癲癇の発作を起こすことがありました。ですから小説の中にもそういう人物が存在するといえるわけですが,このことだけでも発作を起こす人物が小説の中で特別の役割が与えられているといえるでしょう。さらに,これは自身の経験も影響しているのでしょうが,ドストエフスキーが神の似姿として呈示する人物は,癲癇の発作を起こすということがひとつの特徴になっています。ですから癲癇を起こすキリーロフに対して埴谷が注目するのは,当然といえば当然といえます。
さらに埴谷は,キリーロフの癲癇の描写には,たとえば『白痴』のムイシュキンの描写とは異なった面があると指摘しています。ムイシュキンの癲癇の記述が文学的な表現であるのに対して,キリーロフの癲癇の描写は形而上的な把握がなされているというのがその指摘です。僕はこの指摘の是非については追及しませんが,同じように癲癇の発作を起こすのであっても,ムイシュキンの場合とキリーロフの場合とでは,その意味合いには相違があるということは確かだと思います。ムイシュキンの発作は神の似姿ではあり得ても,キリーロフの発作が神の似姿であるとは思えないからです。
まとめると,スペイン語とポルトガル語,ヘブライ語とラテン語そしてオランダ語に関しては,時期は特定できない面はあるものの,それでコミュニケーションをとったり読み書きしたりすることはスピノザにはできたと考えてよさそうです。
一方でスピノザにはそうしたことが不可能だった言語としてはっきりしているのは英語です。ロバート・ボイルRobert Boyleとスピノザの間で直接的に書簡のやり取りが行われず,すべてがオルデンブルクHeinrich Ordenburgを介しているのは,スピノザは英語が,ボイルはラテン語が不得手であったたため,オルデンブルクが通訳する必要があったからだと思われます。また,オルデンブルクに宛てた書簡二十六の中に,もしスピノザが英語に堪能であったら,ボイルが出版した英語の本をホイヘンスChristiaan Huygensはスピノザに貸してくれただろうという主旨のことが書かれていますから,少なくともスピノザは英語が分からなかったということは確定的にいっていいでしょう。
『ポール・ロワイヤル論理学Logique de Port-Royal』はフランス語で書かれたものです。ですから,スピノザがフランス語が理解できたのかは重要です。普通に考えれば蔵書として残っている以上,それを読むことができたからスピノザは所有したのだということになるのですが,蔵書の中に,たとえば贈られたもののように,必ずしも自身で所望して所有するに至ったのではない本があったとしてもおかしくはないからです。
上野と近藤は,スピノザはそれを読むことができたのだといっています。少なくともラテン語ができる人間は,辞書を引きながらであればフランス語は読めるというのが上野の主張です。そしてフランス語の辞書もスピノザの蔵書の中にはありました。なので,程度についてはどうあれ,それをスピノザが読んでまた理解し得る環境にあったということは確かです。そしてここでは『ポール・ロワイヤル論理学』をスピノザが読むことができたかということだけが問題なのですから,たとえばスピノザがフランス語でコミュニケーションをとれたのかといったようなことまでは詮索する必要はありません。
上野はラテン語とフランス語との間には一定の類似があるという主旨のことをいっています。










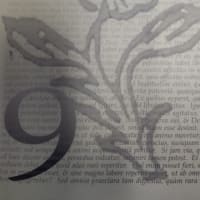


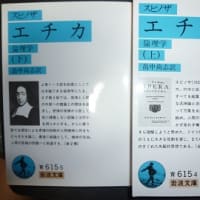

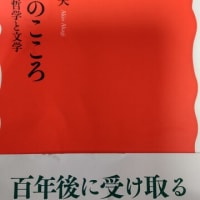








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます