スピノザから出されたブレイエンベルフWillem van Blyenburgへの最後の書簡は書簡二十七で,1665年6月3日付になっています。これはフォールブルフVoorburgから送られたもので,遺稿集Opera Posthumaに掲載されました。ブレイエンベルフがスピノザに送った最初の書簡が書簡十八で,これが1664年12月12日付ですからふたりの文通はおおよそ半年で終了したことになります。この理由は書簡二十一ですでにスピノザが指摘しているように,ブレイエンベルフは『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』でいわれているところの懐疑論者scepticiで,スピノザと文通することはスピノザにとってもブレイエンベルフにとっても益はなく,単なる時間の無駄にすぎなかったからです。
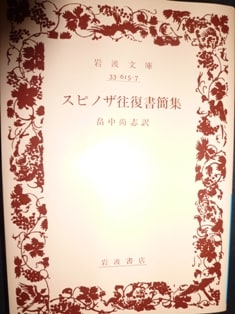
書簡二十七は書簡二十四に対する返事となっています。書簡二十四は1665年3月27日付でスピノザに送られたものですが,書簡二十七に書かれているところによれば,その書簡をスピノザが受け取った時点でアムステルダムAmsterdamに出発するところであり,どうせ書かれていることはそれまでの書簡と同じようなものだろうと推測したので,半分ほど読んで手紙を置いて出掛けてしまったとのことです。これはたぶん事実だったのだろうと思います。ただスピノザはそれより後に届いたオルデンブルクHeinrich Ordenburgからの書簡の返事を先に書いたようですから,もしかしたらこの書簡には返事を書かないつもりだったのかもしれません。
実際の書簡二十四の内容は『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』に関係する質問が多く,かつブレイエンベルフはその後にこの書簡への返事がないことへの不満を述べた書簡をスピノザに送りましたので,後にスピノザも返事を書くことになりました。ただこの書簡はスピノザがブレイエンベルフに宛てた書簡としては短いものであって,ブレイエンベルフが尋ねてきたことに対しても解答していません。むしろブレイエンベルフがそうした質問に対してスピノザが解答することを要求することを放棄するように求めています。
ブレイエンベルフがそれで引き下がったかどうかは分かりません。ただたとえそうであったとしても,スピノザがこれ以降はブレイエンベルフには書簡を書かなかったことは,歴史的な事実として確実視できることなのではないかと思います。
延長の属性Extensionis attributumが物体corpusXであるという命題および無限infinitumが有限finitumであるという命題をそれ自体で不条理であるとするなら,物体Xは延長の属性であるとか有限は無限であるという命題もそれ自体で不条理であることになると思われるかもしれません。ところがスピノザの哲学では,こちらの命題に関しては必ずしもそうはいえない面があるのです。
河井は,持続duratioそのものの中に永遠性aeternitasと時間性の両方が含まれているといっていました。そうすると,永遠aeternumは持続であるという命題は明らかに偽falsitasの命題であるといえるでしょうが,持続は永遠であるという命題は必ずしも偽の命題であるとはいえないことになるでしょう。もちろん持続は時間であるという命題も偽ではない,むしろこれは真verumであるといわれるでしょうが,それと同じ意味において,持続は永遠であるという命題も真であるといえることになります。延長の属性と物体X,および無限と有限の関係に関しても,これと同じことがいえるのです。河井はそれをスピノザの哲学における神Deusが内在の神であるということから説明していましたが,僕はそれを別の観点から論拠づけることを試みます。
第二部定理八系は,個物res singularesは神の属性attributumの中に包容されている限りにおいて存在する場合と,時間的に持続するdurareといわれる限りにおいて存在する場合があることを示しています。また第五部定理二九備考では,個物は一定の時間tempusおよび場所に関係して存在すると認識される場合と,神の中に含まれるものとして認識される場合の二通りがあるといっています。これらは河井が指摘している通り,現実的に存在する個物のうちに,時間性と永遠性の両方が含まれているということをスピノザが認めているというように解することができるでしょう。
ただ,これらを論拠にしようとする場合は,次のような疑問が生じるかもしれません。これらの部分は,現実的に存在する個物のうちに永遠性と時間性の両方が含まれているというより,時間性を含んでいる個物は永遠性の中にも存在しているということなのではないかというものです。そしてもしそうであるなら,持続は永遠であるという命題が含む意味は,僕が示したものと変じてくるでしょう。
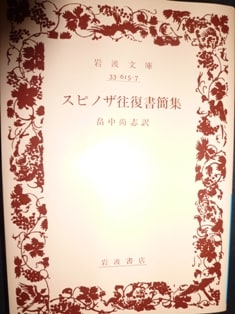
書簡二十七は書簡二十四に対する返事となっています。書簡二十四は1665年3月27日付でスピノザに送られたものですが,書簡二十七に書かれているところによれば,その書簡をスピノザが受け取った時点でアムステルダムAmsterdamに出発するところであり,どうせ書かれていることはそれまでの書簡と同じようなものだろうと推測したので,半分ほど読んで手紙を置いて出掛けてしまったとのことです。これはたぶん事実だったのだろうと思います。ただスピノザはそれより後に届いたオルデンブルクHeinrich Ordenburgからの書簡の返事を先に書いたようですから,もしかしたらこの書簡には返事を書かないつもりだったのかもしれません。
実際の書簡二十四の内容は『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』に関係する質問が多く,かつブレイエンベルフはその後にこの書簡への返事がないことへの不満を述べた書簡をスピノザに送りましたので,後にスピノザも返事を書くことになりました。ただこの書簡はスピノザがブレイエンベルフに宛てた書簡としては短いものであって,ブレイエンベルフが尋ねてきたことに対しても解答していません。むしろブレイエンベルフがそうした質問に対してスピノザが解答することを要求することを放棄するように求めています。
ブレイエンベルフがそれで引き下がったかどうかは分かりません。ただたとえそうであったとしても,スピノザがこれ以降はブレイエンベルフには書簡を書かなかったことは,歴史的な事実として確実視できることなのではないかと思います。
延長の属性Extensionis attributumが物体corpusXであるという命題および無限infinitumが有限finitumであるという命題をそれ自体で不条理であるとするなら,物体Xは延長の属性であるとか有限は無限であるという命題もそれ自体で不条理であることになると思われるかもしれません。ところがスピノザの哲学では,こちらの命題に関しては必ずしもそうはいえない面があるのです。
河井は,持続duratioそのものの中に永遠性aeternitasと時間性の両方が含まれているといっていました。そうすると,永遠aeternumは持続であるという命題は明らかに偽falsitasの命題であるといえるでしょうが,持続は永遠であるという命題は必ずしも偽の命題であるとはいえないことになるでしょう。もちろん持続は時間であるという命題も偽ではない,むしろこれは真verumであるといわれるでしょうが,それと同じ意味において,持続は永遠であるという命題も真であるといえることになります。延長の属性と物体X,および無限と有限の関係に関しても,これと同じことがいえるのです。河井はそれをスピノザの哲学における神Deusが内在の神であるということから説明していましたが,僕はそれを別の観点から論拠づけることを試みます。
第二部定理八系は,個物res singularesは神の属性attributumの中に包容されている限りにおいて存在する場合と,時間的に持続するdurareといわれる限りにおいて存在する場合があることを示しています。また第五部定理二九備考では,個物は一定の時間tempusおよび場所に関係して存在すると認識される場合と,神の中に含まれるものとして認識される場合の二通りがあるといっています。これらは河井が指摘している通り,現実的に存在する個物のうちに,時間性と永遠性の両方が含まれているということをスピノザが認めているというように解することができるでしょう。
ただ,これらを論拠にしようとする場合は,次のような疑問が生じるかもしれません。これらの部分は,現実的に存在する個物のうちに永遠性と時間性の両方が含まれているというより,時間性を含んでいる個物は永遠性の中にも存在しているということなのではないかというものです。そしてもしそうであるなら,持続は永遠であるという命題が含む意味は,僕が示したものと変じてくるでしょう。













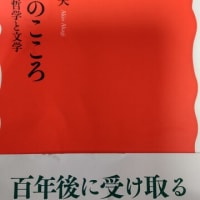

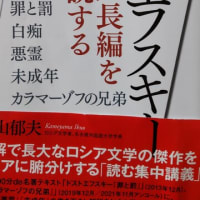








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます