僕は希望と不安は表裏一体の感情affectusであると解します。よってある感情が希望spesから生じるならばその同じ感情は不安metusからも生じるし,逆にある感情が不安から生じるのであれば,その感情は希望からも生じると解します。スピノザが第三部諸感情の定義一三説明でいっていることからして,そのように解するのが妥当であると考えるからです。よって第三部諸感情の定義一四の安堵securitasは,希望および不安を原因causaとして生じる喜びlaetitiaであり,第三部諸感情の定義一五の絶望desperatioは,希望および不安から生じる悲しみtristitiaであると解します。
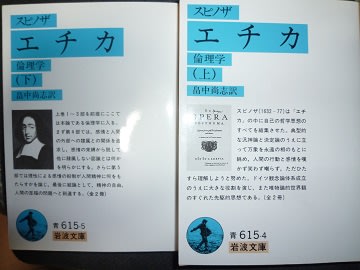
しかし岩波文庫版の訳者である畠中尚志は,僕とは異なった見解を示しています。畠中によれば,安堵とは希望から生じる喜びであり,絶望は不安から生じる悲しみです。いい換えればそれらふたつの感情は,希望ないしは不安からのみ発生するのであって,前者は不安,後者は希望から発生するのではありません。ただし畠中は,希望を原因として悲しみは発生せず,また不安を原因として喜びは発生しないといっているのではありません。不安から発生する喜びもあるし,希望から発生する悲しみもあるということは認めています。ですがそれらは,安堵や絶望ではなく,それとはまた別の感情であるといっているのです。
畠中が不安から発生する喜びであるといっているのは,第三部諸感情の定義一六の歓喜です。
「歓喜とは恐怖に反して起こった過去の物の観念を伴った喜びである」。
何度もいっていますが,恐怖metusと不安は同一語の別訳です。
第一部定理一五備考から容易に理解できるように,実体substantiaとしての量を概念するconcipereためには,現実的に存在する量を表象するimaginariことは役には立ちません。では,もし実体としての量を概念して,これを学問の基礎とするなら,こうした学問は僕たちが表象しているもの,いい換えれば現実的に存在するもの,あるいは現実的に存在しているものを対象とした学問であり得るのでしょうか。これを数学に限定して問うなら,スピノザが目指すような,あるいはスピノザが必要としているような数学というのは,僕たちの知性intellectusの外に現実的に存在しているものを対象とした数学であり得るのでしょうか。このような疑問が,実体としての量を規定する数学に対して投げ掛けられることになります。そしてその答えが,そうであり得るであるのかそうではあり得ないであるのかということと関係なく,そもそもこのような疑問が投げ掛けられてしまうということ自体が,僕にはかねてから,数学者たちを困惑させる要素になるのではないかと思えていたのです。というのも,自然科学というのは,普通は知性の外に実在するものを対象とした学問であると認識されているからです。
こうした疑問というのは実体としての量を起点として生じるのですが,数学が現実的に存在する事物を対象とした学問であり得るのか,あるいは実際にそうであるのかという類の疑問は,別の観点からも投げ掛けることができます。それはスピノザが事物の定義Definitioをどのように説明しているのかという観点です。
スピノザがあげる定義の条件のひとつに,ものの定義からそのもののすべての特質proprietasが導かれなければならないというものがあります。この条件を満たすためには,ものの定義にはそのものの起成原因causa efficiensが含まれているのが望ましいことになります。それがなぜ関連するのかということは,かつて定義そのものを考察の対象としたときに詳しく探求しましたからここでは繰り返しません。今は,ものの特質を導くためには,ものの本性essentiaだけでなく,ものの原因も必要とされている,あるいは必要とされる場合があるといっておきます。ただしこの場合の起成原因は,そのものが現実的に発生する原因を意味しません。
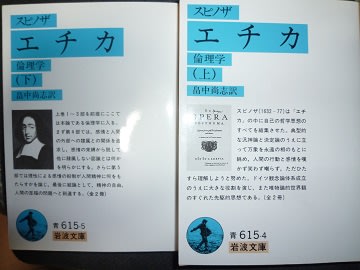
しかし岩波文庫版の訳者である畠中尚志は,僕とは異なった見解を示しています。畠中によれば,安堵とは希望から生じる喜びであり,絶望は不安から生じる悲しみです。いい換えればそれらふたつの感情は,希望ないしは不安からのみ発生するのであって,前者は不安,後者は希望から発生するのではありません。ただし畠中は,希望を原因として悲しみは発生せず,また不安を原因として喜びは発生しないといっているのではありません。不安から発生する喜びもあるし,希望から発生する悲しみもあるということは認めています。ですがそれらは,安堵や絶望ではなく,それとはまた別の感情であるといっているのです。
畠中が不安から発生する喜びであるといっているのは,第三部諸感情の定義一六の歓喜です。
「歓喜とは恐怖に反して起こった過去の物の観念を伴った喜びである」。
何度もいっていますが,恐怖metusと不安は同一語の別訳です。
第一部定理一五備考から容易に理解できるように,実体substantiaとしての量を概念するconcipereためには,現実的に存在する量を表象するimaginariことは役には立ちません。では,もし実体としての量を概念して,これを学問の基礎とするなら,こうした学問は僕たちが表象しているもの,いい換えれば現実的に存在するもの,あるいは現実的に存在しているものを対象とした学問であり得るのでしょうか。これを数学に限定して問うなら,スピノザが目指すような,あるいはスピノザが必要としているような数学というのは,僕たちの知性intellectusの外に現実的に存在しているものを対象とした数学であり得るのでしょうか。このような疑問が,実体としての量を規定する数学に対して投げ掛けられることになります。そしてその答えが,そうであり得るであるのかそうではあり得ないであるのかということと関係なく,そもそもこのような疑問が投げ掛けられてしまうということ自体が,僕にはかねてから,数学者たちを困惑させる要素になるのではないかと思えていたのです。というのも,自然科学というのは,普通は知性の外に実在するものを対象とした学問であると認識されているからです。
こうした疑問というのは実体としての量を起点として生じるのですが,数学が現実的に存在する事物を対象とした学問であり得るのか,あるいは実際にそうであるのかという類の疑問は,別の観点からも投げ掛けることができます。それはスピノザが事物の定義Definitioをどのように説明しているのかという観点です。
スピノザがあげる定義の条件のひとつに,ものの定義からそのもののすべての特質proprietasが導かれなければならないというものがあります。この条件を満たすためには,ものの定義にはそのものの起成原因causa efficiensが含まれているのが望ましいことになります。それがなぜ関連するのかということは,かつて定義そのものを考察の対象としたときに詳しく探求しましたからここでは繰り返しません。今は,ものの特質を導くためには,ものの本性essentiaだけでなく,ものの原因も必要とされている,あるいは必要とされる場合があるといっておきます。ただしこの場合の起成原因は,そのものが現実的に発生する原因を意味しません。






















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます