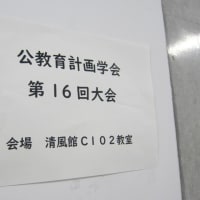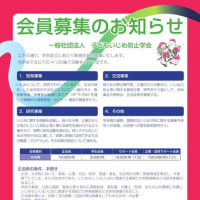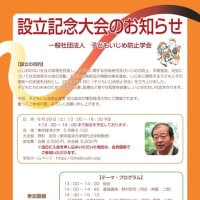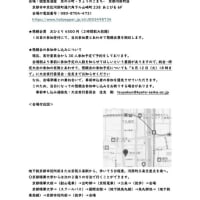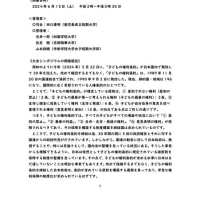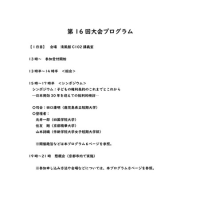先月から今月にかけて、このブログでも公開してきたとおり、私は大阪市役所ホームページ「市民の声」から何度も青少年会館「廃止」をめぐる諸問題や、あるいは、大阪市の市政改革をめぐる諸問題について、質問・意見を述べるという活動をしてきました。
そして、その活動については、基本的にこれは市役所・市教委各部署の現場担当者を困らせる意図でやっているものではなく、市政上層部の考えていることを問い合わせたいという趣旨でやってきたもの。したがって、「ちょっとこれ以上突っ込んでも、市役所・市教委各部署の担当者レベルでは答えづらい質問・意見ばかりになってきたのかな?」という感触を先週・先々週あたりから得てきたので、「これ以上は控えよう」という判断をした次第です。
でも、その後も、例えばパーティー券問題について「きちんと市長室で調査をする」という回答が届いたり、他の件でも、青少年会館を廃止しないでという子どもからの要望について市教委などで対処していること、「子ども青少年局(仮称)」について内部調整を今、積極的に進めていることなど、各部署からのごていねいなお返事を電子メールや文書でいただいています。
まずはこの点について、この場でひとこと、お礼申し上げます。もちろん、回答の内容については、まだまだ問い合わせたいこともありますが、それについてはひとまずおきます。本当に忙しい中、なんとか回答しなければならないと思って、事務の担当者の人がいっしょうけんめい動かれたのだなぁということがよくわかりますので。
ただ、忘れてはならないのは、9月27日に「コンプライアンス(法令順守)」のあり方について質問した件について、未だにお返事がないこと。もうすぐ、質問から一ヶ月くらいになりますが・・・・。もしかしたら、今日は自宅にいるので、次に大学に出向いたときに文書でこのときの回答が届いているのかもしれません。
でも、もう一度、9月27日に「コンプライアンス」に関連してどういう質問をしたのか、ここで重要な部分だけ、あらためて引用しておきます。
「さて、私の手元にある『解説教育六法(2006年版)』(三省堂)では、地方公務員法第32条で、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」が定められています。これがいわゆる「コンプライアンス」の地方公務員法上の根拠になるものと思われます。
と同時に、この条文を読んでいて、ふと疑問に思ったことがあります。
それは、もしも上司が、地方公務員法第32条にいう「法令・条例・地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程」を「逸脱」あるいは「無視」する職務命令を出した場合、はたして、大阪市職員に「上司の命令に従う義務」は生じるのかどうか、というところです。
地方公務員法の建前からすると「上司の命令」に従う必要はあるが、その「上司の命令」がそもそも「法令等の趣旨を逸脱あるいは無視している場合」はどうなるかという問題は、かなりコンプライアンス論の根幹にかかわる問題だとは思います。」
実はこの問題、市役所側としてそう簡単に答えが出せないことは、私としては前々からわかっていたものです。
ちなみに、法令解釈上のスジで考えたら、「もしも上司の命令それ自体が法令等に違反しているということであれば、そもそもその上司の命令自体が違法で、上司の責任がまず問われるべきなのだから、部下にはその上司の命令に従う義務がない」という風に、私は考えます。
しかし、市役所として私の考えを認めてしまったら、今、一生懸命、何事も「法令と上司の命令に従え」と言って、市政改革をすすめようとしている「コンプライアンス」論の枠組みが崩れますね。なぜなら、今後、上司の命令のなかに「違法」な部分があることを認めたら、部下はそれを根拠に「この命令には従えない」と、反撃を食らわすことができるわけですからね。少なくとも今後、私のような考えを市役所が認めた場合、上司は自分のやろうとしていることが「法令違反にはあたらない」と常に理論武装していないと、部下に対して指示・命令を出すことができなくなりますよ。
でも、だからといって、「コンプライアンス」論を積極的に主張する以上は、こういう私からの質問・意見に対しても、きちんと答えられるようなものでないといけませんよね。すなわち、「上司の指示・命令は法令解釈上無謬であり、常に従わなければならない」ということを、私の意見に対して説得力ある形で市役所としてきちんと位置づけなければ、私の意見のほうが通ってしまうからです。
しかし、「常識的に考えて、すべての上司の指示が、法令解釈上常に無謬でありうるなど、そんなことありえないでしょう。たとえ数は少なくても、解釈のまちがいや誤解などが生じる余地がありうる。したがって、法令違反の上司の指示等が生じる危険性が常に存在する」というのは、すぐわかると思います。そうすると、そういう上司の指示等のまちがいに対して、はたして部下は従う必要があるのか、という私の問いから、市役所側は逃げられないわけですよね。
そんなわけで、まだ返事の戻ってこないこの質問に対して、大阪市役所側が答えづらいこと、なかなか回答ができない事情もよくわかります。しかし、私はこれにどう回答してくるのか、とても楽しみに待っています。