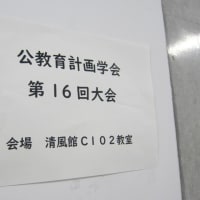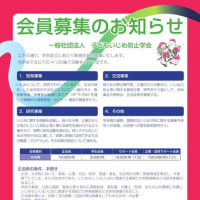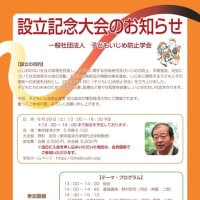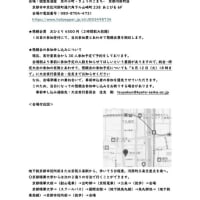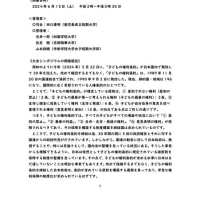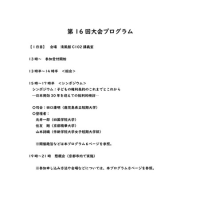久々の更新になります。このところの私は、こちらのブログで扱ってきたようなテーマについて考えたり、行動したりすることを一見、控えているようにも見えます。ですが、実はほかの研究テーマだとか社会的活動、あるいは、日々の仕事に取り組む中で、案外、こちらのブログで扱ってきたテーマを深めるにあたってのヒントを得ることがあります。そのことを、下記のとおり書き記しておきます。やや文体が変わりますが、ご容赦ください。
その1:当事者による「語り合い」や「気づき」の場の重要性
学校における死亡事故・事件の被害者遺族が、その事故・事件後のつらさや怒り、悩みや、学校・教育行政の事故・事件後の対応上の諸問題、事故・事件後に生じる「二次被害」の問題などについて、日ごろの人間関係を離れて自由に語り合う場が、今はほんとうに少ない。そんな状況のなかで、同じような事故・事件に遭遇した被害者遺族が集まって、そこで自分たちが日ごろ抱えているつらさや怒り、悩みなどを話し、これから対応すべき課題が何なのかをお互いに整理しあう。そのような会が生まれている。それが「学校事故・事件を語る会」の取組みである。ちなみに、この会のことは、もうひとつの日記帳ブログで詳しく触れたので、これ以上はこちらでは触れない。
この「学校事故・事件を語る会」のほかにも、たとえば不登校の子どものいる親の会や、いわゆるフリースクールの親の会などのように、何らかの子ども・若者とつきあう家族、特に親が抱えている困難について、日ごろの生活の場を離れて自由に語り合う場が生まれている。子育て支援活動における親たちのサークルにも、こうした側面があるだろう。
こういう当事者による「語り合い」や「気づき」の機会を、これからどのように作り上げていくのか。これは社会教育・生涯学習の課題でもあるだろうし、地域福祉やまちづくりの課題でもあるだろうし、人権や反差別、貧困などの課題に取り組む社会運動の課題でもあるだろう。
少なくとも今後の大阪市内の各地区において、「市民交流センター(仮称)」なるものが生まれようとしている状況のなかで、このような当事者による「語り合い」や「気づき」の機会をどう位置づけていくのか。それぞれの社会運動が今一度、確認していく必要があるのではないか。
それこそ、各地区の解放運動だって、被差別当事者とその支援者たちによる「語り合い」や「気づき」の場の整備、あるいは、同じ地区内に住む古い住民と新しい住民との相互の意見交流、「語り合い」や「気づき」の場づくりから、もう一度、新たな活動スタイルを模索してもいいのではないだろうか。そのきっかけとして、各地区内での子ども会活動の再開、保護者会の組織づくり、識字教室その他の活動などの場が使えるなら、どんどん活用するといいと思う。
その2:当事者と向き合う、領域横断的(いわゆる「学際的」)な視点の重要性
あくまでも私の目に映る限りなのだが、人権や反差別、貧困にかかわる研究活動や実践活動も、このところはあまりにも「細分化」されすぎて、その最先端で取り組んでいる研究や実践相互間の関係が見えづらいところがあるように思う。
もちろん、個々の研究や実践に取り組んでいる方々の善意やまじめさは否定しないし、したくもない。だがしかし、脇で見ていると、その善意やまじめさゆえに、ある特定の課題をさらに掘り下げることばかりに夢中になっていて、その課題を追究することによって、いったい、どんな将来展望が開けてくるのかが見えてこないような、そんなことすらあるように思えるときがある。
特に、人権や反差別、貧困などの問題にかかわって、今までのものの見方・考え方の問い直し(相対化)にかかわる研究や実践活動をはじめていると、その問い直しがさらなる問い直しを呼んで、ますます、袋小路に陥ってしまうことすら、今は生じつつあるように思う。そうなってくると、「いったい、それって、何のための(あるいは誰とつながるための)問い直しか?」ということを、私などは問いたくなってしまう。
もちろん人権や反差別、貧困などの諸問題について、社会全体がまだ「平穏」な情勢下にあれば、そういう研究や実践活動におけるさまざまな「問い直し」が袋小路に入っているケースがいくつか見られても、さほど問題はないかもしれない。
しかし、今、私たちが直面している状況は、そういう「もたつき」を待っていてはくれない。研究や実践活動に関する議論が「もたもた」している間に、これまで継続されてきた人権施策や子ども施策等々は打ち切られ、さまざまな社会運動が取り組み、実績を挙げてきたことも次々とやりづらくなる。そんな状況におかれているのが、今なのではないか?
特に過去の議論の「問い直し」が袋小路におちいって、「もたもた」していて身動きのとれない状況にあることは、今の人権施策や人権に関する社会運動などが目障りで、何かと「つぶしたい」と思う側にとっては、好都合であろう。
また、あまりにも研究や実践活動が細分化しすぎて、お互いに横の連携がとりあえないくらい、誰が何をやっているのかよくわからくなってきた状況もまた、人権施策や人権に関する社会運動などが目障りで、何かと「つぶしたい」と思う側にとっては、好都合であろう。それは研究や実践活動、あるいは社会運動の側が自らで自らを「分断」させているということであり、ひとつひとつ、その「分断」をうまく利用すれば、人権施策や人権に関する社会運動などを「つぶしたい」と思う側は、いろんな細工をすることができるからである。
さらに、あまりにも研究や実践活動が細分化しすぎてしまうと、自分の取り組んでいることがなんらかの形で行き詰ると、それでもう「だめだ」と思ってしまいかねない。目の前のことばかりに追われるのではなく、もう少し大きな視野をもって全体状況を見直せば、別の分野で、別の取組みがアプローチしていることによって、今、直面している行き詰まりが打開できるかもしれない、ということに気づく可能性もでてくるだろう。でも、そうした全体状況をふりかえる余裕が、研究や実践活動の細分化によって、「まじめさ」と「善意」ゆえに失われてくることもあるのではないか。あるいは、ひとつまちがうと、「その細分化された自分の一領域だけ守れたらいい」という思いも芽生えてくるかもしれない。そうなると、ますます「分断」が、自分たちの内部で生じてくるだろう。
そういうことから考えると、今、まさに人権や反差別、貧困などの諸問題に取り組む研究や実践活動に必要なことは、もう一度、当事者の暮らしている現場にこちらから出向いていき、当事者に向き合って、今、何が検討すべき課題なのかを把握しなおすこと。また、その把握しなおしたことをもとに、細分化された研究や実践活動をもう一度、今の課題に対応できるようにつなぎあわせ、領域横断的(もしくは学際的)なものに組みなおしていくこと。 この2つのことではないかと思う。
特に人権施策などにおいて「縦割り」行政の弊害を指摘したいのであれば、研究や実践活動の側も各研究領域別に「縦割り」の状況を問い直して、当事者の直面する課題に即して、自らの立場を組みなおすことが必要なのではないだろうか。そして、まずは自らが領域横断的(あるいは学際的)な課題意識を持ち、当事者と話をしながら、「問い直し」の袋小路に陥らないように現実的な検討課題を設定して、何かに取り組んでいくことが今は必要なのではないだろうか。
<script type="text/javascript"></script> <script src="http://j1.ax.xrea.com/l.j?id=100541685" type="text/javascript"></script> <noscript>