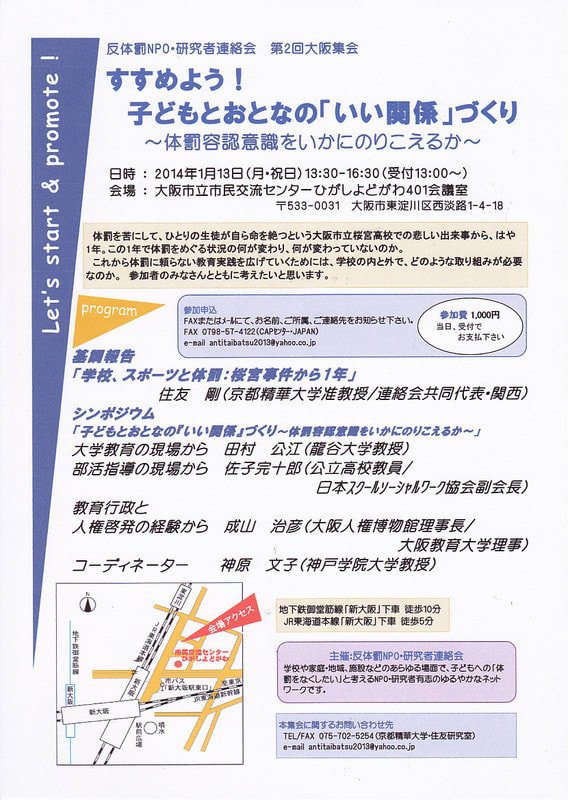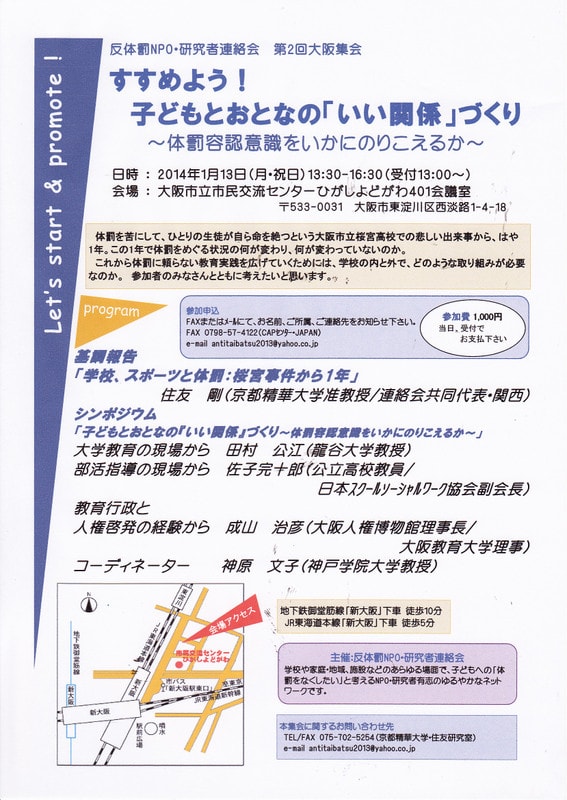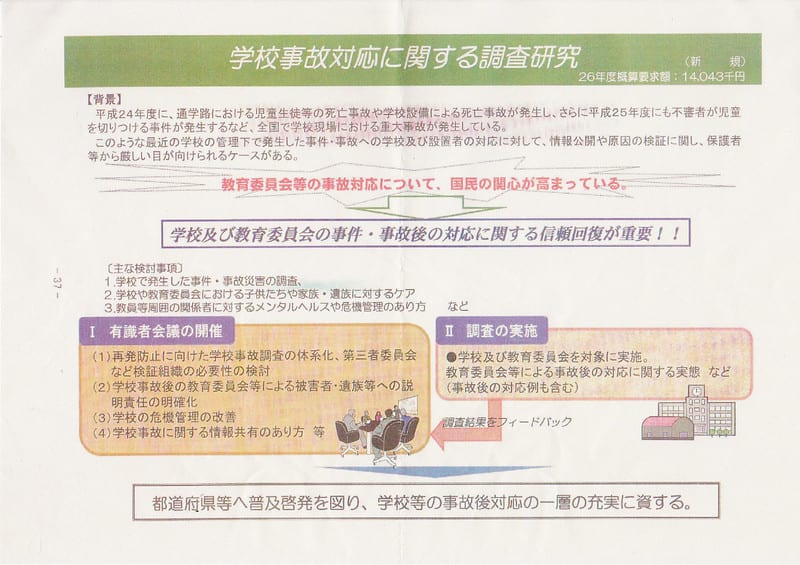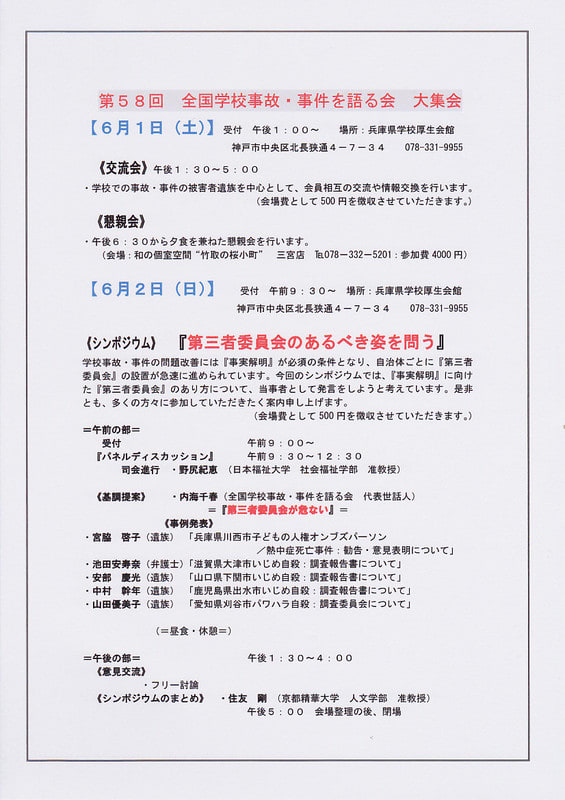「問題児童らを隔離、『特別教室』で指導へ 大阪市教委案」(朝日新聞デジタル、2014年6月9日)
http://www.asahi.com/articles/ASG686JYMG68PTIL003.html
以下の内容は、この記事に関してフェイスブックに書いた内容の転載です。
<以下、転載部分>
ところで、このプランをつくった人にはぜひ、お聞きしたいのですが・・・。
次のようなレベル3以上のケースは、本当にその問題行動を起こした子どもに問題があるのか、それとも・・・??
(1)「こんなまずい給食の弁当食えるか~!!」と昼休みになるたびにいらだって、教室で荒れていた子どもが、再三の教職員の注意にも従わなくなった。そんなことが続いたある日、ある教員に昼休み、「またお前、弁当のことで荒れるのか。ええ加減、飽きてこないか」と言われたことに腹を立てて、そばにあった彫刻刀で切り付けてしまった、というケース。
(2)全国一斉学力テストの結果で保護者に学校選択をさせることが続いた結果、自分の学校が廃校になりそうだということがわかり、他の仲間をさそってそれに抗議する行動を思いついた。それが学校にバリケードをつくって、教職員たちを排除して、立てこもって授業させない・・・という行為だった、というケース。(なんか「ぼくらの7日間戦争」っていう映画みたいだなあ・・・)
(3)執拗にシカト(無視)や陰口を中心に「いじめ」を繰り返す子どもと、その同調者に囲まれて長期間学校で過ごすなかで、教員に相談しても一向に解決せず、もうがまんしきれなくなって、いじめられていた子どもがいじめていた子どもをナイフで刺して、重傷を負わせたケース。
(4)何度も本人は嫌がり、やめてくれと訴えているのに、執拗に教員が子どものある口調や身体的特徴などを理由に暴言を吐くので、悩み抜いた子どもが他の子どもを誘って、その教員に暴行を負わせたケース。
それから、従来の出席停止措置でも、たとえば子どもや保護者からの意見の聴取など、適正な手続きにもとづいておこなわれるべきことが多々あるかと思うんですが、そこはレベル4以上のケースの場合、市教委や学校ではどういう手続きをとるのでしょうか?
あと、レベル4または5のケースで一定期間、在籍校を離れて別の教室で指導を受けた子供については、もとの在籍校への復帰の時期をどのような形で見極め、対応していくことになるのでしょうか。また、在籍校ではない別の教室に通っている期間中の当該の子どもへの指導等は、どのような体制で行うことになるのでしょうか。
ついでにいうと、問題行動への対応に長けた教員や心理学などの専門家をこの特別な教室に配置して対処するというのですが、「だったらなぜ、その人たちを問題を抱えた子どものいる学校に優先的に配置して対応する」という方針はとらないのかしら? さらには、こうした教職員や専門家を市全体に増員して配置する・・・という方針はないのかしら?
いろいろと、実務的なことから、市教委のたてたこのプランについて、聴いてみたいことがいっぱいあるなあ。
誰かマスコミの方、この件、私が上に書いた例を出しながら、ぜひ取材してみてください。
http://www.asahi.com/articles/ASG686JYMG68PTIL003.html
以下の内容は、この記事に関してフェイスブックに書いた内容の転載です。
<以下、転載部分>
ところで、このプランをつくった人にはぜひ、お聞きしたいのですが・・・。
次のようなレベル3以上のケースは、本当にその問題行動を起こした子どもに問題があるのか、それとも・・・??
(1)「こんなまずい給食の弁当食えるか~!!」と昼休みになるたびにいらだって、教室で荒れていた子どもが、再三の教職員の注意にも従わなくなった。そんなことが続いたある日、ある教員に昼休み、「またお前、弁当のことで荒れるのか。ええ加減、飽きてこないか」と言われたことに腹を立てて、そばにあった彫刻刀で切り付けてしまった、というケース。
(2)全国一斉学力テストの結果で保護者に学校選択をさせることが続いた結果、自分の学校が廃校になりそうだということがわかり、他の仲間をさそってそれに抗議する行動を思いついた。それが学校にバリケードをつくって、教職員たちを排除して、立てこもって授業させない・・・という行為だった、というケース。(なんか「ぼくらの7日間戦争」っていう映画みたいだなあ・・・)
(3)執拗にシカト(無視)や陰口を中心に「いじめ」を繰り返す子どもと、その同調者に囲まれて長期間学校で過ごすなかで、教員に相談しても一向に解決せず、もうがまんしきれなくなって、いじめられていた子どもがいじめていた子どもをナイフで刺して、重傷を負わせたケース。
(4)何度も本人は嫌がり、やめてくれと訴えているのに、執拗に教員が子どものある口調や身体的特徴などを理由に暴言を吐くので、悩み抜いた子どもが他の子どもを誘って、その教員に暴行を負わせたケース。
それから、従来の出席停止措置でも、たとえば子どもや保護者からの意見の聴取など、適正な手続きにもとづいておこなわれるべきことが多々あるかと思うんですが、そこはレベル4以上のケースの場合、市教委や学校ではどういう手続きをとるのでしょうか?
あと、レベル4または5のケースで一定期間、在籍校を離れて別の教室で指導を受けた子供については、もとの在籍校への復帰の時期をどのような形で見極め、対応していくことになるのでしょうか。また、在籍校ではない別の教室に通っている期間中の当該の子どもへの指導等は、どのような体制で行うことになるのでしょうか。
ついでにいうと、問題行動への対応に長けた教員や心理学などの専門家をこの特別な教室に配置して対処するというのですが、「だったらなぜ、その人たちを問題を抱えた子どものいる学校に優先的に配置して対応する」という方針はとらないのかしら? さらには、こうした教職員や専門家を市全体に増員して配置する・・・という方針はないのかしら?
いろいろと、実務的なことから、市教委のたてたこのプランについて、聴いてみたいことがいっぱいあるなあ。
誰かマスコミの方、この件、私が上に書いた例を出しながら、ぜひ取材してみてください。