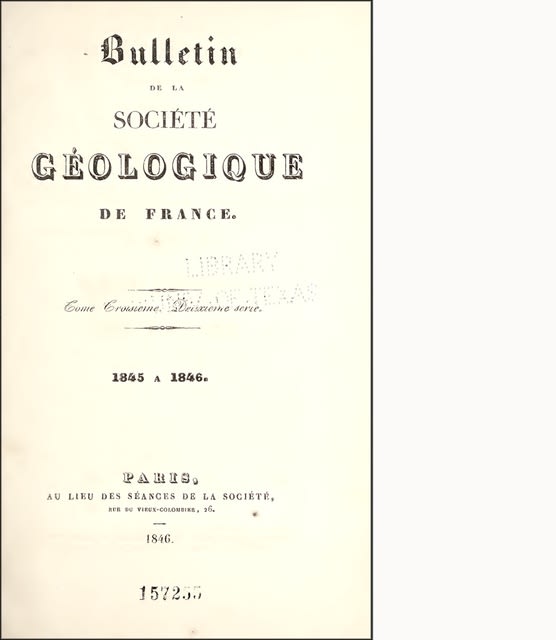Anchitherium の最初の二つの種がいずれもPalaeotheriumに由来することまで調べた。Palaeotherium は1804年にCuvierが提唱した属で、その折にPalaeotherium magnum, Palaeotherium medium, Palaeotherium minus の三種を記載しているようだ。しかしその論文は見つけられなかった。見つかったのは8年後のこの論文。
⚪︎ Cuvier, Georges, 1812. Recherches sur les ossemens fossiles de Quadripèdes, Tome 3, Sur les Espèces d’animaux dont proviennent les Os Fossiles. 1-28, Pl. 1-7. (四足動物の化石骨の研究、3. 化石骨が由来する動物の種類について)
ここでは、先ほどの3種類に加えてその後記載されたいくつかが記録されている。それにしも、最初に記載した種類がmagnum, medium, minus つまり大・中・小というのはシンプルというか安易な命名である。これら3種のうちどれが模式種なのだろう? ある資料のリストではPalaeotherium magnum が最初に出てくるから、これが模式種としたのだろうか。

680 Cuvier, 1812. Pl. 1. Palaeotherium medium 左下顎
元の属はあまり興味がないからこれくらいにして。種の方については、Anchitherium aurelianenseの記載論文は次のもの。
⚪︎ Cuvier, Georges, 1825. Recherches sur les ossemens fossiles. Dufour et d'Ocagne editions Paris, 4,514 pp. S. 255. (化石骨の研究)<未入手>
この本は当時有名なものだったらしく, 多くの文献で省略して引用してある。非常な大作で、4,514というのはページ数らしい。
もう一つのAnchitherium ezquerrae の記載は、Anchitherium属の記載されたMeyer, 1844である。論文のデータは前回書いたのでここでは省略する。Ezquerraはスペイン北部の内陸の都市名で、Madridから200kmほど北にある。これで、登場した属や種の由来はだいたい判明した。
平牧では、Matsumotoが記載した標本の後、しばらくは同じような標本は見つからなかった。40年後、前のものよりもずっと良い標本が報告された。
⚪︎ Shikama, Tokio and Shinji Yoshida, 1961. On a equid fossil from Hiramaki formation. Transactions and Proceedings of the Palaeontological Society, Japan, New Series, no. 44, pp. 171-174, pl. 26. (平牧層からのウマ類の化石)
この標本はMatsumotoで報告されたのと同じ可児市山崎で発見されたもので、左右の下顎(一部欠損)である。

681 Shikama and Yoshida, 1961, Pl. 26(一部)Anchitherium hypohippoides 下顎
写真は、原図からアレンジしたもので、上から右下顎咬合面拡大、背面、右側面、である。
その後、上顎も良好な標本が産出した。報告されたのは次の論文。
⚪︎ 奥村 潔・岡崎美彦・吉田新二・長谷川善和, 1977. 可児町産の哺乳動物化石. In 平牧の地層と化石 可児ニュータウン化石調査報告書・岐阜県可児町教育委員会. 21-45, Plates IV-1 - IV-16.

682 奥村・他, 1977, Plate IV-2. Anchitherium hypohippoides 左上顎
この標本が発見されたのは、ホロタイプや下顎標本の産地から350メートルほど南東に当たる可児町大森である。標本は左上顎の頬歯列で、論文では第3全臼歯から第3大臼歯までとなっているが、これは誤りで、第2前臼歯から第2大臼歯であり、後にこの後の第三大臼歯が埋もれていることがわかった。写真は第3大臼歯が見えない状態で撮られたもの。
これらの報告後20年以上経って、Anchitherium hypohippoidesを疑問種と扱う意見が公表された。その論文は下記のもの。
⚪︎ Miyata Kazunori and Tomida Yukumotsu, 2010. Anchitherium (Mammalia, Perissodactyla, Equidae) from the Early Miocene Hiramaki Formation, Gifu Prefecture, Japan, and its implication for the early diversification of Asian Anchitherium. Journal of Paleontology. Vol.84. No.4: 763–773. (岐阜県の下部中新統平牧層からのAnchitherium(奇蹄類ウマ科))
論文では、ホロタイプの二本の歯は同一の個体でなく、特に上顎歯は別の動物のものと推測されることや、下顎の歯には種を区別できるような特徴がないことなどからこの種類を疑問種とした。一方で大森産の上顎臼歯列の標本と、山崎産の下顎標本を、Anchitherium aff. A. gobiense Colbert, 1939 として扱っている。提唱された学名の保全という意味では、この取り扱いはあまり勧められない。私はhypohippoides の使用を続けたい。
Anchitherium gobiense の記載は、次の論文。もちろんMatsumotoのhypohippoides の記載(1921年)よりもだいぶん後のこと。
⚪︎ Colbert, Edwin Harris, 1939. A new Anchitheriinae horse from the Tung Gur Formation of Mongolia. American Museum Novitates 1019: 1-9. (モンゴル・Tung Gur層からのAnchitheriinae亜科新種)
標本は、モンゴルのTung Gurから産したもの。文中図がある。ここに示した上下の顎の図の他、四肢骨の図(Fig. 3)がある。

683 Colbert, 1939. Fig. 1. Anchitherium gobiense holotype: 右上顎歯列

684 Colbert, 1939. Fig. 2. Anchitherium gobiense paratype: 左下顎と歯列
これらの骨(と四肢骨)は同じ場所で採集されたもので、たぶん同一の個体のものとしている。図には計測値の表から計算したスケールを書き込んだ。
Edwin Harris Colbert (1905−2001)は、このブログで1年ほど前に紹介した。1977年2月にお会いした。奥様とご一緒に、京都から日帰りで奈良に行ってきた。夜は祇園でしゃぶしゃぶのご馳走にご相伴させていただいた。私の役割は案内人+通訳だったが、恐れを知らない頃だったからできたのだった。

685 Dr. Colbert. 1977年2月 奈良公園