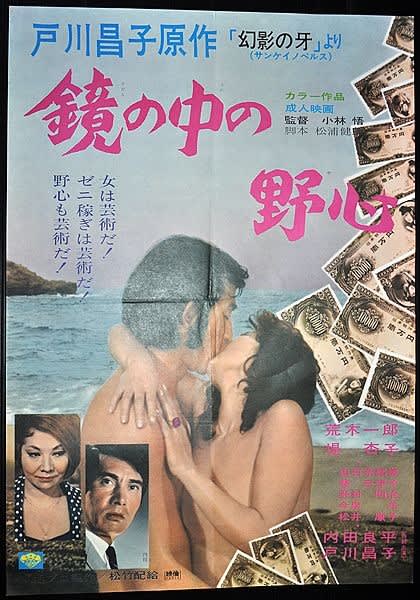ちょっと読んでみて面白かった記事を。
37歳で日テレ退社 “落語小料理屋”の女将が振り返る「私が『笑点』のディレクターだったとき」
6/21(日) 11:00配信
それで私が「なるほどねえ」と思ったのがこちら。
>(前略)
――そのアドバイス通り、大学卒業後は制作職で日テレに入社されました。配属先もドラマ班ということで、早速好きな仕事をされていたんでしょうか?
中田 うーん、好きな仕事でしたけど、「辛い」が9割、「楽しい」が1割くらいでしたね(笑)。
――辛いというのは、やはり体力的な部分で?
中田 そうですね。当時のテレビって、朝5時集合、夜1時終了みたいな世界だったので……。編集所には32時とか書いてあったりして、若いのに遊びにも行けない。撮影中は周りにコンビニもないようなスタジオにずっと泊まりこんで、寝るときも人と一緒ですから。
――その頃に手がけられたのはどんな作品ですか?
中田 『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』、『ホタルノヒカリ』、『ハケンの品格』などの作品に助監督として入りました。いわゆるADですね。仕事としては、ディレクターの意志を役者さんに伝える立場なので、常に板挟みで。「自分だったらこうしたい」という思いを表現できなかったのが、特にきつかったですね。撮影が全て終わるオールアップの日が近づいてくると、仲の良い衣装さんと「マジック10」「マジック9」と、密かに残りの日数を数えたりしていました(笑)。
「半分嘘で半分本当」のバラエティへの戸惑い
――そこからディレクターになるまで何年かかったんでしょうか?
中田 私は9年かかりました。でも、その辛い“修業”が済んで、ようやくディレクターになれたと思ったら、わずか1年でバラエティに異動になってしまったんです。タイミング的にもまさか異動するとは思っていなかったので、それこそ目の前が真っ暗になりました。
――ドラマとバラエティでは、仕事の内容も全然違うものですか?
中田 ドラマは完全に作り込んだ世界を見せるわけですが、バラエティは「半分嘘で半分本当」という世界です。なので、ドラマと同じ感覚でバラエティを作ると、すごく不自然な感じになってしまうんです。バラエティに移ってからは、そのことをよく指摘されたんですが、正直「いまさらそんなこと言われても」と(笑)。
――それでもそのときは、会社を辞めようとは思わなかった?
『笑点』のディレクターってどんな仕事?
中田 そうですね。バラエティとはいえ、やっぱり番組を創るのは好きでしたし、異動後しばらくして『笑点』の担当になったことも大きかったです。他のバラエティ番組とは違って、『笑点』とはめちゃくちゃ相性が良かったんですよ。
――それは、どんな点が?
中田 噺家さんたちの世界が、ドラマと近かったからかもしれません。テレビである以上、偶然の要素は必ずあるんですが、師匠たちがもともと持っている芸というのは、ドラマと同じで完璧に作り込んでいるものなので、だから入りやすかったのかな、と。それと、『笑点』はすごくオープンで、アットホームな雰囲気なんです。たとえば、師匠たちの楽屋は大部屋で、全員一緒なんですよ。
――意外ですね! 皆さん個室なのかと思っていました。
中田 寄席の楽屋は大部屋なので、たぶんそれと同じにしているんだと思います。逆に部屋が分かれちゃうと、師匠たちもどうしていいのかわからない(笑)。楽屋はスタッフも出入り自由なので、時間があるときはみんなでワイワイおしゃべりしていて、そんな雰囲気がすごく楽しくて。私はそれまで落語とは縁がなかったんですが、寄席に行くと師匠たちが喜んでくれることもあって、よく通うようになりました。
――ちなみに『笑点』のディレクターというのは、どんな仕事なんでしょうか?
中田 実は、ほとんどやることがないんです(笑)。編集はするんですが、これまでに積み上げてきた番組の“型”もあるので、そんなに大変ではなくて。基本的には師匠たちのお相手と言いますか、現場の雰囲気作りが仕事です。だから楽しかったのかもしれないですね。
ディレクター35歳限界説
――そんな充実した日々を過ごされていたのに、なぜ退社を決意されたのですか?
中田 結局、『笑点』には1年しかいられなかったんです。35歳のときに、すぐまた異動になって。今度は編成局という部署で、完璧なデスクワークでした。それまでは仕事中に座ることなんてほとんどなかったのに、朝から晩まで机にかじりついてタイムテーブルを決めたり、CMの料金計算をしたり。あとは経営側から下りてきた細かなルールを各部署に伝えたりするんですが、これが私には全く合っていなくて。何かの役には立ってるんだろうけど、この仕事は一体何なんだろうと(笑)。
――それがきっかけで退社を?
中田 「なんか私、すごくつまんない人間になってるな」と思ってしまって。このままずっと会社の言うことを聞いていたら、つまんないばばあになっちゃうな、と(笑)。だったら自分のやりたいことをやって、楽しいばばあになりたいと思いました。
――とはいえもう1度、制作に戻れるチャンスもあったのでは?
中田 もともとテレビ局には、「ディレクター35歳限界説」というのがあるんです。35歳までに売れないと、現場から離れなくてはいけないという“暗黙の了解”ですね。そのタイムリミットは全員に平等にやってくるんです。センスの面でも体力の面でも、やはり若くないとできない仕事ですから。
100人中、2人か3人しか生き残れない世界
――ディレクターが「売れる」というのは、具体的には?
中田 総合演出になる、という意味です。ただ、総合演出になっても、いつその番組が終わるかはわからないので。結局、100人ディレクターがいても、ずっと総合演出として残れるのは2人か3人くらいじゃないですかね。ごく一部の売れっ子だけが残って、あとはいろいろな部署に散っていくんです。
――狭き門ですね。
中田 超狭き門です。私は32歳でバラエティに異動したんですが、そこで3年やりながら「ああ、自分は残れないだろうな」と予感はしていました。
(後略)
それでこの女性は日本テレビを退職するのですが、続きに興味のある方はご自身で読んでください。例によって長い引用になりましたが、私が興味深く感じたのはこちら。
>テレビ局には、「ディレクター35歳限界説」というのがあるんです。35歳までに売れないと、現場から離れなくてはいけないという“暗黙の了解”ですね。そのタイムリミットは全員に平等にやってくるんです。センスの面でも体力の面でも、やはり若くないとできない仕事ですから。
>ディレクターが「売れる」というのは、具体的には?
中田 総合演出になる、という意味です。ただ、総合演出になっても、いつその番組が終わるかはわからないので。結局、100人ディレクターがいても、ずっと総合演出として残れるのは2人か3人くらいじゃないですかね。ごく一部の売れっ子だけが残って、あとはいろいろな部署に散っていくんです。
私はテレビ局の内情なんかに詳しくないので、ディレクター35歳限界説なんて知りませんでしたが、つまり35歳までで才能や適性を見きわめられるということですね。それは仕方ないというものですが、新卒で入っても十何年くらいで制作職から身を引くというのは、難関の東京キー局に入った人間としても悔しいでしょうね。 テレビ局ったってもちろん営業職、総務職、経理職、技術職いろいろですが、世間一般のイメージでの花形は、やはり報道職と制作職でしょう。アナウンサーはやはり少々別格です。
それで十年を超えたくらいで、だいたい適性、能力が分かっちゃってあこがれの場所から離れることを余儀なくされるというのは、才能の限界を突きつけられるわけで、これはやはり残念だし苦しいですよね。言うまでもなく、テレビ局だってそんなに統括する立場のディレクターを必要とするわけもないので、それ自体は「理の当然」というやつでしょうが、卓越した才能でないと、生き残れないというものなわけです。上の記事で「笑点」ではそんなにすることがなかったと女性が語っているのは、たぶんですが、テレビ局も彼女の才覚にそんなに期待していなかったという側面もあったのでしょうね。そして彼女もそれを感じていたということでしょう。
それでこれも同じだなあと思うのが、映画の助監督(監督助手ほかの名称もあり)です。今はそんな時代でもありませんが、日本の映画界が景気が良かった時代は、各映画会社は、東京大学や京都大学などの有名大学の主に文学部出身者を「助監督」として採用し、それで映画監督につけて仕事をさせて、能力のあるものを最終的には監督に昇格させるというシステムでした。海外の場合、むしろ助監督というのは専門職ですが、日本ではある時期までは映画監督になるための通過点、登竜門みたいなものでした。
が、日本映画の景気が悪くなり、各映画会社が俳優をふくむ専属スタッフを抱えられる時代でなくなり(先日記事にしたひし美ゆり子が72年3月で東宝の専属でなくなったこともその一環です。先日亡くなった加藤茂雄氏も同じ年に東宝の専属でなくなっているとのこと)、みなフリーになったり特定のプロダクション所属になったりする時代となると、もはや助監督が映画監督の通過点というものでもなくなりました。このあたりは、Wikipediaのこちらをごらんください。
それでWikipediaを引用すれば
>映画界の助監督、特にチーフ助監督は、他のパートのメインスタッフ、撮影、照明、美術、録音といった責任者と同等の立場であり、ギャラも原則的には同等である(年齢やキャリアによっては異なる)。日本ではアシスタントとつくと、なにか半人前の修行中のような印象がついてしまうが、アメリカではアシストという立場はサッカーの得点と同じく、助手ではなく対等関係である。映画界では「映画監督は素人でもできるが、チーフ助監督は素人にはできない」と言われている。現にハリウッドでは新人監督が映画を撮る場合、助監督の方がギャラが高かったり、権限が強かったりすることもある。またエグゼクティブプロデューサー兼助監督などという兼務があったりする。いずれにせよ、助監督=監督に顎で使われる使いっ走りという印象は原則として映画界では大きな間違いである。もちろん、ケースバイケースではあり、特にTVなど少人数の現場ほどアシスタントの立場は軽いことから、コントなどで「虐められる助監督」のイメージが流布されてしまった嫌いはある。
>往年の映画会社においては、助監督で修行を積むことが監督へのほぼ唯一の道であったが(会社の方針によって助監督の経験がない者に監督をさせようとしたら、石原慎太郎や大林宣彦のように助監督が反対することが多かった)、現在では監督になる意志のないフリーの助監督も存在する。
>映画の斜陽化によって製作本数が激減し、それに伴う合理化によって俳優・監督・スタッフの長期専属契約のシステムがなくなり、多くのスタッフがフリーとなった現在は、映画監督になるための手段として、必ずしも助監督を経験しなければならないという訳ではない。かつては大林宣彦監督のように、助監督を経験しない映画監督は珍しいとされてきたが、現在はテレビ業界やCM、シナリオライター、芸能人といった異業界からの監督就任も多く、むしろベテランの助監督が監督を補佐やアドバイスをするという傾向が強くなってきている。
ということです。でなければ、田中絹代や伊丹十三や和田誠といった人たちが映画監督なんかできるわけがない(すみません、この人たちにうらみはありません。伊丹はそんなに好きじゃありませんが)。
それで例えば、山田洋次の映画で長きにわたって助監督を務めた五十嵐敬司なんて、けっきょく監督にならないで終わりました。たぶんある時点で、監督になりたいという意欲が薄れたのでしょうが、そういうのももったいないと思います。大島渚の初期の松竹作品では、田村孟や石堂淑朗が助監督でしたが、石堂は監督にならず、田村も1本監督しただけです。崔洋一監督は、大島作品の『愛のコリーダ 』で助監督を務めましたが、彼のように大物監督になれる人も多くない。
この数年、昔の日本映画を観る機会が多いのですが、クレジット(昔ですから、エンドクレジットはほぼなし)で「助監督」というのに注目していますと、あまり知っている名前はないわけです。つまり監督になれなかった、あるいはわずかな監督作品を残して映画界から去った、もしくは監督から違うスタッフになった人もいるかもです。Wikipediaで名前がリンクされていない助監督を見ると、ああ、このひと監督になれなかったのかなあとかいろいろ考えます。
上の田村や石堂といった人たちは、その後脚本家として一世を風靡したからまだいいとして、そうでない人のほうが多いでしょうから、これもなかなか大変ですね。世の中、大物映画監督や名前が知られている大プロデューサー、ディレクター(たとえばこちらの人物など)の陰には、死屍累々(もちろん本当に死んでいる人はそんなに多くないでしょうが、テレビ局も過労死の少なくない職場です)たる脱落者がいるわけです。なんでもそうでしょうが、勤め人としての助監督の時代でもやはり競争は熾烈です。1932年早生まれの大島渚は1959年に監督デビュー、31年生まれの山田洋次は61年にデビューしましたが、このような若いデビューが可能だったのは、松竹があまり景気が良くなくて、新しい監督に期待したためでもあります。
そうこう考えてみると、やはり映画とかテレビなんかは、報道はまた違う職種ですが、作る側より劇場や自宅で楽しんでいるほうがいいのかもですね。映画が好きなら1度くらいは製作スタッフ(俳優をふくむ)にあこがれるでしょうし、私も同じですが、エキストラをしていて、映画はやはり助監督次第だとか、映画作りも大変だとかいろいろ考えたこともあります。
上の記事の女性の将来に幸あれと祈念してこの記事を終えます。