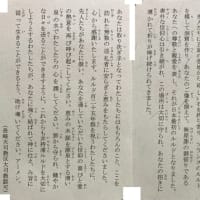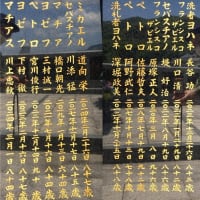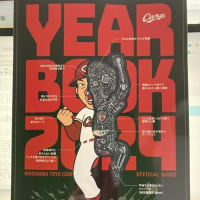●わたしは自動車を運転します。どちらかというと気の短いわたしは、急いで運転をすることが多いような気がします。五島では、たぶん急いでも5分か、せいぜい10分くらいしか早く着きません。それなのに、急いでしまうのは、まず出発時間が遅いからです。
●目的地まで30分かかる場所に向かおうとします。たとえば、朝8時の五島産業汽船に乗るとしましょう。少し余裕を持って出発すればよいのに、最終的に出発する時間は7時25分になってしまいます。これでは、よほど急がないと、船の切符を買って乗船するためにはほんの少しの余裕もありません。
●7時25分に浜串を出発しました。初めは順調に車も進んでいますが、10分走ったころに自分の前にダンプカーが現れまして、目の前が真っ暗になりました。このダンプカーが前を塞いで、スイスイ走ることができないからです。
●イライラしながら走り続け、本当に30分かかって鯛ノ浦のターミナルに到着しました。気分はマイナスです。ダンプカーのことをいつまでも引きずっていました。あのダンプさえいなければ、あんなに冷や汗をかかないで到着したのに。
●でも考えてみると、30分で間違いなく到着したのですから、本当は感謝すべきなのです。船に間に合わなくなるという最悪の時代を避けることができたのですから、本当は運が良かったと、感謝すべきでした。もっと言うと、ダンプカーのおかげで、わたしは安全運転できたはずです。もしダンプカーがいなくて、わたしがスピードを上げて鯛ノ浦に向かっていたら、わたしが事故を起こしていたかもしれません。
●いろいろ考えると、わたしは十分に、感謝できる条件がそろっていました。けれどもそのほとんどを、当たり前のように思っていたので、感謝の気持ちが湧いてこなかったのです。車を持っていること、信号が一か所もなくて、警察の取り締まりも決してないような裏道が備えられていること、ダンプカーが前を先導してくれて、わたしは後をついて行くだけで鯛ノ浦までたどり着けたこと。当たり前のように思っていたこれらのことは、当たり前のことではなくて、感謝できることだったわけです。
●どうして感謝の気持ちが湧いてこないのか。それは、自分が受けている恩恵を当たり前だと思っているからです。この車社会の生活を当たり前と思って生きて、時間から時間に忙しく動いて回る生活を、当たり前のことだと思っているから、感謝できないのではないでしょうか。このような状態は、自分に原因がある状態です。さまざまな恩恵を受けていながら、自分に妨げがあるために、恩恵に感謝できなくなっているわけです。
●自分に妨げがあると、受けている恩恵を「これは当たり前ではない」と気付くことができません。わたしたちは三日間、練成会に参加しています。この三日間は、神さまのためだけにおささげする三日間です。皆さんの人生の中で、神さまのためだけに、三日間も時間を使うことは、前にも後にもこの練成会一回きりかもしれません。
●この三日間は、あなたの人生にとってかけがえのない恩恵になります。さらに、あなたが戻っていく小教区にとっても、かけがえのない恩恵になります。それなのに、もしわたしの心の中に、「どうしてわたしは練成会なんかに参加しなければならないのだろうか」「わたしは無理やり練成会に参加させられた」というような思いをぬぐい切れなかったとしたら、せっかくの恩恵が働かなくなるのではないでしょうか。
●わたしたちにいろいろな方法で、いつでも与えられる恩恵は、わたしの中に妨げがあると、どうしても十分に力を発揮することができないのです。恩恵が十分に働かなくなる原因は、わたしの中に妨げがある場合と、自分以外に妨げがある場合と、両方あると思いますが、多くの場合は、自分の中にある妨げが原因なのです。
●それは「自我」と言ったり、「自己愛」と言ったりしますが、わたしは言葉にとらわれずに、自分自身の体験をそのまま話してみたいと思います。
●家族の中で自分だけがカトリックだという人も、中にはいるかもしれません。あるいは、そういう環境の人を知っているかもしれません。自分以外の人はカトリックではないので、環境としてはとても厳しい環境でしょう。けれども、恵みはただ一人カトリックであるあなたを通して働きます。その人がカトリックであることを神は大切に思って、家族の分も恵みを注いでくださるのかもしれません。
●「わたしは周りにだれもカトリックの人がいないから、力を発揮できない」「わたしだけがカトリックだから、わたしは恵まれていない」わたしはそうは思いません。あなただけがカトリック、だったらあなたを頼みとして、神さまの恵みが働き始めます。その人を頼みの綱として、神は恩恵を注ごうと考えておられると思います。
●自分以外の妨げが主な原因なのではなく、わたし自身に、わたしの中に妨げがあって、恩恵が十分に働かないのだと考えるべきです。今日目が覚めて生きていること、これだけでも恩恵ですが、わたしがそう思っていなければ、恵みとして働かないのです。(詳細に)
●証しを立てるためにも、恩恵は働きます。この時も、自分の中に妨げがあると、恩恵は十分に働いてくれないのです。9月21日、聖マタイ使徒福音記者の祝日の聖書朗読を例に考えてみましょう。
◆キリストの体は一つ(エフェソ4・1-7,11-13)
4:1 そこで、主に結ばれて囚人となっているわたしはあなたがたに勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、
4:2 一切高ぶることなく、柔和で、寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、
4:3 平和のきずなで結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。
4:4 体は一つ、霊は一つです。それは、あなたがたが、一つの希望にあずかるようにと招かれているのと同じです。
4:5 主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、
4:6 すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのものの内におられます。
4:7 しかし、わたしたち一人一人に、キリストの賜物のはかりに従って、恵みが与えられています。
4:11 そして、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。
4:12 こうして、聖なる者たちは奉仕の業に適した者とされ、キリストの体を造り上げてゆき、
4:13 ついには、わたしたちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。
◆マタイを弟子にする(マタイ9・9-13)
9:9 イエスはそこをたち、通りがかりに、マタイという人が収税所に座っているのを見かけて、「わたしに従いなさい」と言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。
9:10 イエスがその家で食事をしておられたときのことである。徴税人や罪人も大勢やって来て、イエスや弟子たちと同席していた。
9:11 ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、「なぜ、あなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか」と言った。
9:12 イエスはこれを聞いて言われた。「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。
9:13 『わたしが求めるのは憐れみであって、いけにえではない』とはどういう意味か、行って学びなさい。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」
9月21日(年間第25水曜日・聖マタイ使徒福音記者)神の招きがすべての人に
霊による一致を保って生きる
●ある日、教会での結婚を希望する青年たちが訪ねてきました。結婚講座の約束をして、若いカップルは講座に参加し始めました。「結婚生活を続けていくのに大切な心がけは何だと思いますか」と尋ねると、「相手を大切にすることです」と答えてくれました。
●互いに愛し合い、相手を大切に思うことはもちろんですが、わたしはもう一つ、本人たちが気づいていないことについて触れました。「わたしは、『自分たちの力だけでは足りない』ということをわきまえておくことだと思うよ。どんなに努力しても、理解できない行動や考え方があったり、折り合えなかったりしたとき、それでもなお夫婦であり続けるためには、神の支えが欠かせない。そう思いませんか?」本人たちは、はっとさせられていたようです。
●「自分たちの力だけでは足りない」「神の助けが必要だ」と自覚するとき、結婚生活をする人に十分に恩恵が働きます。自分たちが愛しあえば足りると思っている間は、恩恵が十分に働かないわけです。夫婦自身に、恩恵が働くのを妨げる原因があるからです。
●確かに、愛による一致は、夫婦の根幹を成すものですが、人間の努力だけで夫婦の絆は保てないのではないでしょうか。どうしても継続できなくなってしまう結婚生活の中には、自分たちの努力だけでは足りないのであり、神に頼ることが何にもまして大切なのだと気づいたなら、もっと違う結果になったケースもあるはずです。
●配偶者は互いに、愛による一致と、霊による一致を保って生きる。そうして初めて、深い絆で結ばれると思うのです。結婚する人たちだけでなく、位階的交わりにある人、奉献生活にある人、あらゆる信徒が、互いを愛する気持ちと、個人の力だけでは真の一致を保つことはできません。
●第一朗読は教えます。神に心を開き、霊による一致を求めるとき、「わたしたちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。」(エフェソ四13)ここまでたどり着いた時、すべての人が、生活の中で証しを立てる人になります。
神の招きに全力で応える
●マタイの召命は、ほかの弟子たちとは一線を画したものと感じます。徴税人は、徴収した税を、自分たちを支配しているローマに納める人々で、おまけに自分たちの取り分も裁量が認められていました。「不正な人、罪人」と考えられていたのに、あえてイエスは声をかけます。その特殊な事情を書き残すことは、特別な意味があると福音記者は考えたのでしょう。
●マタイの召命を通してイエスは、今や神の支配が、「徴税人や罪人」にまで及んでいることを示そうとしました。ファリサイ派の人々にとって神の支配にあずかることは律法の遵守と切っても切れない関係にありますが、イエスが示そうとする神の支配は、律法遵守にとらわれず、どこまでも誰にも及んでいます。
●マタイを含め徴税人や罪人が神に招かれて一つの食事の席に着き、一つの教えに導かれ、イエスの招きに答えていく。こうした姿は本来あるべき神の憐れみの現れですが、ファリサイ派の人々にとっては耐えられないことでした。マタイ福音記者はあえて、ユダヤ教からの改宗者である読者に書き残すに値すると、考えたのではないでしょうか。
●ファリサイ派の人々は、神の恵みは律法を完全に守る人に与えられるのであって、罪人には与えられないという考えでした。神さまにこんなことができるはずがないと、神さまの力を小さく制限していたのは、自分たちの思い込みでした。ファリサイ派の人々に神の恵みが十分働かなかったのは、彼らの中に妨げがあったからです。彼らが心を開き、神の恵みの奥深さを受け入れたなら、彼らの中でも恩恵が十分働いたに違いありません。
●神の憐れみ深さは、律法を守ることができずに排除されている人々にも浸透していきます。深く染み込み、弱さを覆います。神がここまでして人を招いている。その愛に、全力で応えようとする徴税人のマタイの姿は、すべての人を招く神の姿を誰よりも感じ取っているし、誰よりも力強く語っています。
●イエスの「行って学びなさい。」という言葉は、今も響いています。わたしたちが社会にあって証し人となるために、神に全面的に心を開くための場所、神の憐れみによる支配を確実に学ぶ場所を、わたしたちは持っている必要があります。わたしはそれはそれぞれが所属している教会だと思います。
●それぞれの教会であずかるミサ、小教区評議会、ロザリオなどの信心の集いです。これらの場所に心を開いて参加するとき、わたしたちの中の妨げは取り除かれ、立派な証し人として、歩いていけるようになります。練成会を通して、皆さまのさらなる成長をお祈り申し上げます。