<neW !>
「太陽の自分エクササイズ ~自己受容ヴァージョン~」
リリース!
「自己受容」「自己表現」を網羅した、「This is Meと言える自分になる」 太陽の自分エクササイズ。
それに対して、こちらの「自己受容ヴァージョン」は自己受容に特化した凝縮版です。
今だけの特典あり!
是非こちらをご覧下さい。
********************************************
<今後のワークショップ予定>
「色で暮らしを彩る講座」
場所:ヒーリングサロン「些々羅」 岐阜市
STEP1 募集中! 参加費:¥15000(税込)
※どこで、を問わず、色について学んだことがある人は自己申告により参加費が半額になります。
[内容]
・色からのメッセージ
・色の性質
・その色を使ってどんなことが可能になるの? ~五感を使って色を取り入れる~
座学というより、楽しいワークショップ形式で自然に色のメッセージを自分に取り入れましょう!
STEP2(※STEP2はSTEP1を受講した人のみ受けることができます) ¥20000
STEP3(※STEP3はSTEP1,2を受講した人のみ受けることができます) ¥30000
9/11(水) 10:00~17:00(※ランチ休憩1時間あり) 満席
9/14(土) 10:00~17:00(※ランチ休憩1時間あり) 満席
9/16(月・祝)10:00~17:00(※ランチ休憩1時間あり) 満席
10/11(金) 10:00~17:00(※ランチ休憩1時間あり) 満席
お問い合わせは、 chakra@aura-soma.name まで
********************************************
岐阜の「CINEX」という映画館は、ときどき大手のシネコンではやっていないような映画がかかることがあります。
この「兄消える」という映画もそうでした。(ごめんなさいね。私が知らなかっただけかもしれません)

でもたぶん、じみ~な映画でしたので、そんな大ヒットをハナから狙ったという感じでもないと思うんですよね。
あまり宣伝されている感じでもないし。
なにせ、登場人物は老人ばかりですので、絵面的にも派手さはまったくありません。
しかし、なかなか渋い味のある映画でした。
私の年齢になって観るから余計にそう感じたのかもしれませんが。
いちおう、「映画.com」のあらすじを載せておきます。
『信州・上田を舞台に、40年ぶりに再会した老兄弟の絆を描いたドラマ。戦後昭和を代表する喜劇俳優として知られ、170本以上の映画に出演した柳澤慎一が、本作を自らの遺作にする意向で約60年ぶりに映画主演。同じく大ベテランの俳優で、舞台や映画など幅広く活躍してきた高橋長英が共演し、対照的な兄弟を演じた。町工場を細々と営み、100歳で亡くなった父親の葬式を終えたばかりの76歳の鉄男のもとに、40年前に家を飛び出したきりだった80歳の兄・金之助が、わけありな若い女性・樹里を連れて舞い戻ってくる。独身で真面目な鉄男と、金之助と樹里。3人の奇妙な共同生活が始まるが、やがて金之助の過去や樹里の素性が明らかになり、兄弟がそれぞれに抱えた家族や故郷への思いもまた、よみがえっていく。兄・金之助を柳澤、弟・鉄男を高橋が演じ、樹里役を土屋貴子が務めた。劇団「文学座」のベテラン演出家・西川信廣が初めてメガホンを取り、俳優・劇作家・小説家として活躍する戌井昭人が、西川の自伝的エピソードを盛り込み脚本を手がけた。』
映画の冒頭は100歳で亡くなった父親の葬儀のシーンから始まります。
それが終わるとすぐに、40年行方知れずになっていた80歳になる兄が、若い女性を連れて(若いといっても80歳の兄が連れてくる女性としては若い、という意味で、映画のなかでも50代か60代という雰囲気ですが)、74歳の生真面目一辺倒で独身を通して父の鉄工所を細々と守ってきた弟の元に、
「これからここで世話になるわ」
と言って戻ってくるところから始まります。
んじゃ、「兄帰る」じゃないの? どうして「兄消える」なの? と最初私もそう思ったのですが、それは映画を観ればわかりますので、ここで語ることはやめておきます。
この兄弟の対比が実に興味深かったです。
弟のほうが地道に堅実に生きてきたわけですから、多少なりとも生活にゆとりがあっても不思議ではないのですが、弟はとにかく父が創りあげた会社をつぶさないようにする、ということだけに使命を感じて生きてきたので、鉄工の機械をローンで借りて、それを返すために受注を受けたのをひとりでコツコツとこなして、という生活で手一杯のようです。
それに対して兄は、恰好といい昔の芸人さんのように洒脱で、語り口もソフトで飄々としていてなんだか人生悟っているっぽい。
コーヒー豆にこだわって1杯のコーヒーを点てたり、ナポリタンの由来を知っていたりと、朝はお決まりのパンと少しばかりのソーセージ、昼はカップラーメンという弟の食生活に比べるとなんだかゆとりがあって贅沢な感じ。
そんな暮らしができるわけがないという匂いはどこか常にそこはかとなくつきまとっているのですが、それでもその場その場が楽しければそれでいいじゃないか、と言われたらそのとおりですしね。
兄は、弟に、
「この様子を見ると、おまえにもし嫁さんと子どもがいたりしたら、とっくにこの工場はつぶれていただろうなぁ」
としみじみと言うシーンがあります。
それがわかっているから結婚はしなかったんじゃないか、と弟は言いたいかもしれません。
だから兄さんのように誰にも迷惑かけてないじゃないか、と。
弟が結婚したほうが幸せだったのか、ひとりでいたほうが幸せだったのか、それは誰にもわかりません。
この映画を観て私は、登場人物の誰もに共感できました。
そして、誰だって、この中の誰かになる可能性はあるんだ、と思いました。
「おまえだって人に追われるような人生になる可能性が0とは言えないんだぞ」というレベルではなく、もっともっと色濃く、すぐにでもそういう人生になる可能性だってあるんだぞ、というくらいに思いました。
弟のようにとにかく親の稼業を継いで、その親が亡くなるまでは何が何でもつぶすわけにはいかない、ということが生活のすべてになる可能性が私にない、とは言えなかった、と思う。
実際には私の親は「自分の仕事なんて継がせたくない」という言動でしたので、私もそんなことは考えずにきましたが、もし親が、
「おまえにここを託すからな。この仕事を守り抜いてくれよ」
なんて言うタイプだったとしたら、また自分がどういう選択をしていたかわかりませんもん。
そしてもし自分が継ぐのがイヤで、放蕩グセのある兄だったら・・・? と思うとそれもまた私ならそうなっていたかもしれない要素もあるな、とも思います。
そして各地をさすらうようにして色んな人と出会い、色んな仕事を楽しみ、人生を楽しみ・・ それはそれでいいなぁ、とも思います。
そしてその兄が連れてきている女性。
彼女の人生がどういうものかは映画の後半に明かされますが、そういう風に自分は絶対ならなかった、とはとうてい言い切れるものではないな、と思いますし。
またご近所さんで同じように町工場を営む弟さんの友人。
ある日突然訪れて、
「わし、工場畳もうと思うんだわ」
と言います。
もう売ることも決めて、奥さんの実家の田舎に移り住むことも決めていました。
もっと早い時期にどうにかならなかったのか!? とつい思いがちですが、また自分がこの人のようにならなかった、とは全然言えません。
ただ1つだけ思ったのは、たとえどの人の人生であったとしても、それぞれに味があり、それぞれに幸せだったんだよなぁ、ということです。
みんな必死に生きているから。
漫然と生きている人なんて誰もいないから。
最近、つくづく思うのですが、人間の幸せって究極的には、「ただ生き抜くこと」。
それに尽きるんじゃないかなぁ、と。
いやいや、もう死んだほうが幸せなくらい辛かったよ、とおっしゃる方もいらっしゃいましょう。
でも、それでも結果的に死ななかったわけじゃないですか。
それがすべての答えです。
古来から人間はただただサバイバルに必死だったはずです。
じゃあ、1日のほとんどの時間を食べ物を狩ることに費やして、ただひたすら生き延びることに必死だった原始の頃の人間には幸せはなかったのか、と言ったらそうではないはずです。
生き抜いて、生き抜いて、生き抜ききったぞ、という人生最期のときに、
「よくやった、自分。もはやここまでか、というところまで、雑巾の最後の1滴を絞るところまで生きたぞ」
って思えたら、それが幸せってことなんじゃないでしょうか。
現代ではそんなサバイバルをすることはないからこそ、幸せの本質を見失っている人が多すぎる。
そんな風にさえ思いました。
でもこの映画の老人たちはみな、人生を謳歌し、必死に生きていました。
それが、まぁ、暗い部分もあったけど、淡々とした映画のなかに力強さを感じたのだ、と思います。
「太陽の自分エクササイズ ~自己受容ヴァージョン~」
リリース!
「自己受容」「自己表現」を網羅した、「This is Meと言える自分になる」 太陽の自分エクササイズ。
それに対して、こちらの「自己受容ヴァージョン」は自己受容に特化した凝縮版です。
今だけの特典あり!
是非こちらをご覧下さい。
********************************************
<今後のワークショップ予定>
「色で暮らしを彩る講座」
場所:ヒーリングサロン「些々羅」 岐阜市
STEP1 募集中! 参加費:¥15000(税込)
※どこで、を問わず、色について学んだことがある人は自己申告により参加費が半額になります。
[内容]
・色からのメッセージ
・色の性質
・その色を使ってどんなことが可能になるの? ~五感を使って色を取り入れる~
座学というより、楽しいワークショップ形式で自然に色のメッセージを自分に取り入れましょう!
STEP2(※STEP2はSTEP1を受講した人のみ受けることができます) ¥20000
STEP3(※STEP3はSTEP1,2を受講した人のみ受けることができます) ¥30000
9/11(水) 10:00~17:00(※ランチ休憩1時間あり) 満席
9/14(土) 10:00~17:00(※ランチ休憩1時間あり) 満席
9/16(月・祝)10:00~17:00(※ランチ休憩1時間あり) 満席
10/11(金) 10:00~17:00(※ランチ休憩1時間あり) 満席
お問い合わせは、 chakra@aura-soma.name まで
********************************************
岐阜の「CINEX」という映画館は、ときどき大手のシネコンではやっていないような映画がかかることがあります。
この「兄消える」という映画もそうでした。(ごめんなさいね。私が知らなかっただけかもしれません)

でもたぶん、じみ~な映画でしたので、そんな大ヒットをハナから狙ったという感じでもないと思うんですよね。
あまり宣伝されている感じでもないし。
なにせ、登場人物は老人ばかりですので、絵面的にも派手さはまったくありません。
しかし、なかなか渋い味のある映画でした。
私の年齢になって観るから余計にそう感じたのかもしれませんが。
いちおう、「映画.com」のあらすじを載せておきます。
『信州・上田を舞台に、40年ぶりに再会した老兄弟の絆を描いたドラマ。戦後昭和を代表する喜劇俳優として知られ、170本以上の映画に出演した柳澤慎一が、本作を自らの遺作にする意向で約60年ぶりに映画主演。同じく大ベテランの俳優で、舞台や映画など幅広く活躍してきた高橋長英が共演し、対照的な兄弟を演じた。町工場を細々と営み、100歳で亡くなった父親の葬式を終えたばかりの76歳の鉄男のもとに、40年前に家を飛び出したきりだった80歳の兄・金之助が、わけありな若い女性・樹里を連れて舞い戻ってくる。独身で真面目な鉄男と、金之助と樹里。3人の奇妙な共同生活が始まるが、やがて金之助の過去や樹里の素性が明らかになり、兄弟がそれぞれに抱えた家族や故郷への思いもまた、よみがえっていく。兄・金之助を柳澤、弟・鉄男を高橋が演じ、樹里役を土屋貴子が務めた。劇団「文学座」のベテラン演出家・西川信廣が初めてメガホンを取り、俳優・劇作家・小説家として活躍する戌井昭人が、西川の自伝的エピソードを盛り込み脚本を手がけた。』
映画の冒頭は100歳で亡くなった父親の葬儀のシーンから始まります。
それが終わるとすぐに、40年行方知れずになっていた80歳になる兄が、若い女性を連れて(若いといっても80歳の兄が連れてくる女性としては若い、という意味で、映画のなかでも50代か60代という雰囲気ですが)、74歳の生真面目一辺倒で独身を通して父の鉄工所を細々と守ってきた弟の元に、
「これからここで世話になるわ」
と言って戻ってくるところから始まります。
んじゃ、「兄帰る」じゃないの? どうして「兄消える」なの? と最初私もそう思ったのですが、それは映画を観ればわかりますので、ここで語ることはやめておきます。
この兄弟の対比が実に興味深かったです。
弟のほうが地道に堅実に生きてきたわけですから、多少なりとも生活にゆとりがあっても不思議ではないのですが、弟はとにかく父が創りあげた会社をつぶさないようにする、ということだけに使命を感じて生きてきたので、鉄工の機械をローンで借りて、それを返すために受注を受けたのをひとりでコツコツとこなして、という生活で手一杯のようです。
それに対して兄は、恰好といい昔の芸人さんのように洒脱で、語り口もソフトで飄々としていてなんだか人生悟っているっぽい。
コーヒー豆にこだわって1杯のコーヒーを点てたり、ナポリタンの由来を知っていたりと、朝はお決まりのパンと少しばかりのソーセージ、昼はカップラーメンという弟の食生活に比べるとなんだかゆとりがあって贅沢な感じ。
そんな暮らしができるわけがないという匂いはどこか常にそこはかとなくつきまとっているのですが、それでもその場その場が楽しければそれでいいじゃないか、と言われたらそのとおりですしね。
兄は、弟に、
「この様子を見ると、おまえにもし嫁さんと子どもがいたりしたら、とっくにこの工場はつぶれていただろうなぁ」
としみじみと言うシーンがあります。
それがわかっているから結婚はしなかったんじゃないか、と弟は言いたいかもしれません。
だから兄さんのように誰にも迷惑かけてないじゃないか、と。
弟が結婚したほうが幸せだったのか、ひとりでいたほうが幸せだったのか、それは誰にもわかりません。
この映画を観て私は、登場人物の誰もに共感できました。
そして、誰だって、この中の誰かになる可能性はあるんだ、と思いました。
「おまえだって人に追われるような人生になる可能性が0とは言えないんだぞ」というレベルではなく、もっともっと色濃く、すぐにでもそういう人生になる可能性だってあるんだぞ、というくらいに思いました。
弟のようにとにかく親の稼業を継いで、その親が亡くなるまでは何が何でもつぶすわけにはいかない、ということが生活のすべてになる可能性が私にない、とは言えなかった、と思う。
実際には私の親は「自分の仕事なんて継がせたくない」という言動でしたので、私もそんなことは考えずにきましたが、もし親が、
「おまえにここを託すからな。この仕事を守り抜いてくれよ」
なんて言うタイプだったとしたら、また自分がどういう選択をしていたかわかりませんもん。
そしてもし自分が継ぐのがイヤで、放蕩グセのある兄だったら・・・? と思うとそれもまた私ならそうなっていたかもしれない要素もあるな、とも思います。
そして各地をさすらうようにして色んな人と出会い、色んな仕事を楽しみ、人生を楽しみ・・ それはそれでいいなぁ、とも思います。
そしてその兄が連れてきている女性。
彼女の人生がどういうものかは映画の後半に明かされますが、そういう風に自分は絶対ならなかった、とはとうてい言い切れるものではないな、と思いますし。
またご近所さんで同じように町工場を営む弟さんの友人。
ある日突然訪れて、
「わし、工場畳もうと思うんだわ」
と言います。
もう売ることも決めて、奥さんの実家の田舎に移り住むことも決めていました。
もっと早い時期にどうにかならなかったのか!? とつい思いがちですが、また自分がこの人のようにならなかった、とは全然言えません。
ただ1つだけ思ったのは、たとえどの人の人生であったとしても、それぞれに味があり、それぞれに幸せだったんだよなぁ、ということです。
みんな必死に生きているから。
漫然と生きている人なんて誰もいないから。
最近、つくづく思うのですが、人間の幸せって究極的には、「ただ生き抜くこと」。
それに尽きるんじゃないかなぁ、と。
いやいや、もう死んだほうが幸せなくらい辛かったよ、とおっしゃる方もいらっしゃいましょう。
でも、それでも結果的に死ななかったわけじゃないですか。
それがすべての答えです。
古来から人間はただただサバイバルに必死だったはずです。
じゃあ、1日のほとんどの時間を食べ物を狩ることに費やして、ただひたすら生き延びることに必死だった原始の頃の人間には幸せはなかったのか、と言ったらそうではないはずです。
生き抜いて、生き抜いて、生き抜ききったぞ、という人生最期のときに、
「よくやった、自分。もはやここまでか、というところまで、雑巾の最後の1滴を絞るところまで生きたぞ」
って思えたら、それが幸せってことなんじゃないでしょうか。
現代ではそんなサバイバルをすることはないからこそ、幸せの本質を見失っている人が多すぎる。
そんな風にさえ思いました。
でもこの映画の老人たちはみな、人生を謳歌し、必死に生きていました。
それが、まぁ、暗い部分もあったけど、淡々とした映画のなかに力強さを感じたのだ、と思います。










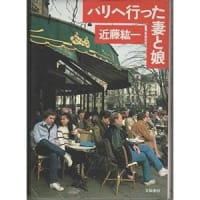








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます