神野直彦(2002)『地域再生の経済学』中公新書
「財政と民主主義」を読んでの再読である。そこには財政あっての経済とある。国家債務が危機的な状態にある中、国の失敗を国民と自治体にしわ寄せする。それでも武器の爆買い、自民党の裏金である。国民の怒りは3補選で野党勝利に表れた。以下本の抜き書きである。( )内は私のコメント。
工業都市が衰退しているのも、歴史が工業社会から情報・知識社会へ転換しているからである。情報・知識社会になったからといって、ものづくりが終わりを告げるというわけではない。(ものづくりは農林業も含むべきである。)生産性の向上とは、人間の知識の向上のたまものである。工業社会から情報・知識社会へと転換するエポックに、工業都市は衰退し地方都市は荒廃する。そこで都市再生が課題となる。(全国的に工業都市は衰退したが、地方都市の豊田市の工業は衰退していないけれど、人口減や下請け企業と農林業の衰退などがみられる。)
ヨーロッパの地域再生とは、市場主義によらない地域再生であり、それは市民の共同の経済である財政による地域再生と言うことができる。都市再生のキーワードは環境と文化である。自動車の侵入しない人間が歩きたくなる市街地の地価は上昇し、高級ブランド店やフランチャイズ店が進出して商店街は活況を呈している。市場主義による都市再生によって市街地の地価が下落し、かつ商店街が荒廃している日本の現状とは好対照をなしている。(現在はEUでは移民が増え右翼ナショナリズムが台頭。豊田市では再開発で高層ビルが出来、人口が増えても既存の商店は追い出され、百貨店、スーパーも閉鎖に追い込まれている。それでもイベントを軸に都市整備をトヨタと進めている。)人間的都市に優秀な人間が集結し、新しい産業が芽生え、ストラスブール(フランス北東部の都市)では雇用も増加している。
失敗に学習することなく、今また市場主義に基づく都市再生が展開している。大地の上に巨大な構造物が竣立するけれども、大地の上から人間の生活は奪われ、無機質な死せる都市が誕生するだけである。地域再生とは、人間の生活の場の創造に他ならない(豊田市では駅前再開発で高層マンションは増え、綺麗になったが賑わいがない。地元商店は追い出され、ついにメグリアまで撤退に追い込まれた。それでもイベント型の都市整備をすすめる。失敗に学ぶことがない)。サスティナブルシティは人間の生活の場としての持続可能性である。つまりサスティナブルシティとは工業の衰退によって、荒廃した都市の生活の場としての持続可能性(sustainable)を目指す都市に、再生しようとする動きである。(豊田市のすすめる「コンパクトシティ」は駅周辺に人口や都市施設を集約するが、農山村は放置し衰退している)。地域社会再生は帝国を目指す覇権国アメリカが、推進するグローバリゼーションへの対抗モデルでもある。グローバリゼーションこそ自然破壊の最大の脅威であり、人類の生存を脅かす破壊者でもある。良好な自然環境とともに人間的接触(交流)を可能にする公共空間が提供されなければ、地域文化を沸き立たせることはできない。(スタジアムのある中央公園は、農地を潰し洪水浸水区域に木をたくさん植える公園計画で、スタジアムのための大駐車計画でありPFIでトヨタ系会社が作ろうとするものである。市民に知られては困り、情報が未開示である)。市場主義を拒否した地域再生とは、市民の共同の経済である財政による地域再生であることを意味する。地域再生とは「公」を再生し大地の上に、人間の生活を築く戦略だと言うことができる。
農業では生活の場は生産の場と一致する。農業社会の都市とは農村の余剰生産物が取引される市場であり、周辺に配置されている農村の交流の場ということができる。都市には、二つの顔がある。一つは市場という顔で、もう一つは自治という顔である。
終わろうとしている大量生産・大量消費の工業社会は、国民国家の時代でもあった。このエポック(時節)には、国民国家の時代も激しく動揺しているということができる。国民国家が競争原理に基づく市場経済を、福祉国家を形成して制御することで実現した大量生産・大量消費の工業社会が行き詰まっているからといって、それが失敗だったというわけではない。歴史的使命を終えたということができる。
生産性上昇の恩恵にあずかれるものは、企業に雇用されているものだけである。働いていない失業者や、働くことのできない疾病者あるいは高齢者などは除外されてしまう。そこで政治システムが所得再分配を実施する。例えば埼玉県が、所得再分配を強化すれば埼玉県に貧しい者が流入し、豊かなものが流出してしまう。これが地方自治体が所得再分配を実施しても意味がない、という理由である。所得再分配国家の前提だったブレトン・ウッズ体制は、1971年にアメリカの一方的な通告によってもろくも崩れることになる。一環としてドルと金の交換を停止し、実質的にドル切り下げとなる輸入課徴金賦課を発表したからである。
工業では自然が排除され、合成ゴムに限らず自然には存在しない多くの合成物質が、現在では利用されている。そうした合成物質が自然の再生力を奪い、ひいては人間の生活を破壊して行くことになる。「ヨーロッパ・サスティナブル都市最終報告書」も「市場メカニズムに依存していたのでは、都市の持続可能な成長は実現できない、と述べている。
リストから財政学が継承した思想は大きく二つにまとめられる。第一に、市場経済の外側にある非市場経済をも考察の対象とするということである。第二に、コミュニティつまり地域共同体を重視するということである。 1980年代になると、ブレトン・ウッズ体制が崩れ、金融自由化が進み、資本は一瞬のうちに租税負担の低い国民国家へとフライトしてしまう。逆に貧者に手厚い現金給付を施せば、貧者は流入してくる。そうなればたちまち財政は破綻してしまう。そこで第二次大戦後のブレトン・ウッズ体制の下では資本の自由な動きを制御する資本統制の権限が、国民国家に認められていたのである。
社会的セーフティ・ネットが存在し、努力しないでいい敗者になったとしても救済されてしまうから、モラルハザードが働く。努力した者が報われる社会を形成しよう。効率の悪い者が破れ、効率のよいものが勝者となる 頑張った者は報われる、競争社会が活力を生む、という新自由主義社会である。
やがて皮肉な事に、唯一の地場産業として地方には公共事業が残るだけになった。地方都市が唯一の地域産業である公共事業に、縋らざるを得ない状況が出来上がってしまったのである。(豊田市の財政は恵まれているが、ハードと大企業優遇である。自民党は普通建設事業300億円以上を要望し、市はそれを実施している)。
地域社会に根ざした食文化を失えば、自給率は急速に落ち込む。日本は食の文化を破壊して、食料自給率を落ち込ませてきたけれども、工業製品を輸出することで食糧の輸入を確保してきた。工業製品を製造する工場は1990年代に海外へとフライトをし始めた。(みよし市の食料自給率は9%と議会答弁しているが、豊田市で聞いても教えてもらえない。以前は15%と聞いたことがある)。










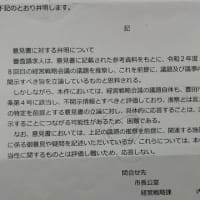















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます