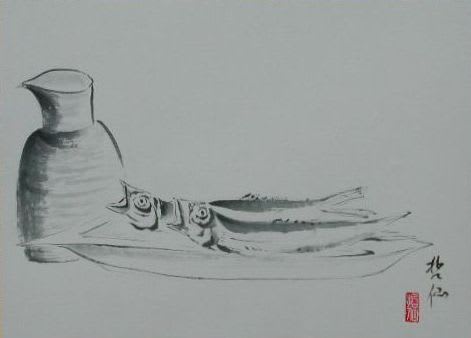冬枯や雀のあるく樋の中 炭太祇(たんたいぎ)
(冬枯や雀のありく戸樋の中)
太祇は江戸中期の江戸の人。俳句を水国に師事したが、師の没後、京の島原に出て伎楼の主人の支援を得る。7歳年下の蕪村とも親交があった。外は冬枯れて、樋(とい)の中の雀の歩く音に心を奪われているのだが、当寺の樋は竹であったろう。雀は歩くことは少なく、両足をそろえて跳ねながら移動する。現在のブリキ、否、プラスティックほど音は出ないだろう。
(冬枯や雀のありく戸樋の中)
太祇は江戸中期の江戸の人。俳句を水国に師事したが、師の没後、京の島原に出て伎楼の主人の支援を得る。7歳年下の蕪村とも親交があった。外は冬枯れて、樋(とい)の中の雀の歩く音に心を奪われているのだが、当寺の樋は竹であったろう。雀は歩くことは少なく、両足をそろえて跳ねながら移動する。現在のブリキ、否、プラスティックほど音は出ないだろう。