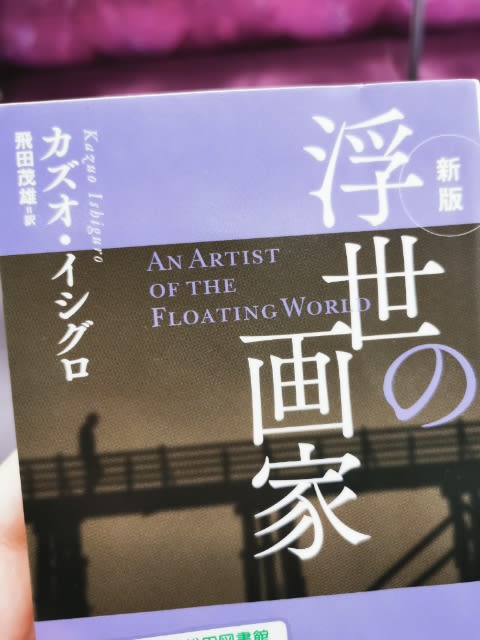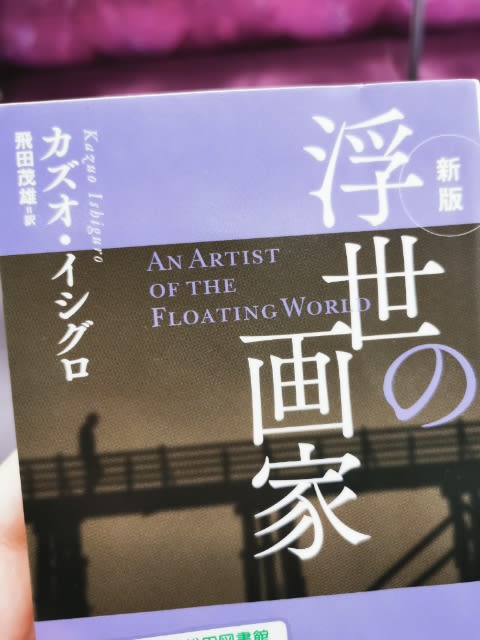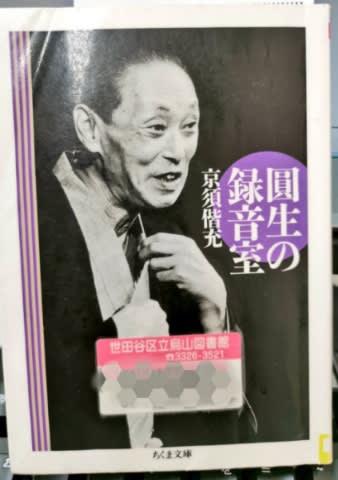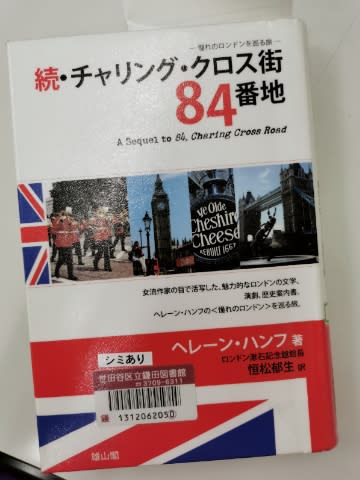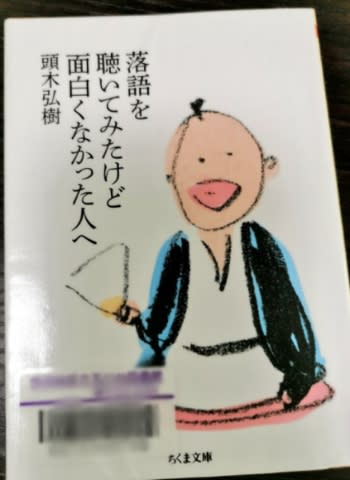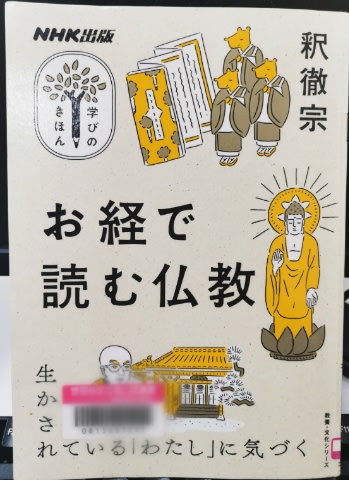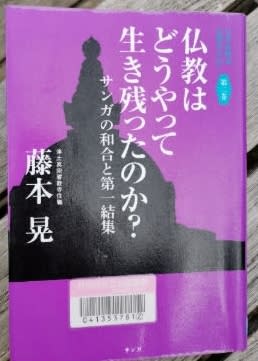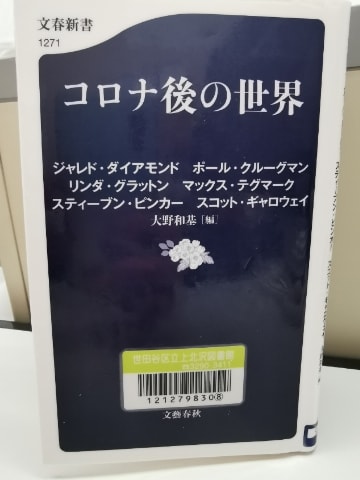今やってるNHKラジオの「古典講読」は万葉集です。私の万葉集の知識は、高校で習ったところまでなので、ほぼ初めて聞く話ばかりで面白いです。
鏡王女(かがみのおおきみ)と中臣鎌足の相聞歌を取り上げている回がありました。
玉櫛笥覆ふを安み明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも
玉櫛笥 みもろの山の さな葛 さ寝ずは遂に 有りかつましじ
万葉集にはいろんな状況の歌が入っていますが、この歌を送りあうタイプのもの(相聞)は、どうして両方セットで後世に伝わっているのでしょうか?
手紙のようなものだとしたら、セットになってるというのは不思議です。この歌の返歌がこの歌、と特定することも難しそうですし・・。
宴会の席などでふたりが一緒の場所にいて、(さらに公衆の面前で)詠みあって第三者が記録してたとかならわかるのですけど。
万葉集にもそういう宴席での余興的な歌もたくさんあるそうです。上記の鏡王女と中臣鎌足の歌がそれに当たるかは知りませんが。
ラブレター的なもので、しかも「人目を忍んでいる」状況の歌なら、残りにくいんじゃないかな?
うーん。
なんだかすごく気になってきました。
そうだ!
同級生に万葉集の専門家になった人がいたっけ。
聞いてみよう。
以下、わたしと同級生(専門家)のやり取り(相聞)です。
私
「こんばんは。 万葉集について質問なのですが…。 個人に宛てた相聞歌とか、どういう経緯で第三者の知るところとなり、歌集に収録されたのでしょうか?? 昔からそれが不思議でしょうがないのです。 昔のことで、コピーもないし、個人にあてた歌が残るのが不思議です。 すみません、気になってしょうがなくなってしまいました。」
友人
「こんばんは。 ご無沙汰です。相談の件、個人的には以下のように考えています。 万葉集の場合、歌人名が分かる相聞の歌はある程度偏りがあります。また歌人名が分からない相聞歌はある程度類型化された表現です。 前者の歌は、恐らくそれぞれが歌のメモなどを残していた。それらが万葉集の編集で利用されたのだと思います。後者の歌は、類型化されているので、似た歌が沢山詠まれていた。そうした歌が現在見るような万葉集の歌なのだと創造されます。 これは古今集以降の王朝和歌とは、また異なる残り方なのだと思います。こんなもんでいかがでしょうか。」
私
「早速のお返事ありがとうこざいます!! めも!! びっくりです。 とすると、万葉集を編むときに、「歌を集めまーす!」とかアナウンスがあり、子孫が応募したとか何でしょうか?(あるいは編者が著名な人の家に行き、「御宅にになんか先祖の歌残ってませんかねー書付とか?」と調査して回ったって感じなんでしょうか?? 類型化した方のは、流行り歌的に その時代の人々が ある程度みんなが知っていたような伝わり方をしていたってことでしょうか??
その辺のことが書かれた参考書とかありますか??」
友人
「編集の時にはある程度周辺の人に頼んだんじゃないですかね。また、古歌集などから拾った歌だと書いてあるので、そうした歌集が早くからあったんだと思います。 類型化した歌は、ある程度知られていたのだと思います。 参考になるような書物、バッチリではないですが、入門書としては、上野誠『万葉集講義』(中公新書)が参考になります。 」
ということで、読んでみました。
「万葉集講義」
面白かった!
はじめはもじどおり「うた」 っていた「うた」が、文字(漢字)の浸透とともに買い留められるようになってゆき、
「だれが、どこで、どんなシチュエーションで」詠んだものか。
が重視されてきた。
というはなしが、目からウロコでした。
硬いタイトルですが、歌の現代語訳が砕けててとても楽しく読めました。
一例を・・・
大伴旅人が九州勤務を終えて都に帰任するときの送別会での山上憶良の歌
あがぬしの御霊たまひて 春さらば 奈良の都に 召上げたまはね
これについた現代語訳が
よっ!わが主人とも頼む大伴旅人サマ。その旅人サマのコネにすがりまして、春になりますれば、奈良の都に栄転させてくださいましな…。旅人サマ。
面白すぎ!でも状況よくわかりますね。