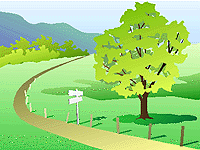マンションにおける 電力 に関しての相談もあります
諸事情の説明は 餅屋は餅屋 で 技術的なこと・改めに必要な総費用のこと など
専門知識を有する方々の解説などを参考にしつつ 疑問点を解決しながらの決断になる
と考えます( アイマイな知識のままでの決断は 厳禁 ですね )
そうした折に まず話題にあがるのは 次の重要な判例です
総戸数544戸のマンション での 圧倒的多数での推進情況下における 反転でした
案件としては 損害賠償等請求 の 裁判です
「高圧受電方式」の採用 に 関する判例です
〔この判決については 以前にも 載せさせていただいています〕
相談の多いことなので あらためて 載せさせていただくこととしました
マンションでお暮らしの方 各種受験者の方 などの参考にしていただければ好いのでは と
考えます
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年(受)第234号 損害賠償等請求事件
平成31年3月5日 第三小法廷判決
主 文
原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
被上告人の請求をいずれも棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人平田直継の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)
について
1 原審が適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人ら及び被上告人は,いずれも札幌市内の区分所有建物5棟から成る
総戸数544戸のマンション(以下「本件マンション」という。)の団地建物所有
者である。
(2) 本件マンションにおいて,団地建物所有者又は専有部分の占有者(以下,
これらを併せて「団地建物所有者等」という。)は,個別に北海道電力株式会社
(以下「電力会社」という。)との間で専有部分において使用する電力の供給契約
(以下「個別契約」という。)を締結し,団地共用部分である電気設備を通じて電
力の供給を受けている。
(3) 平成26年8月に開催された本件マンションの団地管理組合法人(以下「本件団
地管理組合法人」という。)の通常総会において,専有部分の電気料金を削減するた
め,本件団地管理組合法人が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結し,
団地建物所有者等が本件団地管理組合法人との間で専有部分において使用する電力の
供給契約を締結して電力の供給を受ける方式(以下「本件高圧受電方式」という。)
への変更をする旨の決議がされた。
本件高圧受電方式への変更をするためには,個別契約を締結している団地建物所
有者等の全員がその解約をすることが必要とされている。
(4) 平成27年1月に開催された本件団地管理組合法人の臨時総会において,本件
高圧受電方式への変更をするため,電力の供給に用いられる電気設備に関する団地
共用部分につき建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)65条に基
づく規約を変更し,上記規約の細則として「電気供給規則」(以下「本件細則」と
いう。)を設定する旨の決議(以下,上記(3)の決議と併せて「本件決議」という。)
がされた。本件細則は,本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはなら
ないことなどを定めており,本件決議は,本件細則を設定することなどにより団地
建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるものであった。
(5) 本件団地管理組合法人は,平成27年2月,本件決議に基づき,個別契約を締結
している団地建物所有者等に対し,その解約申入れ等を内容とする書面を提出する
よう求め,上告人ら以外の上記団地建物所有者等は,遅くとも同年7月までに上記
書面を提出した。しかし,本件決議に反対していた上告人らは,上記書面を提出せず,
その専有部分についての個別契約の解約申入れをしない。
2 本件は,被上告人が,上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れ
をすべきという本件決議又は本件細則に基づく義務に反して上記解約申入れをしない
ことにより,本件高圧受電方式への変更がされず,被上告人の専有部分の電気料金が
削減されないという損害を被ったと主張して,上告人らに対し,不法行為に基づく損
害賠償を求める事案である。
3 原審は,前記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,被上告人の請求
を認容すべきものとした。
本件マンションにおいて電力は団地共用部分である電気設備を通じて専有部分に
供給されており,本件決議は団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決す
るなどして本件高圧受電方式への変更をすることとしたものであって,その変更を
するためには個別契約の解約が必要である。したがって,上記変更をするために団
地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるなどした本件決議は,法66
条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するから,
上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れをしないことは,本件決
議に基づく義務に反するものであり,被上告人に対する不法行為を構成する。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1) 前記事実関係等によれば,本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議
には,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの,
本件決議のうち,団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,
専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又はその
管理に関する事項を決するものではない。したがって,本件決議の上記部分は,法
66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するも
のとはいえない。このことは,本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の
解約が必要であるとしても異なるものではない。
(2) そして,本件細則が,本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等
に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても,その部分は,法66条
において準用する法30条1項のを定めたものではなく,同項の規約として効力を
有するものとはいえない。
なぜなら,団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解
約するか否かは,それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用
又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし,また,本件高圧受電方
式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず,この変更がさ
れないことにより,専有部分の使用に支障が生じ,又は団地共用部分等の適正な管
理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。
また,その他上告人らにその専有部分についての個別契約の解約申入れをする義
務が本件決議又は本件細則に基づき生ずるような事情はうかがわれない。
(3) 以上によれば,上告人らは,本件決議又は本件細則に基づき上記義務を負うもの
ではなく,上告人らが上記解約申入れをしないことは,被上告人に対する不法行為
を構成するものとはいえない。
5 これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が
ある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そ
して,以上に説示したところによれば,被上告人の請求はいずれも理由がないから,
第1審判決を取り消し,同請求をいずれも棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
・・・・・・・・・・
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
あらためて読んでみても
・・・その変更をするためには個別契約の解約が必要である。したがって,上記変更
をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるなどした本件決
議は,法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有する
とする
理由 3 のところなどは やはり ムリのある展開を述べているのでは という感が
うかがえそうですね
皆さんは いかがですか ?
17条 は [共用部分の変更]
18条 は [共用部分の管理]
ですからね
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
シンプルに言ってしまうと
各専有部分所有者にとって より合理的な電力の利用方法というものが在ると考え
られる場合に その利用方法採用への協力義務を課すことが「団地建物所有者相互
間の事項」に該当することであり 規約で専有部分所有者へのなんらかの制約の発生
も止むを得ないことがある
とするか
そうではなく
専有部分所有の各区分所有者の 私的所有権絶対(自分の財産のことについて 他から
の干渉を受けない
たとえ 一般的には多くの他者にとって経済性の点で負担が軽くなることについてのこ
とであるとしても)の尊重の優位を認めるべき場面なのだ と捉えるか
という
両者においての比較考量のこと なのかな と
自身は解しています
(結論からいうと 法的には 妥当な判決であると 一介の素浪人である自身には思えます・・・
多数ではありますが 各専有部分所有者負担の料金のことであって 共用部分について
の直接的な料金軽減のことではない と 判決文での概要から読めるので・・・つまると
ころ 個人における電力利用対価のことで 圧倒的多数であっても他者がアーダコーダ指図
するのは オカシイ
というところに落ち着きざるを得ない のでは と・・・)
ただ 電力利用の形は サマザマであろう と 考えられるので 各々の案件を ジックリ
検討し
各マンション管理組合の対応も サマザマ でしょうから 判例の結論部だけが 先走りする
ことには 注意が必要なこと 当然ですので 誤解の無いようにしなければなりませんね












![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b7c5897.aceb60c1.1b7c5898.235f6552/?me_id=1213310&item_id=20713037&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5590%2F9784641115590_1_21.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b7c5897.aceb60c1.1b7c5898.235f6552/?me_id=1213310&item_id=20713037&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2Fnoimage_01.gif%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b7c5897.aceb60c1.1b7c5898.235f6552/?me_id=1213310&item_id=17182490&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2043%2F9784535002043.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b7c5897.aceb60c1.1b7c5898.235f6552/?me_id=1213310&item_id=20341969&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3960%2F9784909683960_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b7c5897.aceb60c1.1b7c5898.235f6552/?me_id=1213310&item_id=18724841&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9366%2F9784326499366.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b7c5897.aceb60c1.1b7c5898.235f6552/?me_id=1213310&item_id=20673164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9369%2F9784910499369.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)