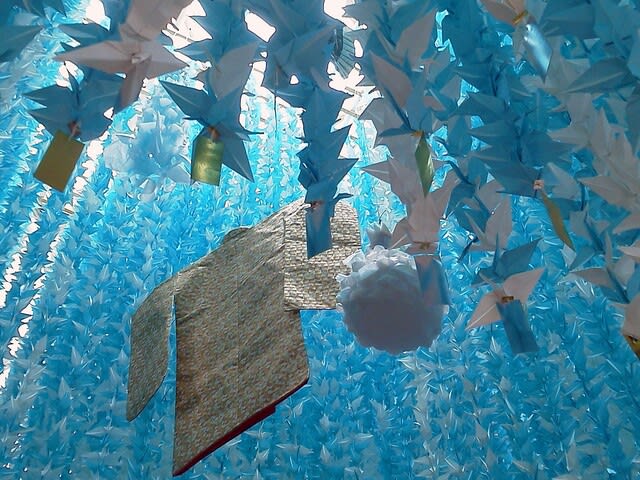好晴の一と日となった文化の日。
気温も上がりシャツ一枚でも十分である。
地元の歴史を学びつつ俳句を詠もうと集まった友と
兵庫の津を楽しく逍遥した。
竹中工務店が建てたという江戸の家屋を模した
兵庫津ミュージアムをまず訪問。そこで
ボランティアガイドさんから少しレクチャーを受ける。
見どころを伺って、さて兵庫津巡りへ出発。
まずは清盛塚、琵琶塚へ。そして槙の並木道を
一篇上人示寂の地である真光寺へ向かう。
お香の良き香りの中、お堂の中を見学してから
墓所に立ち寄りしばし一遍上人を偲ぶ。そして
兵庫大仏のある能福寺へ。日本三大仏のひとつ
と言われる兵庫の大仏様を秋天に仰ぎ見る。
ちなみに後の二つは勿論、奈良と鎌倉の大仏様だ。
それから古代大輪田泊の石椋(いわくら)を見て
運河沿いを歩く。兵庫城跡という標にはほろほろと
木の葉が散っていた。まるで光陰を偲ぶかに。
こういう吟行をしているとあっという間にお昼時間
が来てしまう。お腹も空いたので、中央市場の海鮮丼
を食べようとなったが、これがすでに十人待ちという。
仕方ないのでイオンの中のフードコートでお昼を。
悠久の歴史に思いを馳せつつ、地元兵庫の
歴史を学べた文化の日となった。