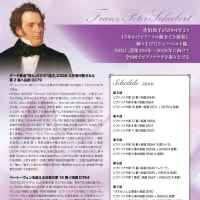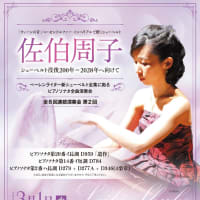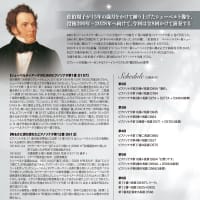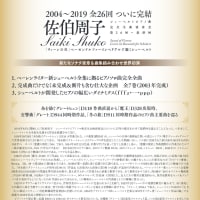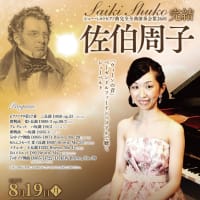『トランスクリプション名曲集』と銘打たれた下野竜也指揮読響公演。「編曲モノ」ばかり6曲ずらりと並べたプログラムは壮観であると同時に、滅多に見ることのできないモノ。私高本が1996年に「デイリー」を立ち上げて以来、「オペラ or オケ → ピアノ」の編曲モノは、高須博リサイタルで何度も取り上げて来たし、2001年12月には「川上敦子リサイタル」で主催したこともあるが、「オルガン or ピアノ など → オケだけの演奏会」は記憶に全くない。新たな試み、に感じる。
冒頭に、「東日本巨大地震」の被災者のために、「拍手無しで」バッハ管弦楽組曲第3番ニ長調アリアが弦5部で演奏され黙祷を捧げた後に、プログラムは開始された。以下の内容。
事前に発表されていなかった(かつ、演奏会後も掲示されなかった)アンコールのモーツァルト作品編曲者を除くと、「最初と最後の原作者がバッハ、それ以外は全て違う作曲家」というのが目を惹く。
がこの演奏会の最大の収穫。冒頭の「バッハ/エルガー」からして「エルガーサウンド」が響く。これは、下野竜也の狙いだ! 「バッハのオリジナル尊重」だと、オルガン曲なので クレッシェンドやデクレッシェンドは不可能。バッハ自身はデュナーミクを変えたい時には「声部数」を変えて対応していたのが、オルガン曲なのである。(他にはトリルで強調する時も多々あった。)
エルガー編曲は「耳当たりが極めて良い」のが美点。勿論、クレッシェンドやデクレッシェンドもある。「滑らか!」の1語に尽きる。続く「ブラームス/ベリオ」はこの日最も違和感があった演奏。四戸世紀のクラリネットは「正調」であったし、下野竜也+読響も誠実な演奏だったのだが、「クラリネット+ピアノのオリジナル版」に比べて、優れた点が聞こえ難いのだ。他の編曲が1930年以前に為されているのに大きく時間が離れて1986年の編曲なことが大きな原因のように思える。1986年には「クラシック音楽用コンサート用編曲需要」は聴き手側からは皆無だったからである。ベリオの才能うんぬんでなく、(ビュッセル以前の編曲者たちは)「流行しなければ、食いはぐれる」危機感の中で編曲している。特に、ベルリオーズとワーグナーは相当に危機感があった「貧乏時代」の編曲だった、と記憶している。「ブラ-ムスのピアノの低音の魅力」が全く生きない編曲に聞こえたが、おそらく編曲に起因すると感じた。なぜなら、直後のアンコールでの 四戸世紀ソロの モーツァルト「アダージオ」ヘ長調K.580a が名演だったからである。原曲が、「ソロクラリネット + 伴奏バセットホルン3重奏」の曲を「ソロクラリネット + 弦5部」で演奏した。私高本は「ザビーネ・マイヤー率いるバセットホルン3重奏団」のCDでしか聴いたことが無かった曲なので、アンコール開始直後は「曲の同定」に少々時間を要した(泣
演奏は素晴らしかった。ちなみに「ベーレンライター新モーツァルト全集」では「縮刷版第17巻P484に掲載」だが、元々が声部に空白のある曲。1789年9月作曲と推定。後半部は「主旋律のみ記入」の楽譜なので、補筆者によって印象が大いに異なるはずなのだが、誰の補筆 & 編曲版だったのだろうか? ブラームス/ベリオ を遙かに上回る名演を聴かせてくれた 四戸 + 読響に感謝! ところで誰の編曲だったのだろうか? 掲示は無かったように思う(泣
後半の開始は目覚ましかった。「ワーグナーサウンド」がいきなり響く。「さまよえるオランダ人」序曲のようだ。よくも悪くも「ワーグナー世界」であり、「グルックの世界」からはちょっと遠い。
続くベルリオーズ編曲は、この日最大の聴きどころ。冒頭の 嶺田のソロチェロから緊密なサウンドが充満。木管も素晴らしい! ワルツ主部の爆発も素晴らしく「幻想交響曲第3楽章の異稿」を聴かせれているかのようだった。
最後のシェーンベルク編曲バッハ:前奏曲とフーガBWV.552「聖アン」。これはエルガー編曲とは「モノが違う」名編曲であり、名演だった。シェーンベルクの編曲と言うと「ブラームスのピアノ4重奏曲第1番編曲」ばかり聴かされたので、相当にイメージが悪かった > 今日まで。
打楽器がカンカン鳴るだけの編曲だからだ > ブラームスのオリジナルに比較して
BWV.552のシェーンベルク編曲は、エルガーを遙かに凌駕する編曲だった。「クラリネットを6本使用」などと言う、信じられない巨大編成なことだけが「演奏頻度あるの?」と思わせたが。
ソリストアンコールまで「編曲モノ」で揃えたこの日の演奏会。定年で退官する四戸も納得でのプログラムだろう。これだけ「統一感が保たれて、作曲者も編曲者も異なる演奏会」を設計したのは誰だろう? 素晴らしい!
・・・で、できることならば、アンコール曲の K.580a の編曲者を教えて下さい > 読響
明日、全く同じ演奏会が 横浜みなとみらいホールである。チケットも余裕。興味ある方は是非是非聴いてほしい。
冒頭に、「東日本巨大地震」の被災者のために、「拍手無しで」バッハ管弦楽組曲第3番ニ長調アリアが弦5部で演奏され黙祷を捧げた後に、プログラムは開始された。以下の内容。
バッハ/エルガー:幻想曲とフーガ ハ短調BWV.537
ブラームス/ベリオ:クラリネットソナタ第1番ヘ短調作品120/1
モーツァルト/???:アダージオ ヘ長調K.580a(アンコール)
グルック/ワーグナー:「アウリスとイフィゲニア」序曲
ウェーバー/ベルリオーズ:「舞踏への勧誘」作品65
ドビュッシー/ビュッセル:小組曲
バッハ/シェーンベルク:前奏曲とフーガ「聖アン」BWV.552
事前に発表されていなかった(かつ、演奏会後も掲示されなかった)アンコールのモーツァルト作品編曲者を除くと、「最初と最後の原作者がバッハ、それ以外は全て違う作曲家」というのが目を惹く。
「編曲者のサウンド優先」がこの演奏会での指揮者=下野竜也の狙いであり、見事に実現した!
がこの演奏会の最大の収穫。冒頭の「バッハ/エルガー」からして「エルガーサウンド」が響く。これは、下野竜也の狙いだ! 「バッハのオリジナル尊重」だと、オルガン曲なので クレッシェンドやデクレッシェンドは不可能。バッハ自身はデュナーミクを変えたい時には「声部数」を変えて対応していたのが、オルガン曲なのである。(他にはトリルで強調する時も多々あった。)
エルガー編曲は「耳当たりが極めて良い」のが美点。勿論、クレッシェンドやデクレッシェンドもある。「滑らか!」の1語に尽きる。続く「ブラームス/ベリオ」はこの日最も違和感があった演奏。四戸世紀のクラリネットは「正調」であったし、下野竜也+読響も誠実な演奏だったのだが、「クラリネット+ピアノのオリジナル版」に比べて、優れた点が聞こえ難いのだ。他の編曲が1930年以前に為されているのに大きく時間が離れて1986年の編曲なことが大きな原因のように思える。1986年には「クラシック音楽用コンサート用編曲需要」は聴き手側からは皆無だったからである。ベリオの才能うんぬんでなく、(ビュッセル以前の編曲者たちは)「流行しなければ、食いはぐれる」危機感の中で編曲している。特に、ベルリオーズとワーグナーは相当に危機感があった「貧乏時代」の編曲だった、と記憶している。「ブラ-ムスのピアノの低音の魅力」が全く生きない編曲に聞こえたが、おそらく編曲に起因すると感じた。なぜなら、直後のアンコールでの 四戸世紀ソロの モーツァルト「アダージオ」ヘ長調K.580a が名演だったからである。原曲が、「ソロクラリネット + 伴奏バセットホルン3重奏」の曲を「ソロクラリネット + 弦5部」で演奏した。私高本は「ザビーネ・マイヤー率いるバセットホルン3重奏団」のCDでしか聴いたことが無かった曲なので、アンコール開始直後は「曲の同定」に少々時間を要した(泣
演奏は素晴らしかった。ちなみに「ベーレンライター新モーツァルト全集」では「縮刷版第17巻P484に掲載」だが、元々が声部に空白のある曲。1789年9月作曲と推定。後半部は「主旋律のみ記入」の楽譜なので、補筆者によって印象が大いに異なるはずなのだが、誰の補筆 & 編曲版だったのだろうか? ブラームス/ベリオ を遙かに上回る名演を聴かせてくれた 四戸 + 読響に感謝! ところで誰の編曲だったのだろうか? 掲示は無かったように思う(泣
後半の開始は目覚ましかった。「ワーグナーサウンド」がいきなり響く。「さまよえるオランダ人」序曲のようだ。よくも悪くも「ワーグナー世界」であり、「グルックの世界」からはちょっと遠い。
続くベルリオーズ編曲は、この日最大の聴きどころ。冒頭の 嶺田のソロチェロから緊密なサウンドが充満。木管も素晴らしい! ワルツ主部の爆発も素晴らしく「幻想交響曲第3楽章の異稿」を聴かせれているかのようだった。
最後のシェーンベルク編曲バッハ:前奏曲とフーガBWV.552「聖アン」。これはエルガー編曲とは「モノが違う」名編曲であり、名演だった。シェーンベルクの編曲と言うと「ブラームスのピアノ4重奏曲第1番編曲」ばかり聴かされたので、相当にイメージが悪かった > 今日まで。
打楽器がカンカン鳴るだけの編曲だからだ > ブラームスのオリジナルに比較して
BWV.552のシェーンベルク編曲は、エルガーを遙かに凌駕する編曲だった。「クラリネットを6本使用」などと言う、信じられない巨大編成なことだけが「演奏頻度あるの?」と思わせたが。
ソリストアンコールまで「編曲モノ」で揃えたこの日の演奏会。定年で退官する四戸も納得でのプログラムだろう。これだけ「統一感が保たれて、作曲者も編曲者も異なる演奏会」を設計したのは誰だろう? 素晴らしい!
・・・で、できることならば、アンコール曲の K.580a の編曲者を教えて下さい > 読響
明日、全く同じ演奏会が 横浜みなとみらいホールである。チケットも余裕。興味ある方は是非是非聴いてほしい。