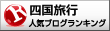8月25日に東京の帰りに掛川城に行って来ました。
日本100名城、第29番目の紀行です。
天正18年(1590年)全国平定した豊臣秀吉は領地に秀吉配下の大名を配置、掛川城に山内一豊が入り初めて天主を創建したとある。安政元年(1854年)東海大地震で天守、御殿、櫓、城門が倒壊した。その後城郭の建物は再建されたが天守は再建されなかった。平成6年に全国で初めて木造で天守を復元したとガイドさんから説明を受けた。元和元年(1615年)一国一城令・武家諸法度が発令、安土桃山時代にあった約3000の城が、170になり幕府は、城持ち大名にたいして城絵図の提出を命じた。絵図が実際の建物と一寸でも違っている事が分かるとその大名は幕府により領地を没収されたり、お家断絶となるので極めて正確に書かれたとされている。掛川城天守の木造復元には此の資料を基に復元されたそうだ。
天守内部に入ってびっくり、それは豪華の木材を使っているのに、階段は欅、天井は青森ヒバを、また杢板として市松模様には高知県の魚梁瀬スギを使っていた。日本初の木造天守復元に掛けた掛川市民の拘りが伺えた素晴らしい天守であった。
なお、山内一豊は1601年関ヶ原の戦いの恩賞により24万石で土佐に転封、高知城天守は、掛川城天守によく似ている。
画像は、龍頭山・標高52,55mの丘に建つ内部造りが素晴らしい掛川天守
私は、天主と天守を使い分けている。前記は、安土桃山時代で、後記、
江戸時代の天守として表記している・・間違っていればご指摘下さい。
日本100名城、第29番目の紀行です。
天正18年(1590年)全国平定した豊臣秀吉は領地に秀吉配下の大名を配置、掛川城に山内一豊が入り初めて天主を創建したとある。安政元年(1854年)東海大地震で天守、御殿、櫓、城門が倒壊した。その後城郭の建物は再建されたが天守は再建されなかった。平成6年に全国で初めて木造で天守を復元したとガイドさんから説明を受けた。元和元年(1615年)一国一城令・武家諸法度が発令、安土桃山時代にあった約3000の城が、170になり幕府は、城持ち大名にたいして城絵図の提出を命じた。絵図が実際の建物と一寸でも違っている事が分かるとその大名は幕府により領地を没収されたり、お家断絶となるので極めて正確に書かれたとされている。掛川城天守の木造復元には此の資料を基に復元されたそうだ。
天守内部に入ってびっくり、それは豪華の木材を使っているのに、階段は欅、天井は青森ヒバを、また杢板として市松模様には高知県の魚梁瀬スギを使っていた。日本初の木造天守復元に掛けた掛川市民の拘りが伺えた素晴らしい天守であった。
なお、山内一豊は1601年関ヶ原の戦いの恩賞により24万石で土佐に転封、高知城天守は、掛川城天守によく似ている。
画像は、龍頭山・標高52,55mの丘に建つ内部造りが素晴らしい掛川天守
私は、天主と天守を使い分けている。前記は、安土桃山時代で、後記、
江戸時代の天守として表記している・・間違っていればご指摘下さい。