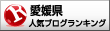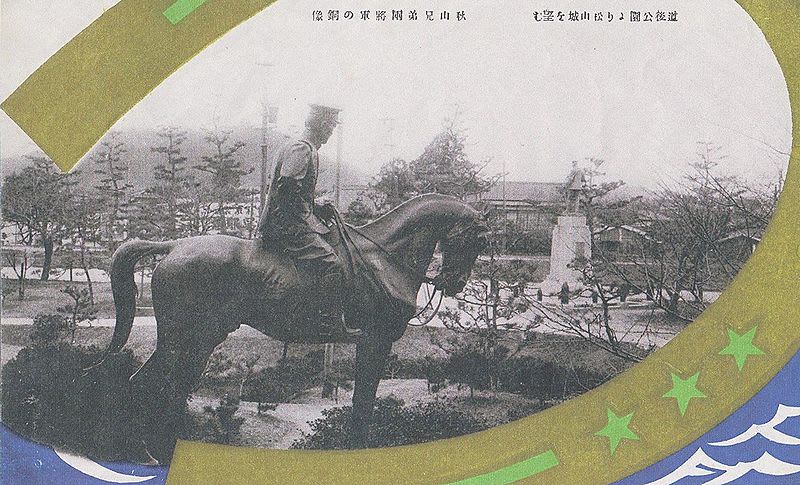えひめ国体は、昭和28年に四国4県で共同開催して以来、64年ぶり、初の単独開催となるもので、愛媛県民総参加のもと、地域をあげて選手や観客をおもてなしするなど、全国から訪れる人々との交流を通した地域の活性化を期待して開催されます。
本県が昔から大切に受け継いできた、四国遍路88ヶ所巡礼文化によって培われた「お接待」の心で、来県される皆さまをおもてなしします。
会期は、平成29年9月30日(土)から10月10日(火)
スローガン:「君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え」
参加するすべての人々が、愛媛を駆け抜ける風のように舞い輝く大会となることをイメージし、愛媛らしく俳句仕立てになっております。
えひめ国体マスコットはみきゃんです。
何にでも前向きで、スポーツが大好きなみきゃんが、えひめ国体を一緒に盛り上げます。
松山市には、松山観光コンベンション協会所属の「松山ボランティアガイドの会」と言う組織があり、松山城・道後温泉等観光地をボランティアでガイドをしております。ガイド全員が、第72回えひめ国体の広報の一環として画像のベストを着用してPR活動をしております。
是非えひめ国体松山にお越し下さい。


第72回国民体育大会愛媛大会マスコットバッチ。
大会愛称は「愛顔(えがお)つなぐえひめ国体」、スローガンは「君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え」。大会マスコットはみきゃんです。
スローガンにある「いしづち」は西日本最高峰・石鎚山、1982mの事です。

松山観光コンベンション協会所属の「松山ボランティアガイドの会」のメンバーはベストを着用し広報活動の一環として寄与しております。
画像はベストの背中に絵画がれている絵文字です。