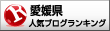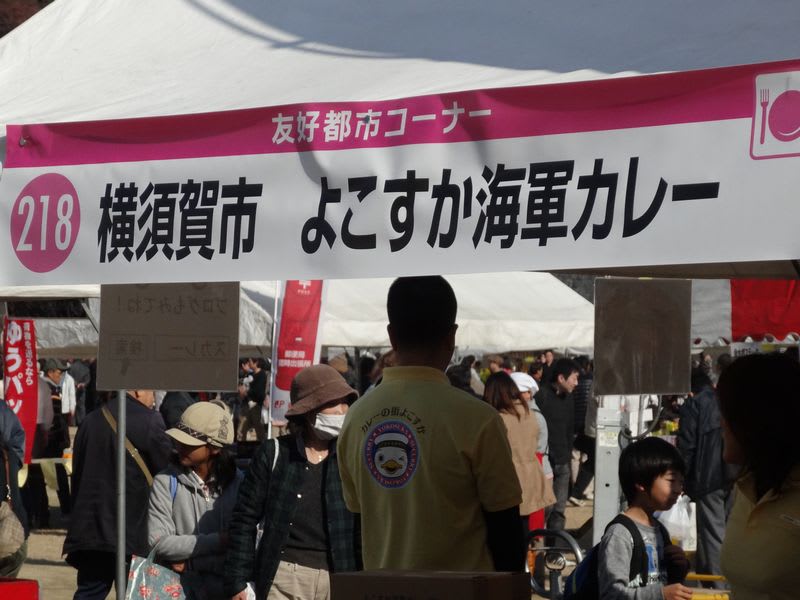昨日28日(水)道後にある湯築城跡にやって来るカワセミを撮りに行ってみた。
カワセミを撮るのは初めて試みであると言うよりも鳥類は初めてである。
以前から湯築城跡にやって来るカワセミを撮影するカメラマンが大勢いることは知っていた。現地に行ってみるとお一人のベテランカメラマンが居たのでカワセミの撮影の秘訣を聞いてみた。プロのカメラマンならば教えてはもらえないだろうが、そこはアマカメラマン色々と教えてくれた。
先ずは、準備するレンズ、カメラ本体をセット(絞り、感度、連写、シャッタースピード)等々、動きのある被写体を撮るのだから難しい。それよりもカワセミが来る場所の把握、時期と時間帯を観察してシャッターチャンスを待つが肝要とか!!・・カワセミは来る場所が殆ど決まった所に来るそうだ。
この時期は、晩秋から冬季に掛けては子育てをしないから水辺に来る事は少ない・・時期は春であると教わった。
しかし全然来ない事はないから待ってみては如何かなとの事、暫し待つ事にした。するとやって来た。
画像はその時のカワセミ・・残念ながら私のレンズは400mmでアップの画像は撮れなかった。800mm以上のレンズが必要の様だ。カワセミは警戒心が非常に強くあまり近づけない。・・だから長いレンズが必要。春までにレンズを準備しておかなくては!!
カワセミは、水辺に生息する小鳥で、鮮やかな水色の体色と長いくちばしが特徴、古くはソニドリ、ヒスイ、青い宝石と呼ばれることもある。

平成14年4月12日に湯築城跡一部復元が完成し史蹟公園として開園、平成14年9月20日に文科相から国史蹟・湯築跡として指定を受けた・・湯築城は、中世の城である・・日本100名城第80番に指定

湯築城跡南側で、画像奥に建物が見えるが(休憩所)この付近にカワセミが来る

休憩所前でカワセミの飛来を根気よくはひたすら待つ・・この日は寒かった


私は10時40分に現地に行った、すると11時33分にやって来た・・私のレンズは短くアップに撮れなかった・・ベテランのカメラマンに聞くと雄のカワセミだそうだ・・常連の撮影者は、雨天以外は毎日撮影に来ているそうで、早朝5時過ぎから午後2時過ぎまで待機するそうだ・・昨日は一度も来なかったが、貴方は今日が始めて運がいいですねと言ってくれたが・・レンズが短く大きく撮れなかった//画像のカワセミは、雄だそうで、雌は下嘴が黄色だそうです

撮るのであれば早く撮って!!俺は多忙なのだからと言わんばかりに此方を見ている

横を向いてくれた・・これでいいかな!!と飛び立った
それから午後3時30分まで待機したがもう来てくれなかった

これがカワセミの巣で、撮ったのは平成16年11月2日湯築城北側で、現在はここには生息してないそうだ

午後3時過ぎカメラをしまい帰る仕度をしていたらこの鳥が飛んできた・・種類は??

湯築城外堀に赤穂から贈られて来たはぜの木が保存されている・・真っ赤に紅葉していた

赤穂から贈られて来たはぜの木説明板が立ててある

湯築城跡には秋山好古揮毫の大きな記念石碑が建立されている
昭和天皇の即位を記念しての碑である
カワセミを撮るのは初めて試みであると言うよりも鳥類は初めてである。
以前から湯築城跡にやって来るカワセミを撮影するカメラマンが大勢いることは知っていた。現地に行ってみるとお一人のベテランカメラマンが居たのでカワセミの撮影の秘訣を聞いてみた。プロのカメラマンならば教えてはもらえないだろうが、そこはアマカメラマン色々と教えてくれた。
先ずは、準備するレンズ、カメラ本体をセット(絞り、感度、連写、シャッタースピード)等々、動きのある被写体を撮るのだから難しい。それよりもカワセミが来る場所の把握、時期と時間帯を観察してシャッターチャンスを待つが肝要とか!!・・カワセミは来る場所が殆ど決まった所に来るそうだ。
この時期は、晩秋から冬季に掛けては子育てをしないから水辺に来る事は少ない・・時期は春であると教わった。
しかし全然来ない事はないから待ってみては如何かなとの事、暫し待つ事にした。するとやって来た。
画像はその時のカワセミ・・残念ながら私のレンズは400mmでアップの画像は撮れなかった。800mm以上のレンズが必要の様だ。カワセミは警戒心が非常に強くあまり近づけない。・・だから長いレンズが必要。春までにレンズを準備しておかなくては!!
カワセミは、水辺に生息する小鳥で、鮮やかな水色の体色と長いくちばしが特徴、古くはソニドリ、ヒスイ、青い宝石と呼ばれることもある。

平成14年4月12日に湯築城跡一部復元が完成し史蹟公園として開園、平成14年9月20日に文科相から国史蹟・湯築跡として指定を受けた・・湯築城は、中世の城である・・日本100名城第80番に指定

湯築城跡南側で、画像奥に建物が見えるが(休憩所)この付近にカワセミが来る

休憩所前でカワセミの飛来を根気よくはひたすら待つ・・この日は寒かった


私は10時40分に現地に行った、すると11時33分にやって来た・・私のレンズは短くアップに撮れなかった・・ベテランのカメラマンに聞くと雄のカワセミだそうだ・・常連の撮影者は、雨天以外は毎日撮影に来ているそうで、早朝5時過ぎから午後2時過ぎまで待機するそうだ・・昨日は一度も来なかったが、貴方は今日が始めて運がいいですねと言ってくれたが・・レンズが短く大きく撮れなかった//画像のカワセミは、雄だそうで、雌は下嘴が黄色だそうです

撮るのであれば早く撮って!!俺は多忙なのだからと言わんばかりに此方を見ている

横を向いてくれた・・これでいいかな!!と飛び立った
それから午後3時30分まで待機したがもう来てくれなかった

これがカワセミの巣で、撮ったのは平成16年11月2日湯築城北側で、現在はここには生息してないそうだ

午後3時過ぎカメラをしまい帰る仕度をしていたらこの鳥が飛んできた・・種類は??

湯築城外堀に赤穂から贈られて来たはぜの木が保存されている・・真っ赤に紅葉していた

赤穂から贈られて来たはぜの木説明板が立ててある

湯築城跡には秋山好古揮毫の大きな記念石碑が建立されている
昭和天皇の即位を記念しての碑である