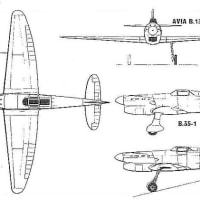大東亜戦争の海軍の戦いについてコンパクトで適切に書かれているものである。ただ海軍の米内光政、山本五十六、井上成美らが反戦の立場から三国同盟に反対したという常識論を書いている(P35)。その後三人が海軍政策から外れると対米強硬派が三国同盟に賛成した、というのだ。相澤淳氏の「海軍の選択」によれば事はそう単純ではないし、そうであろうはずがない。英米協調派と目される山本ですらロンドン条約の随員であった時、財政が厳しいことを言う大蔵省の賀屋興宣を「黙れ、なお言うと鉄拳が飛ぶぞ」と恫喝したのであった。この本には山本がむしろ対米強硬派であり、海軍が三国同盟に反対したのも賛成したのも、建艦予算獲得のためであったことが書かれている。海軍幹部は戦後も嘘をついてまで海軍を護ろうとしている人士がいる。陸軍の行動は満洲利権保護による国家安泰と言う明瞭な目的があったが、海軍には国家なく海軍あるのみであった。前掲書は興味ある一冊である。
閑話休題。昭和十六年七月下旬には海軍中央の対米強硬派の主導によって南部仏印への進駐が行われ、その報復措置として対日石油輸出を全面禁止した(P43)。しかし前傾書によれば米内光政は親ソ反米であり、山本五十六が航空整備に狂奔したのは反米の考え方からである。しかも「大東亜戦争への道」、によれば既に昭和十五年の夏には英米指導者が対日屈伏のために対日石油供給停止について立法まで含めて協議していた(P547)のであり、南部仏印進駐はその口実に過ぎなかった。米国は日本を追い詰める既定の路線を走ったのである。
同書によれば、米国は欧州大戦の推移を見て、日本の南部仏印進駐より前にアイスランドを占領していてグリーンランドに空軍基地を設けていて、日本の南部仏印進駐を非難する資格はなかった(P570)。アメリカも日本も同様に資源確保や軍事的合理性からこれらの行動をとった。本書も結局は全てが日本の行動だけに原因して英米の対日圧力を正当化する、という愚を犯している。外交上の二国間の争いも、一方の国の行動に目を瞑れば他方の国の行動は理由も無い理不尽なものに見えるのである。
山本の真珠湾攻撃の意図について、犠牲を顧みず真珠湾を徹底的に破壊し、敵の闘志を根本から萎えさせるという自らの真意を、南雲機動部隊にも軍令部にも知らせていなかった(P52)という。それを半藤一利氏の証言から、越後人の人見知りで口が重い性格に帰している。しかしこれは指揮官としては見当違いの話であろう。そして山本が、第二撃がやれれば満点だが、泥棒だって帰りは怖いんだ、南雲はやらんだろう(P54)、と言った、というがこれは前述の山本の意図に反した無責任な言動であろう。ここに記されたことが事実ならば山本は指揮官としての能力が欠如している。半藤氏も戸高氏も贔屓の引き倒しをしているのに気付かないのであろうか。
山本五十六は知米派と言われている割に、アメリカの友人に宛てた書簡が全く見当たらない、という秦郁彦氏の指摘を紹介している。他の本でも指摘されているが、山本は何回もアメリカに行っているのにアメリカ人とは付き合わなかったのである。そして攻撃されれば猛烈に反発する米国人気質を知らないから見当違いに士気を阻喪するなどという意図を持ったのである。メイン号を忘れるな、とかアラモ砦を忘れるな、と言ったアメリカの戦史する勉強していなかったのである。だから自ら真珠湾を忘れるな、という標語をアメリカに追加させたのである。
もし日本が一時間前に宣戦布告をしていたところで、アメリカ国民は激高したのは疑いが無い。アラモ砦は奇襲されたので怒ったのではなく、守備隊が全滅したから怒ったのである。しかも守備隊は勝手にメキシコ領に侵入して砦を築いたのである。他国の領土に作った砦を全滅させられても怒る国民が、どうして自国の軍港の艦艇が全滅させられて怒らないと言えるのだろう。宣戦布告の遅れについて重箱の隅をつつく人たちの料簡が知れない。
真珠湾攻撃でもミッドウェー海戦でも事前の特別図演では日本側空母は全滅する、という結果が出たのに、それを抑え込んで作戦を強行したのは山本自身であった(P80)。戸高氏は反戦の人として山本を描こうとしているが、本書が並べた事実をつなぎ合わせれば、山本の重大な欠陥が浮かび上がる。
ブーゲンビル島沖航空戦で、高性能レーダーと戦闘情報センターによる防空戦闘機隊の支援システム、近接信管を備えた高角砲弾を持つようになったため、従来に比べ隔絶した防空能力を持つようになった(P99)、と書く。実際にはそれ以前に射撃指揮装置の能力の差から昭和十七年の珊瑚海海戦でも南太平洋海戦でも日本の攻撃隊は大きな損害を受けている。防空システムにしてもレーダーにしてもこの時突然登場したのではなく、逐次進歩したのである。艦隊の防空能力に大きな差があったのは大戦以前からで、差が広がったのに過ぎない。近接信管の登場はマリアナ沖海戦からで、それも少しが使われたのに過ぎない。
後半では艦隊航空を使えなくなった海軍が陸上機による攻撃を実施したが、それも次々と失敗に終わったことが書かれているが、この戦訓を考慮しない単調な攻撃はもっと批判されてしかるべきである。酸素魚雷の高性能が日本海軍から突撃精神を奪い、実戦での戦果が僅かであった(P128)と書くがその通りである。酸素魚雷も航続距離を短くすれば高速になる。従来の攻撃砲と同じ距離から発射すれば命中率は上がる。酸素魚雷が恐ろしく遠距離で命中した戦果の自慢が戦記にが散見されるが、そんな戦果は期待するものではない。
武蔵の主砲の方位盤が魚雷一本の命中で使えなくなった(P165)と言って、大和型のメカニズムは複雑繊細でわずかな被弾で戦闘能力を失う、と書くが、繊細で脆弱ではあったが複雑だとは思われない。システムの全てが米海軍に比べ改良がはるかに遅れシンプルだったにもも拘わらず脆弱だったのである。である。大和型の欠陥は船体防御にも砲弾にも、いくらでもある。猪口艦長は武蔵が被害に強いことと、射撃に自信があったので射撃精度を高めるため雷爆撃に対する回避行動を行わなかった(P163)、とあるがこれは何かの間違いであろう。
栗田長官は海軍を輸送船と刺し違えて終わらせることに躊躇してレイテ湾突入を放棄した(P174)と同情するが、戦後黙して語らなかった栗田が「疲れていた」とだけ語ったことが象徴するように、そんな立派なものとは思われない。米軍にすらあった、見敵必殺、肉を切らせて骨を切る、の敢闘精神が大戦前から日本海軍では少数派になっていた。被害を恐れるあまりアウトレンジで戦う指揮官が多過ぎたのである。
最後は特攻の話で終わるが、人間魚雷を発案進言したのが中尉、少尉クラスであったように(P181)桜花などの特攻専用の兵器の多くが、下からの必死の提案でなされたのである。形式的にはともかく、根本的には上意下達の精神が少ない日本では兵士たちに、やむなしの気持ちがなければ特攻は実施できない。
総評だが、これだけの大きく幅広いテーマなので、この倍以上の紙幅を費やして書きつくしてほしかった。これだけのページにまとめるならテーマを絞った方が良かったのではないか。