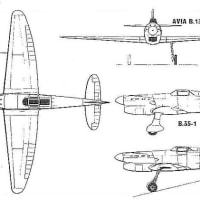本書は中国人の林氏が中国軍が青年を拉致して兵士を調達することを書いている、と紹介されているから読んだのである。小生は太平洋戦争と書くものを信用しない。太平洋戦争はアメリカ側の呼称であり、アメリカの作った史観を受け入れている証拠だからである。ところが本書では一貫して「太平洋戦争(大東亜戦争)」と書く。確かに内容は中途半端なのである。例えば鉄道王ハリマンが日本との共同経営を提案したのを、一旦は受け入れたのを破棄した。もし、この時受け入れていれば、アメリカが蒋介石をコントロールして満州開発しただろうから、日中戦争は起こらず、日米戦争もなく中共の支配もなかっただろう(P54)と書く。
だがアメリカは一貫して満洲の経済支配をねらっていた。日本の大陸権益は早期にアメリカに奪われていたのに違いない。筆者はアメリカの支配欲に鈍感過ぎる。ただ、捏造された「南京大虐殺」という項(P39)を設けているように、南京大虐殺は、ナチスのホロコーストと対比するために連合国がでっち上げたと語るのだが、戦闘に伴う民間人の被害を誇大にとりあげた、としているのは感心しない。南京での民間の被害はほとんど全部が支那軍人の掠奪、殺人、放火などによるものであり、味方の軍人さえ殺している。
せっかく、南京市内で日本軍が米と小麦を支給している時期を、東京裁判の判決では「南京大虐殺」の最中であったとされている(P37)と書いているのにである。平和的人道的とされる米軍の日本占領でさえ、東京、神奈川では初期の一年に何万あるいは何十万という婦女子が強姦され、多数の殺人も行われた。その実態は分からないのである。日本軍の南京占領は、これに比べてはるかに平和的なものだったのである。
1900年代初めにの満洲の人口の9割以上が漢人種だから、五族共和を唱えて満洲人の皇帝を立てるという論理は根拠が薄弱となる(P56)という意見は首肯しかねる。シンガポールがその見本であるが、これは力の論理であって、領有権の主張の正当性があるわけではない。固有の領土であったものを異民族が押し掛けて多数になったからといって、固有の領土という主張が根拠薄弱になるわけではない。戦乱に明け暮れた支那本土とは別に、満洲族の故地に五族協和の国を作るというのは、日本人が初めて考えた壮大な理想であった。
清国滅亡当時の支那は、国際的には中華民国と呼ばれているが、一つの政府により統一されていたわけではないことが書かれている(P58)。袁世凱が大統領となった中華民国を本書では中華民国北京政府と呼ぶ。蒋介石が率いる国民党は南京を首都として中華民国国民政府と呼ぶ。その後北京には張作霖による中華民国軍政府が立てられる。(P60)その間も実態として支那全土は軍閥の割拠する世界であり、統一政権など無い。辛亥革命以後の支那を、蒋介石の国民党と毛沢東の共産党の対立だけと見るのは、単純化などというものではなく、実態を全く反映していない。
「満洲事変後の一九三一年十一月に、中国共産党は江西省の瑞金で中華ソビエト共和国の成立を宣言し、ソビエト共和国政府の名義で日本に宣戦布告した(P85)」というのだから、もし支那事変を抗日戦争として一貫して中共が戦ったと言うなら、支那事変を開始したのは中共であった、ということになる。日本では盧溝橋事件が中共の仕業だとか、盧溝橋事件開始直後に毛沢東が全国に抗日を宣言したことが計画的であった状況証拠にしているが、国際法上は1931年に支那事変は中共により開始され、盧溝橋では軍事衝突がスタートしたのに過ぎない。この間の戦闘なき空白の期間は、朝鮮戦争が国際法上は終わっておらず、休戦状態であるのに類似している。
支那事変は、陸軍が事態を拡大したという軽薄な定説があるが、トラウトマン工作で、中国側の煮え切らない回答で、交渉打ち切りを主張したのは政府であり、陸海軍は反対した。特に陸軍は参謀次長が安易に長期戦に移行することの危険を力説し、政府を追及した。これが大本営による政府不信任の表明だという議論にまで発展した(P109)和平追求が逆に批難されたのである。結局譲歩ぜざるを得なくなったのは大本営であったというのだから、どこが軍部の横暴だというのだろうか。陸軍における不拡大派と拡大派との対立というのは、慎重に対応すべきか一挙に大兵力で決着をつけるかの相違である。事変の長期化を望む陸軍軍人はいなかったのである。
父は大東亜戦争中、北支に出征した。村民は日本軍が来ると日の丸を掲げて歓迎し、国民党軍が来ると、国民党政府の旗を掲げて実にいい加減なもので、日本軍を外国の軍隊と思っていなかったのではないか、と言った。本書にも「農民の中には、日本軍は何処かのく先発の軍隊だろうと思う者までおり、ある地方では日本軍は東北(満洲)の張作霖の軍隊の一部だと思われていた。(P131)」というのだから、父の直感は正しかったのである。漢民族同志ですら言語が通じないのだから、言葉が通じないと言って外国人だとは思わなくても不思議ではない。
さて四章は、期待の林氏が担当している。「ナチスの悲惨を極める状況が伝わってきたころ、中国では徴兵がクライマックスに達していた。当時、徴兵された壮丁たちを収容する施設である、成都の壮丁営に勤務していた医者たちは、ドイツでの恐ろしいやり方に驚くどころか、「ナチスの強制収容所の様子は、我々の所と全く同じである」と語っていた。成都のすぐ近くにあった壮丁営の一つでは、四万人を収容して兵士にする訓練をほどこすはずであったが、多くの人間が連れて来られる途中で死んでしまい、生きて訓練を受けたのは八千人であった。」(P139)その後の本書には、いかに兵士にするために拉致された若者が悲惨な待遇を受け、同胞に殺されていくか延々と書かれている。何も毛沢東だけが残忍な殺人鬼なのではない。
林氏は、劉震雲の小説を引用にして国民党のやり方を非難している(P156)が、日本軍をも批難している。それでも、河南省が干ばつで五百万人が被災し、三百万人以上が餓死したと言われるが、国民党は納税と軍用食糧の負担は変えなかった。この頃河南省に進出した日本軍は軍用食糧を放出し、多くの人が餓死を免れたというのだから、何をかいわんやである。劉は共産党を持ち上げているが、これは現代作家の建前で仕方なかろう。それでも日本軍の人道的措置は書かざるを得ないのである。林氏は中国の色々な小説や資料をチェックした結論として「・・・日本軍占領下の大都市で餓死者が発生したことを示す資料はない。」と断言している。
袁世凱の系統の中華民国北京政府は、蒋介石に滅ぼされた。これを林氏は旧北洋政客という。林氏に言わせると、満洲人、蒙古人と旧北洋政客たちは、「中国近代史上全ての厄災は孫文の三民主義が作りだしたのであった。中国共産党の誕生であり、蒋介石政権の樹立であり、欧米の利益に屈して抗日を行うなど、これらの根源は全て三民主義にあった。」と考えている(P167)。三民主義にそんな威力があったとは思われないが、欧米に利用されたのは確かである。それにこれらの三つは中国近代史上の厄災であることも事実である。ただひとつ蒋介石政権は、大陸から逃亡することによって、蒋経国と李登輝を経て民主義国家になったかに見える。適正規模であれば、漢民族も国民を幸福にできる国家を作れる可能性があるという証明である。ただし金美齢氏が台湾に絶望したように、台湾の民主化の成功はまだ歴史の検証を経ていない。