こうした伝記物はあまり好みではないとはいえ、タイトルに惹かれたこともあって、少し前のことになりますが、『終着駅―トルストイ最後の旅』を見に日比谷のTOHOシネマズシャンテに行ってきました。
(1)伝記物が好みでないというのは、大体が偉大な人物の立派な生涯が描かれているだけで、そこには製作者らの創意工夫の入る余地が少ないように思われるからです。それに、偉大な人物の素晴らしい一生などというものは、人間味に乏しく到底凡人の真似のできるものではなく、一方的に観客側に流れ込んできておしまいになってしまいがちです(別に、映画で何かを教えてもらう必要もありませんし)。
そんなものを見るよりも、駄目な人間のダメさ加減を描き出した映画の方が、もっとずっと身近な感じがして、共感が伴いやすいと思われます。
と思いながらこの映画を見ますと、名声を得るまでの艱難辛苦を描き出すありきたりの伝記物とは違って、トルストイが功成り名を遂げた後の、死の間際の様子を描きだすものでした。
ならば、食わず嫌いはやめて、映画に専念することといたしましょう。
ちなみに、本年は、トルストイが亡くなってちょうど100年目ということで、ある意味で時宜にかなった映画公開と言えるのかもしれません。
さて、この映画は、トルストイが亡くなる1910年のロシアという設定。まだ帝政ロシアの時代で、主な舞台は、ヤースナヤ・ポリャーナ駅(モスクワの南方160km)近くのトルストイの屋敷。そうした枠組みの中で、2組の愛の物語が展開されます。
一つは、トルストイ(クリストファー・プラマー)とその妻ソフィア(ヘレン・ミレン)との関係(16歳違い)、もう一つは、トルストイの秘書になったワレンチン(ジェームズ・マカヴォイ)とマーシャ(屋敷内で展開されるコミューン運動に所属)との関係。
前者については、自分の著作物に対する権利を民衆のために放棄しようとするトルストイと、そんなことはさせじと家族の生活を守るのに必死な妻ソフィアとの確執が描かれます。とはいえ、トルストイも、ソフィアと2人きりになると以前の愛情が蘇るのです。
ついにトルストイは、妻の取り乱した姿に憤って家を出て南に向かいますが、その途中のアスターポヴォ駅(ヤースナヤ・ポリャーナ駅から南東150kmあたり)で死の床についてしまいます。死の間際につぶやいた言葉は、やはり「ソフィア」でした。屋敷にいたソフィアが呼ばれ、夫の最期を看取ります。

トルストイの秘書をやっていたワレンチンは、当初はトルストイ主義を奉じていましたが、トルストイ自身が、ゴリゴリのトルストイ主義者ではなく人間味あふれる人物だということがわかってくるにつれて、奔放なマーシャに惹かれていきます。

コミューン内では性欲は否定されるとして、マーシャはモスクワに返されてしまい2人は別れ別れになるものの、アスターポヴォ駅でトルストイの死を看取ったワレンチンは、自分の下にマーシャを呼び戻します。おそらく、トルストイとソフィアの愛情の深さから何かを感じ取ったからなのでしょう。

映画では、こうした物語が、ワレンチンを狂言回しとして綴られています。
結局のところ、タイトルには“トルストイ”とありますが、別にそんなことはどうでもよく、莫大な財産を自分の主義のために手放そうとする夫と、それを止めさせようとする妻との葛藤、しかしやはりお互いに惹かれあっていたという物語を、もう一つの若い二人の恋愛物語を絡ませて描き出した作品と捉えてしまえばいいのでしょう〔元々、この映画の原作の小説(映画と同タイトル)にある「著者あとがき」の冒頭でも、この本は「フィクションである」と著者ジェイ・パリーニは宣言しているくらいなのですから(新潮文庫版P.471)〕!
この作品では、なんといっても存在感があるのは妻ソフィアです。トルストイの方は、著作権を手放すことなどにつきあれこれ迷ったりするのですが、ソフィアは家の生活を守ること一筋で頑張るのですから、誰も太刀打ちなどできません。それを、『クィーン』で著名なヘレン・ミレンが演じています。同作品でもうかがわれるように気品のある雰囲気を醸し出していますが、そればかりか、遺書の書き換えを知った時の錯乱状態の演技も見事なものです。
なお、トルストイに扮したのは、クリストファー・プラマーで、『Dr.パルナサスの鏡』でパルナサス博士を演じていましたが、今回の映画では、トルストイもかくありなんといった苦悩する姿をうまく演じていると思いました。
この映画はトルストイの死でエンドとなりますが、恋愛物ではなく“true story”に重点を置くというのであれば、むしろトルストイが亡くなった後、ソフィアや他の関係者がどうなったのかの方により興味があるところです。というのも、その7年後にロシア革命が起きるわけで、社会主義体制の中であのコミューンの活動はいったいどうなっていったのでしょうか?
〔ラストで、ソフィアにはトルストイの著作権が移譲されたなどと字幕で表示されますが、そこに至る経緯に興味が惹かれるところです〕
(2)この映画を見るに当たってトルストイ自身のことはドウでもよいと上で言っておきながら、その舌の根も乾かない内にトルストイに少し拘ってみましょう。
特に、トルストイの屋敷で営まれているコミューンの活動については、この映画ではあまり突っ込んだ描写がされていないものの、興味をひかれる点です。
というのも、トルストイ主義とは、原理的には、「自分の生活に必要な労働は、自分でできるような簡素な生活を目指」し、「近代文明や国家、教会、私有財産を否定し、原始キリスト教こそ理想であり、悪に対して神に忠実に非暴力の姿勢をとる」(注)といった内容と思われますが、そういった考え方を基盤に運営されているトルストイのコミューンは、ある面では、現代にも通じるところがあるように考えられるからです。
たとえば、その「公式ブログ」の昨年8月19日の記事「村上春樹の「1Q84」を読んで」において、評論家の田原総一朗氏は、村上春樹氏の最新小説の「「1Q84」の骨子になっているのは学生運動、連合赤軍事件、そして山岸会、それがオウム真理教に至るのである。つまり村上春樹は、若者達が全共闘として戦い、やがて様々のコミューンを作りそして宗教団体へと転じていく、この流れを描きたかったのであろう」と述べています。
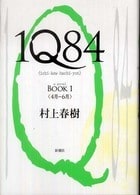
さらに、社会学者・大澤真幸氏が主宰する雑誌『O』の本年7月号は、「特集 もうひとつの1Q84」と題され、『1Q84』(新潮社)が同氏によって分析されているところ、その末尾の「参考資料」の「『1Q84』―大澤真幸によるあらすじ」には、概略次のように述べられています(関連する部分だけですが)。
この小説の主人公の一人である天吾(30歳の男性で予備校講師)は、「ふかえり」(深田絵里子)という17歳の少女が文学賞に応募してきた小説「空気さなぎ」を、ゴーストライターとして書き直します(その結果、同作品は、文学賞を受賞し、単行本はベストセラーになります)。
ところで、この「ふかえり」は、宗教法人「さきがけ」のリーダー(一種の教祖)である深田保の娘なのです。
その深田保は、1960年代に学生運動の指導者でもあり、学生運動の挫折の後、配下の学生を連れて、農業で生計を立てているコミューン「タカシマ塾」に入ります(この「タカシマ塾」のモデルは、おそらくヤマギシ会でしょう)。 その後、彼は、「タカシマ塾」から離れ、仲間とともに、山梨県の過疎の村に、農業的なコミューン「さきがけ」を建設します。
「さきがけ」の中で、現実の革命を求めるラディカルなグループが、「あけぼの」という別のコミューンを作ります(このグループは、警察との銃撃戦の末壊滅しますが、モデルは連合赤軍でしょう)。
「さきがけ」の残りのグループは穏健ですが、いつの間にか非常に閉鎖的な宗教法人になってしまいます(「さきがけ」のモデルはオウム真理教でしょうし、リーダーの深田保は麻原彰晃に対応しているのでしょう)。
以上の物語は、小説『1Q84』の「BOOK1」第10章及び第12章に書かれているところ、コミューン「タカシマ塾」については、「完全な共同生活を営み、農業で生計を立てている。酪農にも力を入れ、規模は全国的です。私有財産は一切認められず、持ち物はすべて共有になる」と天吾は説明しています(P.222)。
こうした側面を見ると、この「タカシマ塾」は、遠くトルストイの理想としたコミューンにも通じていると言えるのではないでしょうか?
(注)このサイトの記事からの引用です。
(3)映画評論家はこの作品に好意的のようです。
山口拓朗氏は、「トルストイが掲げる「理想の愛」と、トルストイの実生活が写し出す「現実の愛」。その狭間で悶々としながらも、最後にはワレンチン自身が実体験を通じて、愛の本質を見極めていく姿勢がいい。「愛」は教えられるものではなく、自分自身の体感として創造されるべきもの――。映画のテーマはここに集約されているのかもしれない」として70点を、
渡まち子氏は、「単純な理想主義だけでは人は幸せにはなれないものだ。まして夫婦の間には苦楽を共にした歴史があった。そのことを若いワレンチンが汲み取って人間的に成長するという設定が意義深い」し、「ヘレン・ミレンとクリストファー・ブラマーという名優二人がこの困った夫婦を格調高く、それでいて少しコミカルに、愛情深く演じていて、素晴らしい」として70点を、
福本次郎氏は、「トルストイのアイデアを極めようとするチェルコトフと家族を守ろうとするソフィヤ、トルストイはその板挟みになりながらも苦悩を顔に出さず飄々としている。このあたりの微妙な三角関係のバランスに、ワレンチンの恋を絡める展開は口当たりがよい」として60点を、
それぞれ与えています。
★★★☆☆
象のロケット:終着駅
(1)伝記物が好みでないというのは、大体が偉大な人物の立派な生涯が描かれているだけで、そこには製作者らの創意工夫の入る余地が少ないように思われるからです。それに、偉大な人物の素晴らしい一生などというものは、人間味に乏しく到底凡人の真似のできるものではなく、一方的に観客側に流れ込んできておしまいになってしまいがちです(別に、映画で何かを教えてもらう必要もありませんし)。
そんなものを見るよりも、駄目な人間のダメさ加減を描き出した映画の方が、もっとずっと身近な感じがして、共感が伴いやすいと思われます。
と思いながらこの映画を見ますと、名声を得るまでの艱難辛苦を描き出すありきたりの伝記物とは違って、トルストイが功成り名を遂げた後の、死の間際の様子を描きだすものでした。
ならば、食わず嫌いはやめて、映画に専念することといたしましょう。
ちなみに、本年は、トルストイが亡くなってちょうど100年目ということで、ある意味で時宜にかなった映画公開と言えるのかもしれません。
さて、この映画は、トルストイが亡くなる1910年のロシアという設定。まだ帝政ロシアの時代で、主な舞台は、ヤースナヤ・ポリャーナ駅(モスクワの南方160km)近くのトルストイの屋敷。そうした枠組みの中で、2組の愛の物語が展開されます。
一つは、トルストイ(クリストファー・プラマー)とその妻ソフィア(ヘレン・ミレン)との関係(16歳違い)、もう一つは、トルストイの秘書になったワレンチン(ジェームズ・マカヴォイ)とマーシャ(屋敷内で展開されるコミューン運動に所属)との関係。
前者については、自分の著作物に対する権利を民衆のために放棄しようとするトルストイと、そんなことはさせじと家族の生活を守るのに必死な妻ソフィアとの確執が描かれます。とはいえ、トルストイも、ソフィアと2人きりになると以前の愛情が蘇るのです。
ついにトルストイは、妻の取り乱した姿に憤って家を出て南に向かいますが、その途中のアスターポヴォ駅(ヤースナヤ・ポリャーナ駅から南東150kmあたり)で死の床についてしまいます。死の間際につぶやいた言葉は、やはり「ソフィア」でした。屋敷にいたソフィアが呼ばれ、夫の最期を看取ります。

トルストイの秘書をやっていたワレンチンは、当初はトルストイ主義を奉じていましたが、トルストイ自身が、ゴリゴリのトルストイ主義者ではなく人間味あふれる人物だということがわかってくるにつれて、奔放なマーシャに惹かれていきます。

コミューン内では性欲は否定されるとして、マーシャはモスクワに返されてしまい2人は別れ別れになるものの、アスターポヴォ駅でトルストイの死を看取ったワレンチンは、自分の下にマーシャを呼び戻します。おそらく、トルストイとソフィアの愛情の深さから何かを感じ取ったからなのでしょう。

映画では、こうした物語が、ワレンチンを狂言回しとして綴られています。
結局のところ、タイトルには“トルストイ”とありますが、別にそんなことはどうでもよく、莫大な財産を自分の主義のために手放そうとする夫と、それを止めさせようとする妻との葛藤、しかしやはりお互いに惹かれあっていたという物語を、もう一つの若い二人の恋愛物語を絡ませて描き出した作品と捉えてしまえばいいのでしょう〔元々、この映画の原作の小説(映画と同タイトル)にある「著者あとがき」の冒頭でも、この本は「フィクションである」と著者ジェイ・パリーニは宣言しているくらいなのですから(新潮文庫版P.471)〕!
この作品では、なんといっても存在感があるのは妻ソフィアです。トルストイの方は、著作権を手放すことなどにつきあれこれ迷ったりするのですが、ソフィアは家の生活を守ること一筋で頑張るのですから、誰も太刀打ちなどできません。それを、『クィーン』で著名なヘレン・ミレンが演じています。同作品でもうかがわれるように気品のある雰囲気を醸し出していますが、そればかりか、遺書の書き換えを知った時の錯乱状態の演技も見事なものです。
なお、トルストイに扮したのは、クリストファー・プラマーで、『Dr.パルナサスの鏡』でパルナサス博士を演じていましたが、今回の映画では、トルストイもかくありなんといった苦悩する姿をうまく演じていると思いました。
この映画はトルストイの死でエンドとなりますが、恋愛物ではなく“true story”に重点を置くというのであれば、むしろトルストイが亡くなった後、ソフィアや他の関係者がどうなったのかの方により興味があるところです。というのも、その7年後にロシア革命が起きるわけで、社会主義体制の中であのコミューンの活動はいったいどうなっていったのでしょうか?
〔ラストで、ソフィアにはトルストイの著作権が移譲されたなどと字幕で表示されますが、そこに至る経緯に興味が惹かれるところです〕
(2)この映画を見るに当たってトルストイ自身のことはドウでもよいと上で言っておきながら、その舌の根も乾かない内にトルストイに少し拘ってみましょう。
特に、トルストイの屋敷で営まれているコミューンの活動については、この映画ではあまり突っ込んだ描写がされていないものの、興味をひかれる点です。
というのも、トルストイ主義とは、原理的には、「自分の生活に必要な労働は、自分でできるような簡素な生活を目指」し、「近代文明や国家、教会、私有財産を否定し、原始キリスト教こそ理想であり、悪に対して神に忠実に非暴力の姿勢をとる」(注)といった内容と思われますが、そういった考え方を基盤に運営されているトルストイのコミューンは、ある面では、現代にも通じるところがあるように考えられるからです。
たとえば、その「公式ブログ」の昨年8月19日の記事「村上春樹の「1Q84」を読んで」において、評論家の田原総一朗氏は、村上春樹氏の最新小説の「「1Q84」の骨子になっているのは学生運動、連合赤軍事件、そして山岸会、それがオウム真理教に至るのである。つまり村上春樹は、若者達が全共闘として戦い、やがて様々のコミューンを作りそして宗教団体へと転じていく、この流れを描きたかったのであろう」と述べています。
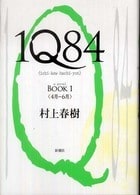
さらに、社会学者・大澤真幸氏が主宰する雑誌『O』の本年7月号は、「特集 もうひとつの1Q84」と題され、『1Q84』(新潮社)が同氏によって分析されているところ、その末尾の「参考資料」の「『1Q84』―大澤真幸によるあらすじ」には、概略次のように述べられています(関連する部分だけですが)。
この小説の主人公の一人である天吾(30歳の男性で予備校講師)は、「ふかえり」(深田絵里子)という17歳の少女が文学賞に応募してきた小説「空気さなぎ」を、ゴーストライターとして書き直します(その結果、同作品は、文学賞を受賞し、単行本はベストセラーになります)。
ところで、この「ふかえり」は、宗教法人「さきがけ」のリーダー(一種の教祖)である深田保の娘なのです。
その深田保は、1960年代に学生運動の指導者でもあり、学生運動の挫折の後、配下の学生を連れて、農業で生計を立てているコミューン「タカシマ塾」に入ります(この「タカシマ塾」のモデルは、おそらくヤマギシ会でしょう)。 その後、彼は、「タカシマ塾」から離れ、仲間とともに、山梨県の過疎の村に、農業的なコミューン「さきがけ」を建設します。
「さきがけ」の中で、現実の革命を求めるラディカルなグループが、「あけぼの」という別のコミューンを作ります(このグループは、警察との銃撃戦の末壊滅しますが、モデルは連合赤軍でしょう)。
「さきがけ」の残りのグループは穏健ですが、いつの間にか非常に閉鎖的な宗教法人になってしまいます(「さきがけ」のモデルはオウム真理教でしょうし、リーダーの深田保は麻原彰晃に対応しているのでしょう)。
以上の物語は、小説『1Q84』の「BOOK1」第10章及び第12章に書かれているところ、コミューン「タカシマ塾」については、「完全な共同生活を営み、農業で生計を立てている。酪農にも力を入れ、規模は全国的です。私有財産は一切認められず、持ち物はすべて共有になる」と天吾は説明しています(P.222)。
こうした側面を見ると、この「タカシマ塾」は、遠くトルストイの理想としたコミューンにも通じていると言えるのではないでしょうか?
(注)このサイトの記事からの引用です。
(3)映画評論家はこの作品に好意的のようです。
山口拓朗氏は、「トルストイが掲げる「理想の愛」と、トルストイの実生活が写し出す「現実の愛」。その狭間で悶々としながらも、最後にはワレンチン自身が実体験を通じて、愛の本質を見極めていく姿勢がいい。「愛」は教えられるものではなく、自分自身の体感として創造されるべきもの――。映画のテーマはここに集約されているのかもしれない」として70点を、
渡まち子氏は、「単純な理想主義だけでは人は幸せにはなれないものだ。まして夫婦の間には苦楽を共にした歴史があった。そのことを若いワレンチンが汲み取って人間的に成長するという設定が意義深い」し、「ヘレン・ミレンとクリストファー・ブラマーという名優二人がこの困った夫婦を格調高く、それでいて少しコミカルに、愛情深く演じていて、素晴らしい」として70点を、
福本次郎氏は、「トルストイのアイデアを極めようとするチェルコトフと家族を守ろうとするソフィヤ、トルストイはその板挟みになりながらも苦悩を顔に出さず飄々としている。このあたりの微妙な三角関係のバランスに、ワレンチンの恋を絡める展開は口当たりがよい」として60点を、
それぞれ与えています。
★★★☆☆
象のロケット:終着駅




































