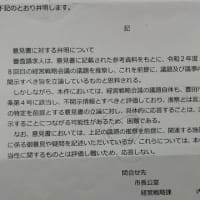GW前に日銀が為替介入し、1$160円が153円になっている。アベノミクスの反省も、「出口戦略」もなく、利上げができない日本で、これで円安が止まるか?山田博文「国債ビジネスと債務大国日本の危機」(新日本出版社)以下、抜き書きである。
5章 日本の金融 財政危機 ⑥
国債の投資が増えると国債金利は低下(国債価格は上昇)する。従って、長期金利の水準を中央銀行の金融政策で決定することは本来不可能である。アベノミクスは日銀からのマネタリーベースを拡大すれば、自動的にマネーストックが増えたし、2%の物価目標も達成できるとの誤った理論(貨幣数量説)で失敗したが、また同じ過ちを犯す。
YCCの狙いは国債利回りに代表される長期金利を、定位固定化することにある。日本が抱えこんだ1441兆円の政府債権残高(国債・財投・地方債)などは、すでに自国の経済規模(GDP)の2.6倍に達している。その大半は一般会計を発行母体にした普通国債発行残高(1068兆円)である。財務省は財政の持続可能性を見る上では、税収を生み出す元となる国の経済規模GDPに対して、総額でどの位の借金をしているかどうか重要、と指摘する。日本は財政の持続可能性が危うくなる世界のトップクラスの「政府債務大国」と言える。日本の国家財政は歳入の4割が借金に依存し、歳出の3割弱が借金返済に費消される自転車操業(サラ金)であり、火の車状態にある。
内外の金利格差を拡大させてきた。その上国内産業の空洞化や貿易赤字の拡大は、日本経済の弱体化と日本売りを誘発し、投機的な円売り環境を誘発してきた。その結果、日本だけほぼ半世紀ぶりの円安となり、輸入価格上昇→国内物価上昇⇒国民生活破壊の悪しきメカニズムが作動することになった。
インフレ物価高、バブル経済の暴走を抑え込むには、過剰なマネーを民間金融市場から引き上げる金融引き締め政策が不可欠である。各国中央銀行はこの間連続して金利を引き上げつつ、量的金融緩和から量的引き締めへと金融政策を転換してきた。
食料品やエネルギー関係価格が高騰するのは、いずれも輸入に依存する割合が高く円相場の動向に左右されるからである。異次元金融緩和政策の十年は半世紀ぶりの円安水準を記録した。2012年から2020年の期間に1ドル79円から137円へ7割も暴落した。インフレは日本国民の貯蓄を直撃する。預金金利から物価の上昇率を差し引いた預金の購買力は、2020年には-4%を記録した。インフレ・物価高、実質賃金の低下に加えて預貯金の購買力も低下する、トリプルパンチに国民はさらされている。
政府の一般会計は、国債発行残高の過半を保有するまでになった。日銀による国債の爆買い=日銀信用の供与によって支えられた。戦後の財政法(第五条)が日銀引き受けによる国債発行を禁じたのは、戦費調達を日銀の国債引き受けに依存した戦前の不幸な教訓からであった。日銀は独立性を失い、政府の「子会社」として国債増発を(民間銀行を迂回し)支えてきた。
日銀の抱える国債の含み損9兆5081億円は、日銀の純資産額(22年9月末現在)5兆365億円を2倍近く超過して、日銀は巨額の債務超過に陥っているのである。
異次元金融緩和政策の十年で大幅に上昇したのは株価であった。日経平均株価は2012年から22年にかけて、実体経済が低迷しているにも関わらず2.5倍に上昇した。2023年8月20日現在株式市場に日銀から37兆1160億円(簿価ベース)の資金が供給されてきた。株式市場に、日銀信用が供給されることで市場実勢を超えた株高=官製株式バブルが引き起こされた。貯蓄から投資を推進する政府日銀に支えられ、株式の配当金や大企業の内部留保金もほぼ倍増した。日銀が株を買って資本金を供給してくれるので、経営が悪化しても会社は倒産しない。現在日本の一般会計歳出は、増大する国債費や2倍になった防衛費に食いつぶされ、国民の生存権を担保する社会保障関係費が削減される事態に陥っている。23年度予算では防衛関係予算が戦後最高の伸びを記録する一方で、社会保障関係費では自然増の1500億円が削減され医療介護年金の全てが圧縮された。
長期金利の上昇や金利引き上げは、株式市場や不動産市場に流入しバブル経済を膨張させていた過剰なマネーを、高金利になった国債や元本保証型の預貯金などにシフトさせるので、バブル経済の縮小、株式・不動産価格の下落を誘発する。投資に失敗し、自ら経営破綻の危機に陥った大手金融機関の場合、「大きすぎてつぶせない」ということを主張し、各国政府からの巨額の公的資金と各種の支援策を引き出してきた。
日本資本主義は、①国家財政と日銀信用へのタカリの構造で、実体経済の成長より金融市場において、多様な金融収益を追求するカジノ型金融ビジネスが優先された。②国民経済と国民生活は、株価・金利・為替相場の変動など、予測不能の経済動向に振り回され不安定化する。3生産高、売上高が減っているにも関わらず、賃金削減や資金の運用を通じて内部留保金を累増させていく企業経営が横行する。④ものづくり国家日本から株式・債券・為替等の売買取引で、キャピタルゲインを追求する金融収奪型国家へ転落した。⑤対米従属の下で、ウォール街と国際金融独占体が日本の大株主経営支配者に成長し、日本の企業と国民は内外の金融独占資本から二重の金融収奪を受けるようになった。
現在の政府の債務残高は、対GDP比は軍事調達のために日銀引き受けで国債が大増発された1945年の終戦時を上回る水準である。当時はGHQの強大な外国権力を背景に、最高税率90%の財産税が断行された。
コメント
政府に借金返済の「出口戦略」は無いだけでなく、武器爆買いで軍事費増大である。ものづくりは車だけはない、食料自給率は下がり国民の安全は保障されない。国民生活は二の次で、財界・金融界の言いなりであり自民党政権の裏金で動いている。また、アメリカのいいなりで、日本国民のくらし・平和は曲がり角にあると思う。