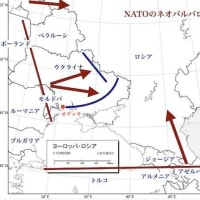世界の主な宗教は旧約聖書がベースでキリスト教、イスラム教、ユダヤ教・・・宗教規範等のタルムード、タルムードに触れ、批判することは欧米では地位、職等を間違いなく失います。欧米のみならず世界でもタブーで、日本人にはとてもついていけない内容です。
世界には、本物と偽者のユダヤ人がいます。
本物ユダヤ人は旧約聖書に記載された民(スファラディー・ユダヤ人)で、聖書の血統(アブラハム・イサク・ヤコブ・・・有色人種)です。
対し、偽ユダヤ人(アシュケナージ・ユダヤ人)は、7世紀中ごろ旧カザール大国に住んでいたカザール人が、ユダヤ教に改宗した人達で、旧約聖書に記載された民とは何の関係も有りません。今日、ユダヤ人言った場合は90%以上がこのアシュケナージ・ユダヤ人、ユダヤ教徒を指します。このユダヤ教徒は18巻からなるタルムードを学びますが、存在等々を必ず否定します。
タルムードはユダヤ教の教典で、へ理屈ラビ(宗教的指導者)の妄言集みたいなものです。聖書のことばをねじ曲げ、人間的な教えに変え、 自分たちに都合のいいように解釈していると言われています。
タルムードは2500年位前、ユダヤ人がバビロンに捕囚され、そこのバビロンの思想等々を学び、ユダヤ教を捨て、このタルムード思想を口伝として伝え、1500年位前に文書としてヘブライ語で書かれており18巻の大きな書です。絶対にヘブライ語以外に訳すことは許されないと言われていますがが、一回だけ英語に訳されたようですが、18巻全て回収等されたと言われています。
ユダヤ教のベースは旧約聖書ですが、中でも重要視されているのが冒頭の5書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記をトーラーと言われ、モーゼが神から授けられたものです。成文化されずに口伝で伝えられたものをミシュナと言われています。
タルムードとは、ヘブライ語で研究という意味があり、ユダヤ教の律法、道徳、習慣等をまとめたものと言われ、トーラーに次いで権威のあるものとされ、ミシュナ(Mishnah)とゲマラ(Gemara)の二つから構成されているようです。
簡単に言えば日常生活規範で、生きかたを記したものがタルムードと言えます。6部構成、63編から成る文書群でユダヤの民法とも呼ばれています。
タルムードの中には、民族的排他性と独善的選民思想が含まれている所があります。その問題箇所、ゾハール2ー64・Bの一部を以下に記しておきます。
タルムードには選民思想という特徴があり、ゴイと言う言葉が出てきますが、ゴイとは非ユダヤ人=家畜ブタと解釈されています。ゴイムというのはゴイの複数形です。
一説ではユダヤ人の子供達は4歳位でモーセ五書を暗唱、5歳位で預言書と聖文学、タルムードを学び、12歳位ではモーセ五書はほとんど暗記していると言われています。
13歳で成人式を迎えた時には、ユダヤ教の基礎をマスターしていると言われています。13歳以降勉強は、死ぬまで続くと言われています。ユダヤ人はタルムードを否定しますが、ユダヤ人の殆どは間違いなくタルムードを学び、研究します、この事実は過去、故ベギン首相がはっきり肯定しています。
イスラエルでは子供たちは殆んどテレビは見ませんと言うより放映してる時間が限定されており、ニュース、クラシック音楽ぐらいのようです。(今は少しは変わったかも知れません。)
過去ユダヤ人(アシュケナージ・ユダヤ人)がヨーロッパで迫害を受けたのは、このタルムードを基盤とした社会生活が原因とも言われています。
世界、日本の歴史教育等々では、これらの迫害の主原因がタルムードであることを絶対に教えませんし、ヒットラー台頭の主因です。イエス・キリストの処刑の主因も当時タルムード思想に染まっていたいた人達をイエス・キリストは徹底非難したからです。
私達はタルムードを知ることにより、世界の諸問題の本質等を知ることが出来、世界を見る目が変わるかもしれません。何故なら過去、現在、世界を支配しているのはタルムードを日々の規範とするユダヤ人(アシュケナージ・ユダヤ人)達で、世界の未来をも支配するでしょう。
勿論、世界には国等々の発展のため活躍しておられるアシュケナージ・ユダヤ人もおられます、有名なのは現ロシアのメドヴェージェフ首相です。両親とも大学教授と言う環境で育っています、タルムードとは無縁の人です。
*****************
タルムード抜粋一例
ユダヤ人はゴイ(非ユダヤ人)から奪ってよい。ユダヤ人はゴイから金をだまし取ってよい。ゴイは金を持つべきではなく、持てば神の名において不名誉となるだろう。
(シュルハン・アルフ、コーゼン・ハミズパットの348)
ゴイに向って誓いを立てた者は、盗賊であれ税吏であれ、責任を取らなくてよい。
(トセフタ・スゼブノットの11)
ゴイにわれらの信教を教える者は、ユダヤ人を殺すに等しい。もしもゴイがわれらの教説を知ったならば、かれらは公然とわれらを殺すだろう。
(リブル・デヴィッドの書の37)
ユダヤ人がラビの書物のどこかを説明してくれと頼まれたなら、ただただ、うその説明をするべきであり、本当のことを教えてこの指示を裏切る共犯者となってはならない。この律法を破る者は生かしておいてはならない。
(リブル・デイヴィドの37)
ゴイがわれらの書物には何かゴイを害することが書いてあるのではないかと聞いたら、偽りの誓いを立てなければならない。そして、そのようなことは誓って書いてないと言わなければならない。
(ザーロット・ウザボット、ジュル・ダの書の17)
タルムードを学ぶゴイ、それを助けるユダヤ人はことごとく生かしておいてはならない。
(サンヘドリン、59、ア・アボダ・ゾラ、8の6。ザギガの13)
神はユダヤ人にすべての方法を用い、詐欺、強力、高利貸、窃盗によってキリスト教徒の財産を奪取することを命ずる。(オルディン1、トラクト1、ディスト4)
我々はタルムードがモーセの律法書に対して絶対的優越性を有することを認むるものなり。(イスラエル文庫、1864年)
律法(聖書)は多少とも重要ではあるが、長老方が聖典に記されたことばは常に重要である。
タルムードの決定は、生ける神のことばである。エホバも天国で問題が起きたときは、現世のラビに意見を聞き給う。(ラビ・メナヘン、第5書の注解)
神は夜の間にタルムードを学び給う。<メナヘム・ベン・シラ法師>
汝らは人類であるが、世界の他の国民は人類にあらずして獣類である。(ババ・メチア、146の6)
汝らイスラエル人は人間なれど、他の民族は人間に非ず。彼らの魂汚れし霊より出でたればなり。(メナヘム・ベン・シラ法師)
イスラエル人は人間と呼ばる。しかれども偶像礼拝者は汚れし霊より出でしものなれば、豚と呼ばるるなり。(ロイベン法師)
悪魔と世界の諸民族とは、畜獣に数えらるべきなり。(ナフタリ法師)
犬は異邦人より勝れたるものなり。(アシ法師)
汝殺すなかれ、とのおきては、イスラエル人を殺すなかれ、との意なり、ゴイ、ノアの子ら、異教徒はイスラエル人にあらず。
(モシェー・バル・マエモン)
ゴイに金を貸す時は必ず高利を以てすべし。
(モシェー・バル・マエモン)
拾得物を紛失者に返却すべしとの戒は、ユダヤ人に対してのみ守らるべきものにして、ゴイに対しては然らず。このことに就き亡きわれらの教法師たちの言えるあり。すなわち、「遺失物とはすべてなんじの兄弟の失いしところの物を指すものにして、ゴイの失える物は然らず。その理由は、ゴイは神に属する者に非ずして、地の邪神に属する者なるゆえなり。ゆえにゴイの失えるすべての物は、この世にては再び見つけらるることなき遺失物にして、その所有者にかえるべきにあらず。財宝は唯一イスラエル人にふさわし
く、他の民はこれに値いせざるものなればなり。
これ預言者イザヤ(26ノ19)の言えるがごとしと。(ゲルソン法師)
他民族の有する所有物はすべてユダヤ民族に属すべきものである。ゆえになんらの遠慮なくこれをユダヤ民族の手に収むること差し支えなし。
(シュルハンアルクのショッツェン・ハミッバッド348)
ゴイがゴイまたはユダヤ人を殺した場合には、その責任を負うべきであるが、ユダヤ人がゴイを殺した場合には責任を負うべきものでない。
(トセフタ、アブダ・ザラ8の5)
「盗賊」ということばの解釈。ゴイは、ゴイからであろうとユダヤ人からであろうと、盗むこと奪うこと女奴隷を使うことは禁じられる。だが彼(ユダヤ人)はゴイに禁じられているこれらのすべてのことをなしても禁じられない。(トセフタ、アボダ・ザラの5)
偶像礼拝に帰依せる非ユダヤ人及び、いやしき牧人はこれを殺すことを許さず。されど彼らが危険に面し、また死に瀕せりとて彼らを救うことは許されず。例えば彼らの一人が水に落ちたるとき、報酬ある場合と雖も彼を救い上ぐべからず。また彼らを瀕死の病よりも、いやすべからず。報酬ある場合と雖も。しかれども、われらと彼らの間に敵意の生ずるを防止するためならば、報酬無き場合にも彼らを救出し、また、いやすことをゆるさる。しかれども偶像を拝む者、罪を犯す者、おきてと預言者を否む者は、これを殺すべし。而して公然と殺すを得ば、そのごとくなせ。しかするを得ざる場合には、彼らの死を促進せよ。たとえば彼らの一人井戸に落ちたるとき、その井戸に、はしごあらば、これを取去り、直ちに再び持来るべしとの遁辞を用い、かくすることにより落ちたる者の身を救い得べき道を奪うべし。
(シュルハン・アルフ、第2巻智慧の教)