三鷹市民大学、東京女子大名誉教授大久保喬樹「日本の文化」─他者としての日本─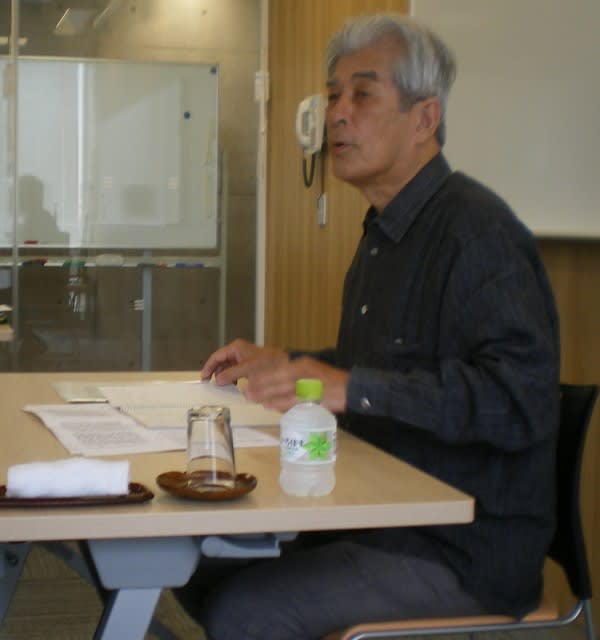
近世のヨーロッパが外国に目を向けたのは先ず、18世紀に中近東に対するオリエント趣味だった。エキゾチックなアラビヤ(千夜一夜物語)
極東の日本に目が向けられたのは19世紀に入ってからだった。そこで対照的な二人の外国人から見た日本を見てみよう。
ピエール・ロチ
彼は海軍の軍人であり、トルコやタヒチなど各所に寄りながらご現地妻との恋を題材にご当地小説を書いていた。
1885年長崎に寄港、結婚斡旋業者を介して日本人妻を娶りひと月暮らし、体験談を「お菊さん」という小説にして、1887年にフランスで発刊大衆受けする。
「・・・そうだ、皮膚の黄色い、髪の毛の黒い、猫のやうな目をした小さい女をさがそう。可愛らしいのでなくちゃいかん。人形よりあまり大きくないやつでね・・・」
「彼女の神々と死者に対する観念のどんなものであるかを、誰がわかるだろう? 彼女には魂があるか? 魂があると自分でも思っているだろうか?」
「私の思想が、例えば鳥の変幻極まりなき想念や猿の夢想などから隔たっているほどに、この娘たちの思想から隔たっているような感じがする・・・」
・・・現地妻との恋物語はやがてプッチーニの「蝶々夫人」の下敷きとなる。
2度目の来日で「秋の日本」という旅行記をものにする。
「聖なる都、京都の中で、私にとって驚きだったのは三十三間堂・・・あらゆる天上世界から抜け出してきた神々が、なにか黙示録的な光景、世界の終末に立ち向かうように並んでいるのだ・・・」
「なんとふぞろいで、変化に富み、珍妙な代物だろう、この京都というのは! ・・・それにしても」なんと広大な宗教遺物置き場、・・・」
そして東京では鹿鳴館について語っている。
「皇族の姫君と侍女一行の入場。・・・どこか異界の住人か、月から降りてきた人々か、・・・」
「なんともちっぽけな、青ざめて血の気の薄い女性たちが二手に分かれて、小人国の妖精のような様子で進んでくる・・・」
「このとてつもない官製のどたばたお笑い芝居に華やかでエキゾチックなおどけの味わいを添えているのだ」
特に「日光体験」が強烈だったようだ。
宇都宮から人力車で険しい山を登り、華厳の滝から東照宮という<黄金パレス>行き着いた彼の眼には「最も私の心をうった理想的に日本的な光景だった」と述べている。
「神官たちの音楽はだらだら続いている。それはいらだたしいほど単調で、執拗な呪文の調子を帯びているが、いつかはその呪文は効験をあらわし、神秘的な目的を果たすのだろう」
「ここにきて初めて私は、この奇妙な国の心臓そのもの、それも、生気にあふれ、芸術や儀式や宗教などの活力で躍動する心臓に入り込んだという実感を得た」
「ここでは、ほんの一本の線ですら、我々とは深く異質であり、まるで、どこか近所の遊星からやってきた物が我々地球世界とはなんの交渉もないのと同様だ」
─続く─
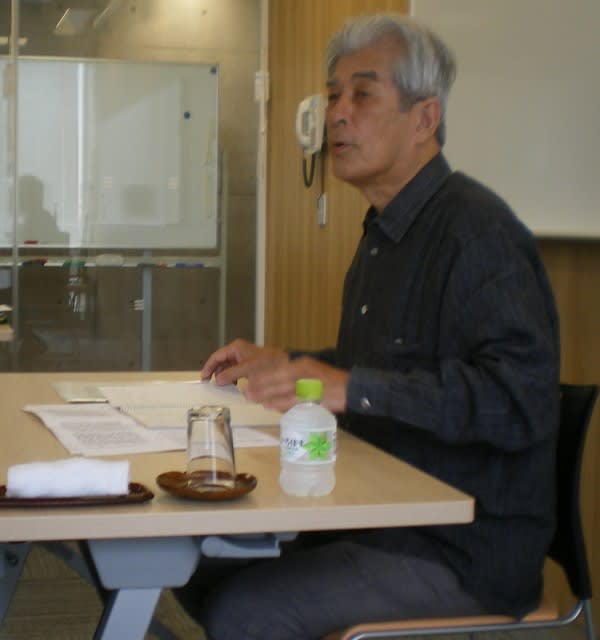
近世のヨーロッパが外国に目を向けたのは先ず、18世紀に中近東に対するオリエント趣味だった。エキゾチックなアラビヤ(千夜一夜物語)
極東の日本に目が向けられたのは19世紀に入ってからだった。そこで対照的な二人の外国人から見た日本を見てみよう。
ピエール・ロチ

彼は海軍の軍人であり、トルコやタヒチなど各所に寄りながらご現地妻との恋を題材にご当地小説を書いていた。
1885年長崎に寄港、結婚斡旋業者を介して日本人妻を娶りひと月暮らし、体験談を「お菊さん」という小説にして、1887年にフランスで発刊大衆受けする。

「・・・そうだ、皮膚の黄色い、髪の毛の黒い、猫のやうな目をした小さい女をさがそう。可愛らしいのでなくちゃいかん。人形よりあまり大きくないやつでね・・・」
「彼女の神々と死者に対する観念のどんなものであるかを、誰がわかるだろう? 彼女には魂があるか? 魂があると自分でも思っているだろうか?」
「私の思想が、例えば鳥の変幻極まりなき想念や猿の夢想などから隔たっているほどに、この娘たちの思想から隔たっているような感じがする・・・」
・・・現地妻との恋物語はやがてプッチーニの「蝶々夫人」の下敷きとなる。

2度目の来日で「秋の日本」という旅行記をものにする。

「聖なる都、京都の中で、私にとって驚きだったのは三十三間堂・・・あらゆる天上世界から抜け出してきた神々が、なにか黙示録的な光景、世界の終末に立ち向かうように並んでいるのだ・・・」

「なんとふぞろいで、変化に富み、珍妙な代物だろう、この京都というのは! ・・・それにしても」なんと広大な宗教遺物置き場、・・・」
そして東京では鹿鳴館について語っている。

「皇族の姫君と侍女一行の入場。・・・どこか異界の住人か、月から降りてきた人々か、・・・」
「なんともちっぽけな、青ざめて血の気の薄い女性たちが二手に分かれて、小人国の妖精のような様子で進んでくる・・・」
「このとてつもない官製のどたばたお笑い芝居に華やかでエキゾチックなおどけの味わいを添えているのだ」
特に「日光体験」が強烈だったようだ。

宇都宮から人力車で険しい山を登り、華厳の滝から東照宮という<黄金パレス>行き着いた彼の眼には「最も私の心をうった理想的に日本的な光景だった」と述べている。
「神官たちの音楽はだらだら続いている。それはいらだたしいほど単調で、執拗な呪文の調子を帯びているが、いつかはその呪文は効験をあらわし、神秘的な目的を果たすのだろう」
「ここにきて初めて私は、この奇妙な国の心臓そのもの、それも、生気にあふれ、芸術や儀式や宗教などの活力で躍動する心臓に入り込んだという実感を得た」
「ここでは、ほんの一本の線ですら、我々とは深く異質であり、まるで、どこか近所の遊星からやってきた物が我々地球世界とはなんの交渉もないのと同様だ」
─続く─















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます