 ハードボイルドの巨匠、レイモンドチャンドラーの描くカッコいい女を<長いお別れ>の中からピックアップしてみる。
ハードボイルドの巨匠、レイモンドチャンドラーの描くカッコいい女を<長いお別れ>の中からピックアップしてみる。
としをとった給仕がそばを通りかかって、残り少なになったスカッチと水をながめた。私が頭をふり、彼が白髪頭をうなずかせたとき、すばらしい<夢の女>が入ってきた。一瞬、バーの中がしずまりかえった。活動家らしい男たちは早口でしゃべっていた口をつぐみ、カウンターの酔っ払いはバーテンに話しかけるのをやめた。ちょうど、指揮者が譜面台をかるくたたいて両手をあげたときのようだった。
かなり背のたかい、すらりとした女で、特別仕立ての白麻の服に黒と白の水玉のスカーフを頚にまいていた。髪はおとぎばなしの王女のようにうすい金色に輝いていた。頭にかぶった帽子の中に金髪が巣の中の小鳥のようにまるまっていた。眼はめったに見かけないヤグルマソウの花のようなブルーで、まつ毛は長く、眼につかないほどのうすい色だった。向こうの端のテーブルまで歩いて行って、白の長手袋を脱ぎはじめると、さっきのとしよりの給仕が私などは一度もされた覚えのないいんぎんな態度でテーブルをひいた。彼女は腰をおろして、手袋をハンドバックのストラップにはさみ、やさしい笑顔で礼をいった。笑顔があまり美しかったので、給仕は電気に打たれたように緊張した。女はひじょうに低い声で何かいった。給仕はからだをまげて、急いで出て行った。人生の一大事が起こったような急ぎ方だった。
私はじっと見つめた。彼女は私の視線をとらえて、目を半インチほどあけた。私はもうそっちを見ていなかった。しかし、どこを見ていたにせよ、私は呼吸(いき)をのんでいた。
 ひとり、あるいは何人かの男がくつろいでいたバーに、ひとりのすばらしい女が入ってきたことで、雰囲気が一変する。ぼくは映画のシーンを見ている気になり、その先のストーリーを勝手に展開させていた。
ひとり、あるいは何人かの男がくつろいでいたバーに、ひとりのすばらしい女が入ってきたことで、雰囲気が一変する。ぼくは映画のシーンを見ている気になり、その先のストーリーを勝手に展開させていた。


















 ぼくは、高校まで金沢にいたが、このシイノキについて見覚えはあるが由来までは知らなかった。
ぼくは、高校まで金沢にいたが、このシイノキについて見覚えはあるが由来までは知らなかった。



 正直言って、半村良氏のことはよく知らない。
正直言って、半村良氏のことはよく知らない。
 以前、スリップの上へレインコートを着て、電車で出勤して来た若いホステスを見たことがある。梅雨のおわりの頃で、蒸し暑い雨の日であった。
以前、スリップの上へレインコートを着て、電車で出勤して来た若いホステスを見たことがある。梅雨のおわりの頃で、蒸し暑い雨の日であった。 現実はロマンチックな、あるいは感動的なシーンに充ちているわけではない。
現実はロマンチックな、あるいは感動的なシーンに充ちているわけではない。












 その後、青春の実感である喪失感や虚無感そして再生を描き新境地を拓いたという、1987年に出版した<ノルウエイの森>が430万部のベストセラーとなる。
その後、青春の実感である喪失感や虚無感そして再生を描き新境地を拓いたという、1987年に出版した<ノルウエイの森>が430万部のベストセラーとなる。
 土曜日の夜にはみんなだいたい外に遊びに出ていたから、ロビーはいつもより人も少なくしんとしていた。僕はいつもそんな沈黙の空間にちらちらと浮かんでいる光の粒子を見つめながら、自分の心を見定めようと努力してみた。いったい俺は何を求めているんだろう そしていったい人は俺に何を求めているんだろう? しかし答えらしい答えは見つからなかった。僕はときどき空中に漂う光の粒子に向けて手を伸ばしてみたが、その指先は何にも触れなかった。
土曜日の夜にはみんなだいたい外に遊びに出ていたから、ロビーはいつもより人も少なくしんとしていた。僕はいつもそんな沈黙の空間にちらちらと浮かんでいる光の粒子を見つめながら、自分の心を見定めようと努力してみた。いったい俺は何を求めているんだろう そしていったい人は俺に何を求めているんだろう? しかし答えらしい答えは見つからなかった。僕はときどき空中に漂う光の粒子に向けて手を伸ばしてみたが、その指先は何にも触れなかった。 僕は奇妙に非現実的な月の光に照らされた道を辿って雑木林の中に入り、あてもなく歩を運んだ。そんな月の光の下ではいろんな物音が不思議な響き方をした。僕の足音はまるで海底を歩いている人の足音のように、どこかまったく別の方向から鈍く響いて聞こえてきた、時折後ろの方でかさっという小さな乾いた音がした。夜の動物たちが息を殺してじっと僕が立ち去るのを待っているような、そんな重苦しさが林の中に漂っていた。
僕は奇妙に非現実的な月の光に照らされた道を辿って雑木林の中に入り、あてもなく歩を運んだ。そんな月の光の下ではいろんな物音が不思議な響き方をした。僕の足音はまるで海底を歩いている人の足音のように、どこかまったく別の方向から鈍く響いて聞こえてきた、時折後ろの方でかさっという小さな乾いた音がした。夜の動物たちが息を殺してじっと僕が立ち去るのを待っているような、そんな重苦しさが林の中に漂っていた。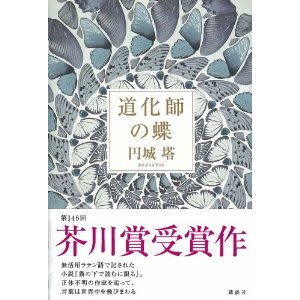

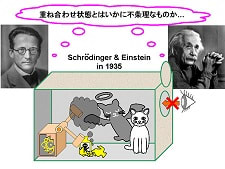
 作者の円城塔氏も言っている。
作者の円城塔氏も言っている。
 ぼくは先日三鷹通信で取り上げた、現役編集者主宰の読書会<ベストセラーとは>を思い出した。
ぼくは先日三鷹通信で取り上げた、現役編集者主宰の読書会<ベストセラーとは>を思い出した。
 ぼくも、すでに古希を超えた。
ぼくも、すでに古希を超えた。