「今日は豚カツでも食いに行くか・・・」
「トンカツ、いいね」
目黒の豚カツ屋は開店早々だったが、既にカウンターは満席だった。

やむなくボクらは後ろで客が食べる様子をしばらく眺めていなければならなかった。
食べやすいように包丁を入れた揚げたての豚カツを、ホッホと言いながら食べている。

キャベツは食べ放題だった。
細長く繊細に切られたキャベツは楽々と客の口に収まり、あっという間に皿は空になる。
間髪を入れずに「はい、どうぞ!」と威勢よくキャベツのお代わりが盛られる。
食べ終わた客が支払いのお札を財布から引き出すと同時に、
「はい、ありがとうございました!」と元気の女子店員からつり銭が渡される。
これも間髪を入れずだ。

こうして客も次から次へと気持ちよく回転させられていった。
権之助坂の10円寿司へも行った。

「割り勘だぞ」
藤原の意図にも気づかず、ボクらは「当然だよ」と声をそろえた。
カウンターに5人並んで食べ始める。
始めのうちはみんな、何をたべようかなと迷いながら注文し、味わいながら食べていた。
ところがひとり藤原 だけは次から次へと間髪を入れず注文した。
だけは次から次へと間髪を入れず注文した。
他のものもあわててピッチを速めた。
しかしダッシュが早く、からだの大きい藤原にかなうわけがなかった。
結局10円寿司にしては高いものにつき。不平等割り勘となった。
─続く─
「トンカツ、いいね」
目黒の豚カツ屋は開店早々だったが、既にカウンターは満席だった。

やむなくボクらは後ろで客が食べる様子をしばらく眺めていなければならなかった。
食べやすいように包丁を入れた揚げたての豚カツを、ホッホと言いながら食べている。

キャベツは食べ放題だった。
細長く繊細に切られたキャベツは楽々と客の口に収まり、あっという間に皿は空になる。
間髪を入れずに「はい、どうぞ!」と威勢よくキャベツのお代わりが盛られる。
食べ終わた客が支払いのお札を財布から引き出すと同時に、
「はい、ありがとうございました!」と元気の女子店員からつり銭が渡される。
これも間髪を入れずだ。

こうして客も次から次へと気持ちよく回転させられていった。
権之助坂の10円寿司へも行った。

「割り勘だぞ」
藤原の意図にも気づかず、ボクらは「当然だよ」と声をそろえた。
カウンターに5人並んで食べ始める。
始めのうちはみんな、何をたべようかなと迷いながら注文し、味わいながら食べていた。
ところがひとり藤原
 だけは次から次へと間髪を入れず注文した。
だけは次から次へと間髪を入れず注文した。他のものもあわててピッチを速めた。
しかしダッシュが早く、からだの大きい藤原にかなうわけがなかった。
結局10円寿司にしては高いものにつき。不平等割り勘となった。
─続く─























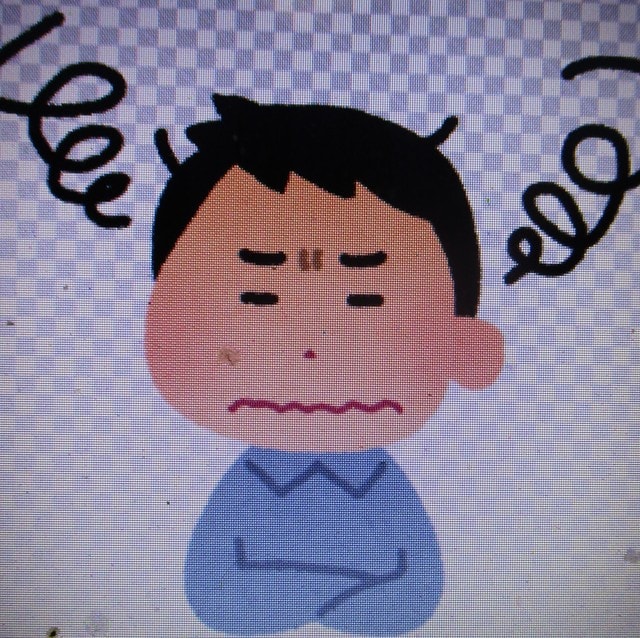 そいうう思いがとつぜん腑に落ちた。
そいうう思いがとつぜん腑に落ちた。



















