万葉雑記 色眼鏡 二八四 今週のみそひと歌を振り返る その一〇四
今週は気になった漢字表記に遊びます。それが集歌2717の「鬼」ですし、集歌2719の「物」です。これらの言葉は共に「もの」と訓じます。
集歌2717 朝東風尓 井堤越浪之 世蝶似裳 不相鬼故 瀧毛響動二
試訓 朝(あさ)東風(こち)に井堤(ゐで)越す波し寄(よ)てふにも逢はぬものゆゑ瀧(たぎ)もとどろに
試訳 朝、東風に堰を越し外に溢れる川波が寄せると云う。そのように貴方が私に心を寄せると云うときも、私が心を閉ざして貴方の求婚を受け入れないものだから、周囲の催促が激流の音のように轟き騒がしいことです。
注意 三句目「世蝶似裳」の定訓はありません。一般に「蝶」を「染」の誤字と扱って「外目にも」と訓んでいます。なお、この歌は、「東風」を「こち」、「鬼」を「もの」と訓むように難訓の歌です。ここで「蝶」を「てふ」とそのままに訓んでみました。その時、「鬼」に「隠(をん)」の意味合いをも拾っています。
訓読 朝(あさ)東風(こち)に井堤(ゐで)越す波の外目(そよめ)にも逢はぬものゆゑ瀧(たぎ)もとどろに
意訳 朝、東風に堰を越し外に溢れる川波が遠くから判るように、遠くから見つめ合った訳でもないのに、噂だけが激流のように轟きわたる。
集歌2719 隠沼乃 下尓戀者 飽不足 人尓語都 可忌物乎
訓読 隠沼(こもりぬ)の下に恋ふれば飽き足らず人に語りつ忌(い)むべきものを
私訳 水が流れ出ることのない隠沼のように表に出すことなく心の底に恋い焦がれていると、秘めた恋に満足できずに、人に貴方への恋心を語ってしまった。慎むべきなのに。
注意 原歌の「戀」を「恋い焦がれる」の意味合いより、もっと直接的な「男女の愛の営み」と解釈すると、女が詠う歌の「隠沼」のイメージは男によって為されたある夜の女性の状態を示します。
個々の歌は意訳文と注意書きで概要を紹介しましたので、改めての紹介は端折らせて頂きます。
さて話題としています「もの」ですが、古語では仏・神・鬼・魂などの霊妙な作用をもたらす存在を意味したようです。古語では、怪しい気配や感覚を「け」と称したようで、常日頃の雰囲気や感覚とは違う状態を「もののけ(物の気)」と云う言葉で表現しています。
ただ、飛鳥から奈良時代にこの「もの」に漢字として「鬼」と云うものを当て文字として表現するようになりますが、平安時代頃には「鬼」と云う漢字の中国語の発音「おぬ・おん」から和語の発音「おに」が生まれたようです。一般的に言葉としての「鬼」は、和語の発音「おに」が生まれたことと共に道教や儒教での「鬼」と云うイメージが人々の間で優先となり、現代の「鬼(おに)」と云う理解と発音に繋がったとします。
本来の大和言葉の「もの」は人間界での人が理解できる事象を超えた自然が発する気や現象を示すものですから、万葉集に「もの」の言葉に「鬼」と云う漢字を与えたとしても邪悪なもの、恐ろしいものと云う意味合いより、不可思議なもののような語感の方が強いと考えます。
このような「もの」と云う言葉の感覚を前提としますと、集歌2717の四句目「不相鬼故」は、求婚して来た男は女の家族からすると夫とするには相応しい人物なのですが、肝心の求婚された女からすると「なんとなく、気が乗らない」と云う気分・感情を的確に示す漢字表現なのかもしれません。女にとって求婚して来た男の身分・地位・年齢からすれば実に相応しいが、一方で抱かれ、子をなしても良いと云うほどの「気」が湧かないと云うことでしょうか。現代風では「不相鬼故」は「ときめかない」と云う表現と同等かもしれません。歌ではその相応しい相手と云う状況を「蝶」と云う漢字が持つ「喜び、優雅、転生」と云うもの、また「似」と云うものを使う二句目「世蝶似裳」の表現・用字が示しているのでしょう。なお、当然ですが、一般には「蝶」は「染」の誤記としますから、弊ブログの解釈は酔論であり、妄想です。
妄想の続きに集歌2719の歌を眺めてみます。歌の五句目は「可忌物乎」と表現します。古語から解釈しますと「可忌物」は実に直線的な漢字表現です。ここで「忌」は別に「斎」とも表記し、「畏敬すべき崇高なものや不浄なものなどを、神秘的なものとして恐れ避ける」と云う意味合いの言葉とされますから、「もの」とは畏敬すべき崇高なものの意味からすればぴったりと云うところです。発声では「いむべきものを」ですが、漢字表現からすれば「自然界の定めとして貴女と結ばれた出会い=「もの」を、崇高なものとして受け止めるべき事柄と云うことになるでしょうか。
現代、家族の数え方には一戸、二戸と云うものがあり、この戸は戸籍上の繋がりがあり同居している家族をイメージします。ところが飛鳥・奈良時代の律令制度での戸は確かに同一の籍に載る家族を意味しますが、必ずしも同じ家屋に同居するとは規定していなかったようです。現代に置き換えると、ある種、同じ地域に住む同じ苗字を持つ血族をもって一戸としていたようですので、一戸の規模が複数の家族集団ですので30~40人と云うものも特異なものではありません。確かに昭和以前の研究者は欧米風の核家族を暗黙の戸と云う基準と据えていたみたいですので、平成時代と大正・昭和期での戸の構成人数・規模が違いますので律令体制や租庸調税制の理解がまったくに相違します。
古代、男は入り婿婚が原則ですので男は婚姻により女が属する集団に移動する、つまり、男と女が安定的に結ばれるには女が属する戸の人びとに認知される必要があります。恋愛が安定的に成就するには、物事を波立たせず平穏に進める必要がありますから、場の雰囲気が醸成され女方の家族集団に認知されるまでは人々の噂話の話題にならないことが重要だったようです。歌は、その物の順番に違い、女方の家族集団に認知される前に男女の仲が里の人びとの噂話に昇ったと云うことでしょうか。ただし、男の言い訳として、歌の末句では女との仲は自然界の流れとして定まっていたことと表現しているのでしょう。ある種、言い訳は神の定めですと云うことです。
今回、「もの」と云う古語に注目して遊んでみました。ただし、一般的な鑑賞からしますとデタラメで酔論だけです。そのようなものとしてご笑納ください。
今週は気になった漢字表記に遊びます。それが集歌2717の「鬼」ですし、集歌2719の「物」です。これらの言葉は共に「もの」と訓じます。
集歌2717 朝東風尓 井堤越浪之 世蝶似裳 不相鬼故 瀧毛響動二
試訓 朝(あさ)東風(こち)に井堤(ゐで)越す波し寄(よ)てふにも逢はぬものゆゑ瀧(たぎ)もとどろに
試訳 朝、東風に堰を越し外に溢れる川波が寄せると云う。そのように貴方が私に心を寄せると云うときも、私が心を閉ざして貴方の求婚を受け入れないものだから、周囲の催促が激流の音のように轟き騒がしいことです。
注意 三句目「世蝶似裳」の定訓はありません。一般に「蝶」を「染」の誤字と扱って「外目にも」と訓んでいます。なお、この歌は、「東風」を「こち」、「鬼」を「もの」と訓むように難訓の歌です。ここで「蝶」を「てふ」とそのままに訓んでみました。その時、「鬼」に「隠(をん)」の意味合いをも拾っています。
訓読 朝(あさ)東風(こち)に井堤(ゐで)越す波の外目(そよめ)にも逢はぬものゆゑ瀧(たぎ)もとどろに
意訳 朝、東風に堰を越し外に溢れる川波が遠くから判るように、遠くから見つめ合った訳でもないのに、噂だけが激流のように轟きわたる。
集歌2719 隠沼乃 下尓戀者 飽不足 人尓語都 可忌物乎
訓読 隠沼(こもりぬ)の下に恋ふれば飽き足らず人に語りつ忌(い)むべきものを
私訳 水が流れ出ることのない隠沼のように表に出すことなく心の底に恋い焦がれていると、秘めた恋に満足できずに、人に貴方への恋心を語ってしまった。慎むべきなのに。
注意 原歌の「戀」を「恋い焦がれる」の意味合いより、もっと直接的な「男女の愛の営み」と解釈すると、女が詠う歌の「隠沼」のイメージは男によって為されたある夜の女性の状態を示します。
個々の歌は意訳文と注意書きで概要を紹介しましたので、改めての紹介は端折らせて頂きます。
さて話題としています「もの」ですが、古語では仏・神・鬼・魂などの霊妙な作用をもたらす存在を意味したようです。古語では、怪しい気配や感覚を「け」と称したようで、常日頃の雰囲気や感覚とは違う状態を「もののけ(物の気)」と云う言葉で表現しています。
ただ、飛鳥から奈良時代にこの「もの」に漢字として「鬼」と云うものを当て文字として表現するようになりますが、平安時代頃には「鬼」と云う漢字の中国語の発音「おぬ・おん」から和語の発音「おに」が生まれたようです。一般的に言葉としての「鬼」は、和語の発音「おに」が生まれたことと共に道教や儒教での「鬼」と云うイメージが人々の間で優先となり、現代の「鬼(おに)」と云う理解と発音に繋がったとします。
本来の大和言葉の「もの」は人間界での人が理解できる事象を超えた自然が発する気や現象を示すものですから、万葉集に「もの」の言葉に「鬼」と云う漢字を与えたとしても邪悪なもの、恐ろしいものと云う意味合いより、不可思議なもののような語感の方が強いと考えます。
このような「もの」と云う言葉の感覚を前提としますと、集歌2717の四句目「不相鬼故」は、求婚して来た男は女の家族からすると夫とするには相応しい人物なのですが、肝心の求婚された女からすると「なんとなく、気が乗らない」と云う気分・感情を的確に示す漢字表現なのかもしれません。女にとって求婚して来た男の身分・地位・年齢からすれば実に相応しいが、一方で抱かれ、子をなしても良いと云うほどの「気」が湧かないと云うことでしょうか。現代風では「不相鬼故」は「ときめかない」と云う表現と同等かもしれません。歌ではその相応しい相手と云う状況を「蝶」と云う漢字が持つ「喜び、優雅、転生」と云うもの、また「似」と云うものを使う二句目「世蝶似裳」の表現・用字が示しているのでしょう。なお、当然ですが、一般には「蝶」は「染」の誤記としますから、弊ブログの解釈は酔論であり、妄想です。
妄想の続きに集歌2719の歌を眺めてみます。歌の五句目は「可忌物乎」と表現します。古語から解釈しますと「可忌物」は実に直線的な漢字表現です。ここで「忌」は別に「斎」とも表記し、「畏敬すべき崇高なものや不浄なものなどを、神秘的なものとして恐れ避ける」と云う意味合いの言葉とされますから、「もの」とは畏敬すべき崇高なものの意味からすればぴったりと云うところです。発声では「いむべきものを」ですが、漢字表現からすれば「自然界の定めとして貴女と結ばれた出会い=「もの」を、崇高なものとして受け止めるべき事柄と云うことになるでしょうか。
現代、家族の数え方には一戸、二戸と云うものがあり、この戸は戸籍上の繋がりがあり同居している家族をイメージします。ところが飛鳥・奈良時代の律令制度での戸は確かに同一の籍に載る家族を意味しますが、必ずしも同じ家屋に同居するとは規定していなかったようです。現代に置き換えると、ある種、同じ地域に住む同じ苗字を持つ血族をもって一戸としていたようですので、一戸の規模が複数の家族集団ですので30~40人と云うものも特異なものではありません。確かに昭和以前の研究者は欧米風の核家族を暗黙の戸と云う基準と据えていたみたいですので、平成時代と大正・昭和期での戸の構成人数・規模が違いますので律令体制や租庸調税制の理解がまったくに相違します。
古代、男は入り婿婚が原則ですので男は婚姻により女が属する集団に移動する、つまり、男と女が安定的に結ばれるには女が属する戸の人びとに認知される必要があります。恋愛が安定的に成就するには、物事を波立たせず平穏に進める必要がありますから、場の雰囲気が醸成され女方の家族集団に認知されるまでは人々の噂話の話題にならないことが重要だったようです。歌は、その物の順番に違い、女方の家族集団に認知される前に男女の仲が里の人びとの噂話に昇ったと云うことでしょうか。ただし、男の言い訳として、歌の末句では女との仲は自然界の流れとして定まっていたことと表現しているのでしょう。ある種、言い訳は神の定めですと云うことです。
今回、「もの」と云う古語に注目して遊んでみました。ただし、一般的な鑑賞からしますとデタラメで酔論だけです。そのようなものとしてご笑納ください。













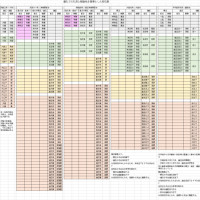




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます