第三部定理一五備考でいっておいたような事情から,スピノザは同感sympathiaと反感antipathiaを感情affectusとしては定義しませんでした。ただそれは,それらを感情としては認めなかったという意味ではありません。そこでの説明および第三部定理一五からより明らかなように,同感は喜びlaetitiaですし反感は悲しみtristitiaですから,それが感情であることは疑い得ないのです。そこでスピノザは,それらが事物に備わった性質ではないということを明らかにするために,別の名称を与えてそれぞれを定義することにしたのです。

このうち,同感に該当する感情は好感propensioといわれ,第三部諸感情の定義八に示されました。同感も好感も日本語では変わるところはないかもしれませんが,元のラテン語には意味の違いがあったというように解してください。
「好感とは偶然によって喜びの原因となるようなある物の観念を伴なった喜びである」。
ここでは基本感情affectus primariiとしての喜びの一種と規定されていますが,第三部諸感情の定義六から理解できるように,外部の原因の観念を伴なった喜びLaetitia, concomitante idea causae externaeは愛amorといわれるわけですから,もう少し狭く説明すれば,愛が喜びの一種で,好感は愛の一種であるということになります。これは第三部定理一五備考の本文からも明らかですし,第三部定理一五系からも明らかだといえます。
注意しておきたいのは,好感は愛の一種で,とくに偶然による愛の一種であるということです。日本語でいうと第三部諸感情の定義一九の好意favorは好感とそうも変わらないように受け取ることができますが,好意がそうであるように,好感にもまた特殊な要件が与えられています。とくに,好意というのはその定義Definitioからも分かるように,偶然によるものではありませんから,スピノザの哲学では好感という愛と好意という愛は,同じように愛の一種ではあるものの,完全に異なった感情です。ある感情が好意でもあり好感でもあるということは,それぞれの定義から理解できるように,あり得ないのです。
その結果effectusの確実性が外的環境によって左右されるのであれば,ある人間の何がしかの行為の結果というのは,その人間の本性natura humanaのみによっては十全に説明され得ないことになります。自殺というのはそのような行為のひとつなのです。だから第三部定理六や第三部定理七と,現実的に存在する人間は自殺することがあるということは両立するのであって,これがそれらが両立するということを示す結果の外在性だと吉田はいっているわけです。
この部分で吉田が自殺という行為に関して論述している動機の外在性と結果の外在性というのはこれですべてなのですが,僕は動機の外在性ということは以前から知っていたのに対し,結果の外在性というのはそれまで考えたことがなかった事柄ですから,この点については補足的に僕自身による考察を加えます。というのは吉田のこの説明から,結果としての外在性というのは,原因causaとしての外在性も含むのではないかというように思ったからです。ただしここで原因というのは,動機の外在性といわれるような,思惟の様態cogitandi modiに関連するような原因のことではなく,人間の身体humanum corpusが現実的に存在することをやめる,一般的にいえば死ぬということに関しての,原因の外在性のことです。したがってここからは人間の身体だけを対象として考察していきますから,人間の精神mens humanaのうちにどのような思惟作用が生じているのかということには注目しません。この点を前もって注意しておいてください。
吉田がいっているように,僕たちは何事かをなすときに,その結果に対して確実であるためには,自分自身が十全な原因causa adaequataである必要があるのであって,もしも部分的原因causa partialisとして何事かをなすという場合には,直接的にその確実性を得ることはできず,間接的に確実性を高めることしかできません。このことが自殺に対しても妥当するということは吉田がいっている通りです。そしてこれは,人間は死ぬということに対して確実であることはできないというのと同じなのですから,人間は自分の死に対して,自分自身が十全な原因ではあり得ないというのと同じです。もっともこれは,第三部定理四で個物res singularis一般についていわれていることそのものです。

このうち,同感に該当する感情は好感propensioといわれ,第三部諸感情の定義八に示されました。同感も好感も日本語では変わるところはないかもしれませんが,元のラテン語には意味の違いがあったというように解してください。
「好感とは偶然によって喜びの原因となるようなある物の観念を伴なった喜びである」。
ここでは基本感情affectus primariiとしての喜びの一種と規定されていますが,第三部諸感情の定義六から理解できるように,外部の原因の観念を伴なった喜びLaetitia, concomitante idea causae externaeは愛amorといわれるわけですから,もう少し狭く説明すれば,愛が喜びの一種で,好感は愛の一種であるということになります。これは第三部定理一五備考の本文からも明らかですし,第三部定理一五系からも明らかだといえます。
注意しておきたいのは,好感は愛の一種で,とくに偶然による愛の一種であるということです。日本語でいうと第三部諸感情の定義一九の好意favorは好感とそうも変わらないように受け取ることができますが,好意がそうであるように,好感にもまた特殊な要件が与えられています。とくに,好意というのはその定義Definitioからも分かるように,偶然によるものではありませんから,スピノザの哲学では好感という愛と好意という愛は,同じように愛の一種ではあるものの,完全に異なった感情です。ある感情が好意でもあり好感でもあるということは,それぞれの定義から理解できるように,あり得ないのです。
その結果effectusの確実性が外的環境によって左右されるのであれば,ある人間の何がしかの行為の結果というのは,その人間の本性natura humanaのみによっては十全に説明され得ないことになります。自殺というのはそのような行為のひとつなのです。だから第三部定理六や第三部定理七と,現実的に存在する人間は自殺することがあるということは両立するのであって,これがそれらが両立するということを示す結果の外在性だと吉田はいっているわけです。
この部分で吉田が自殺という行為に関して論述している動機の外在性と結果の外在性というのはこれですべてなのですが,僕は動機の外在性ということは以前から知っていたのに対し,結果の外在性というのはそれまで考えたことがなかった事柄ですから,この点については補足的に僕自身による考察を加えます。というのは吉田のこの説明から,結果としての外在性というのは,原因causaとしての外在性も含むのではないかというように思ったからです。ただしここで原因というのは,動機の外在性といわれるような,思惟の様態cogitandi modiに関連するような原因のことではなく,人間の身体humanum corpusが現実的に存在することをやめる,一般的にいえば死ぬということに関しての,原因の外在性のことです。したがってここからは人間の身体だけを対象として考察していきますから,人間の精神mens humanaのうちにどのような思惟作用が生じているのかということには注目しません。この点を前もって注意しておいてください。
吉田がいっているように,僕たちは何事かをなすときに,その結果に対して確実であるためには,自分自身が十全な原因causa adaequataである必要があるのであって,もしも部分的原因causa partialisとして何事かをなすという場合には,直接的にその確実性を得ることはできず,間接的に確実性を高めることしかできません。このことが自殺に対しても妥当するということは吉田がいっている通りです。そしてこれは,人間は死ぬということに対して確実であることはできないというのと同じなのですから,人間は自分の死に対して,自分自身が十全な原因ではあり得ないというのと同じです。もっともこれは,第三部定理四で個物res singularis一般についていわれていることそのものです。











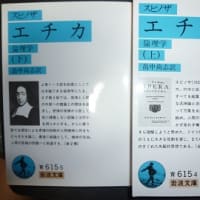
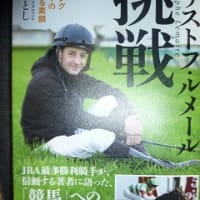






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます