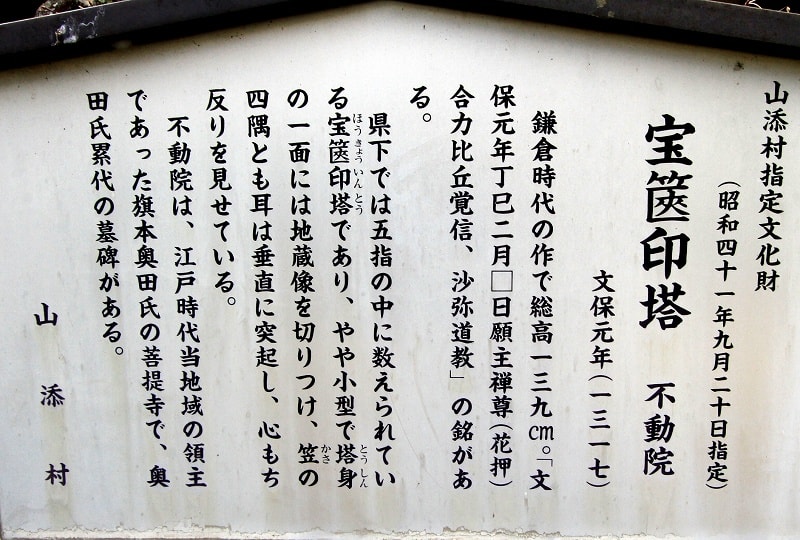山添村の中心地、大西集落の道路を挟んで北面する小高い岡に建つ「極楽寺」境内墓にある「郷塔」と呼ばれる五輪塔。

道路からは少し解り辛い場所に建つ極楽寺は、無住で小さい一堂があるだけの田舎寺、集落の公民館を兼ねて居るようで、長閑な集落を一望に見下ろせる。

奈良様式の複弁反花座の上に建つ五輪塔は、高さ154cmと小振りながら全て造立当初のままで保存状態が良好。

地輪の一面に正中二年(1325)乙丑4月□日の銘が有り、鎌倉後期の造立・・・・山添村の文化財に指定されて居る。

前述の不動院とは歩いても10分弱程の位置にあり、鎌倉後期のこの土地の仏教文化が偲ばれる。

一方、無縁仏の集積の中には・・・後列中央に総高約1.3mの阿弥陀坐像石仏と、高さ約70cmの地蔵箱石仏が目を惹く。

阿弥陀石仏は江戸期のありふれた作風ながら、地蔵箱石仏は上部に枘突起が有り、元は笠石が載っていたもので、室町後期の様式をよく表している。
胸元で断裂しているのは、ちょっと痛々しいのですが・・・・。
撮影2012.4.14