大阪で開催されたG20が終わりました。
大阪の隣県に住んでいるわが身にも
ピリピリした緊張感が伝わってきました。
新幹線のコインロッカーやごみ箱の閉鎖、
高速道路の封鎖、
大阪は学校も休校になっていました。
全国から警備の人たちも集まっていました。
何も起きないというのは
当たり前のことのようですが
実はすごいことです。
万全の準備があってこその
「何も(事件や事故が)ない」状態なのだなと思います。
医療通訳の仕事も似ているところがあります。
通訳はその場所で発語されたすべてが正しく通訳できて
はじめて100点(当たり前)といえます。
通訳がいない状態で話している(言語の壁がない)のと同じです。
その状態から、単語が漏れたり、解釈が間違えていたりすると
どんどん減点されていきます90点、80点、70点・・・。
逆に120点になることは仕事の性格上、そうそうありません。
その減点部分をいかに減らすかが、
通訳者の力量になってきます。
暗記に自信があっても、メモをとったり
確実にわからない単語は発語者にいい直しをお願いしたり
本人に伝わっていないようであれば他の言葉で表現したり。
伝えるために頭の中はすごい勢いで
言葉の引き出しを開けたり閉めたりしながら、適切な言葉を探しています。
私たちが医療通訳の勉強をするのはその引き出しを多くするためです。
医療通訳者が未熟なせいで、困るのは通訳者ではなく、患者です。
そういうことを肝に銘じで、
「なにもない」通訳を目指したいと思います。
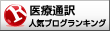
大阪の隣県に住んでいるわが身にも
ピリピリした緊張感が伝わってきました。
新幹線のコインロッカーやごみ箱の閉鎖、
高速道路の封鎖、
大阪は学校も休校になっていました。
全国から警備の人たちも集まっていました。
何も起きないというのは
当たり前のことのようですが
実はすごいことです。
万全の準備があってこその
「何も(事件や事故が)ない」状態なのだなと思います。
医療通訳の仕事も似ているところがあります。
通訳はその場所で発語されたすべてが正しく通訳できて
はじめて100点(当たり前)といえます。
通訳がいない状態で話している(言語の壁がない)のと同じです。
その状態から、単語が漏れたり、解釈が間違えていたりすると
どんどん減点されていきます90点、80点、70点・・・。
逆に120点になることは仕事の性格上、そうそうありません。
その減点部分をいかに減らすかが、
通訳者の力量になってきます。
暗記に自信があっても、メモをとったり
確実にわからない単語は発語者にいい直しをお願いしたり
本人に伝わっていないようであれば他の言葉で表現したり。
伝えるために頭の中はすごい勢いで
言葉の引き出しを開けたり閉めたりしながら、適切な言葉を探しています。
私たちが医療通訳の勉強をするのはその引き出しを多くするためです。
医療通訳者が未熟なせいで、困るのは通訳者ではなく、患者です。
そういうことを肝に銘じで、
「なにもない」通訳を目指したいと思います。










