kan-haru blog 2008
< 総合INDEX へ
山谷の鎮守様諏訪神社
諏訪神社(大田区大森西2-23-6 地図参照)の創建は明らかでないが、1964年(昭和39年)には五百年祭が盛大に行われ、1936年(昭和11年)に村社に定められた、東京府下荏原郡大森村字山谷(東山谷:大森東二丁目、南山谷:大森西三丁目、北山谷:大森西二丁目)の鎮守様(「大森町界隈あれこれ 大森町の社寺 諏訪神社その1」参照)です。
1938年(昭和13年)から大森町に住みついて山谷の鎮守様諏訪神社には、お祭りや神社にまつわる行事にはお参りするのが習わしで、子供や孫の七五三にはお祝いを行い、家族の無病息災を祈願しています。
2月の諏訪神社の行事には、節分のほかに初午、針供養が行われます。この古来のしきたりの祭りごとに、今年は鎮守様の諏訪神社で参加してきました。
節分
節分は、季節(立春・立夏・立秋・立冬)の始まりの前日のことで、特に江戸時代以後は立春の前日をさすことが多くなりました。今年は2月4日が立春で、節分は3日の日曜日に当たりました。
節分には、年男、年女により豆まきが行われますが、これは平安時代に中国から伝わった1年の最後の日に疫鬼を祓って新年を迎える宮中の行事の追儺の儀式からきたもので、立春を四季が一巡りした1年の最初の日であることから、その前日の節分は年の最後の日として都から鬼を追い厄を祓う豆まきが行われたと云われます。
今年は、大森町に住んで70年になり、年男を希望して豆まきに参加したのですが、当日は生憎と前夜からの雪のため豆まきはできずに、集まった人に手渡しで豆を授与しました。
諏訪神社の豆まきの行事は、豆まきを希望する37名の年男・年女を午後3時から3回に分けて行われました。

当日の年男の順番は、1組となりましたので午後3時前に社務所で羽織袴を付けて本殿に上がり、神官が祝詞を奉じた後で代表に合わせて2礼2拍手1礼をして御祭神にお詣りし、次に神官から授けられた一握りの豆を、「福は内」と唱え御祭神の内に2回捲いてから、外に「鬼は外」を唱え1回捲きます。儀式を終えてから、当日は悪天のため本殿内で御簾を下ろして記念写真を撮り、豆まきの準備は完了です。

雪のため豆が撒けないので、諏訪会館横で並んで待っている人に豆、お菓子などが入っている袋を手渡しで授与しました。写真は、2007年の豆まき風景(「大森町界隈あれこれ 大森町風景・風物詩 諏訪神社節分」参照)です。

2007年豆まき風景
豆まきが済んでから、諏訪会館内で年男・年女一同が席に付き、食会(なおらい)で乾杯し今年は良い年であることを願って歓談します。帰りには、除禍招福祈祷守護のお札とお土産を頂戴して節分の儀式は終了です。
初午と針供養
・初午
今年の初午は、2月の12日ですが、やはり天気が悪く雨に祟られましたが、午後3時から開始の諏訪神社に見に行ってきました。
初午は、2月の最初の午の日の稲荷社の縁日で、稲荷本社の京都伏見稲荷の神が降りたのがこの日であったとされ、全国の稲荷社で祀りの行事が行われます。
初午の行事は、農耕を司る倉稲魂神(うがのみたまのかみ~宇迦之御霊神とも表記)を祀って五穀豊穣や福徳を祈願する稲荷信仰です。
昔の諏訪神社の周辺は、田圃と畑の農村でしたので、豊作を祈る農家の信仰が厚かったので、諏訪神社の境内に末社の稲荷様を祀られたのでしょう。
午後3時には、神社役員やお参りに来た人が諏訪会館に集まり、神主さんの先導でお稲荷さまで祝詞を挙げて儀式を行います。代表に合わせて参詣します。

初午の俗信に、4月初めの巳の日の菜の花祭りの夜と初午の何れかに雨が降らないと火に祟られるとか、初午の早い年は火事が多いとか云われますが、今年は雨が降り12日の最も遅い日が初午ですので、良い年に恵まれることが期待できるかも知れません。

・針供養
諏訪神社には、内川沿いに金山神社(「大森町界隈あれこれ 大森町の社寺 諏訪神社その2」参照)という金山彦大神(カナヤマヒコノオオカミ)を祀った境外の別社があります。
針供養は、折れた縫い針を供養し淡島神社に収める行事で、2月8日に行われるのが一般ですが、諏訪神社では、初午の行事に合わせて2月12日に金山神社で針供養が営なまわれます。
昔は針仕事が女性にとっての重要な仕事でしたので、折れた針を供養して普段固いものばかり刺しているので、やわらかいコンニャクや豆腐に刺して休ませて、裁縫の上達をお祈りしたのです。

針供養(写真拡大)
金山神社(地図参照)での針供養は、稲荷社の初午祭を済ませてから、神主さんと神社役員や針供養をする女性が参列して豆腐に針を刺して神殿に捧げ、祝詞を挙げて供養をして代表に合わせあて参拝します。

初午と針供養の儀式の後、15時30分から一般参詣者にお菓子が配られます。今年は雨模様のため、例年に比べて参詣者が少ない様でした。
穴八幡神社一陽来復御守のお祭り
江戸時代の元禄年間から穴八幡宮に伝来する一陽来復御守の祭り方(「風景・風物詩 初詣風物詩 穴八幡神社と放生寺 その2」参照)は、冬至、大晦日または節分の午前0時に、恵方の巳午(真南から少し東)方向にお守りの文字を向けて、反対の子亥(北)側の柱か壁の高いところに、糊を付けて貼らないとご利益が授からないと云われております。1月5日の初詣りで戴いてきた御守を、諏訪神社の節分の日に家の北側の壁に貼りお祭りしました。今年は、無病息災でいられることを願っております。

< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(2月分掲載Indexへ)
カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町風景別総目次 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 内川風景 大森町を流れる昭和の面影 第2回 へ
< 総合INDEX へ
山谷の鎮守様諏訪神社
諏訪神社(大田区大森西2-23-6 地図参照)の創建は明らかでないが、1964年(昭和39年)には五百年祭が盛大に行われ、1936年(昭和11年)に村社に定められた、東京府下荏原郡大森村字山谷(東山谷:大森東二丁目、南山谷:大森西三丁目、北山谷:大森西二丁目)の鎮守様(「大森町界隈あれこれ 大森町の社寺 諏訪神社その1」参照)です。
1938年(昭和13年)から大森町に住みついて山谷の鎮守様諏訪神社には、お祭りや神社にまつわる行事にはお参りするのが習わしで、子供や孫の七五三にはお祝いを行い、家族の無病息災を祈願しています。
2月の諏訪神社の行事には、節分のほかに初午、針供養が行われます。この古来のしきたりの祭りごとに、今年は鎮守様の諏訪神社で参加してきました。
節分
節分は、季節(立春・立夏・立秋・立冬)の始まりの前日のことで、特に江戸時代以後は立春の前日をさすことが多くなりました。今年は2月4日が立春で、節分は3日の日曜日に当たりました。
節分には、年男、年女により豆まきが行われますが、これは平安時代に中国から伝わった1年の最後の日に疫鬼を祓って新年を迎える宮中の行事の追儺の儀式からきたもので、立春を四季が一巡りした1年の最初の日であることから、その前日の節分は年の最後の日として都から鬼を追い厄を祓う豆まきが行われたと云われます。
今年は、大森町に住んで70年になり、年男を希望して豆まきに参加したのですが、当日は生憎と前夜からの雪のため豆まきはできずに、集まった人に手渡しで豆を授与しました。
諏訪神社の豆まきの行事は、豆まきを希望する37名の年男・年女を午後3時から3回に分けて行われました。

当日の年男の順番は、1組となりましたので午後3時前に社務所で羽織袴を付けて本殿に上がり、神官が祝詞を奉じた後で代表に合わせて2礼2拍手1礼をして御祭神にお詣りし、次に神官から授けられた一握りの豆を、「福は内」と唱え御祭神の内に2回捲いてから、外に「鬼は外」を唱え1回捲きます。儀式を終えてから、当日は悪天のため本殿内で御簾を下ろして記念写真を撮り、豆まきの準備は完了です。

雪のため豆が撒けないので、諏訪会館横で並んで待っている人に豆、お菓子などが入っている袋を手渡しで授与しました。写真は、2007年の豆まき風景(「大森町界隈あれこれ 大森町風景・風物詩 諏訪神社節分」参照)です。

2007年豆まき風景
豆まきが済んでから、諏訪会館内で年男・年女一同が席に付き、食会(なおらい)で乾杯し今年は良い年であることを願って歓談します。帰りには、除禍招福祈祷守護のお札とお土産を頂戴して節分の儀式は終了です。
初午と針供養
・初午
今年の初午は、2月の12日ですが、やはり天気が悪く雨に祟られましたが、午後3時から開始の諏訪神社に見に行ってきました。
初午は、2月の最初の午の日の稲荷社の縁日で、稲荷本社の京都伏見稲荷の神が降りたのがこの日であったとされ、全国の稲荷社で祀りの行事が行われます。
初午の行事は、農耕を司る倉稲魂神(うがのみたまのかみ~宇迦之御霊神とも表記)を祀って五穀豊穣や福徳を祈願する稲荷信仰です。
昔の諏訪神社の周辺は、田圃と畑の農村でしたので、豊作を祈る農家の信仰が厚かったので、諏訪神社の境内に末社の稲荷様を祀られたのでしょう。
午後3時には、神社役員やお参りに来た人が諏訪会館に集まり、神主さんの先導でお稲荷さまで祝詞を挙げて儀式を行います。代表に合わせて参詣します。

初午の俗信に、4月初めの巳の日の菜の花祭りの夜と初午の何れかに雨が降らないと火に祟られるとか、初午の早い年は火事が多いとか云われますが、今年は雨が降り12日の最も遅い日が初午ですので、良い年に恵まれることが期待できるかも知れません。

・針供養
諏訪神社には、内川沿いに金山神社(「大森町界隈あれこれ 大森町の社寺 諏訪神社その2」参照)という金山彦大神(カナヤマヒコノオオカミ)を祀った境外の別社があります。
針供養は、折れた縫い針を供養し淡島神社に収める行事で、2月8日に行われるのが一般ですが、諏訪神社では、初午の行事に合わせて2月12日に金山神社で針供養が営なまわれます。
昔は針仕事が女性にとっての重要な仕事でしたので、折れた針を供養して普段固いものばかり刺しているので、やわらかいコンニャクや豆腐に刺して休ませて、裁縫の上達をお祈りしたのです。

針供養(写真拡大)
金山神社(地図参照)での針供養は、稲荷社の初午祭を済ませてから、神主さんと神社役員や針供養をする女性が参列して豆腐に針を刺して神殿に捧げ、祝詞を挙げて供養をして代表に合わせあて参拝します。

初午と針供養の儀式の後、15時30分から一般参詣者にお菓子が配られます。今年は雨模様のため、例年に比べて参詣者が少ない様でした。
穴八幡神社一陽来復御守のお祭り
江戸時代の元禄年間から穴八幡宮に伝来する一陽来復御守の祭り方(「風景・風物詩 初詣風物詩 穴八幡神社と放生寺 その2」参照)は、冬至、大晦日または節分の午前0時に、恵方の巳午(真南から少し東)方向にお守りの文字を向けて、反対の子亥(北)側の柱か壁の高いところに、糊を付けて貼らないとご利益が授からないと云われております。1月5日の初詣りで戴いてきた御守を、諏訪神社の節分の日に家の北側の壁に貼りお祭りしました。今年は、無病息災でいられることを願っております。

< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(2月分掲載Indexへ)
カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町風景別総目次 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 内川風景 大森町を流れる昭和の面影 第2回 へ


























































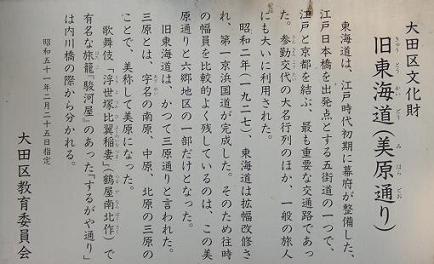
 東海道
東海道
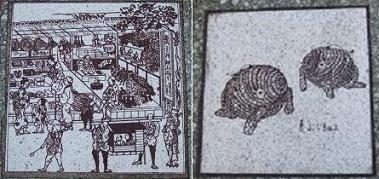 麦わら細工
麦わら細工



