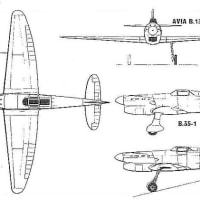◎このブログに興味をお持ちの方は、ここをクリックして小生のホームページも御覧下さい。
最近読んだ「逆転の大中国史」の著者の作なので大いに期待した。期待に反せず小生の「満洲国」の考え方に大きな一石を投じた。アメリカ人のブロンソン・レー氏は、戦前「満洲国出現の合理性」を書いた。満洲国建国を全面的に擁護しており、最近、新訳が出版されている(ただし邦訳のタイトルは異なる)。
だが、レー氏が言うのは、満洲国を否定する当時の米国の対日対支政策が、レー氏の考える米国建国の理念に反している、という主旨で書いているのであって、日本の対支、対満洲政策の擁護になっているのは、その結果に過ぎないのである。結果として、それが米国にとって正しかったのは、米国の政策の結果支那は共産化し、米国の多大な投資と宣教師の犠牲は無駄になり、朝鮮戦争という厄災に襲われる結果を招来したことでも分かる。
米国が対日戦など企図せず、日本と協調の道を歩めば、戦後の米国の厄災はなかったのみならず、大英帝国も保全されたのである。皮肉なことに、そうなっていたなら、欧米の植民地政策は続き、日本は白人国際社会で、有色人種国家として孤立の道を歩み続けなければならなかったであろう。
レー氏の支持した日本の満洲国建国、というのは日本の当面の政策とも合致している。日本の利益ともなるはずのものだった。ところが、というか、だから、というべきか、楊氏のようにモンゴルの独立を願うモンゴル出身者にとっては、満洲国は希望ではなかったというのだ。
「満洲国の版図の三分の二は昔から云うと蒙人の土地であり、満洲地域の原住民はこの蒙古人と漢人の両民族であった。(中略)ところが満洲国が出来て見ると五族協和の旗じるしのもとでも人口が多く三千万に近い漢民族の民政となってしまい蒙古人は少数民族の悲しさ、自然と軽視されがちとなり、日本人で蒙古関係に熱心な指導者はいわゆる蒙古狂扱いされる傾向となり・・・」という興安軍の経理だった斎藤実俊の著書を引用している(P207)。
これを米国に適用すると恐ろしいことが分かる。蒙古人はネイティブアメリカン(アメリカインディアン)が蒙古人に相当する。元々の住人のインディアンは広漠とした居留地に住むしか、民族のアイデンティティーは維持できない。それどころか、飲んだくれ荒れた生活をして自滅しつつある。
満洲人は皇帝が溥儀となったからまし、とモンゴル人に比べれば言えないこともないが、内実はそうでもなかろう。日本が支那本土に比べたら人々の安寧の地を作り、多数民族として将来実権を握る可能性まで含めれば、一番得をしたのは漢人である、といえないこともない。しかも日本の投資は、毛沢東のでたらめな経済政策にもかかわらず、満洲を食いつぶすことによって、鄧小平復権の時代まで中共を持たすことができた。
移民と自由と民主主義の国という、レー氏の建国の理念は、結局アングロサクソンのものであって、黒人やインディアンのものではなかった。同様に満洲国建国は根本的には、軍事的経済的に日本のためであった。楊氏は肯定しにくいだろうが、欧米諸国の対外政策に比べれば、日本の五族協和政策などは、良心的なものであった。
蒙古の土地はまた、日本人には想像できにくい特殊なものであり過ぎた。「草原を掘れば、たちまち砂漠と化してしまうことを経験的に知っているから(P207)」モンゴル人は土地を掘ることを嫌い、草原にそのまま大便をするのだという。日本流を押しつけるばかりではない。日本の対支政策の方便として蒙古独立を、蒙古自治に置き換えたりしたのだという。
日本の敗戦によって多くのモンゴル人がソ連を頼り、ソ連の傀儡政権とはいえ独立国家の体裁をとっていた結果、ソ連の崩壊とともに独立国となることができた。これはソ連の共産主義の毒牙にかかった多くのモンゴル人犠牲者を出し、現在にも残るであろう共産主義の残滓があるとはいえ、北半分だけでもモンゴルは独立の故地を持つことができたのは、楊氏には幸運な結果といえるのであろうか。
少なくとも、中共に支配され、草原は耕かし尽され民族のアイデンティティーも喪失しつつある南モンゴル(著者はそう呼ぶ)に比べればよほどよい、といえるのだろう。本書によれば多くのモンゴル人闘士が、独立のため、ソ連を利用し日本を利用した。結局独立は自らの手で勝ち取るものである。
そのことは、民族のアイデンティティーを喪失しつつある、我々日本人にこそ当てはまる。理屈はともかく、元来保守の心情を持たない小生が言っても詮方ないことではあるが。楊氏の文言は日本人に対しても辛らつではあるが、根底で日本に対する同情あるいは信頼があるように思われる。