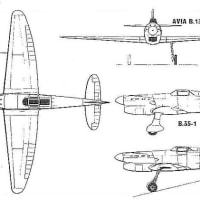昭和陸軍の軌跡。永田鉄山の構想ととその分岐・・・興味のある方は、ここをクリックして、アクセスして下さい・川田稔・中公新書
論旨は明快である。前半は永田鉄山の国家総動員論について説明している。後半は欧州戦争勃発に呼応して、対ソ戦と対英米戦の構想についての、武藤章と田中新一の対立について叙述している。永田の構想は、戦時の国家総動員について、戦時の動員ばかりではなく、平時の準備と構想が必要である、というのである。
永田の構想を引き継いだ二人は、支那大陸と南方における資源確保という点では共通するものの、田中は対ソ開戦論者であり対米戦争不可避と考えているのに対して、武藤は対ソ戦は行うべきではなく、対米戦も回避すべく努力したという。この本だけ読むと特に田中などの陸軍の唯我独尊で日本の国力をも考えない軍人官僚の典型、と読める。だが、そこに至るまでの幕末以降の日本の環境、というものが書かれていないからそう読むのである。もちろんこの本にそこまで書く目的が無いから、片手落ちと批判するのは筋違いである。この本は、当時の時局に対して陸軍の主流となった統制派の軍人官僚、永田鉄山、武藤章、田中新一の考え方の動きを詳細に叙述して貴重である。石原莞爾については付け足しであろう。
明治以来の日本史を概括してみよう。迫るロシアの脅威に対して、安閑と構え清の属国に甘えて自立しない不安定な朝鮮の独立のために日清戦争を戦った。しかし弱体化する清朝は満洲をロシアに奪われても危機感が無く、朝鮮まで併呑する構えであった。日本は満洲を奪われないために日露戦争を戦ったのであった。ここで満蒙権益なるものを得ることになった。それは資源や市場を持たない日本にとって貴重なものであった。ここで現代日本人が忘れた、江藤淳氏によれば忘れさせられた2つのことがある。
第一は、戦前の世界は、弱い民族は西洋に植民地化されてしまう弱肉強食の世界であって、民族の独立を保つには、強い軍隊を保持しなければならなかったのである。日露戦争で日本は精強陸軍と無敵艦隊の評価を得た。米海軍士官にとって東郷元帥はあこがれのまとですらあった。米軍は目の前の呉軍港は徹底的に破壊しながらも、海軍兵学校には1発も撃たなかったのである。
第二は、軍備が近代化すればするほど、強い陸海軍を保持するには、多くの資源と経済活動のための市場を必要とする。米英のテリトリーの外でこれらを獲得する場所は支那大陸しかなかった。日本の強い陸海軍とは、いつその基盤を失うかもしれない極めて脆弱な存在だった。既に日本の満洲での独占的権益は確立していた。そのことはリットン調査団でさえ許容していた。悪いことに、米国は「門戸開放」と称して支那本土と大陸に進出を図った。一方で自らは中南米は他国の進出を許さない聖域としていたのにである。そう言う米国が自らの生活圏は犯してはならず、日本の死活的利益にかかわる地域には進出させろ、と言うのはいかにも勝手である。
しかも大陸は清朝崩壊後の戦国時代であった。国際法上は中華民国として承認されていたが、実態は地域政府と軍閥が乱立していた。ようやく蒋介石政権と共産党に収束したのは日米開戦の頃に過ぎない。しかもこれら地方政府と軍閥は、外国軍隊の干渉によって支那の統一を行おうとしていた。そのターゲットに選ばれたのがお人好しの日本であった。そういう当時の状況を考えれば、永田、東條、武藤、田中ら統制派軍人の考えはアメリカに比べれば強欲どころか、辛うじて日本の独立を維持しようとする努力に過ぎない。日米交渉が妥結しても結局日本は陸海軍を維持できなくなり、欧米に侵食される運命だったのである。
だから本書にあるように、武藤に反抗して対米早期開戦を叫んだ田中の主張も一理ある。彼らは日本が真剣の上を素足で歩いているような日本の状況は百も承知していたのである。田中が武藤軍務局長や東條首相と罵倒を交えた大喧嘩をしたのは私心によるものではない。保身であれば更迭されるこんな行為は避けるのである。陸士や陸大で戦史を研究して日露戦争は辛勝に過ぎず、運よく勝ったと考えたの石原莞爾ばかりではなかった。石原はそれを公言し、他の軍人が言わなかっただけのことである。彼らは無敵皇軍と言う神話を信じていた愚か者たちではない。無敵皇軍でなければ日本は存立できないと考えていたのであって、ただひとつの望みだったのである。大東亜戦争の結果、有色人種の民族自決が成り自由貿易が出来る現在の状況が、戦前にもあったかのごとくの誤解が全ての間違いである。
また、本書にあるように永田らの陸軍が日本の政府を牛耳ろうと考えたことについても一言しておく。日本の存亡に死活的な存在となった満洲の安定に、幣原外交を始めとする日本外交は無力であった。支那の無法に対して余りに妥協的であった結果、支那からは侮日を受けた上に、欧米からは支那と妥協して出し抜くつもりではないかと疑われて、対日政策を硬化させる体たらくであった。しかも政党政府は何ら展望を示さずに統帥権干犯などと軍事を政権争奪に利用するありさまだった。しかし陸軍軍人は官僚化したとはいえ、関東軍と言う最前線で抗日侮日に向き合って、日本の満洲政策の失策を見せられて、しかも在留邦人の保護をしなければならない現実から、日本の戦略とはいかなるものでなければならないかを身を持って知らされていたのである。その点、海軍は陸軍との予算獲得競争にだけ勤しんでいたのであって、政党と同じく国家戦略の展望を持つ必然性はなかった。
本書で米国が対日戦を決意したのは、欧州戦争の勃発に伴う英国の崩壊を防ぐためであった、と言うのは一面正しい。しかしこれだけではない。資本が支那大陸と満洲にしか活路を見いだせず、アメリカも同じ所にフロンティアを求めている以上、日米の対決は避けられなかったのだし、日米開戦の動機のひとつともなっている。そうでもなければ、支那から発進した数百機の大編隊で日本本土を爆撃しようという計画が真珠湾攻撃当時進行中であった、ということを説明できまい。
本書で驚かされるのは、昭和十六年四月の時点で米国の世論調査では、欧州参戦支持が80%余りに達していた(P234)、という重大な事実をあっさり書いていることである。今までの日本の常識では、真珠湾攻撃が始まるまでは米国民は厭戦気分に満ちていて、真珠湾攻撃がこれを吹き飛ばした、ということになっていた。以前私は、欧州戦争に米国が中立を犯して公然と支援していたことと「幻の日本本土爆撃計画」と言う本にこの計画が大手マスコミで大々的に報道されていたことから米国に厭戦気分はなかったと論じたが、これは正しかったのである。だから山本五十六が開戦通告が遅れたことを知って思慮深げに、「これで眠れる獅子を起こしてしまった」と怒っている「トラトラトラ」という米国映画の場面がいかに噴飯ものか分かる。
それにしても、米国民が厭戦気分だったという誤認はさておいても、日本に最初の一発を撃たせようというルーズベルト政権の計画はいくらでも実証されているのに、当時米政府が開戦したくなかったなどという馬鹿げた説すら公然と日本では流布されている。このように客観的な事実に対する認識の共有すらなくては、日本の近現代史の論争は永遠に空回りし続けるのである。日本人はあの巨大な大東亜戦史から何の教訓も得ていない。それは米国の巧みな言論統制と洗脳によるものであっても、現在ではそれを打破する情報はいくらでも市井にすらある。