『四国八十八ヶ所霊場巡拝結願 お礼参りの旅(10月7日~8日)』 東 寺【成願】
四国八十八箇所霊場を廻り"結願"、高野山奥之院お礼参りをして"満願"。京都の東寺にお参りして"成満"ということで、高野山奥之院にて満願を達成したその足で、京都の東寺へ向かいました。東寺は唯一残る平安京の遺構であり、京都にある真言宗の総本山。教王護国寺ともいいます。桓武天皇による平安京遷都の2年後、延歴15年(796)に、都の南端に官寺として創設されました。その後、弘仁14年(823)、嵯峨天皇から弘法大師に下賜され、密教の根本道場となります。東寺を託された弘法大師は、密教の主尊である大日如来を境内の中心にすえ、広大な寺域に曼荼羅を表現しようと造営にあたったとされ、弘法大師自らは御影堂の場所に住房を構えたとのこと。弘法大師は東寺で過ごした後に高野山に向かいますが「身は高野 心は東寺に納めおく 大師の誓いあらたなりけり」という歌を残したと言われています。今でも弘法大師の命日、毎月21日、境内に1000店ほどの露店(コロナ禍前)で賑わいをみせる弘法市、通称"弘法さん"は、京の風物詩。創建からおよそ1,200年、平成6年(1994)には、世界文化遺産「古都京都の文化財」の構成資産として世界遺産登録されています。東寺には、2012年6月10日京都の世界文化遺産巡りで訪れた以来の参拝ですが、当時は修学旅行生の皆さんのワイワイガヤガヤで満ち溢れていたのを覚えています。さすがにコロナ禍、今回は参拝客は少なく、四国八十八ヶ所霊場巡礼の成願にふさわしい静かで落ち着いた雰囲気の中にてお参りすることができました。とは言え、金堂内は静粛厳守、お祈りと納札を納めたのみでしたので、御影堂(大師堂)では、最後の般若心経、ご真言をマスク越しながら高らかに唱え、遂に"成願"となりました。食堂の納経所では、納経帳の最終頁に弘法大師の御朱印をいただき、ひと安心。御詠歌入り白衣には、東寺の御朱印の場所がなかったため、ご真言"南無大師遍照金剛"の南無の上に御朱印を頂戴しました。実は東寺の御朱印は9種類(弘法大師、大日如来、薬師如来、毘沙門天、不動明王、十一面観音菩薩、愛染明王、八幡大菩薩、虚空蔵菩薩)あるのですが、さすがにお遍路さんのいでたちで、四国霊場八十八ヶ所納経帳にて、言わずもがなの弘法大師の御朱印を。ご苦労さまでしたとの労いのお言葉をいただき、あらためてじ~んときてしまいました。弘法大師と共に旅した同行二人、ここに終着、念願の成願となりました。それではあらためまして、高祖弘法大師御法号〝南無大師遍照金剛 南無大師遍照金剛 南無大師遍照金剛〟 回向ノ文〝(願わくば)この功徳を以って普く一切に及ぼし 我等と衆生と皆共に佛道を成ぜん〟合掌。
【東 寺】
真言宗総本山 教王護国寺 東寺 〒601-8473 京都府京都市九条町1番地
慶賀門

金 堂 【国宝】桃山時代
[ご本尊] 薬師如来 [ご真言] おん ころころ せんだり まとうぎ そわか


金堂内 薬師三尊⦅月光菩薩 薬師如来 日光菩薩⦆(重要文化財) (リーフレットより)

講 堂 【重要文化財】 室町時代
[ご本尊] 大日如来 [ご真言] おん あびらうんけん ばざらだと ばん

講堂内 立体曼荼羅 (リーフレットより)

講堂内 不動明王【国宝】 (絵葉書より)


御影堂(大師堂) 【国宝】 南北朝時代
[ご本尊] 弘法大師 [ご法号] 南無大師遍照金剛

御影堂(大師堂)後堂
[ご本尊] 不動明王 [ご真言] のうまくさんまんだ ばざら だん せんだん
まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん


食 堂 [ご本尊] 十一面観世音菩薩 [ご真言] おん まか きゃろにきゃ そわか

五重塔 【国宝】 江戸時代




四国八十八箇所霊場を廻り"結願"、高野山奥之院お礼参りをして"満願"。京都の東寺にお参りして"成満"ということで、高野山奥之院にて満願を達成したその足で、京都の東寺へ向かいました。東寺は唯一残る平安京の遺構であり、京都にある真言宗の総本山。教王護国寺ともいいます。桓武天皇による平安京遷都の2年後、延歴15年(796)に、都の南端に官寺として創設されました。その後、弘仁14年(823)、嵯峨天皇から弘法大師に下賜され、密教の根本道場となります。東寺を託された弘法大師は、密教の主尊である大日如来を境内の中心にすえ、広大な寺域に曼荼羅を表現しようと造営にあたったとされ、弘法大師自らは御影堂の場所に住房を構えたとのこと。弘法大師は東寺で過ごした後に高野山に向かいますが「身は高野 心は東寺に納めおく 大師の誓いあらたなりけり」という歌を残したと言われています。今でも弘法大師の命日、毎月21日、境内に1000店ほどの露店(コロナ禍前)で賑わいをみせる弘法市、通称"弘法さん"は、京の風物詩。創建からおよそ1,200年、平成6年(1994)には、世界文化遺産「古都京都の文化財」の構成資産として世界遺産登録されています。東寺には、2012年6月10日京都の世界文化遺産巡りで訪れた以来の参拝ですが、当時は修学旅行生の皆さんのワイワイガヤガヤで満ち溢れていたのを覚えています。さすがにコロナ禍、今回は参拝客は少なく、四国八十八ヶ所霊場巡礼の成願にふさわしい静かで落ち着いた雰囲気の中にてお参りすることができました。とは言え、金堂内は静粛厳守、お祈りと納札を納めたのみでしたので、御影堂(大師堂)では、最後の般若心経、ご真言をマスク越しながら高らかに唱え、遂に"成願"となりました。食堂の納経所では、納経帳の最終頁に弘法大師の御朱印をいただき、ひと安心。御詠歌入り白衣には、東寺の御朱印の場所がなかったため、ご真言"南無大師遍照金剛"の南無の上に御朱印を頂戴しました。実は東寺の御朱印は9種類(弘法大師、大日如来、薬師如来、毘沙門天、不動明王、十一面観音菩薩、愛染明王、八幡大菩薩、虚空蔵菩薩)あるのですが、さすがにお遍路さんのいでたちで、四国霊場八十八ヶ所納経帳にて、言わずもがなの弘法大師の御朱印を。ご苦労さまでしたとの労いのお言葉をいただき、あらためてじ~んときてしまいました。弘法大師と共に旅した同行二人、ここに終着、念願の成願となりました。それではあらためまして、高祖弘法大師御法号〝南無大師遍照金剛 南無大師遍照金剛 南無大師遍照金剛〟 回向ノ文〝(願わくば)この功徳を以って普く一切に及ぼし 我等と衆生と皆共に佛道を成ぜん〟合掌。
【東 寺】
真言宗総本山 教王護国寺 東寺 〒601-8473 京都府京都市九条町1番地
慶賀門

金 堂 【国宝】桃山時代
[ご本尊] 薬師如来 [ご真言] おん ころころ せんだり まとうぎ そわか


金堂内 薬師三尊⦅月光菩薩 薬師如来 日光菩薩⦆(重要文化財) (リーフレットより)

講 堂 【重要文化財】 室町時代
[ご本尊] 大日如来 [ご真言] おん あびらうんけん ばざらだと ばん

講堂内 立体曼荼羅 (リーフレットより)

講堂内 不動明王【国宝】 (絵葉書より)


御影堂(大師堂) 【国宝】 南北朝時代
[ご本尊] 弘法大師 [ご法号] 南無大師遍照金剛

御影堂(大師堂)後堂
[ご本尊] 不動明王 [ご真言] のうまくさんまんだ ばざら だん せんだん
まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん


食 堂 [ご本尊] 十一面観世音菩薩 [ご真言] おん まか きゃろにきゃ そわか

五重塔 【国宝】 江戸時代













 7日の宿泊は、宿坊へ。宿坊宿泊は、阿波の国、第六番、安楽寺さん以来。高野山の山内では52ヶ寺が宿坊を提供しているとのことですが、今回は金剛峯寺のすぐそばの普賢院さんにお世話になりました。高野山の精進料理といえば胡麻豆腐、夕食にて食しましたが期待とおりで大変おいしゅうございました。お膳での食事は、団体旅行の宴会場を思い出しますが、宿坊での完全黙食のもと、茶碗やお椀を拝むように手のひらに取ると、その温かみがとても有難く、食の尊さが染み入りました。夕食後は、ライトアップされた壇上伽藍へ。出がけに普賢院さんから熊に気を付けてとのアドバイスをいただき少々緊張の夜間散策となりましたが、高野山の澄み切った空気に、根本大塔などの朱色が照明に映え、その美しさに息を飲みます。ライトアップされた大門、中門の力士像は陰影が協調され、その迫力は増し増しに。高野山での特別な夜を、宿坊に泊まったのは大正解。朝のお勤めは、6時半から。ご本堂にて読経とお焼香、その後、弘法大師の十大弟子のひとりの華厳寺道雄の作で弘法大師が点眼されたとのご本尊・普賢菩薩像を真近で拝み、金剛薩埵像、大黒天や、金剛吼・竜王吼・畏十力吼・電吼・無量力吼の名称が付けられる五幅からなる五大力菩薩像の仏画白描図など普賢院内名跡寶聚院を見学、巡拝。特に印象深かったのは、平成8年に請来された仏舎利の拝観とその周りの八体仏。その後の朝食では、がんもどきの有難さを習得。とてもとても貴重な体験ができ、ありがとうございました。
7日の宿泊は、宿坊へ。宿坊宿泊は、阿波の国、第六番、安楽寺さん以来。高野山の山内では52ヶ寺が宿坊を提供しているとのことですが、今回は金剛峯寺のすぐそばの普賢院さんにお世話になりました。高野山の精進料理といえば胡麻豆腐、夕食にて食しましたが期待とおりで大変おいしゅうございました。お膳での食事は、団体旅行の宴会場を思い出しますが、宿坊での完全黙食のもと、茶碗やお椀を拝むように手のひらに取ると、その温かみがとても有難く、食の尊さが染み入りました。夕食後は、ライトアップされた壇上伽藍へ。出がけに普賢院さんから熊に気を付けてとのアドバイスをいただき少々緊張の夜間散策となりましたが、高野山の澄み切った空気に、根本大塔などの朱色が照明に映え、その美しさに息を飲みます。ライトアップされた大門、中門の力士像は陰影が協調され、その迫力は増し増しに。高野山での特別な夜を、宿坊に泊まったのは大正解。朝のお勤めは、6時半から。ご本堂にて読経とお焼香、その後、弘法大師の十大弟子のひとりの華厳寺道雄の作で弘法大師が点眼されたとのご本尊・普賢菩薩像を真近で拝み、金剛薩埵像、大黒天や、金剛吼・竜王吼・畏十力吼・電吼・無量力吼の名称が付けられる五幅からなる五大力菩薩像の仏画白描図など普賢院内名跡寶聚院を見学、巡拝。特に印象深かったのは、平成8年に請来された仏舎利の拝観とその周りの八体仏。その後の朝食では、がんもどきの有難さを習得。とてもとても貴重な体験ができ、ありがとうございました。

























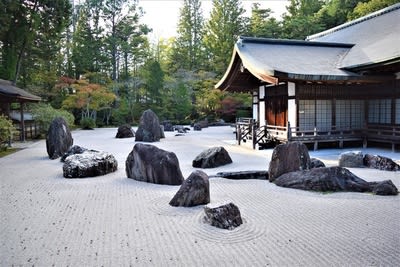
















 高野山を訪れるのは、平成24年(2012)11月3日以来、当時は、神戸在住で京都奈良の世界遺産巡りから『紀伊山地の霊場と参詣道』へ足を延ばした観光目的の世界遺産巡り。時は流れ、今回はお礼参りということで、白衣に輪袈裟、サンヤ袋にはお数珠、納札、勤行本、ロウソク、線香、ライターを入れ、御朱印を頂戴すべく納経帳を持参。訪問目的が違うと装いだけでなく心構えまで違ってくるから不思議です。さて、高野山は、平安時代のはじめに弘法大師によって開かれた日本仏教の聖地。金剛峯寺という名称は、弘法大師が「金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)」というお経より名付けられたと伝えられています。「総本山金剛峯寺」という場合は、金剛峯寺だけではなく高野山全体を指します。高野山は「一山境内地」と称し、高野山の至る所がお寺の境内地であり、高野山全体がお寺です。まず迎えてくれるのは『大門』。さらに進むと『壇上伽藍』となります。伽藍とは、梵語(サンスクリット)のサンガ・アーラーマの音訳で、本来僧侶が集い修行をする閑静清浄なところの意。高野山金剛峰寺は、弘仁7年(816)弘法大師により開創されましたが、その造営は壇上伽藍からはじめ、密教思想に基づく金堂、大塔、西塔、僧房などを建立しました。壇上伽藍は、胎蔵曼荼羅の世界を表しているといわれています。高野山全体を金剛峯寺という寺院と見たとき、その境内地の核にあたる場所にあり、古来より弘法大師入定の地である奥之院と並んで、信仰の中心として大切にされてきました。諸堂多く、見どころいっぱいの壇上伽藍。金堂と根本大塔は内部拝観できましたが、他の諸堂は外観を眺めつつの壇上伽藍ひと回り。伽藍御供所では、金堂(薬師如来)の御朱印、大塔(大日如来)の御朱印2つをいただきました。根本大塔などは夜ライトアップされるとのことで、当夜は宿坊泊りなので、夜、再訪する予定。夕方ということもあり巡拝者、観光客もほとんどなく、静寂さが身に染み入る壇上伽藍でした。
高野山を訪れるのは、平成24年(2012)11月3日以来、当時は、神戸在住で京都奈良の世界遺産巡りから『紀伊山地の霊場と参詣道』へ足を延ばした観光目的の世界遺産巡り。時は流れ、今回はお礼参りということで、白衣に輪袈裟、サンヤ袋にはお数珠、納札、勤行本、ロウソク、線香、ライターを入れ、御朱印を頂戴すべく納経帳を持参。訪問目的が違うと装いだけでなく心構えまで違ってくるから不思議です。さて、高野山は、平安時代のはじめに弘法大師によって開かれた日本仏教の聖地。金剛峯寺という名称は、弘法大師が「金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)」というお経より名付けられたと伝えられています。「総本山金剛峯寺」という場合は、金剛峯寺だけではなく高野山全体を指します。高野山は「一山境内地」と称し、高野山の至る所がお寺の境内地であり、高野山全体がお寺です。まず迎えてくれるのは『大門』。さらに進むと『壇上伽藍』となります。伽藍とは、梵語(サンスクリット)のサンガ・アーラーマの音訳で、本来僧侶が集い修行をする閑静清浄なところの意。高野山金剛峰寺は、弘仁7年(816)弘法大師により開創されましたが、その造営は壇上伽藍からはじめ、密教思想に基づく金堂、大塔、西塔、僧房などを建立しました。壇上伽藍は、胎蔵曼荼羅の世界を表しているといわれています。高野山全体を金剛峯寺という寺院と見たとき、その境内地の核にあたる場所にあり、古来より弘法大師入定の地である奥之院と並んで、信仰の中心として大切にされてきました。諸堂多く、見どころいっぱいの壇上伽藍。金堂と根本大塔は内部拝観できましたが、他の諸堂は外観を眺めつつの壇上伽藍ひと回り。伽藍御供所では、金堂(薬師如来)の御朱印、大塔(大日如来)の御朱印2つをいただきました。根本大塔などは夜ライトアップされるとのことで、当夜は宿坊泊りなので、夜、再訪する予定。夕方ということもあり巡拝者、観光客もほとんどなく、静寂さが身に染み入る壇上伽藍でした。













 昨年GoToトラベルを利用し11月25日~12月4日に巡拝した「四国八十八ヶ所霊場」結願後の高野山お礼参りに、約1年越しとなりましたが、高野山を訪れました。その間、新型コロナウィルスは、年末&年明けからの第3波、春先の第4波、夏休みにピークが最高を迎えた第5波と猛威を奮っていましたが、ようやく10月を迎え落ち着きを見せています。第6波が来る前にと「高野山 奥之院」にて弘法大師さまに結願のご報告をすべく待望のお礼参りを決行した次第。まずは、弘法大師のお母さまが祀られ、かつて高野山が女人禁制だった頃は女人高野とも呼ばれた『慈尊院』を参拝です。『慈尊院』は、弘仁7年(816)弘法大師が、高野山開創に際し、高野山参詣の要所にあたるこの地に表玄関として伽藍を草創し、庶務を司る政所、高野山への宿所、冬期の避寒修行の場所とされました。息子の姿を一目見たいと大師の母公(玉依御前)が香川県善通寺より訪ねて来るも、当時の高野山は女人禁制であったため、この慈尊院で暮らすことに。また、母公の身を案じた弘法大師は高野山より月に九度、慈尊院を訪ね来られたことから、この地が九度山という町名になったと伝えられています。承知2年(835)2月5日、母公は83歳でご逝去。弘法大師は母公のために弥勒堂(御廟)を建て弥勒菩薩を安置。時代とともに弥勒菩薩が母公の化身と崇められ、高野山に上がれない女性の信仰を深め「女人高野」として親しまれてきました。慈尊院とは弥勒菩薩の別名で、これより表向きに『慈尊院』となったとのこと。また、女性の象徴である乳房型の絵馬を奉納すると願いが叶うのだそう。弥勒菩薩像は国宝に指定され、平成16年(2004)7月ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』として、慈尊院ならびに慈尊院弥勒堂が登録されています。ちょうど「くどやま件p祭2021」が開催されていて、表門の暖簾や拝堂に艶やかで美しい装飾が散りばめられており、いかにも「女人高野」らしき雰囲気を味わうことができました。
昨年GoToトラベルを利用し11月25日~12月4日に巡拝した「四国八十八ヶ所霊場」結願後の高野山お礼参りに、約1年越しとなりましたが、高野山を訪れました。その間、新型コロナウィルスは、年末&年明けからの第3波、春先の第4波、夏休みにピークが最高を迎えた第5波と猛威を奮っていましたが、ようやく10月を迎え落ち着きを見せています。第6波が来る前にと「高野山 奥之院」にて弘法大師さまに結願のご報告をすべく待望のお礼参りを決行した次第。まずは、弘法大師のお母さまが祀られ、かつて高野山が女人禁制だった頃は女人高野とも呼ばれた『慈尊院』を参拝です。『慈尊院』は、弘仁7年(816)弘法大師が、高野山開創に際し、高野山参詣の要所にあたるこの地に表玄関として伽藍を草創し、庶務を司る政所、高野山への宿所、冬期の避寒修行の場所とされました。息子の姿を一目見たいと大師の母公(玉依御前)が香川県善通寺より訪ねて来るも、当時の高野山は女人禁制であったため、この慈尊院で暮らすことに。また、母公の身を案じた弘法大師は高野山より月に九度、慈尊院を訪ね来られたことから、この地が九度山という町名になったと伝えられています。承知2年(835)2月5日、母公は83歳でご逝去。弘法大師は母公のために弥勒堂(御廟)を建て弥勒菩薩を安置。時代とともに弥勒菩薩が母公の化身と崇められ、高野山に上がれない女性の信仰を深め「女人高野」として親しまれてきました。慈尊院とは弥勒菩薩の別名で、これより表向きに『慈尊院』となったとのこと。また、女性の象徴である乳房型の絵馬を奉納すると願いが叶うのだそう。弥勒菩薩像は国宝に指定され、平成16年(2004)7月ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』として、慈尊院ならびに慈尊院弥勒堂が登録されています。ちょうど「くどやま件p祭2021」が開催されていて、表門の暖簾や拝堂に艶やかで美しい装飾が散りばめられており、いかにも「女人高野」らしき雰囲気を味わうことができました。











