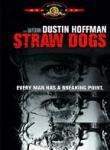この作品を知るまでパシフィッククレストトレイル(PCT)のことは知りませんでした。太平洋側のアメリカ=メキシコ国境からアメリカ=カナダ国境までの自然歩道を4~6か月かけて歩くらしいのですが、ウィキによると総延長4000キロ以上となっているので、この作品の主人公はどこかの途中地点からスタートして1600キロ歩いたってことなのかな。それでも十分にすごい。
主人公はシェリルストレイドリースディザースプーン。母ボビーローラダーンの死を受け入れることができず、ドラッグと男に溺れ結婚生活は(当然)破たんし、誰の子か分からない子を妊娠してしまうという堕ちるとこまで堕ちた女性が心機一転人生を立て直そうとこのPCTに挑戦する。
この自然歩道にはアメリカの大自然が残り、砂漠地帯、山岳地帯、雪山と色んなところを通らなければならない。要所要所には挑戦者たちのためのキャビンがあったり、途中の町があったりして、そこにあらかじめ必要になるであろう荷物を自分でもしくは後から家族などが送って来てそれを受け取ることはできるが、その間の道は過酷で、そこを一人きりでテントで寝泊まりして過ごす。
最初に書いたシェリルの境遇は、物語の始めに語られるわけではなくPCTを歩き始めたシェリルの姿から始まり、彼女がこの挑戦を通して自分の過去の行動や母親との思い出をフラッシュバックしていく形で観客に語られる。
シェリルは鬼のように重い荷物を背負い、1日目の夕飯で取扱説明書を見ながら使っているバーナーの燃料を間違えて持ってきたことに気付く。ここで彼女がこういう挑戦をするにはどれほど素人かということが分かる。素人な上に舐めて来ている。バーナーの説明書さえ初見だったくらいなんだから。どうやら登山靴もサイズの合わないものを履いているらしく足がだんだん辛い状況にもなってくる。
最初の一歩から「なんでこんなことに挑戦しようと思ったんだろ」と後悔しているシェリルだが、ぶーたれながらも歩みは一歩ずつ前に進めていく。そんな彼女に好感が持てる。
徐々に明らかになる彼女の人生。離婚したことは最初に分かるが、原因が彼女の浮気ということが衝撃だ。しかも「何度もね」と回想シーンの夫が言う。彼女は夫がいるにも関わらずドラッグに溺れ、手当たり次第に男と寝まくっていた。
少しずつ母親との思い出のシーンも語られるのだが、初めはよくこういう物語に出てくる問題のあるお母さんなのかと思って見ていたら、実は正反対。暴力夫から逃げ出し女手一つで自分と弟を育ててくれたお母さん。シェリルが大学時代には同じ大学に入って勉強しようという意欲もあるし、不幸な状況にあってもいつも鼻歌を歌って明るく過ごすすべを知っていたお母さん。大学時代のシェリルが生意気にも「娘が自分より教養があるってどんな気分?」なんて尋ねても「それが私の目標だったわ。娘を自分より教養のある女性に育てること」と言い切る立派なお母さん。そんなお母さんがガンで余命数ヶ月だと宣告されてしまう。妻であることや母であることという仮面を脱ぎ去り一人の人間としてこれからは生きていける、そう思っていた矢先の病だった。
シェリルにとってはあまりに大きかった母という存在。そんな精神的支柱を失い壊れてしまったシェリルの心。シェリルの無茶苦茶な行動は母の死に起因していたのだった。ドラッグと男に溺れながらも母親への罪悪感は捨てきれなかったシェリル。このままではいけないと彼女はPCTに挑戦したのだった。
女性一人のPCT挑戦というのは珍しいらしく、道中挑戦者たちの間でシェリルは話題になっていたらしい。女性だからということで親切を受けることもあったし、怖い目に遭うこともあった。過酷な自然の中でもしかしたら一番怖いのは人間に会うことかもしれない。それでもやはり人からのぬくもりを感じることのほうが多いのだろう。途中の町で出会った男性と一夜を共にするシェリルに「おいおい、まだそういうことする?」と思ったけど、あそこまで一人きりでずっといると人恋しくもなるだろうなと理解できる部分もあった。
シェリルの回想シーンはとてもヘヴィだけど、彼女の実際の道のりは過酷な状況に加えて、軽いユーモアを持って語られる。この語り口のうまさは脚本を担当したニックホーンビィのおかげかもしれない。そして、シリアスもコミカルも巧みに演じ分けるリースはさすがだと感じました。この作品でアカデミー賞、リースは主演、母ロビーを演じたローラダーンは助演でノミネートされていて、他にも受賞はなかったけどたくさんの賞にノミネートされていました。
最後に山中でおばあちゃんと一緒にいる男の子に出会って、シェリルに「Red River Valley」を歌ってくれるのですが、これがもう望郷の念を誘うのですよー。ワタクシも大好きな歌でなぜかじーんと来て涙ぐんでしまうんですよねー。この時シェリルはこの小さな男の子にお母さんを病気を亡くしたことを話すのですが、これが母親を亡くして以来初めて素直に誰かにその事実を話した時だったかもしれません。この子と別れたあとにシェリルは号泣するのですが、あれでまさに初めて彼女は救われたんだなぁと思います。
1人で1600キロ歩く映画と聞くと退屈に思われるかもしれませんが、全然そんなことはない作品です。
オマケ 「朝陽と夕陽は見ようと思えば毎日見ることができる」自分から美しい物を見ようとする姿勢が大切というシェリルのお母さんボビーの名言です。
「朝陽と夕陽は見ようと思えば毎日見ることができる」自分から美しい物を見ようとする姿勢が大切というシェリルのお母さんボビーの名言です。
ケーブルテレビで見ました。日本映画は詳しくないので全然予備知識なしで見ました。大沢たかおが好きというのもあって。
幼い少女が撲殺され遺棄されるという事件が起き、同じ手口で事件を起こし保釈されたばかりの清丸国秀藤原竜也が指名手配される。被害者の祖父であり資産家の蜷川隆興山崎努は清丸を殺した者に10億円の報酬を払うと新聞広告を出す。清丸は身の危険を感じ福岡署に自ら出頭。SPの銘刈(大沢たかお)、白岩松嶋奈々子は警視庁捜査一課の奥村岸谷五郎、神箸永山絢斗、福岡県警の関谷伊武雅刀らと5人で福岡から東京まで清丸を護送することになる。
蜷川がものすごい資産家でっていうなら、あんな広告ださないでももっとこっそり誰かに依頼したほうが確実に清丸を殺せた気はするんだよなぁ。あんなに警察官まで抱き込めるなら、内部の人間にこっそり頼んだほうが、あんな大々的に護衛がつかなくて済むわけだし、、、とか思うところは多々あるのですが、まずこの設定は設定として受け入れるとしましょう。それができるかどうかでこの作品の評価は大きく変わってくると思います。ワタクシはとりあえず受け入れました。
この設定さえ受け入れてしまえば、結構面白い作品だと思います。1億人が敵みたいな中で護送しなければいけない5人の刑事たち。機動隊の中にも清丸を襲うものが出てくるし、清丸の居場所をどんなに工作してもネット上にばれている。この中のスパイは誰だと疑心暗鬼にもなる。一方で、幼い少女を無残な形で殺害した清丸という男の命を守る必要がどこにあるのかという葛藤もある。清丸を殺すことはできなくとも殺そうとしただけで未遂に終わっても1億円がもらえるらしく、敵は増える一方だ。
大沢たかおがいつものひょろっとした印象では全然なくて、さすがに角刈りまではいかないけど、いつものモデル風の髪型ではなくて実際に刑事さんや普通の中年のサラリーマンがしていそうな髪型にしていて、中堅どころの刑事という役柄にうまくなりきっていた。警視庁捜査一課とは言えあんなに若い神箸が年上の刑事にあんな口の利き方が許されるもんかいなぁと疑問があったんだけど、永山絢斗の憎ったらしい演技は見ていて本気で腹が立ったから上手だってことだろう。藤原竜也はあいかわらずの大げさ演技だったけど、今回はそれが清丸の気持ち悪さを増幅させていて良かったと思う。
途中、清丸の過去の被害者の父親高橋和也が清丸を殺そうとする場面で、白岩が「誰かが清丸を殺すなら彼が一番ふさわしい」と言うところは確かにそうだよなと思ってしまうのだけど、それでもやはり銘苅は任務をまっとうするほうを選ぶ。白岩にしてみても清丸を殺せば10億入ると銘苅に言われても「蜷川の誤算でしたね。お金が入らないなら殺したのに」と言うところは結構かっこよかったな。
白岩が清丸に殺されたのはすごく腹が立ったな。白岩は優秀なSPなのに油断し過ぎだよ。まぁそれでこそ、銘苅の怒りが倍増して最後の対決につながるわけだけどね。あの最後の大沢たかお鬼気迫る演技はすごく良かったなぁ。それまでもいつもよりかなり太い声を出して銘苅という刑事になりきっていたけど、あのシーンでは清丸や、自分の妻をひき殺した飲酒運転の犯人への怒りや悲しみややるせなさが全部出ていてすごく良かった。
あとから漫画「ビーバップハイスクール」の作者木内一裕が書いた小説が原作というのを知って驚きました。それでちょっとくさいセリフが多いのかなと思ったり、、、そこまでめちゃくちゃ変ってことはなかったけど、ちょこっと引っかかるセリフはありました。最後の「国家に威信にかけて(銘苅の)命を救ってくれ」なんて警察のエライさんが救急隊員に言うところは一番ぷぷっとしてしまいました。
死刑宣告を受けた清丸が「後悔、反省しています。どうせ死刑になるならもっとやっとけば良かった」というセリフがあります。このセリフは、もしただ衝撃の一言を狙っただけだったとしたらがっかりですけど、ワタクシはやっぱり考えさせられました。確かにそういう考え方ってあると思うんですよね。だからこそ、死刑はやはり抑止力にはなりえないんだろうなと思います。といって死刑廃止論者になれないどこか割り切れない思いがワタクシの中にはあるのですが。
ネットのレビューを見ると良い評価と悪い評価に極端に二分されている感じですね。ばっかばかしい~と思ってしまった人には面白くない作品だろうなぁとは思うし、そう思う人がいるだろうなというのは理解できます。ワタクシは楽しんで見ることができました。
作品の紹介を読むと一風変わった設定だったので面白そうだなと思って見に行きました。主演のシアーシャローナンはとても注目している若手女優さんという理由もありました。
16歳のエリザベス(シアーシャ)はアメリカからイギリスに住むいとこたちに初めて会いに来た。彼女は父親のつけたエリザベスという名前が大嫌いで周りの人にはデイジーと呼んでと言っている。髪を金髪に染め鼻ピアスをし常にヘッドホンで音楽を聞いている反抗期まっただ中といった雰囲気のデイジー。空港に迎えに来たのはいとこ兄弟の次男坊アイザックトムホランド。なんだか田舎のダサい子って感じでフレンドリーに接してくるけれどデイジーは一切打ち解けようとしない。家に着くと妹のパイパーハーリーバードがデイジーの到着を楽しみにしていてまとわりついてくるが、それもデイジーにとってはうっとうしいだけ。唯一長男のエディージョージマッケイがカッコ良くて少しドキッとした。
3人の母親アンナチャンセラーは仕事に忙しく家は散らかり放題だが、子どもたちにとってはパラダイスのようで隣の家の男の子もいつも遊びに来ていた。一緒に釣りに行こうとか、泳ぎに行こうとかアイザックは一所懸命デイジーを誘うがデイジーは素っ気ない。しかし、エディーとの間に少しずつ恋心が芽生え頑なだったデイジーの心が開き始める。
いとこ同士でありながらエディーとデイジーは恋に落ち、2人を中心に子どもたちは楽しい時を過ごす。しかし、それもつかの間、ロンドンで核爆発が起き第三次世界大戦へと突入しようとしていた。3人の母親はスイスに出張中で、子どもたちだけで田舎でなんとか暮らしていたが、デイジーはアメリカ人ということで大使館から脱出のための航空券を渡される。しかし、デイジーはこれを無視しエディーたちと一緒にいる道を選ぶ。
彼らのいる田舎にも軍隊がやってきて女子と男子を引き離し、離ればなれにさせられてしまう。デイジーは別れるときにエディーが言った「何があってもここに戻って来よう」という言葉を胸に預けられた先で脱走の準備をし始める。
戦争が舞台となっていますが、これ完全に青春物語ですね。原作もハイティーンをターゲットにしたものなんでしょうね。このあとパイパーを連れて疎開先を脱走しエディーたちと住んでいた家に戻ろうとするデイジーとその周辺で起きている悲惨な状況の描写があり、最終的に甘ったれた反抗的な少女が自らの運命を強く受け入れて愛する者と行きていく決心をするまでが描かれる物語。
話しそのものは単純で確かに高校生向けという感じなのですが、子どもたちが自由に遊ぶ姿や惹かれ合うデイジーとエディーや、戦況がまったく分からないまま混乱に陥る人々など大人が見ても飽きることはありません。前半の牧歌的な部分と後半の悲惨な部分の対照がとても効果的でした。戦争や紛争、テロが起きて奪われるすべての物が前半に集約されています。突如訪れる戦禍の混沌が、現在の世界中の状況を見ていると他人事とは思えずぞっとする部分もありました。
それに何と言ってもシアーシャローナンが素晴らしい。登場人物はたくさんいるもののほとんどが彼女の独壇場と言っても過言ではないこの作品の中で、見事に1本の映画を背負って立っています。彼女はこれまでも複雑な役を演じているし演技の面ではすでにお墨付きだと思うのですが、いままでのイメージが清楚な感じだったので、このアイラインをぐるぐる入れた反抗期のアメリカンガールというのは意外なキャスティングでした。でもそれを何の違和感もなく演じてしまうところがやはりこんなに若くして演技派と言われる彼女だけあると思います。
原題は「How I Live Now」で、「今の私の生き方」「私はこう生きている」って感じなので、どうしてわざわざ「生きていける」という訳にしたのかは少し疑問です。題名だけではなくデイジーの最後のセリフにもなっているので「生きていける」にしたのは少し違和感がありました。
若い子の感性で見ればもっとビビットに感じるものがあるのではないかなぁと思います。
三谷幸喜の脚本の舞台作品だということは知っていて、すごく見たかったのですが、舞台で見られる機会がなくて悔しい思いをしていたら、ケーブルテレビで放映があるというので見てみました。ケーブルテレビの放映を知るまで、この作品が映画化されているということを知りませんでした。
昭和15年戦時下の日本。演劇はお上の検閲を通らないと上演できなかった。劇団「笑の大学」の座付作家・椿一稲垣吾郎は検閲官・向坂睦夫役所広司の面談を受けていた。
基本的には、椿と向坂の二人しか登場しない密室劇で映画化されるにあたって、少し別のシーンも加えられているが、おそらく舞台では完全に面談室で二人だけのお芝居なのだろう。
まず、椿が持参した脚本は「ジュリオとロミエット」。言わずと知れた「ロミオとジュリエット」のパロディものの喜劇だ。しかし、向坂に敵国イギリスの作品を使うとは何事だと舞台を日本に変更するよう命じられる。そこで、翌日椿はロミオとジュリエットを寛一お宮にした脚本を持ってくる。舞台がイタリアから日本に移ったことから、予期せぬ笑いが生まれ脚本は逆に良くなる。その後も向坂からどこかしら指摘を受けるたびに、書き直すという作業が数日続き、そのたびに脚本が面白くなっていくという皮肉な結果が生まれてくる。
向坂は今まで生きてきて心の底から笑ったことなどないという堅物。逆に椿は何を書かせてもついつい笑いの方向へ走ってしまうという根っからの喜劇作家。この二人が噛みあうはずがない。最初はそのズレが笑いにつながっていくのだが、途中からだんだん向坂に変化が現れる。何を読んでも何を見ても笑わなかったはずの向坂が、なぜか脚本の直しに必死になるようになる。椿のペースに乗せられて一緒にセリフを言って体を動かして、新しいアイデアまで出し始める。最初は完全に上演中止に追いやるつもりだった向坂が妙にイキイキし始める中盤からがまた面白い。
三谷幸喜独特の脚本だから、好き嫌いは別れるところだと思うし、四六時中笑っているというより、時々くすっと笑いが来るっていう感じなんだけど、登場人物がほぼ二人だけという心地よい緊張感もあってあっという間に時が流れる。
これを見ていると、あ~三谷幸喜って本当に喜劇が好きで好きでたまらないんだなぁって思う。ある意味では、この作品の中には彼の喜劇作家としての極意が詰まっていると考えてもいいのかもしれない。
もちろん、戦時中のお話ということは分かって見ているのだし、戦時中だからこそ成り立つ設定なんだけど、最後にあんなサプライズが待っているとは思いもしなかった。なんか気を抜いていたというか。。。あ、そうか、そういう展開ももちろんありえるんだ、ってちょっと抜け殻のようになってしまった。そして、不覚にも本気で泣かされてしまったよ。なんかねー、別に三谷幸喜の脚本すべてが好きなわけじゃないし、妙に鼻につくところもあるにはあるんだけどさ、それでもその作品を見ると喜劇だけど泣けるっていうねー、こういう人情喜劇を書ける人っていうのは本当に貴重だなぁと思いました。
ワタクシはペドロアルモドバル監督が好きだ。彼の作品のすべてが好きとは言わない。なんだこれ?最悪!みたいに思った作品もある。でも、それでもやっぱりアルモドバルは嫌いになれない。
この作品、原作があるらしいのだけど、描かれる世界はとってもアルモドバル的。彼はいつも「君はこれを“愛”と呼ぶか?」というテーマをぶつけてくる。いやいやいやいや、これを“愛”だなんて言えないよ。っていつも思うんだけど、それでもそんな形の“愛”もあるのかもしれないと思ってしまう、、、というか錯覚しそうになるとでも言っておいたほうがいいでしょうかねぇ。
数年前、ロベルレガル医師アントニオバンデラスの妻は不倫相手ロベルトアラモと駆け落ちする途中交通事故で全身やけどを負い、命は助かったものの自らの醜い姿に絶望して自殺。そのせいで娘ノルマブランカスアレスは精神のバランスを崩して入院してしまう。
退院することができたノルマだったが、友人の結婚式に参加した際、パーティを抜け出した男にレイプされまた精神を病み、やがてノルマも自殺してしまう。犯人を突き止めたロベルはそ男ビセンテジャンコルネットを拉致・監禁する。
物語は時系列通りには進まず、まず始めにロベル医師と監禁されている美しい女性患者ベラエレナアナヤの生活が描かれる。ベラはなぜか全身タイツをまとっており、医師の家で鍵のかかった部屋で生活をさせられている。ベラには自由がなく、メイドのマリリアマリアパレデスに買い物なども頼んでいるようだ。ベラが自殺をはかり、それから過去に戻って物語が始まる。
ロベルの過去と現在がどのようにつながるのか全く話が見えない中で進んでいくのだけど、まぁなんとなく途中からは分かるけど、それにしてもまぁ、、、すごいね。完全にネタバレしてしまうけど、娘をレイプした男を拉致して性転換しちゃうんだからなぁ。そこまではまぁもしかしたら究極の罰という意味では考えられないことではないかもしれないけど、女にしてしまっただけではなくて、顔から肌からすべて変えてしまって亡き妻にソックリにしてしまい、しかもその元レイプ男を愛してしまうっていうんだから、もう倒錯しまくり。
これで女にされてしまったビセンテもロベルを愛してしまい…っていうさらなる倒錯の世界に進むのかと思いきや、案外その辺は普通でビセンテが復讐を遂げて自分の家に帰ってくるところで終わる。この自分の家ってのがお母さんが経営しているブティックで、そこにビセンテがかつて好きだった女店員がいるんだけど、その店員さんはどうやらレズビアンでビセンテの想いは叶わなかったという過去があるので、女になって帰ってきたビセンテにはその人と結ばれる可能性がでてきたというのは深読みしすぎ?ビセンテの心は男性のままだろうからどうだか分かんないけど。
それにしても、ビセンテはノルマをレイプしたといっても、あんなのほとんど合意の上って感じだったし、ノルマが精神病だなんて知らなかったんだし、ほんとうに災難としか言いようがないね。
ベラを演じたエレナアナヤが非常に美しく、アルモドバル好みの女優さんという雰囲気だ。アルモドバルはゲイだけど美しい女性が好きですね。一種の憧れなのかな。崇拝対象というか。
相当エログロなんで、ワタクシは嫌いじゃない内容でしたが、アルモドバルファンじゃない方にはあえてオススメはしません。
「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」
カズオイシグロの作品は「日の名残り」しか知りませんが、映画を見て好きになり、原作も読みました。「日の名残り」の文学的なイメージを持っていたので、今回の作品も同じような雰囲気のものかなぁと思っていました。ワタクシは楽しみにしている作品ほど事前情報を入れないようにするので、この作品についてはポスターを見てキャストを知っていたくらいであとはただなんとなく想像していただけでした。
なので、冒頭からもうかなりビックリ。「1960年不治の病の治療法が分かり…1963年平均寿命は100歳を超えた」という文章。頭の中が「?」でいっぱいになりました。「なんのこっちゃ???」次に映ったのがキャシーキャリーマリガンの姿。「私が介護する人は臓器提供を前にしても落ち着いていた」と言って映るのがベッドに寝かされていまから手術をされる様子のトミーアンドリューガーフィールド。「はい???」
これってSF映画だったのかーーーっ!!!
場面は変わってキャシーとトミーがまだ子供だったころに戻る。ヘイルシャムという寄宿舎。ここでは“特別な”子供たちが集められていた。いじめられていたトミーを元気づけたキャシー。そんな二人に嫉妬してトミーに近づいたキャシーの親友のルースキーラナイトレー。ここの子供たちは寄宿舎から出ることは許されず、外の世界には怖いものが潜んでいると教えられている。時々やってくるおもちゃなどの物資は壊れかけたものや古いものばかり。何かがおかしい。それが最初のシーンへの答えとつながっていく。
彼らが臓器提供のためだけに“製造”されたクローンであるということは物語のかなり最初に分かってしまうことなので、これは特にその事実を“衝撃”として売りにしているものではないのでしょう。彼らは自分がいつか臓器提供のための手術によって死んでしまう(彼らの言葉では“終了”してしまう)ということを知っていて、その運命を受け入れ粛々と生活している。管理された生活の中で特に反乱を起こす者もいない。臓器提供をするクローンたちの世話係として「介護士」になれば、自分の臓器提供が数年遅らせられることや、本当に愛し合っている男女には数年の猶予が与えられるという噂に小さな小さな望みをつなぐだけだ。
クローンによる臓器提供と言えば、「アイランド」という映画があって、あの作品ではクローンたちが反乱を起こしていた。もしかしたら、そのほうが自然な感情として受け入れられやすいかもしれない。だが、小さいころから親もなくすがる大人もなく共に育ってきた子供たちは世間を知らず、まるでそれが“当たり前”かのように育っていく。特に厳しく洗脳する必要などなく、彼らは静かに運命を受け入れている。これはある意味“厳しい洗脳”ではないが“日頃の教育”の賜物で、そのほうが実はとても怖かったりする。途中でルーシー先生サリーホーキンスが、この政策に反対だったのか、彼らにその事実を告げるシーンがあるが、それでも子供たちは動揺しない。まるで先生がどうして動揺しているのかまったく分からないかのように。こういったゾッとするような状況がよくある近未来の無機質な世界で展開するのではなく、イギリスの片田舎の森に囲まれた温かい雰囲気の中で起こるものだから、余計に寒々しい感じがする。
彼らが簡単に反乱を起こさないのはやはり彼らのアイデンティティの欠如というものから来ていると考えればいいのだろうか。親もなくなんのルーツもないところから来た彼らには、帰るところも行きたいところもなく反乱を起こす確固たる理由が見つけられないでいるのかもしれない。もちろん、彼らにも「生」への渇望はあり、だからこそウソか本当か分からない噂にすがったりするのだけど、それにしても彼らが望んでいるのは“猶予”であり、臓器提供の拒否ではない。そして、なんのルーツもない自分たちだからこそ、自分の“オリジナル”の人間を探すことに必死にもなるのだろう。彼らにとってそれはただひとつすがって生きられるものだったのかもしれない。
そんな状況の中、キャシー、トミー、ルースの三角関係も描かれるのだけど、彼らの運命を知っているだけにすべてがあまりにも儚く切ない。クローンたちもワタクシたちと同じように恋に悩み、友情や嫉妬に悩んでいる中、彼らを製造した人間たちは「そもそもクローンに魂なんてあるのか?」と思っているという残酷さ。彼らに感情移入しながら見ていたワタクシは涙が止まらなかった。
最初にこの設定に違和感を覚えて入り込めなかった人にとっては、退屈な作品になってしまうかもしれないけど、ワタクシは全体的な雰囲気も話の展開も結構好きで、こういうSF的な要素と文芸的な要素を絡ませてひとつの作品に仕上げられるカズオイシグロってやっぱりすごいなぁと思いました。
「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」
ワタクシももちろん知ってはいたが、どんな内容の作品なのか詳しくは知らず、いままで見ないできたのだけど、少し前にケーブルテレビでやっていたのを録画していたので、今回初めて見てみた。
物語は何か唐突な印象でスタートする。どこかの田舎町。主人公たちの会話でここがイギリスだということが分かる。妻スーザンジョージの出身地に引っ越しをしてきた若い夫婦。妻の昔の恋人チャーリーなどとも再会する。
町の雰囲気はなぜかこの夫(ホフマン)のほうを受け入れてはいない様子。彼がアメリカ人だからか、それとも学者だからか、それとも彼らのスーザンと結婚したからか、この田舎町の荒くれ者の男たちはとにかく彼のことが気に入らないようだ。
始まりの瞬間から状況がよく把握できないのだけど、それでも全体に流れる不穏な空気というものを感じ取ることはできる。何か一触即発的な雰囲気が流れていて、とても居心地が悪い。
途中まではこの夫婦に何か危険なことが迫るのかと思って見ているのだけど、どうやらこの夫婦もうまくいかなくなってきている。夫が研究に没頭しすぎるところや、妻が子供っぽすぎるところですれ違いが生じていたが、飼っていた猫が何者かによって殺されたところから加速度的に夫婦仲がおかしくなってくる。
このスーザンジョージ演じる妻が一体何を考えているのかよく分からない。よくいる尻が軽いというかこう、男を翻弄するのが好きなタイプの女の人なのかな。結局そのせいで自分が危ない目に遭うのだけど、それも途中から彼女も望んでいる風になって、よく分からない。あれって単に男が勝手に「本当はお前も喜んでいるんだろう?」と思い込んでいるやつの具現化なのか、実際に彼女がそんな女だったのか?彼女をレイプした元恋人チャーリーのことは夫と違ってたくましくて頼りがいがあると思っていたみたいだから後者のほうだったのかもしれないけど、その後銃で脅されてたとは言え、その友達にもレイプされるシーンではチャーリーに押さえつけられていたわけだから、チャーリーの本性も分かっちゃったってとこだったのかな。あーいうタイプの女性は痛い目を見ないと分からないのかも。
でも物語はそのレイプシーンからちょっと違う方向へ進んで、町の知的障害者の男が少女に誘惑され、あやまって少女を殺してしまい逃げる途中に、彼を車で轢いてしまったこのダスティンホフマン夫妻が彼の手当をしようと自宅連れ帰ったところ、チャーリーを含むその少女の家族がその男をリンチしようと夫妻の家にやってくるという突然の進展を見せる。
ここで、チャーリー他町の男たちの暴力におびえた妻は知的障害者の男を引き渡すことを主張するが、夫は頑としてみとめない。いままで妻に、争いごとを好まず、逃げてばかりのつまらない男と言われていた夫はここへきて、いきなり何かがプチンと切れてしまったかのように、町の男たちの暴力に暴力で対抗する。
ここでの彼のキレ具合が、恐ろしくも面白い。気弱な男のキレっぷりにゾクゾクする。「アメリカには暴力が蔓延しているんだって?」なんて言っていたイギリスの田舎町の男たちのほうがよっぽど暴力的だった。これがここで逆転するという皮肉なときがくる。
妻は知的障害者などリンチに遭って死んでも構わないと主張する。もうこの時点で夫は妻に愛想を尽かしていただろう。それが最後に決定的になるシーンがある。侵入してきた男の一人に妻がまたレイプされそうになる。妻が思わず助けを呼んだのは「チャーリー!」だった。あの喧噪の中でさえ、夫は確実に聞いただろう。自分以外の男に助けを求める妻の声。夫はその瞬間おそらくすべてを悟っただろう。
いままでのシーンはこの瞬間のために、ネチネチと積み上げられてきたのだ。町の人たちの雰囲気、ネズミ駆除の男の不気味な笑い声、暴走する保守、大音響で鳴り響くフォークロア音楽、レコード針の擦れる音。ネチネチネチネチ。これがサムペキンパーの才能なのか。
暴力を肯定するとこは非常に危険なことであるということは、もちろん分かっているが、この作品を見た後には、脱力感とともに奇妙なカタルシスがあることも否定できない。
ジョーイはそのことがマフィアの連中にバレたら大変なことになると、夜の街をオレグを探して右往左往。イタリアマフィア、ロシアマフィア、汚職警官、ポン引きが絡んで大変な事態になってしまう。
まず、ポールウォーカーがマフィアの下っ端っていうのが、なんかミスキャストだなぁと思っていたんですよねー。それに彼の風貌にしては子供がなんだか大きくて奥さんテレサヴェラファーミガの連れ子?とかややこしいことを考えてしまったんですが、普通に3人家族だったようです。後で調べたらポールウォーカーとヴェラファーミガって同い年なんですね。なんか、ヴェラファーミガのほうが年上に見えたので、勝手に想像してしまいました。
んで、ポールウォーカーがミスキャストな話ですが、これは最後まで見て納得。そうだよねー。彼がただのチンピラなんてありえない。でも、妻にまで内緒ってあるんかな?知り合ってからずっと?彼女はチンピラと結婚したと思ったらなんと!ってめっちゃビックリしない?ってかビックリだけで済まんか。それで良かったーって思うのが普通かもしれないけど、筋金入りのチンピラ家族出の女の人だったら、逆にがっかりしたりして?
オレグが逃げ回る途中で、変な夫婦に拉致されて、その変態夫婦が子供をさらってワイセツビデオ撮ったりして、あげくに殺してるっていう奴らだったんだけど、そこへ迎えに行ったテレサが怒りのあまりその夫婦を撃ち殺してしまうってシークエンスが、映画の流れとはまったく関係ないやーん!このシチュエーションいらんくないか?と思ったんだけど、実はこの作品中一番スッキリしたシーンだったりして、なんか好き。さすが、チンピラと結婚するだけのことはあるよ、テレサ。
今回キャメロンブライトくんは全然しゃべらない役なんですが、何かを訴えかける大きな瞳で守ってあげたくなる雰囲気を醸し出していますね。子役が大人の俳優として成功するのは難しいけど、彼ならこれからも良い役者になってくれるのではないかと期待しています。
チャンズパルミンテリ、久しぶりに見たなーと思っていたら悪徳汚職警官だった。あのイヤらしい感じにピッタリなんですが、彼はあったかい人柄を演じるとそれもそれでハマるし、やっぱり演技力の賜物なのですね。
なんか途中途中がまどろっこしいところもありながら、オレグと消えた拳銃の行方を追って、先の見えない展開が面白い作品でした。ポールウォーカーとヴェラファーミガが好きなのでちょっとひいき目もありということで。
白血病の姉ケイトソフィアヴァシリーヴァのドナーとなるべく、遺伝子操作によって誕生した11歳のアナ(アビゲイル)は、もうこれ以上姉のために自分の体を犠牲のするのはイヤだと、両親を訴えることにする。
この作品の説明はだいたい上に書いた感じのことがどこを見ても書いてあると思う。この説明文を読んでワタクシは、とってもアメリカ的な裁判ものなのかと思っていたのだけど、実際にはそういうところにスポットがあてられているのではなく、きちんと病気の娘のいる家族というものに焦点があてられていてホッとした。
ケイトを助けたいあまり、ケイトを最優先事項にすることが家族全員の当然の義務であると考え、アナに訴えられたあとも本気でアナと戦おうとする母親サラ(キャメロン)
サラの気持ちも理解しつつも、アナの訴えをきちんと受け止め話し合おうとする父親ブライアンジェイソンパトリック。
自分の病気が自分を蝕んでいくことには耐えられても、家族を蝕んでいくことに耐えられないケイト。
姉のケイトが病気になったことで失読症の自分のことは常に二の次にされてきた弟ジェシーエヴァンエリングソン。
もうこれ以上ケイトのために犠牲になるのはイヤだと両親を訴えるアナ。
この作品のいいところはこの家族5人全員にきちっとスポットがあてられているところだと感じました。ケイトの病気ことが中心になっているのはもちろんですが、それをそれぞれがどのように受け止めているのか、それぞれの心の中はどうなっているのかということをきちんと描いているところが素晴らしいと思います。こういうタイプの映画ではおろそかになりがちな、弟ジェシーの立場の役どころもきちんと描かれていて、ワタクシはそこが好きでした。ケイトと同じ病気のテイラートーマスデッカーとの恋愛もひとつのエピソードとしてだけではなく、微妙な心のひだまできちんと描かれていたし。
そして、この5人に加えて、アナが弁護を依頼するキャンベルアレグザンダー弁護士アレックボールドウィン、この裁判の担当判事ジョーンキューザック。この二人が脇でしっかり映画を締めてくれる。この二人がすごくイイ人なんですよねー。それがまた泣ける。この二人それぞれのシチュエーションがうまく物語にもフィットしていて良いです。
ワタクシはもう中盤からずっと号泣状態でした。まーそりゃーお涙頂戴ですよ。そんなこと分かってます。それでもね。だって子供が病気なんだもん。最後まで戦いたいお母さんの勝手ぶりも仕方ない。ないがしろにされる他の兄弟たちのやるせなさも辛い。家族を心配するケイトが痛々しい。そして、この兄弟3人の仲の良さにも泣けるんですよ。ちゃんとそれぞれがそれぞれを想い合ってる。ケイトがそれぞれに申し訳ないと思っている気持ち、自分の病気への苛立ち、悲しみ。やっぱり涙なしでは見られない。あのケイト手作りの本はもう反則ってくらい泣けた。最後はお母さんのほうがケイトに諭されてたりなんかして。子供のためにすべてを投げ打つことができる母親は強いけど、その分その存在がなくなることに対しては当の本人より弱い存在になってしまうっていう部分にも、すごくストレートに感動しました。
結局アナの行動には秘密があって、それが徐々に明らかにされていくんだけど、そこんとこもまぁだいたい想像はつくんですが、それでもやっぱり感動しちゃいました。時間軸をいじってあって、映画的にもうまい作りになっていると思います。
キャメロンは、いつも太陽のように笑っていて欲しい人ではあるけれど、こういう役もちゃんとこなせます。いままでだって、ヘンテコな役や真面目な役もやってきるしね。アビゲイルちゃんは子役の中では群を抜くうまさではないでしょうか。ケイト役のソフィアヴァシリーヴァは実際にスキンヘッドにするという気合の入れよう。ジェシー役のエヴァンエリングソンもテイラー役のトーマスデッカーも二人とも可愛い格好良くてこれから要注目。もしかして、何年かして振り返ると、ものすごい面子の家族ってことになるのかも。
やはり、1959年の製作というだけあって、カメラワークとかセットとかそういったものは現代の映像を見慣れているワタクシたちにしてみれば、かなりちゃちい感じがしてしまうのですが、その辺は昔のことだから仕方ないので、あまり考えないで見ることにしました。
フランキー堺演じる主人公清水豊松は土佐の高知で妻新珠三千代と理髪店を営んでいる。戦時中ではあったが、土佐の片田舎ではなんとなくのんびりした空気が漂っていた。豊松が戦争時のスローガン「欲しがりません、勝つまでは」を息子に言ってきかせるときに「欲しがるまでは勝ちません」と間違えて言ってしまうシーンがあるが、このシーン一つとっても豊松の気持ちの中でそこまで切羽詰まっていたものがあったとは思えない。
だが、そんな豊松に対してもとうとう赤紙が来てしまう。
ここから前線での様子が語られるのかと思いきや、前線の様子を描いている時間は非常に短い。ただ、そこで、豊松が兵士としてはかなりドンくさく、上官にはにらまれていて、捕虜を無理やり処刑させられたということは端的ではあるが、きちんと描かれている。
戦後、戦争が終わって良かったなぁ、なぁんてのんきにお客さんと話している豊松のところにGHQがやって来て、戦犯として逮捕されてしまう。戦場で上官の命令に従って捕虜を処刑した罪であった。
裁判では、豊松が何を言ってもアメリカさんにはいまいち通じない。「上官の命令は絶対であるし、上官の命令は天皇陛下の命令である」といくら主張しても、日本軍の体質そのものを理解しない検事や判事には通じない。豊松は絞首刑を宣言されてしまう。
戦犯が入る巣鴨プリズンで、かつての上官が豊松に謝罪に来て、自分ひとりが責任を取ればいいことだと言ったことにより、豊松はこの上官と親しくなるが彼は処刑されてしまう。その後、処刑される人数は減っていき、日本とアメリカが講和条約を結べば戦犯も釈放となるだろうと楽観的なムードが漂っていたところへ豊松の突然の刑の執行の日が来てしまう。
この時代のことだ。高知と巣鴨はあまりにも遠い。一人で店を切り盛りしている奥さんはそう何度も面会に来られるわけではない。その数えるほどの面会の中でも、豊松は命令を聞いただけの二等兵の自分が処刑などされるわけはないと思っているから、そこまで重苦しいやりとりもない。妻と息子に会えない寂しさはあるが、いまがんばって店を守っておいてくれれば、自分もすぐに戻るからと思っているのだ。
そこへ突然の死刑執行。どうして急に刑を執行することになったのか、豊松には知らせられない。と同時に観客にも知らせられないから、「えっ?なんで?」となるところだが、それは豊松が感じた気持ちそのままなのだから、あえて観客にも説明がなくてもおかしくはないと思う。そこで豊松は有名な「もし生まれ変わるなら私は貝になりたい」という遺書を書く。貝ならば、戦争もない、兵隊もいない、家族のことを心配することもない。突然に明日処刑になる豊松は最後に家族に会うことすらできなかった。この“家族のことを心配する必要もない”というフレーズで豊松が冷たい人だと感じる人もいるだろうが、ワタクシは逆に豊松が家族のことをもの凄く心配しているからこそ出たセリフだと思う。自分は命令されるがままに戦争へ行き、そこで人を殺し、処刑される。なんと無念なことだっただろう。それを思うと涙が止まらなかった。ライバル店ができても女手ひとつで店を切り盛りしている妻、お父さんが帰って来るまではおこずかいをせびるのをガマンしている息子。そんな二人が豊松が帰って来ることを信じて暮らしている処刑当日の姿がまた涙を誘う。劇中何度も流れる「よさこい」のメロディーが悲しく響き渡る。
実際に、二等兵が戦犯として死刑に処された例はないという事実から、この映画を嘘っぱちだと言う人もいるだろう。それはそうなのかもしれない。しかし、二等兵でのちに減刑されたとはいえ、実際に死刑を宣告された人はいたわけだ。彼らの気持ちはいかばかりだったことだろうか。
東京裁判を否定することによって、日本の侵略戦争を正当化しようという気持ちは、さらさらない。ただやはり加害者側の国にも一番苦しい目に遭うのはいつも庶民だということだけは事実だと思う。
ドイツでは誰もが知っている英雄シュタウフェンベルク大佐トムクルーズのヒトラー暗殺計画「ワルキューレ作戦」の映画化。
うん、そうですね。これ、ちょっと映画としてはどうかな。ヒトラーが暗殺されたんじゃないってことは誰もが知っていることだしな。ということはこの作戦が失敗に終わるって分かってて見ないといけないわけだ。たとえそうでも観客を惹きつける作品を作ることはできるだろう。でも、この作品はそこまで惹きつけられるものではなかったな。悪くはないけど、もう一声ってとこですかね。
なんで、トムクルーズが?ハリウッドが?英語で?みたいなことはこの際置いときます。世界市場を考えれば、そういうことも普通に行われるのだということでしょうし。トムクルーズがシュタウフェンベルク大佐を演じることに関してはドイツでは意見が分かれ、遺族は反対していたということだけど、ならばなぜドイツ人がドイツ語で彼を題材に映画を作らない?と思ったらドイツでテレビ映画が2004年に作られているのね。ドイツがこれを大々的に世界市場の映画として作らないのは、ヒトラーを否定はしていてもドイツ軍の将校をドイツ自身が肯定的に描くことに、批難が出ることを恐れているからなのかな?あ、これは単なるワタクシの憶測です。
映画としては、生真面目に作られている感じはするし、好感は持てるのだけど、もう少し将校同士の人間関係とか、仲間を見つけるまでのスリリングさとかを描いてほしかったなと思います。あんなふうに反ヒトラーの仲間がたくさんいたのは事実なんだろうけど、誰が反ヒトラーで誰が親ヒトラーなのか、あの体制の中で反ヒトラーの仲間を見つけるのはそう簡単ではなかったろうし、下手すれば話を持ちかけた相手に密告とかされちゃってそのまま死刑とかになりかねないのに、結構簡単に仲間がゾロゾロと集まってくるところがなんだか簡単に見え過ぎたような気がする。この作戦が失敗することは分かっているんだから、そういうところに重点を置いても良かったような。
会議中に爆弾をしかけ、爆発はさせたものの爆弾も1個しか仕掛けられなかったし、爆破は密室ではなかったし、ヒトラーが死んだことを確認できたわけでもないのに、シュタウフェンベルク大佐がムキになって作戦を推し進めようとしたところが、それまでの焦燥感などが描ききれていなかったがために、「えっ?なんでそんな無理すんのさ」って感じに思えて、意地だけで進めるには犠牲になる命が多すぎやしないか?と思ってしまった。実際にはどうだったかは知らないけど、映画を見るとそう感じてしまう。もちろん、これは結果論でそのときはイチかバチかやってみるしかなかったのかもしれない。だからこそ、そのあたりをうまく描き出して欲しかった。
ヒトラーが死んだかどうか報告する役目だった人がどうしてあんな中途半端な報告をしてしまったのかっていうのがどうにもよく分からなかったし、通信部と予備隊を味方につけられなかったのは失敗だったけど、時間が足りなかったことを考えると仕方なかったのか。ここでも反ヒトラー派と親ヒトラー派の攻防みたいなものをもう少し描いて欲しかった。
この作品を2時間ちょうどに収めたことはかなり評価できますね。最近は長い映画が多いからね。それにトムクルーズの大作ですから、脇役もいい人が集まってるし。ビルナイの演技も良かったし、ケネスブラナーがこの作戦が失敗したことを知って自決するシーンはこの映画で唯一うるっときたシーンでした。
ドイツでは超有名なシュタウフェンベルク大佐ですが、国外では知らない人が多いだろうし、それを誰も見ないようなドイツ映画(失礼!ワタクシなら見ますが一般的にという意味です)で作るよりハリウッドがビッグバジェットで作ったほうが世界的にナチスに対抗したドイツ人兵士がたくさんいたということを知れるいい機会になると思うので、それに関してはいい評価をしてもいいんじゃないでしょうか。
このブログを読んでくれている方の中には、ワタクシがマドンナのファンであることをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。マドンナはいままで、女優として映画作りに参加してきて、本人も映画はとてもむずかしいと話していますし、実際映画界では大きな成功をおさめたとは言いがたいかもしれません。彼女はそれでも、映画はむずかしい、だからこそ、いいものを作りたいといままで映画の世界に関わってきていました。そんな彼女が今回は女優ではなく、監督として映画に関わることにしたようです。マドンナが映画を監督するとなれば、まぁファンとしては見に行かないわけにはいかないでしょう。ただ、ワタクシの中でマドンナのファンのワタクシと映画オタクのワタクシがちょっと戦っていました。マドンナファンのワタクシとしては、見に行くべし!と、映画オタクのワタクシとしては、スーパースターがメガホンを握った映画…期待薄だな。が交錯していました。
果たして結果はどうだったでしょう?
うん。まぁ悪くないな。というのが見終わった感想でした。あの大物アーティスト、マドンナが監督をしているというのが、邪魔してしまうのですが、彼女も映画監督というカテゴリーではまったくの新人。そういう新人が撮ったと思えば、悪くない作品ではないでしょうか。彼女は50歳ですが、もっと若い映画学校の生徒に毛が生えた程度の年齢の子が撮ったような感覚とでも言いましょうか。この映画はまさに、マドンナが成功を収める前の自分自身を撮ったようなものですから、ある意味、その印象は正しいのかもしれませんね。
主役のAKを演じるユージンハッツは、有名な人らしいですが、ワタクシはぜんぜん知りませんでした。彼の風貌はちょっと苦手ですが、歌っているときは最高にカッコよかったですね。そして、AKの友人である、バレリーナを夢見るホリーホリーウエストンとアフリカの子供たちを助けることを夢見るジュリエットヴィッキーマクルアもそれぞれ3人ともが若いころのマドンナを表現しているようで、ストーリーは単純ですが、役者陣がそれぞれいい感じだったと思います。それに、みんな悪いこともするけど、基本的にいい子っていうのが、マドンナらしいなって思いました。マドンナってすごく若い人の可能性を信じてるところがあるからね。
キャストの中ではメインの3人ではありませんが、ホリーのストリップ劇場での面倒見役の先輩フランシーヌを演じたフランチェスカキングドンが超超カッコよかった!
AKがSMの仕事をしていたり、AKの客であるMのだんなエリオットレヴィを喜ばせようと奥さんが奮起したり、ホリーがストリップ劇場でブリトニースピアースの「Baby One More Time...」に合わせて制服で踊ったりっていうのが、マドンナらしい演出というか、ファンが楽しめるようにおまけ的につけているようで、ファン以外が見るとよく分かんないかもなってとこもありました。自分の曲は2曲しか使わなかったけど、ワタクシは使わないほうが良かったかなとも思います。ファンとしては嬉しいんだけど、やっぱり「マドンナが監督してるんだ」っていうことをいちいち思い出してしまうから。
マドンナのファンじゃなかったら、こんな映画そもそも見ないかもしれないですね。うん。まぁ確かにファンじゃなかったら別に見なくてもいいかも。でも、これが第一作ですから、まだまだ映画監督としては未熟ですが、これから良くなる可能性は秘めているんじゃないでしょうか?ファンだからやっぱり採点は甘いかな?
ラッセルクロウはアメリカ本土にいて、家族と朝食を食べ、子供たちを学校に送っていくというごく普通の生活をしている。しかし、彼の耳から携帯のヘッドセットが取られることは片時もない。彼はCIA局員エドホフマン。つねに前線に潜伏しているスパイ、ロジャーフェリス(ディカプリオ)と国際電話で話しながら指令を送っている。
現地にいるロジャーはエドホフマンに指令を仰ぎながらも、現地のことは現地に実際にいる人間にしか分からないとばかりに、時には指令を無視してでも臨機応変にその場のトラブルを回避していく。
CIAの現在の目的は、ヨルダンに暗躍するテロ組織を壊滅すること。そのために現地の情報局の局長ハニマークストロングの協力を仰ぐが、CIAはハニを利用するときは利用して、あとは自分たちの作戦で問題を解決しようとする。
テロ組織、現地にいるCIA局員、アメリカから指令を出すCIA局員、ヨルダン情報局。すべてがウソで塗り固められ、なにが正しい情報かがまったく分からない世界。アメリカは最新鋭の機械を使ってテロ組織を追い詰めようとするが、電子機器を全く使用せず人から人へと伝えられていくテロ組織の伝達方法は最新のテクノロジーをかいくぐっていく。
CIAは無人偵察機で現地のCIA局員を見張って守ったり、テロ組織のアジトを上空からとらえたりしているが、あれは実際のところどうなんでしょうねぇ?本当にあそこまで性能の良い偵察機が使用されているのかなー?10cm四方のものまでとらえられるとか聞きますけどね、ならなぜビンラディンを捕まえられないの?とか思っちゃう。あ、それこそがこの映画の中で言われているテロ組織が最新テクノロジーをしのいじゃうってやつなのか。
映画としては、ラッセルクロウもディカプリオもマークストロングもすごくいい。配役がかなりピタッとハマってますね。ラッセルクロウが登場したころにはこんな役ができる役者になるなんてちっとも思わなかったけどね。「インサイダー」あたりからですかね、イイ味出し始めたのは。レオはいつもどおりもちろんカッコいいし、こういうアクション系も最近手を出し始めてそれが、ただのアクションスターにならないで、社会派な作品でのアクションなところがレオらしいですね。マークストロングは細いアンディガルシアって感じかな?彼よりもうちょっとインテリな気品が漂っていて、ヨルダン情報局の物腰は紳士的だけど、本当はこわ~い長官にピッタリだった。監督はさすがのリドリースコット、弟が撮らなくて良かったよって思っちゃいました。あ、トニーもいい監督だと思いますが、これを彼が撮っていたらもっと娯楽色が強くなって最近彼が凝ってる変な字幕とか出しちゃって残念な結果になっていたと思うから。
ま、要するに全体的にはなにやってんだ、アメリカ!な映画で不謹慎だけど、こんなことに必死になってるCIAがだんだん可笑しくなってきちゃったし、レオ演じる局員がテロ組織に捕えられて、「Welcome to Guantanamo.」と言われたときはちょっとプッと吹いてしまった。いや、これマジ不謹慎なんだろうな。ごめんなさい。もちろん戦争の犠牲者が可笑しいのではなくて、自由の大国アメリカが可笑しく思えてきてしまって。あんまり言い訳してもしょうがないな。リドリーの意図もそこんとこにあるんじゃないのかな?
ヒトラーヘルゲシュナイダーの演説の指導をすることになったユダヤ人俳優アドルフグリュンバウムウルリッヒミューエ。収容所から呼び戻され、ヒトラーの住む宮殿のような建物へ連れて行かれる。このグリュンバウムが垣間見るナチの幹部とヒトラーの心のうちなどをおもしろおかしく描いている。
ナチの統率はさすがドイツ人と思わせるようなカンペキなまでの「書類」と「手続き」の連続で、彼らが出会うと必ず一人一人が「ハイルヒトラー!」と叫んで手を上にあげ、挨拶は時間のかかることこの上ない。そういうところは皮肉っぽくて笑えはしたんですけどね。でもやっぱり、強制収容所に入れられているユダヤ人がヒトラーが子どもの頃虐待されていたとかを知ったからって「この人はただ愛情に飢えているだけなんだ」なんていうセリフを言えちゃうっていうことに抵抗を感じてしまった。ヒトラーに犬の真似をさせたり、「お父さんごめんなさい」って泣かせたり、ユダヤ人夫婦に甘えて二人の間で寝ちゃったりって、思いっきりバカにして笑っちゃおうって感じなのかなー?その辺の意図はよく分からないけど、ワタクシは気持ち悪いだけで笑えなかった。後半は、そんな感じで子供じみたヒトラーとそれに同情し、温かく見守っている感さえあるグリュンバウムという構図がなんとも違和感があって、どうこの話は終わるんだ?って思っていると、ラストは特に衝撃的でもなかったんだよねー。どうせウソの歴史で喜劇ならいっそのこと、あそこでグリュンバウムがチャップリンばりの演説をぶってヨーロッパを救っちゃったほうが良かったなぁなんて思ったりなんかして。ってワケにはいかないか。
史実に忠実にすべきだとかそういうお堅いことを言うつもりはまったくないんだけど、この面白さは残念ながらワタクシには合いませんでした。「ライフイズビューティフル」を見たときの違和感とちょっと似ていたかなぁ。あの作品については、ワタクシは最初好きじゃなかったけど、「あんな場面でも子供のためにユーモアを持ち続ける精神力のすごさ」というものを後から感じて、後になってワタクシの中で受け入れた作品なんだけど、この作品をそんなふうに受け入れる日は来ない気がするなぁ。
「善き人のためのソナタ」でも素晴らしい演技をしていたウルリッヒミューエの演技は今回も素晴らしく、彼の映画を見るのはこれが2本目だったのに、もう故人であることを知ってものすごく残念だ。
今回のスカーレットはいわゆる普通の役。特にお色気ムンムンでもないし、年齢不詳でもありません。頭はいいんだけど、専攻の人類学ではお金儲けはできず、女手ひとつで育ててくれた母ドナマーフィーが望む金融界に就職しようとはしたものの、なんか納得できずセントラルパークでぼーっとしているときにセグウェイの前に飛び出した子供グレイヤーを助け、その母親ミセスXローラリニーに「アニーよ」と自己紹介したところ、「ナニー?まー、ちょうど良かったわ。新しいナニーを探していたのよ」と面接を申し込まれる。現実世界ならここで「いやいや、私はアニーです」と普通に訂正すればいいんだけど、ここは映画の素敵な世界。アニーはきちんと訂正せずにナニーっていいかも
 って面接に出かけていく。
って面接に出かけていく。ミセスX(エックス)って変な名前なんだけど、それはアニーが人類学を専攻していたから、アフリカの原住民とかを観察するような感覚でニューヨークのアッパーイーストに住むお金持ちの実態を観察するっていう意味での観察対象としての「X」なんですね。冒頭のシーンでアニーが自然史博物館で世界のさまざまな地域にする人々のひとつの例としてニューヨークアッパーイーストの人たちを紹介していき、アニーに起こる現実のお話だけじゃなくて、映画的な演出があって楽しい。
さて、ニューヨークのアッパーイーストと言えばお金持ちがたくさん住んでいるところ。父親たちはお金儲けにせいを出し、母親たちはエステに美容整形、なんちゃらセミナーやら慈善事業に忙しい。ならば子育ては誰がするのか?答えはナニー!ってわけ。
アニーはミセスXのお宅に住み込みのナニーとして働き始めるのだけど、彼女のすることはグレイヤーの面倒を見るだけじゃなくてクリーニングを取りに行くだの買い物に行くだの料理を作れだのってそんなことまでやるのーーー???ってことばかり。これってお手伝いさんの領域よねぇ。それだけ給料もいいんかなぁ?
アニーが規則でガチガチのミセスXの目を盗んでグレイヤーを楽しい場所に連れて行ってあげたり、ジャンクフードを食べさせたり、契約上はしちゃいけないんだろうけど、庶民なら、子供なんだもんそれくらいいいじゃんって思うようなことをして徐々にグレイヤーの心をつかんでいく。それと並行して、仕事が忙しくて子供のことなんか全然見てないし、シカゴ支店の女の人と浮気しているミスターXポールジアマッティや、そんな夫と知りながら自分を見てもらおうと必死で子供の心の痛みには目を向けようとしないミセスXの姿が描かれる。この金持ち連中にはほとほと腹が立つんだけど、一生懸命にグレイヤーの面倒を見て、両親のケンカにも傷つけないようにしてあげたり、ミセスXの雑用もがんばってこなしていくアニーがとてもかわいい。
この映画の邦題になっている「クマにキレた」っていうのは実は子ども部屋にあるテディベアの目に設置されたナニー監視カメラにキレたって意味なんですね。原題は「THE NANNY DIARIES」だから、邦題のほうがずっとシャレっ気があるかもしれないですね。
アニーとグレイヤーの交流はもちろん胸にキュンとくるもので、こういう映画の王道ではあるけれどとてもかわいらしい。そして、ミセスXを演じるローラリニーがお金持ちでなんでも物はあるけれど、愛情に飢えてるという女性をとてもうまく演じている。彼女がミセスXの焦燥感みたいなものをうまく表現していたからこそ、最後にアニーの忠告(というかホンネ大爆発!)に心を動かされるところも出来過ぎ感ぎりぎりセーフって思えたんだと思う。
アニーが知り合う“ハーバードのイケメン”はクリスエヴァンスくんで、ワタクシは彼もとても好きなんだけど、今回の役はちょっとイケてなかったな。なんかこの二人の恋愛エピソードはちょっと邪魔だった気がする。
結局アニーはナニーとしてひと夏を過ごしたあと人類学を究めようと人類学専攻でハーバードに奨学金で入ることになるわけだけれども、アニーがナニーになる前に金融界に行こうとしていたように、その道で食えない学問と食える学問があるっちゅうのはなんとも悲しい現実ですね。前途洋々な若者にとってナニーはひと夏の経験で、もう一度大学に入りなおすなんて、なんともアメリカンなラストでありました。
全体的にもうひとパンチほしい作品ではありましたが、随所に笑いあり、ほろりとくるところあり「ブリジットジョーンズ」系の映画としては上出来ではないでしょうか。