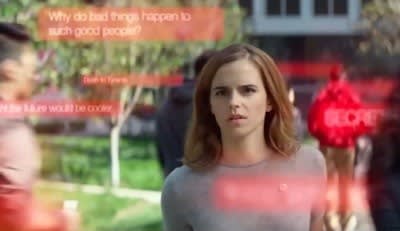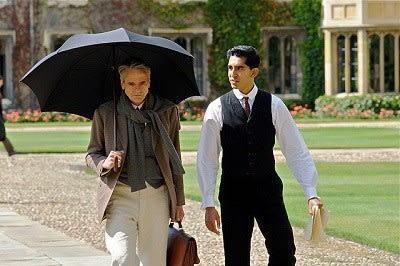何よりもまず最初に言っておきたいことがあります。いままでこのブログでは邦題のセンスが悪いとかミスリードなどを指摘しては来ましたが、今回ほど邦題に腹の立ったことはありません。原題は「Denial」(2016年の原作本の改編時に「History on Trial」から変更)です。原題は「否定」これはホロコースト否定論者の否定でもあるし、否定論者を否定するという意味も含まれているのではないかなと思うのですが、邦題は「否定と肯定」肯定って何?ホロコーストに否定も肯定もないよ?日本のメディアお得意の両論併記ってやつですか?これではまるでホロコーストに否定側と肯定側が存在するかのような書き方です。そんなものは存在しません。ただ事実を否定したい人たちがいるだけ。口に出すのもはばかられるような恥ずかしい邦題つけないで欲しい。
さて、映画の内容ですが。ワタクシはこの映画の存在を知った時に原作本をすぐ手に取って読みました。原作には事細かに裁判の様子やその前の資金集めや資料集めの様子が書かれていました。これが映画になると思うとワクワクして、主演が大好きなレイチェルワイズということもあり、映画を見るのを楽しみにしていたのですが、映画そのものはちょっと全体的に物足りなかった気がしました。
資金集めの部分はイギリスのユダヤ人コミュニティに示談を薦められた話と、スピルバーグが全額出そうとしたとリポーターが話したくらいで、その他の細かいところはカットされていました。アメリカのユダヤ人コミュニティにはスピルバーグ以外にも支援を申し出てくれた人がたくさんいましたし、その方たちとのやりとりもありました。
資料集めはおそらく一番大きなアウシュヴィッツへの訪問部分はきちんと描かれていました。あそこでエモーショナルになってしまうリプシュタット教授(ワイズ)と冷静に証拠を集めようとする弁護士ランプトントムウィルキンソンの姿が対照的に描かれていました。その他にも膨大な資料を集め読み込み、弁護の材料にしていった弁護士やパラリーガルの姿は時間的に入れることはできなかったのでしょう。
肝心の裁判部分ですが、原作を読んでいる者からすると、これ映画だけ見た人はなんで勝ったか分かったかな?と思ってしまいました。原作ではもっとたくさんのやりとりが描かれていたし、証人と否定論者であるデヴィッドアーヴィングティモシースポールとのやりとりも多くそこで少しずつアーヴィングが馬脚を現していく部分がスリリングだったのですが、ちょっと裁判部分にかける時間が短かったような気がします。
映画では裁判そのものよりも、リプシュタット教授と弁護士団の人と人との関係のほうがスポットライトが当たっていたような気がします。自分の良心を信じて突き進んできたリプシュタット教授が裁判では一言も発することを禁じられ他人に自分の運命をゆだねるはめになってしまう。そんな彼女が弁護士たちと信頼関係を築いていく姿をよく映し出していました。ダイアナ妃の離婚弁護士であり、周囲からは名声を求めていると思われがちだった弁護士アンソニージュリアスアンドリュースコットが実は信念の人であり、ホロコーストのサバイバーたちを証言台に立たせるというリプシュタット教授にそんなことをしたら、どんな酷い質問がアーヴィングから飛ぶか分からないとそれを拒否し続けていた姿が素敵でした。
裁判の判決が出てもまだ「内容的には自分は勝った」などとほざいていたアーヴィングのような歴史修正主義者がいまこの日本にもウヨウヨいてイヤになる。
1974年のシドニールメット版はテレビで大昔に見た記憶があるのですが、内容は完全に忘れていました。超がつくほどの有名な小説なのに、その内容も全然知らず、ケネスブラナー監督・主演作品はわりと好きなものが多いというのと、ペネロペクルス、ジュディディンチ、ウィレムデフォーその他豪華キャスト目当てで行きました。
ミステリーなので、内容は書かずにおきますが、結論から言うとワタクシはとても楽しむことができました。まずこのメインの事件に入る前の導入部でエルキュールポアロ(ブラナー)が世界的に有名な探偵で、非常に優秀な人だということを端的に示していて、その後のメインの事件に入る部分もとてもスムーズ。
登場人物が多い作品なので、ぼーっとしていると誰が誰だか分からなくなってしまいそうですが、その辺りも少しずつ説明しながら観客に紹介していく手法はさすが。
立ち往生した豪華列車という所謂密室の中で殺人が起こり、一人一人の常客の正体をポアロが暴いていくわけですが、どうしてあんな限られたソースしかない場所でそこまで全部分かるの?と疑問に思う部分もありつつ、ポアロが指し示す事件の真相へ向かっていく疾走感と真相が明らかになったときのカタルシスが心地よい。
ケネスブラナーは古典作品に新しい解釈を加えて映画化するのが得意ですが、今回のポアロはやたらとアグレッシブな気がしました。杖をついている初老の男という感じなのに、被疑者と追いかけっこしてみせたり取り押さえたりするんですから。原作のポアロがどんな人だか知らないので、これが新解釈なのかどうかワタクシははっきりとは知らないのですが。
導入部でポアロは世の中には正義か悪かしかないと言っていましたが、この事件はポアロの人生観を変える出来事として大きな転機になったかもしれません。最後のポアロとハバート夫人ミシェルファイファーの熱演にふと涙が出そうになるとは驚きのミステリーでした。
シドニールメット版ももう一度見たくなりました。
「ザ・サークル」というSNS会社に入社したメイホランドエマワトソン。最先端の会社で住む場所もあって、会社の敷地内で何もかも用が済んでしまうほどの規模。医療保険も充実していて、多発性硬化症に苦しむメイの父親ビルパクストンに最新の医療を受けさせることもできる。
新人として頑張っていたメイ。CEOのイーモンベイリートムハンクスに注目され、新しい技術の小型カメラを24時間つけてそれを全世界に公開することになる。
最初の頃は、やたらと参加を促される課外活動やらパーティやらに戸惑いを感じていたメイだったのだが、独りでカヌーを漕ぎに夜の海に出た時にあちこちに置かれて公開されている新技術の小型カメラでメイの遭難を見ていた人たちのおかげで救急ヘリが来て助けられ、すっかりこの技術に魅了されてしまう。
って、ちょっと待ってーーーー。いくら自分の命も助けられて父親の病気も助けてもらえたからってこんな若い女の子が自分の生活を24時間全世界の人に公開するなんて頭おかしいとしか思えない。トイレは別って言ってたけどさ、シャワーはどうするの?着がえは?恋人ができたらどうするの?しかも、メイの目線でもカメラがついてるからメイの生活だけじゃなくて周囲の人の生活も公開されちゃう。そのせいで両親のセックスシーンまで全世界に公開されてしまった。それでもメイは「まだシェアすることは良いことだ」というモットーに従って、盲信していく。
この会社に入れてくれた親友のアニーカレンギランが憔悴しきっているのもスルー。この会社の技術の設立者であるタイラフィートジョンボイエガが忠告してくれてもスルー。いや、そこまで陶酔するきっかけあったっけ?とこちらは置いてけぼり。まぁタイの意見をスルー以前になんでタイが勝手にメイのことをやたらと信用してかなりのレベルの人しか入れない秘密の場所に連れて行ってくれるのか超謎。メイがベイリーたちのスパイだったらどうするの?しかもベイリーたちはタイのこと干してるって感じだったんのに、どうしてタイはまだあんな秘密の場所に入るクリアランスを持ってるの?
選挙の投票をサークルのアカウントで義務化とかってディストピア感出したいのかなっていうのも分かるんだけど、これが1980年代とかに作られた作品だったらそれも感じられたかも。
最後にシェアリングの力を使って人を探すという企画でメイの親友だったのにメイのSNSのせいで疎遠になっていたマーサーエラーコルトレーンをみんなで探そうということになり、スマホを持った連中に追いかけられたマーサーが車で逃げ橋から転落して死亡。それでメイが目が覚めるって設定だけど…これ、普通に逮捕者出ないの?ベイリーたちが警察とかに賄賂払ったりしてるから大丈夫だったのかな。
こんなくだらないことからメイの目を覚ますためのマーサーの命の扱いが軽過ぎるわ。タイもメイの決断がなくても自分の技術でそれまでになんとでもできたよね。
結局ベイリーたちが裏でなんか悪いことををしてるっていうのはずっとほのめかされてるけど、そこには対して踏み込まず。アニーがベイリーたちに何をさせられてきたのかも暴かれず。
映画化するくらいだから、原作は面白かったのかな。読んでないのでなんとも言えないのですが、映画を見た印象としては、原作のあらすじを端折って映画にしてみましたってだけに感じました。なんかエマやトムハンクスも編集されて出来上がった作品を見てちょっとびっくりしたんじゃないかなぁと思います。エマを見ているだけで満足な人しか見てはいけない作品かも。あ、でもね、なんかわざとなのか知らんけど妙に自然光使っててエマの顔もよく見えないシーンが多くて、もうせめてエマの顔に照明当ててじっくり見させてよと思ってしまいました。
オマケ 一所懸命エマがアメリカ英語を話している横で親友アニーにスコットランド英語を話されたら、つられそうにならなかったかなと余計な心配をしてしまいました。
一所懸命エマがアメリカ英語を話している横で親友アニーにスコットランド英語を話されたら、つられそうにならなかったかなと余計な心配をしてしまいました。
とにかくジェシカチャスティンが出ると決めた作品なら良い作品に決まっていると思って、彼女の作品はできるだけ見に行くようにしています。今作も以前からとても楽しみにしていました。
敏腕ロビイストのエリザベススローン(チャスティン)。本来は税関係が専門だが、所属する大手ロビー会社から今回銃規制法に反対する銃擁護派のロビー活動の担当にさせられそうになり、銃規制派であるロドルフォシュミットマークストロングが経営する小さなロビー会社に部下4人を連れて移籍。巨大な権力を相手にロビー活動をすることになる。
冷徹なまでに相手の動きを読み、脅しすかしなだめおだて、時には味方の陣営にウソをついたり作戦を内緒にしたりするやり方で敵をこちらサイドに寝返らせていく。自分のロビー活動を成功させるためなら味方をどんなふうに利用しても気にしない。相手が傷つくことなど平気でやってのける。エリザベススローンはそんな人。
それでも彼女がただのイヤな奴に見えないのは、ワタクシがジェシカチャスティンのファンだからなのか。いやそれだけではない、彼女が少ないプライベートの時間に時折見せる寂しそうなまなざし。誰を傷つけても気にしないという態度でいながら、どこか心の奥底では自分が傷ついていそうな雰囲気がある。決して語られない彼女の過去に何があったのか、そこに思いを馳せずにはいられない。
しかし、物語はワタクシのそんなセンチメントを笑い飛ばすかのようにドロドロの闘いが繰り広げられる。彼女が元いた会社の連中は、彼女のせいで負けそうになると彼女がロビー活動で行った法律に反する行為を暴き、スパーリング上院議員ジョンリスゴーを担ぎ上げ彼女を聴聞会にかけた。
弁護士に黙秘権を貫くよう指示されるスローンだったが、議員の挑発に乗り黙秘権を放棄してしまう。あそこまで頭の良い彼女がこんな挑発に乗るなんておかしくない?と思っていたのだが、彼女の行動は何もかも計算されたものなのだ。彼女の中では最後の最後の最後まで全部計算済みだったのだろう。彼女の中での計算外は彼女が買っていたエスコートサービス・フォードジェイクレイシーが偽証罪も適用される聴聞会で「彼女とお金をもらって関係を結んだことはない」と堂々と偽証してみせたところだけだったか。軽薄そうに見えたフォードだったけど、一度は心が通いかけた彼女の秘密を守ってあげたのか。あれは鉄の女にとって嬉しい誤算だったのかも。
ジェシカチャスティンはどの作品を見ても「いやー、やっぱカッコ良かったなー」と思えて、彼女の一番カッコ良かった作品が常に更新されていくような状況なのだけど、今回のエリザベススローンももうめっちゃくちゃカッコ良かった。ひとつ前に書いたシャーリーズセロンの役のフィジカルなカッコ良さではなくて、頭がめちゃくちゃいい人のカッコ良さ。そして他人を犠牲にすることなんてまったく気にしないっていう顔をして実は自己犠牲の精神がとてもあるというあの最後のシークエンスのぞくぞくするようなカッコ良さ。社会派ドラマが好きな方にはぜひぜひ見ていただきたい作品です。
予告を初めて見たときから見に行きたいと思っていた作品です。なんせシャーリーズセロンがカッコ良過ぎるんですもの。
壁が崩壊する直前の東西ベルリン。世界中に暗躍するスパイたちのリストを取り返すべくMI6の腕利きスパイローレンブロートン(セロン)がかり出される。現地にいるMI6のデヴィッドパーシヴァルジェームズマカヴォイと協力してというはずなのだが、このパーシヴァルがどうも信用できない男。リストを巡りMI6(イギリス)、KGB(ソ連)、CIA(アメリカ)、DGSE(フランス)が入り乱れる。あ、シュタージ(東ドイツ)のおっちゃんエディマーサンも出てたな。
正直言って途中からもうストーリーを追うのがしんどくなりました。結局みんな何やってんの?みたいな気になってきて。でもいいんです。シャーリーズセロンのプロモーションビデオを見に行っただけですから。
シャーリーズ演じるローレンブロートンが何から何までカッコいい。タバコを吸う姿、ウォッカを飲む姿、フランスのスパイ・デルフィーヌソフィアブテラとのベッドシーン、闘う姿。この闘う姿っていうのがね、たいがい女性が殴られたりするのって見るのが辛いんですけど、シャーリーズって体がでかいし、とにかくこのローレンが強いからっていうのが一番なんだけど、大の男たちとボコボコにやりやってても爽快感あるんです。何十人相手にしたんだろ。かなり肉弾戦を繰り広げてくれます。ここまでのアクションができるのはシャーリーズの他にはアンジェリーナジョリーかミラジョヴォヴィッチくらいかなぁ。
そして、衣装ももちろんカッコいいし、プラチナブロンドもブルネットもなんでも似合ってしまって惚れ惚れ。
彼らスパイが出入りするホテルやバーなどもベルリンのデカダンスを非常にうまく表現しているし、当時の音楽がガンガンの大音量で流れて最高です。サントラも良さそうだな。
ストーリーはいまいち分かりにくいというか、ストーリーテリングはあまり上手じゃないなと思ったけど、ラストシーンで冷戦が終わったあと、ローレンがどうなったのか続編を見せてくれてもいいなぁと思いました。
アカデミー賞を受賞した後15年間鳴かず飛ばずの脚本家キースマイケルズヒューグラントはエージェントに薦められて田舎の大学の脚本コースの講師の職を引き受ける。次に脚本が書けるまでの腰掛くらいにしか考えていないキースは着任早々まだ授業1日目にも至っていない初日にいきなり大学の学生と関係を持つというふざけた態度。講師の歓迎会でもジェーンオースティンの研究家であるメアリーシェルドン教授アリソンジャネイに女性差別発言をして嫌われ、脚本コースの学生たちも選考のための脚本など読まずフェイスブックで顔を調べて女子はキレイな子、男子はダサいヤツだけを入れた。
そんなふざけきったキースなんだけど、ヒューグラントが演じているせいか、なぜか憎めない。彼の行動を見ていると決して性根の悪いヤツじゃないんだよなぁというのが伝わってくる。学生に簡単に手を出してしまったり、女性差別的なことをジョークのように言ってしまうのもハリウッドという文化にどっぷり浸かっていたせいで、キースが悪いヤツだからじゃないんだなということが分かる。
初めはやる気もなかったキースだけど、学生たちの脚本の指導をしているうちになんだかやりがいのようなものを感じ始める。学生の中にいるシングルマザー・ホリーマリサトメイは同世代でキースに遠慮なく自分の意見を言って、キースとは正反対な性格だけど、彼女のアドバイスにはっとさせられることも。
ミドルエイジクライシス的なものに、定番の学生と教師の交流も混ぜつつ、ハリウッドという広い世界に見えてとても狭い世界に住んでいたキースの目が開いていくという過程を見るのが楽しい作品。
そこに涙もろい学科長のJ・K・シモンズやちょっとキモい役の多いクリスエリオットなど個性の強い役者たちが脇を固めていて、アリソンジェネイも含め全員が役者でありながらコメディセンス抜群の人たちばかりが集まっているから、「間」が最高なんだよね。
特に目新しいものがある脚本なわけじゃないけど、なんだか心温まる作品でした。
「映画」という商業作品や芸術の分野において非常に重要な役割を果たしている「音楽」にスポットを当てたドキュメンタリー。誰もが聞いたことのある挿入歌やテーマ曲、エンディング曲、はたまたシーンのバックに流れる音楽を作っている人たちに次々とインタビューしている。
その作曲家本人のことは顔などもちろん全然知らなくても、その人が作った音楽を聞くとすぐに、「あ~これを作った人か。すごい人だな」となるような人たちが次々に登場して驚かせてくれる。
彼らが監督とともにイメージを膨らませすでに撮影の済んでいる映像に音楽を重ねていく様子が見られてとてもワクワクした。普段映画を見るとき、とてもインパクトのあるシーンや音楽は別として、何気ないシーンのバックに流れている音楽など無意識に耳に入っているだけということもあるが、それが全体は何秒で~とか、何秒目から徐々に盛り上がりをつけて~とか、細かいやりとりがあって、まったくセリフのないシーンなどに深みを加えていく作業が素晴らしい。
映画音楽作りのルールはただひとつ「ルールなどない」ということらしいです。音楽のジャンルも問わずどんな楽器を使うかも問わず、楽器どころか何を使って音を出すかさえも問わない。ここまで自由となると却って難しい作業なのではないかなーと思いました。
彼らが曲作りの辛さなどを語るところで、街でその映画のポスターを見かけるとめっちゃビビるというのが面白かったです。音楽をつけるのはどうしても最後の作業になるからお尻が詰まっていることが多いのでしょう。「公開ってポスターに書いてあるけどまだ半分も曲書けてないのにどうするんだーーー」ってなるっていうのが人間的で面白かった。
そして、作品が出来上がったときに一般に公開している映画館にお客さんの反応を見に行くという人がいて、これも面白かったな。映画を見ずにスクリーン側からお客さんの反応を見て、「気味悪がられていると思う」と言っていて、映画が終わるや否やトイレの個室にこもって、お客さんの感想や鼻歌で挿入歌を歌わないかとかを観察していると言う。映画を見た直後に鼻歌で出てくる曲を書くことができたらこれはもう映画音楽作家としては大成功だろう。
実際に曲を録音していく作業も見ることができるのですが、ここで集まっているスタジオミュージシャンたちのすごさにビックリしました。オーケストラが集められているのですが、彼らは事前に楽譜をもらうことなくその場で初めて楽譜を見て完璧に演奏するというのです。それがスタジオミュージシャンとしては当たり前なんでしょうけど、映画監督などもそれを聞いて驚くみたいですね。しかもそれをそのまま弾くだけではなく、その場でやっぱり全部半音下げてとかここはもっとゆっくりにしてとかいう要望に即座に応えるのですから。作曲家が楽譜は演奏家たちへのラブレターと言っていて、めちゃくちゃカッコいいと思いました。
「うぬぼれでも何でもなく、自分自身が鳥肌の立つような音楽を書けなければ、人を感動させることはできない」と言っていて、これは本当にそうなんだろうなと思いました。ワタクシなんかでは到底理解できない物を作る人の発想だと思うけど、何かすごいものを書けたときというのは、自分でも鳥肌が立つものなのでしょうし、自分はそれくらいのことをやっていると思っていなければできない仕事だと思います。
映画が好きな人にとってはとてもワクワクするドキュメンタリーですので、ぜひご覧になってほしいです。
アインシュタインにも匹敵する頭脳と言われたインド人数学者シュリニヴァーサラマヌジャンデヴパテルのお話。
1941年ケンブリッジ大学の数学者G・H・ハーディジェレミーアイアンズはインドから手紙を受け取る。そこには驚くべき数式の発見が示されており、ハーディ教授はラマヌジャンを呼び寄せる。
母親の反対を受けたラマヌジャンだったが、イギリスに渡ることを決意し、新婚の妻を後で呼び寄せる約束をして船に乗った。
数式は女神が舌の上に置いていくという神秘的なことを言うラマヌジャンと無神論者で数字は得意だが人とのコミュニケーションは苦手なハーディ。西洋式に数式は証明してこそ意味があるということをラマヌジャンに説くが、ひらめきだけで数学を理解してきたラマヌジャンにはそれがなかなか通じない。
インドからイギリスにやって来たラマヌジャンが文化の違いに戸惑うところや、堅物のハーディがなんとかラマヌジャンとコミュニケーションを取ろうとする姿がなんだか可愛らしい。
ただハーディとラマヌジャンの世界の外では、可愛らしいでは済まない現実があり、ラマヌジャンはイギリス人から差別を受けるし、戦時下でベジタリアンの彼が食べるものがろくになく栄養失調から病気になってしまう。ハーディはハーディで彼の味方は友人のリトルウッドトビージョーンズだけだったのに、彼は従軍しなければならなくなってしまう。
そんな中でも2人、不器用な者同士ラマヌジャンの数式の証明に取り組み、ハーディは学者連中を説得し、一度は却下された特別研究員の地位をラマヌジャンに与えることを認めさせる。
数式などひとつも理解できなくとも、この物語に登場する人々の友情とその人生には胸の熱くなるものがあり、マシューブラウン監督は随所に適度な笑いを入れつつ、真面目にストーリーを語ってくれて好感が持てた。
ジェレミーアイアンズの作品は久しぶりに見た気がするのだけど、昔から神経質そうないでたちで今回の人の目をちゃんと見て話せないようなコミュニケーション下手な教授がとてもよく似合っていた。そして、いまやインド人の役はすべて彼に一度はオファーが行くであろうデヴパテル。人気だけではなく実力が伴っているので安心して見ることができる役者さんだ。
お話に登場する数式などはさっぱり分からないのだけど、数学が芸術に通じるという概念だけはなんとなく理解することはできる。ラマヌジャンを見ているとこの世の中にある真理を見つけ出すというのはある意味神の領域であり、それは神秘的な体験なのかもしれないと思える。まったく数学が分からない人でも楽しめる心温まる作品です。
八王子でとある夫婦が殺害される。現場は血の海で、壁に犯人が血文字で書いた「怒」という文字が残されていた。犯人は整形して逃亡中。
千葉。家出して風俗で働いていた愛子宮崎あおいは父・洋平渡辺謙に見つけられ家に連れ戻される。愛子が家出した間に父の職場である港で働き始めた寡黙な男・田代松山ケンイチと愛子は魅かれあうようになる。
東京。ゲイで遊び人の優馬妻夫木聡は、ある日サウナで直人綾野剛という大人しい男に出会い、なんとなく一緒に暮らすようになるが、そのうちお互いが大切な存在となっていく。
沖縄。母親の都合で沖縄に引っ越してきた泉広瀬すずは友達の辰哉佐久本宝に無人島に連れて行ってもらい、そこで野宿生活をしている田中森山未来と出会う。
3人の素性の知れない男性。ニュース映像で流れる八王子事件の犯人と全員どこか似ている。この3人のうちの誰かが犯人ということか。と、思いながら見ていたんですが、途中から実は時系列がいじってあって、この3人は同一人物で犯人が転々と居場所を変えて逃走していっているということなのか?と勘ぐってしまったのだけど、「この3人のうちの誰かが犯人」ということで合っていたらしい。結局誰も犯人じゃないっていうのもアリなのかなぁと思いながら見ていたのですが、、、
3人全員がそれぞれの土地で知り合う人たちと交流して、その知り合う人たちはやがてそれぞれが八王子の犯人なのではないかと疑いを持ち始める。全員が知り合ったのが事件後で、その前に何をしていたのかはっきりしていないということから疑いが生じるのはしょうがない気もする。ニュースで公開される犯人の人相をうまく3人の役者に似せてあった。
すべての話がよくできているので、まったく飽きることなく見ることはできたのですが、最終的に犯人が分かる部分はちょっと納得がいかなかったな。犯人が誰だったかはここでは書かないでおきますが、なんかそれまで普通に良い人って感じだったのに後半に急変するのがついて行けませんでした。犯罪を犯す人でも一見良い人に思えるっていうのはあるかとは思うのですが、犯人を知っている人物が後半に現れて犯人の性格とかを語り始めるのですが、それと彼が全然一致しなくてどうも唐突感が否めない。始めのほうで警察が犯人のアパートを家宅捜査するシーンがありますが、その犯人像と彼を後半で急に合わせてきたという感じがしてしまいました。
そうそうたるメンバーが出演していますが、その中でも宮崎あおいの演技は群を抜いて上手いですね。彼女にはいつも感心させられますが、今回のちょっと普通とはずれていて(少し障害があるのかな)風俗で働くような女性ってさすがにミスキャストでは?と思っていたら、全然違和感がなくて本当にビックリしました。
そして、広瀬すずちゃんも光っていました。彼女は立ち姿だけですでに妙な風格が伴っていて、テレビサイズの女優ではなくて銀幕サイズの女優だなと感じました。すでに大物感が漂っていてこれからがめちゃくちゃ楽しみです。
誰が犯人かというサスペンスよりもそれぞれの人生のドラマを中心に見たほうが面白いかもしれません。
2010年に「ザ・コーヴ」を見たときにどうして「メイキング・オブ・ザ・コーヴ」というカウンタームービーを作らないんだ!という感想を書いていたら、カウンタームービーができた。2015年、映画作りは素人の八木景子監督が作ったというので見たかったのだが、見る機会がなくこの度ケーブルテレビで見ることができました。
正直に言います。まぁとにかく素人くさい。本当に手作り感がすごいです。ぶっちゃけ見ていてしらけそうになるくらいなんだけど、最初にちょっとそこに目をつぶって我慢して見ているとだんだん内容に必死になって見ていました。
太地町の人々、太地町の役人、市長、太地町の活動家、国の役人、シーシェパード、ノルウェーの教授、アニマルプラネットの元カメラマンとインタビューは多岐に渡り、それぞれの人が話す内容もあっちゃこっちゃ行ってちょっと分かりにくい。ワタクシが期待していたのはまさに「ザ・コーヴ」のカウンタームービーで「ザ・コーヴ」のはい、ここがウソ、あそこがウソってひとつひとつ指摘していってくれるような作品だったのですが、これはそこまで逐一やっていくわけではなく全体的な反論となぜここまで捕鯨問題がアメリカで取り上げられるかという疑問に迫るといった感じでした。
結局日本の国が「ザ・コーヴ」に関して何もしなかったのは、こんなことにお金をかけても無駄だからってことだったらしい。捕鯨なんて大した経済効果もないし、日本の片田舎のとある町の人たちがやりたいなら勝手にやったらいいじゃないくらいのもんなんだろう。それプラス、アメリカはベトナム戦争への世界的な非難から目を背けさせるために日本の捕鯨をやり玉に挙げたっていうんだから、それには驚きだったな。シーシェパードがイルカに固執するのは儲かるからっていうのは予想がついたけど、まさかアメリカが自分とこへの非難を避けるために捕鯨問題を利用したとはね。
シーシェパードの人たちにもインタビューをするんだけど、何を聞いてもお話にならないよね。一応質問したことには答えてはくれるけど、内容は要領を得なくてイライラする。あの代表にインタビューさせまいとやたらと手を回してきたシーシェパードの日本人女性にもイライラしたな。
捕鯨問題を原爆の問題と結びつけるのはちょっとどうかと思う部分もありましたね。捕鯨問題でアメリカが日本ばかり責めるのは人種差別があるからというのは、あながち完全な間違いではないかもしれないけど、それだけで断罪してしまうのは危険な気がします。こちらの文化をはなから理解する気がないという傲慢な態度は結局有色人種を下に見ているからというのがあるかもしれないけど、もう少し鯨とイルカを獲って食べることの環境への影響などを科学的な見地からシーシェパードに疑問をぶつけてほしかった。
科学的な資料とか、歴史的な資料もたくさん登場して客観的に判断できるようにはなっているんだけど、その資料の出し方が一瞬映るだけだったりして、物足りなさはあった。
太地町の人たちは「ザ・コーヴ」以降もうメディアはこりごりという感じだっただろうから八木監督が信頼を得るまでは大変だっただろう。そういうところは素人だったのが幸いしたのかもしれない。
と、レビューを書くために人名などネットで調べているとこの作品の「アメリカがベトナム戦争への非難から目を背けさせるために日本の捕鯨をやり玉に挙げた」というのはウソという情報が、、、んーーーなんなんだ。これこそドキュメンタリー作品を鵜のみにしてはいけないというこの作品の意図と合致した意味を持った例になってしまっているではないか。