きうちかずひろ監督「共犯者」を見る。
Vシネマなどオリジナルビデオ全盛の90年代。
そこから台頭した監督は、
望月六郎や三池崇史、黒沢清だけでなく、
きうちかずひろがいたことを忘れてはいけないと思う。
Vシネの竹中直人主演「カルロス」(1991)
で、一躍名を上げたあと、
続編である本作(1999)では小泉今日子をヒロインに、
そして内田裕也を敵役に迎え、惚れ惚れするような
バイオレンス映画をものにしている。
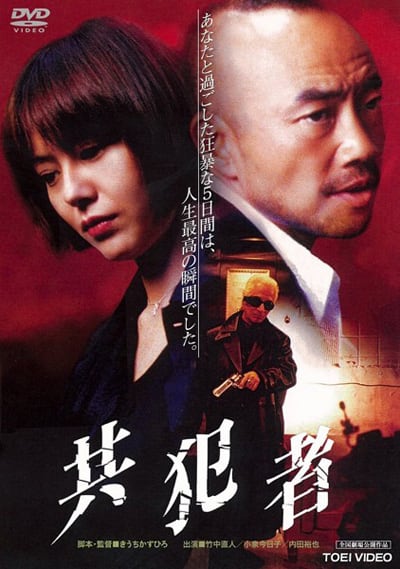
竹中直人扮する
日系二世のブラジル人ヤクザのカルロス。
この男の行動原理は金でも女でもなく、
とにかく戦い、殺し合うことである。
そのために敢えて巨大暴力団にケンカを売り、
自分を窮地に追い込み、殺戮の場に身を投じるのだ。そんな人物像。
内田裕也演じる殺し屋も
カルロスとまったく同類で、人を殺すことだけが
自分の存在理由であるかのような男である。
そんな二人がただ殺し合うクライマックス。
廃墟の暗闇で蠢く竹中直人と内田裕也を追いかける
仙元誠三のカメラワークがなんといっても素晴らしい。
その仙元のカメラだが、
小泉今日子を捉えるときだけ、
暗闇のなか、そっと光を当て、
彼女の美しさを際立たせるのだ。
照明の渡辺三雄との絶妙なアンサンブルというか、
東映セントラルフィルムの職人技を堪能する。
内田裕也に存在感がありすぎて
割を食った感のある小泉今日子だが、
映画の作り手たちは、ちゃんと彼女に華を持たせるのを忘れない。
この頃のキョンキョンがいちばんキレイだったのでは、
と思ったりする1999 年作(今もキレイです)。
























