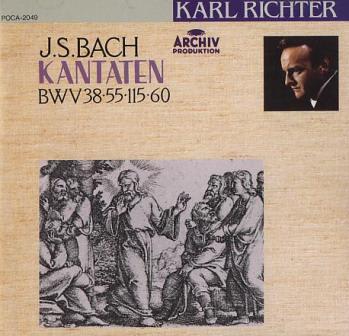人類の運命を変えた気候2万年史 第4回
序 (4)
どのようなシステムでも、小さな変動にたいして強くなるために規模を大きくする。企業組織をみればわかる。しかし耐えられない想定外の変動に対して、組織はもろくも崩れる事がある。金融不安でグローバル金融機関が簡単に倒産した事を我々は2008年に見てきた。文明とは人類の共同体システムだとすれば、大規模になった事で他の集団にたいして強くなるが、多くの人口を抱えて居る事で変動への対応が鈍く、急速な転換が出来ない。小規模であれば波に乗って容易に逃げられたのに、図体が大きいばかりに波に沈むこともあるのだ。紀元前6000年前からメソポタミアには人が住み着いて、紀元前3000年以上前から都市文明が各地で興り農耕と通商で栄えた。紀元前2300年前シュメールの第3王朝(ウル王朝)ができて、灌漑用水路が張り巡らされ、エジプトのファラオに並ぶ世界最強の都市国家となった。ところが火山爆発や旱魃はユーフラテス川付近を砂漠に近い荒廃した地に変え、紀元前2000年にはシュメール人の人口は半減した。高原に移った別の部族が王朝を立てたが、ウル王朝は完全に崩壊して、人々は死に絶えたか離散した。小規模の災害に対して万全の対策として興隆した都市は、より大きな災害に対してますます脆弱になっていた。生存できるか否かは、往々にして規模の問題となる。
序 (4)
どのようなシステムでも、小さな変動にたいして強くなるために規模を大きくする。企業組織をみればわかる。しかし耐えられない想定外の変動に対して、組織はもろくも崩れる事がある。金融不安でグローバル金融機関が簡単に倒産した事を我々は2008年に見てきた。文明とは人類の共同体システムだとすれば、大規模になった事で他の集団にたいして強くなるが、多くの人口を抱えて居る事で変動への対応が鈍く、急速な転換が出来ない。小規模であれば波に乗って容易に逃げられたのに、図体が大きいばかりに波に沈むこともあるのだ。紀元前6000年前からメソポタミアには人が住み着いて、紀元前3000年以上前から都市文明が各地で興り農耕と通商で栄えた。紀元前2300年前シュメールの第3王朝(ウル王朝)ができて、灌漑用水路が張り巡らされ、エジプトのファラオに並ぶ世界最強の都市国家となった。ところが火山爆発や旱魃はユーフラテス川付近を砂漠に近い荒廃した地に変え、紀元前2000年にはシュメール人の人口は半減した。高原に移った別の部族が王朝を立てたが、ウル王朝は完全に崩壊して、人々は死に絶えたか離散した。小規模の災害に対して万全の対策として興隆した都市は、より大きな災害に対してますます脆弱になっていた。生存できるか否かは、往々にして規模の問題となる。